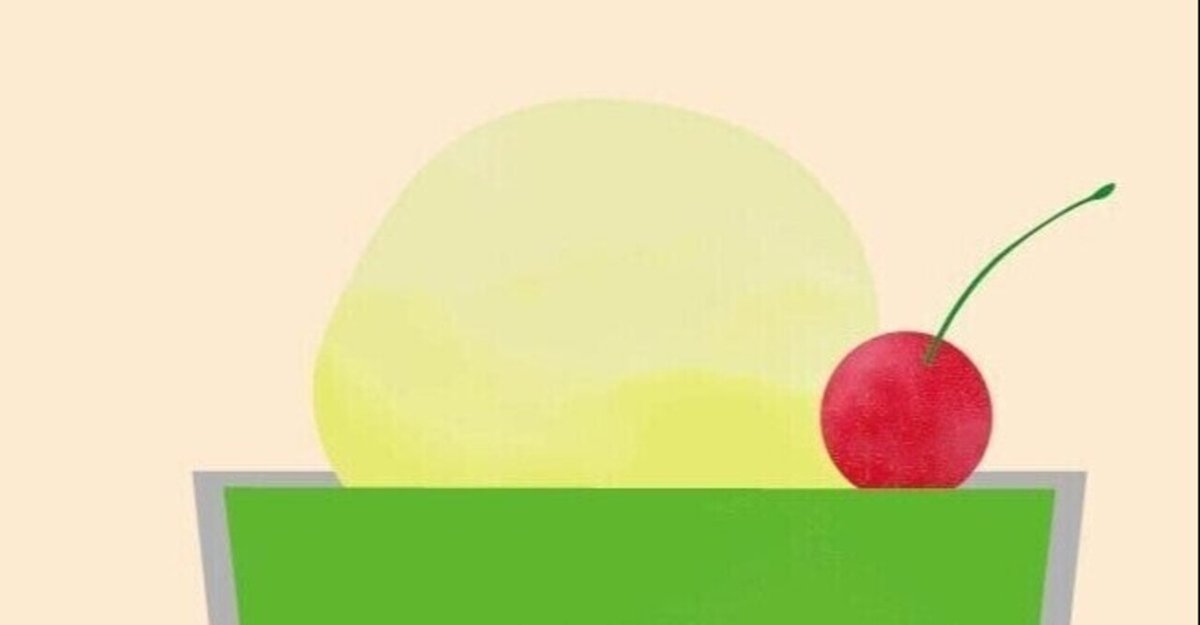
「珈琲とビジネス。」/ショートストーリー
彼は普段通りに優雅な仕草で珈琲を飲んでいる。
それでわたしの方はやっぱりいつもと同じアイスクリームがのったメロンソーダ。
いつまで経っても珈琲が苦手で飲む気がしない。
彼はいつもメロンソーダを飲むわたしを笑ってみている。
「久しぶりだ。今日は何の用かな?私も忙しいがおまえも同じだろう。」
わたしをおまえ呼ばわりするのは彼だけだ。
彼の方が少しだけ年上だから仕方ない。
「うーん。」
「おまえでも言いづらいか。」
そう言うと彼はまた笑って珈琲を飲んだ。
あのカップは唐時代の青磁だ。それも唐の皇帝が使っていた貴重なものだ。
「どうせ。私のビジネスのことだろうが。おまえに非難めいたことを言われる覚えはない。」
「一応、同業者なんだ。」
「そうだが。相手する客がまるで違うだろう。私とおまえでは。」
「仕事の仕方が違うのだから、必然的に客層もかわる。あなたはそれを。」
とそこでわたしは口をつぐんでしまった。
なぜなら。
彼がそういうわたしを嬉しそうに見ているのに気がついたからだ。
何が嬉しいのだろうか。
「どうした。続きを言ってごらん。」
「あなたの相手はいつもひとでないものかひとでなし。心がないお客様相手のはずなのに。時々、気まぐれにわたしのお客様になるはずだったものたちに仕事するのは。」
彼はわたしに最後まで言わせずに。
「営業妨害だと言いたいのかな。まあ、強いて言えばそうなるか。」
「だから。今後はやめてほしいんだ。」
彼はまた青磁のカップに口をつけた。
「この青磁良いだろう。対価にもらったものだ。それで。おまえは私が客に対して押し売りのように無理強いしているとでも言うのか。だが。おまえにもわかっているはず。相手が私を強く呼ぶのだよ。」
そう、彼の言う通りだ。お客様の強い気持ちが明るい方か暗い方のどちらに向かうのかは私たちでコントロールすることはできない。
心あるひとや存在でも、ほんの一瞬の迷いみたいなエネルギーが生ずることがある。
だから。
言い訳めいているがそのせいでわたしは遅れてしまうのだ。
「ただ。私の仕事はおまえの商いと違ってビジネスなのだよ。利益が優先だ。いつもの客なら文句は言わないし、泣いたり後悔したりしないさ。そういうものたちだからな。」
「だから。お願いと言ってよい。わたしの領域を荒らさないでほしい。」
「呼ばれても行くなということか。難しいな。おまえもわかっているはずだ。呼ばれたら行く。ただ、契約が成立するかはお客次第だし、おまえが来れば譲る。それに猫の王のような強力な保護者がいれば退散するしかない。そういうことだ。なんでも屋よ。」
彼の姿がみるみる消える。
「おまえな。あなたでなく、兄さんと呼ぶべきだろう。」
次元の狭間でその言葉とメロンソーダだけが残った。
このお話しからなんでも屋さんが始まりました。↓
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
