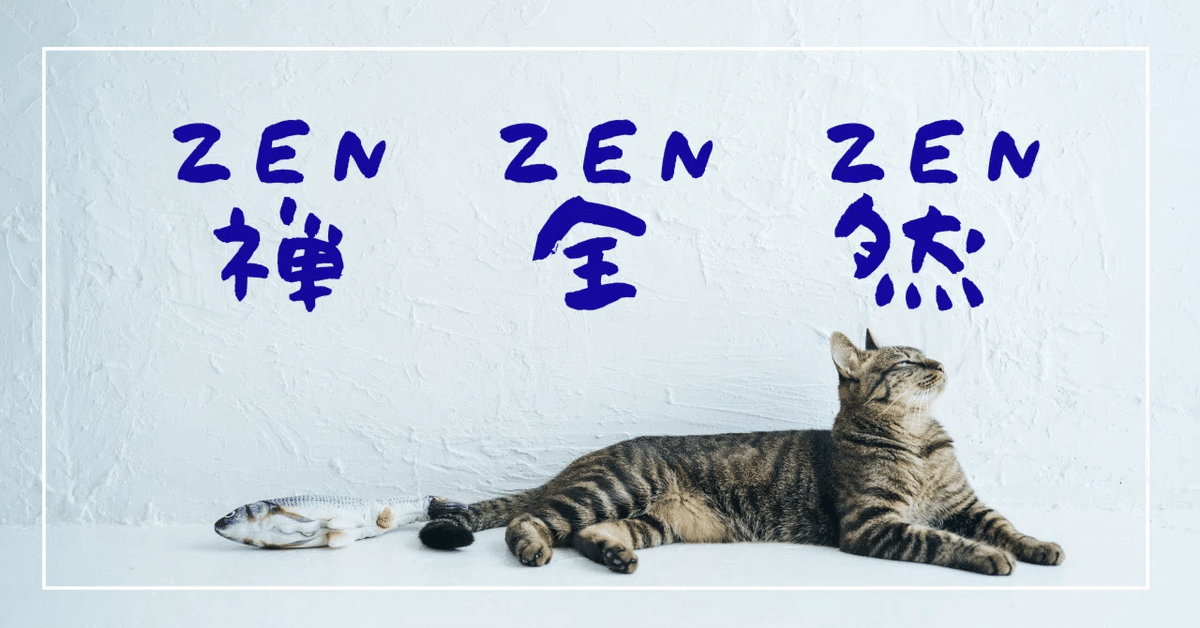
【禅 ZEN】「力を抜く」とはこういうこと『禅がすすめる力の抜き方』平井正修
「力を抜く」とはこういうこと

私は禅宗の僧侶で、たいていの禅僧がそうであるように、
坐禅に自分の生きるよすがを見いだしています。
しかし、坐禅とは何かという点については、
おそらくみなさんとは正反対の考えをもっているはずです。
多くの方は、坐禅を「何か」をつかむ行為、
精神的に欲していたものを手に入れる行為
だと思っていることでしょう。
心を静かに保ってじっと坐っていれば、
やがて無や空の境地に達し、悟りを得るーーというように。
しかし、これはまったく逆なのです。
坐禅とは、何かを得たり足したりするのではなく、
「手にしていたものを手放す」
行為です。
それまでにないものを身につけることで
「何ものか」になろうとするのではなく、
身につけていたものを捨てて、
赤ん坊のような本来の姿へ返る。
そこに坐禅の目的があり、禅の本質があるのです。
ですから、禅がめざすのは、
人から褒められる立派な人間ではありません。
「ただ」の人間であれということです。
花は季節になればただ咲き、
川は海に向かってただ流れていきます。
それと同じように、「ただ生きる」。
それが禅における最高の人間像なのです。
けれども、この「ただ」がきわめて難しい。
何事かをなそうとするとき、私たちの心にはつい、
「うまくやってやろう」
「自分をよく見せてやろう」
という力みーー気負いや背伸び、
こだわりやとらわれが生じます。
そのためにかえって物事をうまくいかなかったり、
問題の解決を遠ざけてしまったりする。
人間にはそういうことが少なくありません。
そんなときは、
心や体からよけいな力みを抜いて
“自然体"で臨むことが大切になってきます。
問題を力で克服しようとするよりも、
自然の流れに身をまかせる。
正面からぶつかりあうよりも、
柳に風と受け流す。
そうした「力を抜く知恵」が必要になってくるのです。
たとえば、洪水の被害は、
高く頑丈な堤防をつくって防止しようとするのが
一般的な考え方でしょう。
しかし、昔の人の知恵はもう少し柔軟だったようで、
江戸期には堤防の一部に水を逃がすための
「抜き穴」をこしらえる例が見られたそうです。
穴をうがてば、そこから水があふれますが、
そのあふれた水は幾重にもつくった水路を通して
安全な場所(田んぽなど)まで導いて、
大きな被害を未然に防いだというのです。
東日本の大震災のあと、
海も見えないような高い堤防を建設することが
いいのかどうか議論はあるようですが、
現代の防災にも、こうした押し寄せてくる自然の力を
上手に逃がしたり、かわしたりする
「やわらかい知恵」が必要とされるのではないでしようか。
つまり、大切なのは
力に力で対抗しようとするガチンコの対決思想ではなく、
押してくる力を「引く」ことで受け流す発想です。
私たちは押す力には、
つい押し返す力で対抗しようとしますが、
押す力には引く力で対応したほうが、
うまくいくことも世の中には多いものです。
手に負えない問題、
考えてもおいそれと答えの見つからない問題。
そういうものには力こぶをつくって正面から対峙するよりも、
いったん棚上げする、放っておく、やりすごす。
そんな「力を抜いた対応」をしたほうが
いい解決策が見つかることもあります。
坐禅の目的は新しい何かを加えるのではなく、
身につけていたよけいな何かを捨てることにあると言いました。
私たちの人生もそうです。
ムダな力を肩から抜く。
ときには押すよりも引く力を優先させる。
背伸びや気負い、こだわりやとらわれから自由になる。
自然体で事に臨む。
身の丈のまま素直にふるまう。
そうしたことが可能になれば、
人生を自在柔軟に生きることにもつながっていくはずです。
こちらの内容は、
『禅がすすめる力の抜き方』
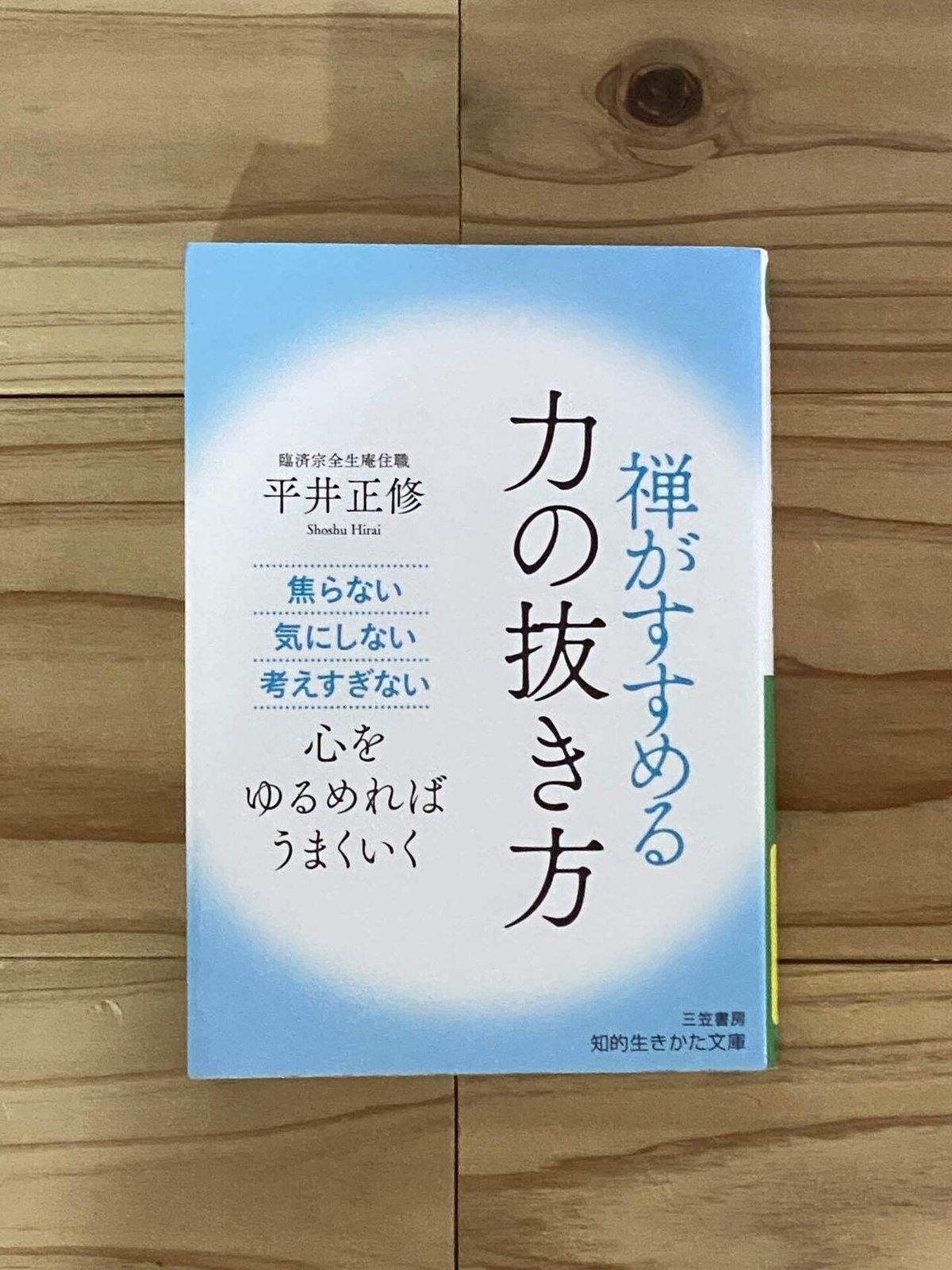
発行所 株式会社三笠書房
著者 平井正修
2019年2月10日 第1刷発行
を引用させて頂いています。
よろしければ、サポートよろしくお願いします❤ ジュニアや保護者様のご負担が少ない ジュニアゴルファー育成を目指しています❕ 一緒に明るい未来を目指しましょう👍
