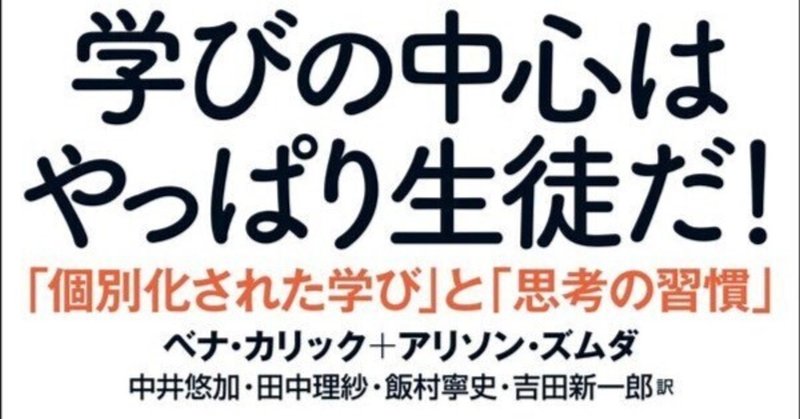
#2個別化された学びを目指してー 『学びの中心はやっぱり生徒だ!』ー
「個別最適な学び」と言われるようになり、子どもを中心とした授業のあり方を模索している人はたくさんいます。また、それを研究主題に掲げて研究に取り組んでいる例も見ます。しかし、その多くは「教師主導の一斉授業」のアレンジであり、子どもが中心にいる学びとは程遠く感じます。
では、個別化された学びはどのように実現されるのでしょうか?今回は、『学びの中心はやっぱり生徒だ!』(ベナ・カリック+アリソン・スムダ著)を読んだことをもとに、考えたことを書いていきます。

1.個別化された学びの4つの特徴
【声】
学習プロセスが始まった段階で、「何を」、「どのように」学ぶのかを決める際に生徒自身が関わること。つまり、教師が与えたことをこなす授業(教科書をやらされる授業)ではなく、学ぶ内容や学び方を自分で決める学びだということです。
【共創】
何を図るのか(学習目標)を明確にし、出来上がるものや成果を想い描き(評価)、望んだ結果を達成するための行動計画を立てて取り組むこと(学習行動)を意味します。
ここで言う「共創」は、子どもと教師が共に創ることです。
【他者との共同構築】
生徒が共通の学習目標を追究するために理論を立てたり、調べたりしながら、他者との関係を通じてアイディアを構築していくことを意味します。
「個別化された学び」と言われると、一人ひとりが独立して学んでいくように捉えられがちですが、他者との関わりが大変重要であるということです。
【自己発見】
学びとしての自分について生徒が理解するプロセスを意味します。
子どもが、誰かの指示を待つのではなく、自らをコントロールする、主体的かつ自立的な学び手になることを目指します。
そのためには、振り返りのあり方を見直したり、教師が管理する教室から子どもが率先して動ける教室へ転換したりする必要があります。
2.思考の習慣
本書では、16の思考の習慣が紹介されています。「思考の習慣」と言われると、イメージしづらいかと思いますが、私は「非認知能力」と言われるものを言語化したものだと捉えています。
思考の習慣の一つに「粘り強く取り組む」という項目があります。授業の中で、こうした視点は見落とされがちです。教科の内容ばかりに目が行ってしまいがちですが、教師や生徒が思考の習慣を使いこなせるようになるようになることも大切であることを忘れるべきではありません。
【16の思考の習慣】
・強く取り組む
・理解と共感をもって聴く
・自分の考えについて考える(メタ認知)
・問いを持ち問題提起をする
・衝動的な言動をコントロールする
・柔軟に考える
・正確さと精度にこだわる
・既習の知識を新しい状況に適用する
・明確に考え、正確に伝える
・創造する、想像する、イノベーションを起こす
・責任あるリスクを取る(思い切ってチャレンジすることを指す)
・互いに協力しあう関係で考える
・五感で情報を収集する
・驚きと不思議に思う気持ちを持って反応する
・ユーモアを生かす
・常に学び続ける
3.「一人ひとりを生かす学習」「個人学習」と「個別化された学び」は違う
この3つの教育モデルを知っておくと、現在の授業の在り方の課題がより見えやすくなってきます。
【一人ひとりを生かす学習】
教師が学びを管理し、その中で子どもたちが方法を選べるというような学習です。
【個人学習】
与えられた課題を自分でこなしていくというイメージでしょうか。こう考えると、現在「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」をめざして一斉授業を脱却している実践ですら、個別化された学びにはなっていないことがほとんどであると言うことがわかります。
【個別化された学び】
「 生徒が自分の願いを追いかけ、問題を探り、解決策をデザインし、好奇心を追い求め、結果が生み出せるようになる生徒主体の革新的な教育モデルです。」とあります。
こう考えると、自治体で導入されている例のある「スタディサプリ」は個人学習の側面が強いし、多くの授業の方法は、良くて「一人ひとりを生かす学習」にとどまっています。一人ひとりを生かす学習にすらなっていないことがほとんどではないでしょうか。
本書では個人学習について「学習が人との関わりの中で育まれると言う部分については見落とされがち」と述べられています。子どもを中心とした学びが行われる授業を目指すにおいて、今よりも解像度を上げて、目指す授業(学びの在り方)を考える必要があると感じました。
4..評価のあり方
【自己評価が大切】
個別化された学びにおいては、生徒の作品を教師のみが判断するよりも、自己評価を多く活用することが求められます。しかし、現状、自己評価の場面や大切さはあまり重要視されていません。自立的な学びてに育てるためには”必須のことなのに”です。現在の「評価」の捉え方は、子どもを選別するための「評定」となってしまっています。A、B、Cをつけることで評価をしたと思い込んでしまっていますし、それこそが評価だと思い込んでしまっているのです。
自己評価するために、ルーブリックを子どもと「共創」することが重要です。どのようなルーブリックを共創していけば良いか考えていきたいです。
【テストは評価の本質ではない】
「健康のバロメーターにするために病院でストレスチェックを受けるようなものだ」というたとえは、とてもわかりやすいと思いました。ストレスチェックの結果をよくするために、どのように回答すれば良い結果になるかということをしても意味がないことは自明です。しかし、日々おこなっているテストは、そのようになってしまっている側面があります。 外部テストをやることでは、子どもの学力は伸びないと言うことです。そう言う意味で、テストの結果は評価の本質とずれがあります。
5.まとめ
日本の学校教育の課題がボロボロと出てくるような、刺激的な本でした。「個別化された学び」「「思考の習慣」「ルーブリック」など、取り入れていきたい実践が多くあり、学びになりました。
一方で、正直、学校教育の現状とのズレが大きすぎて、取り入れることや、そもそもそれらの実践内容を理解することの難しい部分もありました。読み返しながらできるところから実践していき、理解を深めつつ、現在の教育現場に落とし込んでいくことが必要になりそうです。
また、思考の習慣や個別化された学びは、子どもにとってのみではなく、教師にとっても価値のあるものです。むしろ、教師ができていないのに、子どもたちができるといえるでしょうか?教員が思考の習慣を使いこなし、主体的に学んでいく必要があると思います。そのためにできることは何か。学びをアウトプットし、フィードバックしあえる関係・環境を、私の立場からできることとして、校内研究の中で作っていけたらと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
