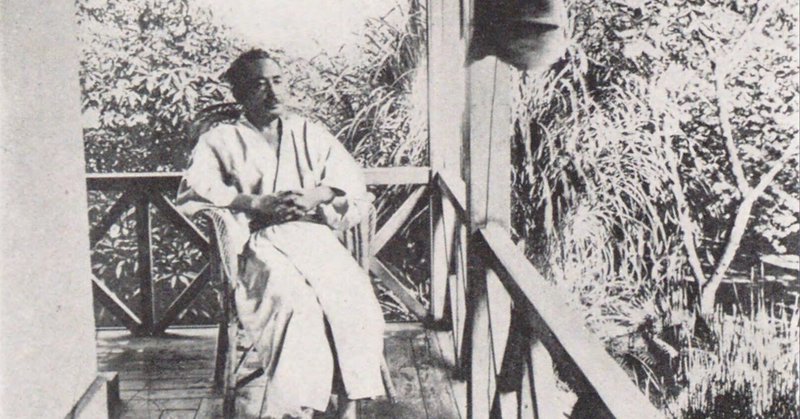
私が好きな夏目漱石の講演(の枝葉部分)2 「文芸と道徳」の新旧道徳論
前置き
(承前)
まだ、前の関連記事が(これを書き始めた時点で)書き終わってないのですが。
勢いがなくならないうちに。忘れないうちに。
二の矢を放ってしまおうという魂胆です。
「文芸と道徳」の新旧道徳論
この講演、下に引っ張った箇所は、私の知る限り、日本の「封建道徳」をもっともうまく言葉で説明したもの(そして、批判する際のとっかかりとなるもの)だと思います。
私は、今日においても時々生き残りを見受けることのある、化石のような「封建道徳論者」が大っ嫌いなものですから。
とりわけこの分析には膝を打ってしまうのです。
前回と同様、お忙しい方は太字部分だけお読みになれば、大体の論旨はつかめるかと。
昔の道徳、これは無論日本での御話ですから昔の道徳といえば維新前の道徳、すなわち徳川氏時代の道徳を指すものでありますが、その昔の道徳はどんなものであるかと云うと、あなた方も御承知の通り、一口に申しますと、完全な一種の理想的の型を拵えて、その型を標準としてその型は吾人が努力の結果実現のできるものとして出立したものであります。だから忠臣でも孝子でももしくは貞女でも、ことごとく完全な模範を前へおいて、我々ごとき至らぬものも意思のいかん、努力のいかんに依っては、この模範通りの事ができるんだといったような教え方、徳義の立て方であったのです。もっとも一概に完全と云いましても、意味の取り方で、いろいろになりますけれども、ここに云うのは仏語などで使う純一無雑まず混り気のないところと見たら差支ないでしょう。例えば鉱のように種々な異分子を含んだ自然物でなくって純金と云ったように精錬した忠臣なり孝子なりを意味しております。かく完全な模型を標榜して、それに達し得る念力をもって修養の功を積むべく余儀なくされたのが昔の徳育であります。
吾々は日に月に個人主義の立場からして世の中を見渡すようになっている。したがって吾々の道徳も自然個人を本位として組み立てられるようになっている。すなわち自我からして道徳律を割り出そうと試みるようになっている。これが現代日本の大勢だとすればロマンチックの道徳換言すれば我が利益のすべてを犠牲に供して他のために行動せねば不徳義であると主張するようなアルトルイスチック一方の見解はどうしても空疎になってこなければならない。昔の道徳すなわち忠とか孝とか貞とかい字を吟味してみると、当時の社会制度にあって絶対の権利を有しておった片方にのみ非常に都合の好いような義務の負担に過ぎないのであります。親の勢が非常に強いとどうしても孝を強いられる。強いられるとは常人として無理をせずに自己本来の情愛だけでは堪えられない過重の分量を要求されるという意味であります。独り孝ばかりではない、忠でも貞でもまた同様の観があります。何しろ人間一生のうちで数えるほどしかない僅少の場合に道義の情火がパッと燃焼した刹那を捉えて、その熱烈純厚の気象を前後に長く引き延ばして、二六時中すべてあのごとくせよと命ずるのは事実上有り得べからざる事を無理に注文するのだから、冷静な科学的観察が進んでその偽りに気がつくと同時に、権威ある道徳律として存在できなくなるのはやむをえない上に、社会組織がだんだん変化して余儀なく個人主義が発展の歩武を進めてくるならばなおさら打撃を蒙こうむるのは明かであります。
人間は完全なものでない、初めは無論、いつまで行っても不純であると、事実の観察に本いた主義を標榜したと云っては間違になるが、自然の成行を逆に点検して四十四年の道徳界を貫いている潮流を一句につづめて見るとこの主義にほかならんように思われるから、つまりは吾々が知らず知らずの間にこの主義を実行して今日に至ったと同じ結果になったのであります。さて自然の事実をそのままに申せば、たといいかな忠臣でも孝子でも貞女でも、一方から云えばそれぞれ相当の美徳を具えているのは無論であるがこれと同時に一方ではずいぶんいかがわしい欠点をもっている。すなわち忠であり孝であり貞であると共に、不忠でもあり不孝でも不貞でもあると云う事であります。こう言葉に現わして云うと何だか非常に悪くなりますが、いかに至徳の人でもどこかしらに悪いところがあるように、人も解釈し自分でも認めつつあるのは疑もない事実だろうと思うのです。現に私がこうやって演壇に立つのは全然諸君のために立つのである、ただ諸君のために立つのである、と救世軍のようなことを言ったって諸君は承知しないでしょう。誰のために立っているかと聞かれたら、社のために立っている、朝日新聞の広告のために立っている、あるいは夏目漱石を天下に紹介するために立っていると答えられるでしょう。それで宜しい。けっして純粋な生一本の動機からここに立って大きな声を出しているのではない。この暑さに襟のグタグタになるほど汗を垂らしてまで諸君のために有益な話をしなければ今晩眠られないというほど奇特な心掛は実のところありません。と云ったところでこう見えても、満更好意も人情も無いわがまま一方の男でもない。打ち明けたところを申せば今度の講演を私が断ったって免職になるほどの大事件ではないので、東京に寝ていて、差支があるとか健康が許さないとか何とかかとか言訳の種を拵えさえすれば、それですむのです。けれども諸君のためを思い、また社のためを思い、と云うと急に偽善めきますが、まあ義理やら好意やらを加味した動機からさっそく出て来たとすればやはり幾分か善人の面影もある。有体に白状すれば私は善人でもあり悪人でも――悪人と云うのは自分ながら少々ひどいようだが、まず善悪とも多少混った人間なる一種の代物で、砂もつき泥もつき汚ない中に金と云うものが有るか無いかぐらいに含まれているくらいのところだろうと思う。私がこういう事を平気で諸君の前で述べて、それであなた方は笑って聴いているくらいなのだから、今の人は昔に比べるとよほど倫理上の意見についても寛大になっている事が分ります。これが制裁の厳重で模範的行動を他に強いなければやまない旧幕時代であったら、こんな露骨を無遠慮にいう私はきっと社長に叱られます。もし社長が大名だったなら叱られるばかりでなく切腹を仰せつかるかも知れないところですけれど、明治四十四年の今日は社長だって黙っている。そうしてあなた方は笑っている。これほど世の中は穏かになって来たのです。倫理観の程度が低くなって来たのです。だんだん住みやすい世の中になって御互に仕合でしょう。
再掲的になりますが、上の文章中、
《人間一生のうちで数えるほどしかない僅少の場合に道義の情火がパッと燃焼した刹那を捉えて、その熱烈純厚の気象を前後に長く引き延ばして、二六時中すべてあのごとくせよと命ずる》
これはさすが漱石と言うべきか、「封建道徳」の構成の見事な表現だと思います。
そんな風に出来上がっている旧道徳については、
・事実上有り得べからざる事を無理に注文するのだから、冷静な科学的観察が進んでその偽りに気がつくと同時に、権威ある道徳律として存在できなくなる
と、冷静に切り捨てられています。
封建道徳に限らず、ある種の熱血ドラマなどでは、
「人間一生のうちで数えるほどしかない僅少の場合」の
「情火がパッと燃焼した刹那を捉えて、」
「二六時中すべてあのごとくせよと命ずる」類のお説教が出てくるものを、かつてはしばしば見かけた気がしますが。
「事実上有り得べからざる事を無理に注文するのだから、冷静な科学的観察が進んでその偽りに気が」つく。
まぁエンタメ作品なら、ある程度、荒唐無稽な筋立てが出てきたっていいでしょうけど。
ありがたいことに、というべきか。
今ではスポーツ漫画とかでもこういう無茶な要求は、滅多に見なくなった気はします。
(以下、工事中。)
※引用文中の「アルトルイスチック」=altruistic。利他主義。egoistic の反対語……とのこと。
