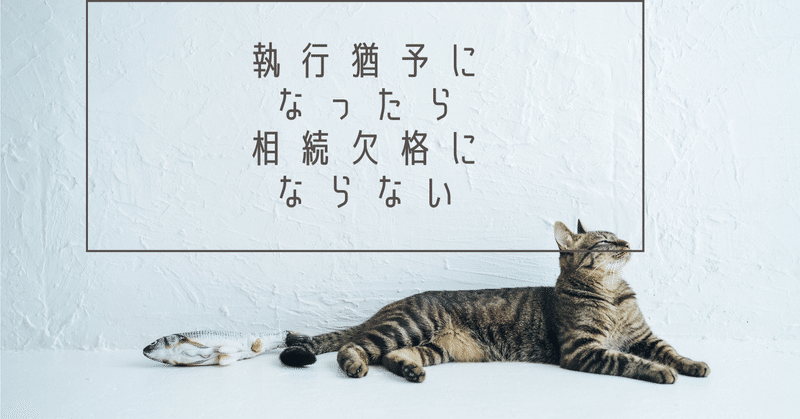
扶養 相続 特別受益者 寄与分など 今日の民法34
○扶養費の求償権が裁判等になった場合
・要扶養者からの請求は 家裁の審判
・他の扶養義務者からの求償 家裁の審判
・第三者からの求償は 民事訴訟
相続
・配偶者の連れ子は代襲相続はない
・執行猶予になったら相続欠格にならない
・認知の遺言を破棄隠匿したら欠格
・未成年後見人の指定の遺言を破棄隠匿しても欠格には当たらない
(認知は相続人が増えるので相続額が変わってきてしまうため)
・欠格を許すことはできない
・廃除は遺言執行者からする(条文)
○相続の可否
・仲介委託契約の委託者受託者の地位は相続されない
・組合員の地位は相続されない
・身元保証人の地位は相続されない
・賃貸借の保証人の地位は相続される
(単なる保証人)
・理事の妻に払われた死亡退職金は妻の権利であり、相続したわけではない
・相続分の指定があり遺言執行者がいる場合は遺産分割できない
・債権相続の対抗要件の通知は受益相続人から内容を明らかにしてする
(相続人全員とすると損をする相続人が通知に協力しないことも考えた特則)
○指定相続分に応じた債務承継の債権者比較
・法定相続分で請求しても後から指定相続分に請求を変更できる
・指定相続分で請求した後、法定相続分に変更して請求できない
特別受益 寄与分
・特別受益の持ち戻しの贈与の価値は贈与時
贈与後の増減額、受贈者の故意過失により滅失した場合でも贈与日の金額を持ち戻し計算とする
・婚姻関係「20年」以上夫婦で遺贈、贈与をした場合は持ち戻し免除と「推定」される
・相続人以外の親族の特別寄与料の支払い請求、相続を知って6ヶ月、相続から1年
・相続分の譲渡をした相続人もその譲受人も双方債務を負う
遺産分割
・遺産分割は一部の分割もできるが、割合的一部の分割はできない(どれを分割できるのかわからない)
・遺産分割禁止は最高5年更新OK
ただし相続から10年を超えることはできない
・10年経過後の遺産分割は特別受益、寄与分は請求できなくなる(令和3年改正)
ただし10年経過前に1人でも相続人が遺産分割の請求をしていれば他の相続人も具体的遺産分割によることができる
また10年経過「後」相続人全員の合意でも具体的相続分による分割ができる
・債務不履行の遺産分割解除できない
(債務不履行は相続財産の承継とはまた別の事柄であるから)
・合意による遺産分割解除できる
○・相続が開始すると債権は当然に分割帰属し、遺産分割の対象とならない
・預貯金債権だけは当然分割はされず、遺産分割の対象となる(金銭と同じ性質を考慮し同じ扱いとした)
・預貯金債権の1/3に法定相続分の払い戻しの制度は資金使途は指定されていない
またその払い戻した金額は改めて遺産分割の対象にならない
お疲れ様でした♪
関連記事もよろしくお願いします!
次の記事
前の記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
