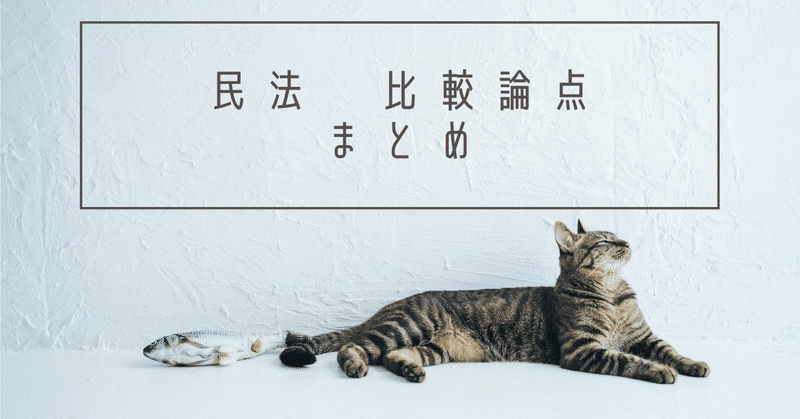
民法比較論点 類似論点を比較して理解を深める
総則
○・賃借人の内縁の妻は夫死亡時に相続人からの明け渡しに権利濫用で拒める場合がある
・賃借人の内縁の妻は夫死亡時に相続人がいなければ借家権を承継できる(借地借家法)
○ 報酬の決定
・任意後見人の報酬は契約で定める
・任意後見監督人の報酬は裁判所が定める(監督人は裁判所が決めるから)
○利益相反
・親子共有で子の共有持分放棄を親が代理しても利益相反にならない
間違えて特別代理人審判で選ばれたらそれはそれで有効
特別代理人がした放棄等を取り消しもできない
・代表取締役共通会社共有の持分放棄は利益相反になる
・相続の時に親が子に代わって放棄すると利益相反
○利益相反比較
・「第三者の債務に親権者と子が連帯保証人」になることは利益相反(親が求償権を得るから)
当然さらにその担保で子の不動産に抵当権設定ももちろん利益相反(親の債務担保)
・第三者の債務を担保するため、親権者が未成年の子を代理して子の不動産に抵当権を設定することは、利益相反行為に当たらない。
・子の債務に親が連帯保証人になることは利益相反とならない
・手形を親と子で共同所持している場合に親がその手形を他人に譲渡することは利益相反にならない
・親権者が未成年の子と共有する土地を、未成年の子に代わって自己の持分とともに他に売却することは、利益相反行為とはならない。
・親権者が子を代理して子と共同で合名会社を設立することは、利益相反行為とはならない
○後見、保佐補助の利益相反の違い
・保佐、補助の場合は利益相反で監督人がいない場合は臨時保佐人、臨時補助人が行う
・後見の場合は特別代理人が行う
○心裡留保の保護要件
・直接の相手方は善意無過失
・第三者は善意であれば足りる
○遡及効特約
・条件は双方の合意で遡及する特約を設けれる
・期限は合意があっで遡及する特約を設けれない(意味がないから)
○解除の遡及効、
・請負ある、
・委任.雇用.寄託.将来効
○追認先
・制限行為能力関係の追認は相手方にする
(制限行為能力者に追認しても効果はない)
○ 公序良俗違反
・不倫関係を廃止する対価として金品の交付をすることは無効
・不倫関係を、廃止をする際、慰謝料損害賠償として金品を交付することは有効
○追認の可否
・成年被後見人は後見人の同意を得ても追認できない(元から同意権がない)
・未成年者は法定代理人の同意を得れば追認できる
○ 復代理人選任の責任
・法定代理人 やむおえない事情がある場合
選任監督のみの責任となる
・任意代理人はそのような規定はない
(改正民法)
○無権代理人への損害賠償請求
・本人が追認をして契約が確定的に有効となった場合でも無権代理人への損害賠償請求はできる
・相手方が表現代理を主張し契約が確定的に有効となった場合、相手方は無権代理人へのの損害賠償請求はできない
(二重の利得となるから)
○双方の同意があれば例外が認められるもの
・追認は原則遡及効で遡及効排除ができる
・条件は原則将来効だが遡及させられる
○求償権の時効起算点と完成猶予の違い
・事前求償権と事後求償権の消滅時効の起算点は異なる
・事前求償を被保全債権として仮差押をしたら完成猶予の効果は事後求償権にも及ぶ
(合理的な意思を考慮して)
○時効援用の可否
・一般債権者は代位で、債務者に対する他の債権者の債権の時効を援用できる
・一般債権者から直接援用はできない
・保証人ほ主たる債務者の取消権を援用できない
・保証人は主たる債務者の消滅時効を援用できる
・連帯債務者は他の債務者の消滅時効を援用できない(履行拒絶はできる)
・物上保証人、第三取得者は抵当権の「被担保債務」の消滅時効を援用できる
・第三取得者は「抵当権」の消滅時効を援用できる
・物上保証人は「抵当権」の消滅時効は援用できない
・後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用できない(反射的利益に過ぎないから)
・詐害行為の受益者は被担保債権の消滅時効を援用できる(取り消される心配がなくなり直接利益を受ける)
・建物賃借人は土地に直接利益がないため土地の時効取得を援用することはできない
(建物賃借人は土地賃貸人不払いの賃料を払う利益はある)
・保証人が、債務の消滅時効を援用した場合に主債務者にその効力は及ばない(複数の援用権者がいる場合にそのうちの1人が援用しても他方には及ばない)
・主債務者が債務の消滅時効を援用すると付従性により保証人の債務も消滅する
○承認の効力の違い
・連帯債務者の1人が承認しても他の債務者の時効更新はない
・主債務者が承認をすると保証人にも効力が及ぶ(保証の付従性から)
○時効の援用
・物上保証人は主債務者の債権の時効を援用できるが抵当権の時効を援用できない
・第三取得者はどちらも援用できる
物権
○占有訴権違い
・占有保持の訴えで損害賠償請求するには故意過失が必要
・占有保全の訴えで損害賠償担保を請求するのは故意過失不要
・占有保持、占有回収の訴えは妨害の回復と損害賠償請求は併存する
・占有保全の訴えは妨害の保全と損害賠償担保は選択的 どちらか
(まだ妨害が生じていないためどちらかで十分だから)
○占有者と留置権者の違い
・善意占有者は果実を収得している場合は通常の必要費は償還できない
・留置権者が果実を収得している場合にも費用の償還ができる
(善意占有者は果実を収得すれば純粋にプラスだが、留置権は果実を収得すればその分債権が減っていく(充当)であるため)
・占有権の有益費償還の期限の許与は悪意者の場合のみ
・留置権の場合は善意悪意問わず許与できる
○即時取得の可否
・未成年者から物を購入した買主は、後に未成年者取消をされた場合、即時取得できない
・未成年者から物を購入した買主からさらに転売を受けた転得者は、後に未成年者取消をされても即時取得を主張できる(192条類推)
・無権代理人から取得した者は即時取得の適応がない(無権代理等の規定が意味なくなるからよってさらに転得した者は即時取得を主張できる)
(ただし無権代理人から取得したものが本人の物でもなかった場合には即時取得の適応がある)
・他人物売買(代理の意思がなく自己のものであるとして)の買主は即時取得の適応がある
○隣地の費用分担
・境界標の設置、保存は等しい割合
・測量の費用は土地の広狭の割合
○共有物分割の解除
・裁判による共有物分割は解除できない
・協議による共有物分割は解除できる
○ 共有農地の共有物分割による持分移転は許可必要、放棄は不要
○双方が履行していない場合
・売主は代金支払いまで果実取得ができる
・買主は引き渡しを受けるまでは利息の支払い、管理費用の支払いは不要
(便宜上の処理)
○動産の対抗要件の欠缺を主張できる第三者
・賃借人は当たる
・受寄者は当たらない(受寄者は478条の準占有者に対する善意無過失弁済の規定で処理するのが判例の考え)
○期間制限
・地上権、地役権は特にない
・賃借権、永小作権は50年
○留置権比較
・民法
牽連性必要
債務者以外の第三者の物を留置できる
○商人間
牽連性不要
債務者所有物
債権発生が商行為であることが必要
○代理商
牽連性不要
債務者以外の第三者の者を留置できる
(本人たる商人と代理商との商取引で占有したことも要しない) 代理商は,その業務の住質上、第三者から占有を取得したり、商人の所有に属さない物を商人のために占有することが少なくないため
本人たる商人のために占有している必要がある
○先順位抵当権被担保債権の時効援用できるかどうか
・後順位抵当権者できない
・第三取得者できる
○抵当権消滅の対抗要件
・抵当権の権利放棄による消滅は登記なくして第三者に対抗できない
・抵当権の弁済による消滅は登記無くして第三者に対抗できる
○抵当権の物上代位の差し押さえ
・抵当権の被担保債権の弁済期到来は必要
(抵当権の実行であるから)
・差し押さえ債権の弁済期到来は不要
(差し押さえは弁済を強制するものではないし弁済期が来てしまうと弁済がされてしまい差し押さえができなくなってしまう)
○ 後順位抵当権者、時効援用できない
仮登記担保に遅れる抵当権者、予約完結権の時効の援用できる
・被相続人が生前抵当権を設定したが登記をしていない場合で限定承認がされた場合登記請求ができない
・被相続人が生前抵当権を設定したが登記をしていない場合で仮登記も入っていない場合は
相続財産法人に登記請求できない
○ 抵当権消滅請求 無償譲受でもできる、対価弁済無償はできない
保証人 消滅請求できない 対価弁済できる
○確定後の根抵当権
・根抵当権極度額減額請求、設定者兼債務者も請求可能
・根抵当権消滅請求、設定者兼債務者は請求不可
○根抵当権の確定期日の登記の効力
・新設 登記は対抗要件
・変更 登記は効力要件
○質権の存続期間
・不動産質は10年が最高(定めがない場合も10年となる)(更新は可能、更新時から10年)
・動産質権は制限はない
○承諾転質 責任転質比較
・原質権の被担保債権額を超える部分
承諾転質 有効
責任転質 無効
・原質権の存続期間を超える部分
承諾転質 有効
責任転質 無効
・転質権の実行における原質権の弁済期到来
承諾転質 不要
責任転質 必要
債権
○選択債権の選択権者が第三者の場合は
選択の通知は債権者債務者どちらでも良い
選択の撤回は債権者債務者両方にする
○ 選択債権、第三者選択できないしたくない時の債務者への選択権移転、履行期到来不要催告不要
債務者から債権者その逆は履行期到来催告の上選択なしで移転
○同時履行の抗弁権
・債権が譲渡された場合譲受人に抗弁権を主張できる
・目的物が譲渡された場合主張できない
○ 特別受益証明作成
・特別受益者が行方不明の際不在者財産管理人は特別受益証明書を作れない
・特別受益者の相続人の1人が行方不明の場合他の相続人と共同で不在者財産管理人が証明書を作れる
○債権譲渡と債務者の抗弁の優劣
・原則債権譲渡の対抗要件は債務者の抗弁取得の先後
・譲渡制限付に悪意ある債権譲渡の場合は債権譲受人が債務者に対して債権譲渡人に支払うよう催告し相当期間経過と債務者の抗弁取得の先後
・第三者対抗要件具備全額債権譲渡で債権譲渡人が破産した場合は債権譲受人の債務者への供託請求と抗弁取得の先後
○悪意の債権譲渡がされた譲渡制限付債権差し押さえの可否
・譲渡制限付き債権譲渡の悪意の「譲受人」の債権者が差し押さえた場合は債務者は履行の拒絶ができる
・譲渡制限付き債権譲渡の悪意の「譲渡人」の債権者が差し押さえた場合は債務者は履行の拒絶ができない
差押、転付債権者への履行拒絶の可否
・譲渡制限付き債権を差押、転付命令を得た債権者に債務者は対抗できない
・譲渡制限付き債権の悪意又は重過失ある譲受人の債権者が差押又は転付命令を受けた場合は債務者は履行を拒絶できる
○予めの通知承諾の可否
・債権譲渡の前に予め通知をしても無効
・債権譲渡の前に予め承諾をするのは有効
(譲受人が特定されていれば)
(債務者保護の観点)
また譲渡が実際された際に対抗力が備わる
○将来債権譲渡と債権譲渡予約の違い
・債権譲渡予約の際に確定日付ある通知をしていても、債権譲渡をしてから通知しなければ対抗要件は備わらない(債権譲渡が確定的にされたことを債務者を等して公示するものである)
・将来債権を譲渡して対抗要件を備えることはできる(確定的に債権が移転しているから)
○第三者弁済の可否
・第三者弁済禁止合意があれば
正当な利益あるでも第三者弁済はできない
・第三者弁済禁止合意がない場合に、正当な利益があれば債務者の意思に反しても弁済できる
・第三者弁済禁止合意がない場合に、正当な利益がなければ債務者の意思に反して弁済できない
ただし債権者が善意で受領した場合は有効となる
・債権者の意思に反した正当な事由のない第三者弁済はできないが、第三者が債務者の委託を受けて弁済することを債権者が知っていた場合は弁済は有効となる(この場合は任意代位となる)
○保証人が求償できる範囲の違い
・債務者の意思に反しない場合は
(当然委託を受けた保証人も同じ)
債務消滅時点で債務者が利益を受けている範囲で求償できる
・債務者の意思に反している場合は
求償時点で債務者が利益を受けている範囲で求償できる
(保証人債務弁済→主債務者全額反対債権取得→債務者へ求償 の順番の場合
意思に反しない保証人は求償できる
意思に反する保証人は求償を拒まれうる)
○保証人と主債務者の通知義務比較
・受託保証人は主債務者に、事前事後双方通知必要
・委託なき保証人は主債務者に事後通知必要 事前は不要
・主債務者は受託保証人には事後通知は必要だが事前通知は不要
・主債務者は委託なき保証人に事前も事後も通知不要
ここから先は
¥ 177
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
