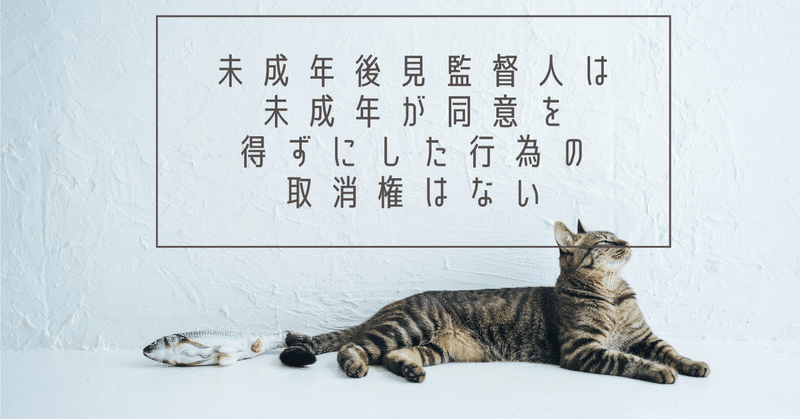
後見など 今日の民法35
・未成年後見人を指定できるのは最後の財産管理権のある親権者が遺言でする場合のみ
・未成年後見監督人は未成年が同意を得ずにした制限行為の取消権はない
・被後見人、被保佐人が後見人になることはできる
・家裁の許可が必要な成年被後見人の居住用不動産の処分には
売買だけでなく賃貸、賃貸の解除も含まれる
・郵便物の管理制度(伸長不可最長6ヶ月の後見人配達)と被後見人の死後事務の特定財産保存、債務弁済、家裁許可による火葬埋葬関する権限の制度は
成年後見のみが対象
任意後見、未成年後見、保佐、補助ではこの制度はない
○遺言で指定できるかどうか
・未成年後見監督人は遺言で指定できる
・成年後見監督人は遺言で指定できない
・未成年後見人複数の場合、共同で行うが財産管理については分掌、単独で行うことを家裁が定めることはできる
よって身上監護を単独行使もしくは身上監護のみしかない未成年後見はない
単独財産管理のみの未成年後見人はあり得る
○後見、保佐補助の利益相反の違い
・保佐、補助の場合は利益相反で監督人がいない場合は臨時保佐人、臨時補助人が行う
・後見の場合は特別代理人が行う
・任意後見、公正証書による 必ず後見監督人がつく、後見監督人が選任された時からスタート 代理権のみ 同意取消権なし 報酬は契約で定める(委任契約なのでまだ定めなければ無償) 比較で監督人の報酬は家裁が定める
後見開始前の解除は公証人の認証がいる(公正証書でなくとも良い)
後見開始後は家裁の許可と正当自由で解除できる
・成年後見人、任意後見は登記
未成年後見は戸籍記載
お疲れ様でした😊
よろしければ関連記事もどうぞ😊
次の記事
前の記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
