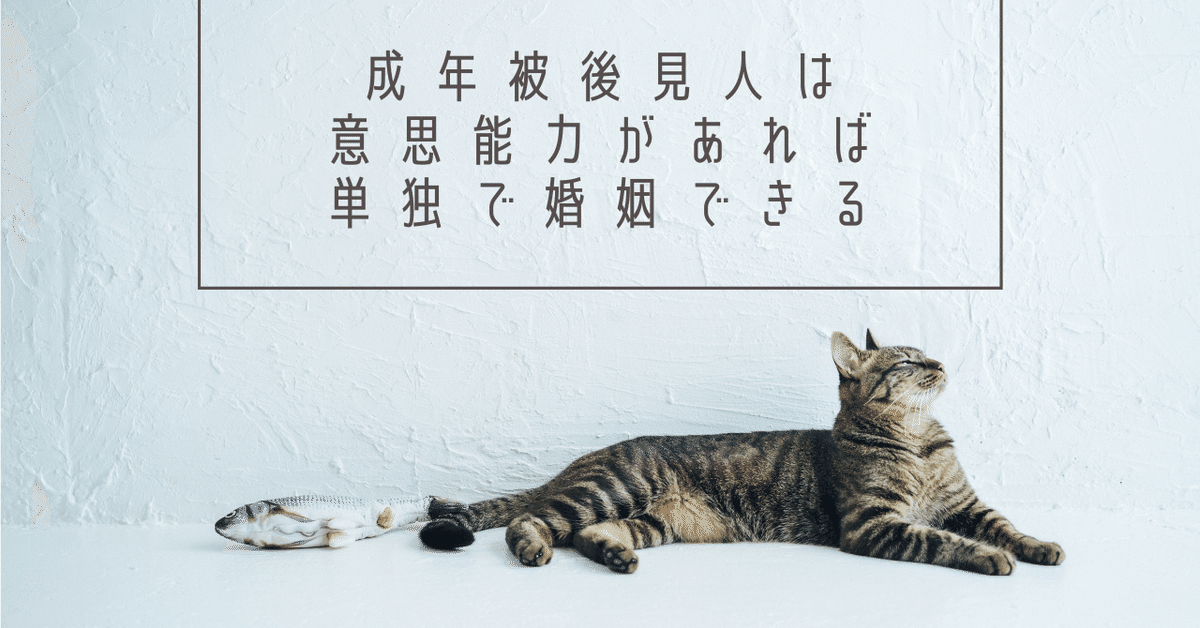
婚姻 離婚 内縁など 今日の民法32
婚姻
・婚姻は婚姻と見られる生活共同体を創設しようとする意思がなければならない
相続をさせるためだけの婚姻無効
嫡出子身分を取得させるための婚姻無効
・成年被後見人は意思能力があれば単独で婚姻できる
○重婚を理由とした後婚取り消しができるか
・重婚になっていても、その後前婚が離婚した場合、前婚の「配偶者」が亡くなった場合、後婚が離婚した場合は重婚を理由とした取り消しはできない
重婚者が死亡した場合は依然として後婚の取り消しできる(後婚配偶者の相続権を遡及的に失わせるため 前婚の配偶者も後婚を取り消し可能)
・近親婚の禁止直系血族直系姻族の禁止は
離縁や離婚による、親族関係、姻族関係終了後でも禁止
○比較
養子の縁組後に生まれた子と養親は離縁後にも
婚姻できない
養子の縁組前に生まれた子と養親は離縁後にも
婚姻できる(縁組前の子と養親には親族関係ははじめから成立しないから)
・いとこと結婚できる
(近親婚の禁止は3親等のところいとこは4親等だから)
・婚姻が無効であれば初めから無効なので相続権も当然無効となる
婚姻取り消しは身分関係取り消しは遡及しない
財産関係は遡及効ある
この場合の不当利得は自己が取り消し原因に善意であれば現存利益を返す
自己が悪意で相手方悪意の場合は利益全部
自己が悪意で相手方善意の場合は利益全部+損害賠償必要
比較で離婚取消は身分、財産双方遡及
利益返還は婚姻取り消しと同様
○婚姻取り消しは基本、各当事者、その家族、検察官(双方生存中)ができる
詐欺強迫の取り消しは各当事者のみしかできない
不適齢婚は適齢に達したら取り消しできない(不適齢者本人は適齢から3ヶ月はできる
・重婚の取り消しは前配偶者の親族はできない
・夫婦間の取り消しは既になされていても書面による贈与でも取り消しができる
・夫婦間の取り消し権は通常の時効にかからない
・夫婦財産契約は原則後から変更できない
・配偶者死亡後の姻族関係終了の届出は配偶者からしかできない
死亡したものの親族からはできない
離婚
・離婚は形式的な意思でできる
(内縁関係に移行する自由があるから)
・監護者は第三者で良い 離婚後に決定しても良い
○・離婚の取り消しは身分関係も、財産関係も遡及する
・婚姻取り消しは身分関係は遡及しないので注意
・出生前に父母が離婚した場合子は離婚の際の氏となる
・離婚の際子の氏は離婚の際の氏
もう一方の親の氏に変更するには家裁の許可が必要
内縁
・内縁の不当な破棄は債務不履行、不法行為どちらもあり得る
○・賃借人の内縁の妻は夫死亡時に相続人からの明け渡しに権利濫用で拒める場合がある
・賃借人の内縁の妻は夫死亡時に相続人がいなければ借家権を承継できる(借地借家法)
・内縁夫婦の共有不動産で内縁の夫が死亡した後内縁の妻が1人で住んでいた場合、その相続人は単独使用分の不当利得返還請求ができない
(一方が死亡した場合は単独使用を承認していたと推定する)
次の記事
前の記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
