
【詩人の読書記録日記】栞の代わりに 2月27日~3月5日
はじめに
こんにちは。長尾早苗です。深夜型になってしまった自分を許せるようになりました。深夜から早朝まで集中して仕事をしています。今週もよろしくお願いします。
2月27日
よく眠った日! そしてよく読んだ日! 内装工事が終わりました。
体の変化が29歳になってから現れ始めたのか、なんだか眠い日が続きます。
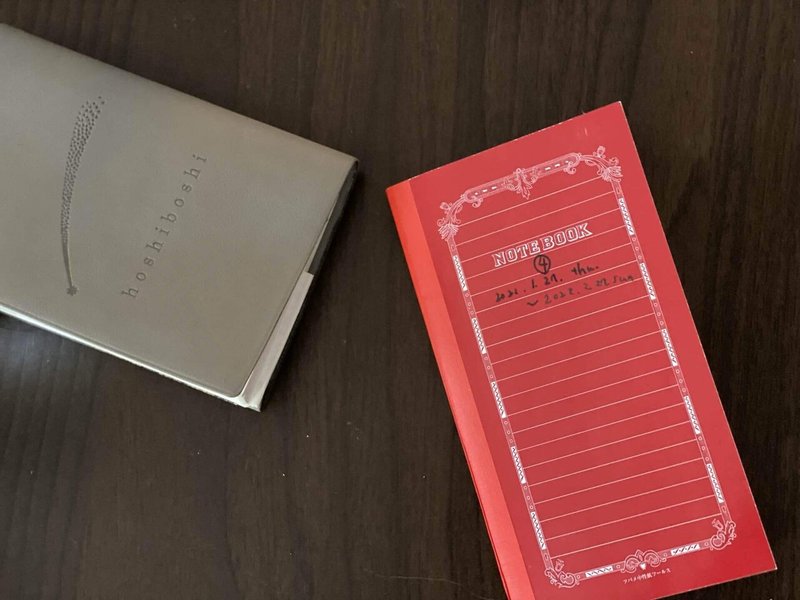
・田中佳祐 竹田信弥『街灯りとしての本屋』雷鳥社
本屋、ということ、本について本当に熱い思いを持った人々が作る場所として、本屋があるのだと思います。
一冊の特別な本を誰かに手に取って欲しい。
そんな思いで、彼ら彼女たちは街の風景に溶け込んでいき、どんな人でも居心地の良い場所としての場づくりに励んでいます。
わたし自身、本を書く身として本屋さんとはご縁がありますが、どのような経営なのかや、本屋を開くにあたってのノウハウなど、さまざまなことを学べた一冊でした。
・萩原朔太郎『猫町他十七篇』岩波文庫
朔太郎の、小説というより散文詩に近い形だと思います。
発想がやはり詩人だなということ、それは日常を見つめてそれを拡大していく書き方と視点ですが、そういうものに長けていると感じました。
朔太郎の人生についても多くの人が述べていますが、彼の詩人として生きる道も、こうやってさまざまな媒体を取りながら進んでいったのかもしれません。
どこか狂気と夢と現実の狭間で生きているように思います。
・小川洋子『夜明けの縁をさ迷う人々』角川書店
小川洋子さんは毎週彼女の読書ラジオを聴くほど好きな作家さんなのです。
彼女が書く小説はどこかアンバランスなものを秘めています。
あと、野球がお好きなのでしょうか。
生と死の狭間で、狂気と現実の狭間でどこか揺れ動く人々。
そんな中で書かれている短編集です。小川洋子ファンにもゾクゾクくると思いますし、彼女の書く物語のアンバランスさにも触れることができます。
・小川洋子『原稿零枚日記』集英社
作家にとって、原稿とは自分との戦いでもあり、そして書けない自分にとてもイライラとしてしまう仕事です。
しかし、書いた原稿を捨てるとしても、休むことなく書き続けなければいけない宿命を持っているし、そこで何枚書けたかで仕事量が決まってしまう。
小川洋子さんのこのエッセイ寄りの物語では、フィクションとノンフィクションの狭間で、小説家としての作家のある種運命的な要素を孕んでいるように思います。
一つ一つの見出しの最後にある原稿用紙何枚という記述が、その職業としての厳しさを物語っているように思いました。
・ジョン・チーヴァー 村上春樹訳『巨大なラジオ/泳ぐ人』新潮社
チーヴァーという作家については初めて触れたのですが、村上春樹さんの文体はやはり翻訳・英語と、とても親和性があるように思います。
とても正気ではいられないような現実の中で、それでも日常を続けていく物語をチーヴァーは書いていますが、それは現代を生きるわたしたちにもつながっていると思っていて。
その物語を、村上春樹さんがわかりやすく翻訳してくれてありがたいです。
・オグ・マンディーノ 菅靖彦訳『この世で一番の奇跡』PHP研究所
幸せになることを、おそれてはいけません。
いつか幸せがやってくることを、おそれてもいけません。
このエッセイのような物語では、その勇気が「信じる」という形で表されています。
それが作者にとってはキリスト教の神であったり、何か信じるよすがとなっていたのでしょう。
どんな人も幸せになっていいし、どんな人でも幸せに祝福される時はくると思っています。
2月28日
29歳になって2週間目が経とうとしています。
28歳の頃はホルモンバランスもめちゃくちゃだったため、落ち着いた29歳から30代を迎えられればいいなと思っていました。
29歳になっていきなり中也賞の発表があり、安心して落ち着いて、
もろもろプレッシャーから逃れられて、今は仕事終わりの強烈な眠気と闘っています。
それでも、28歳の頃よりは落ち着いたと相方さん。
これからも色々なことがあるかもしれないけれど、一緒にこの緊迫した今を生きていければいいな。
去年参加した村上春樹ライブラリーでの連詩が公開されました。ぜひご覧ください。1班の(さなえ)がわたしです。
3月1日
朝、自分の仕事でミスをしてしまい、情けなくなったことがあったので、この日はいつもより動いてウォーキングして、汗をかいて午後のコーヒー後に相方さんと話し合っていました。それからは自分のなかでも整理がついて笑い合うことができるようになって、相方さんに感謝です。新作1編。

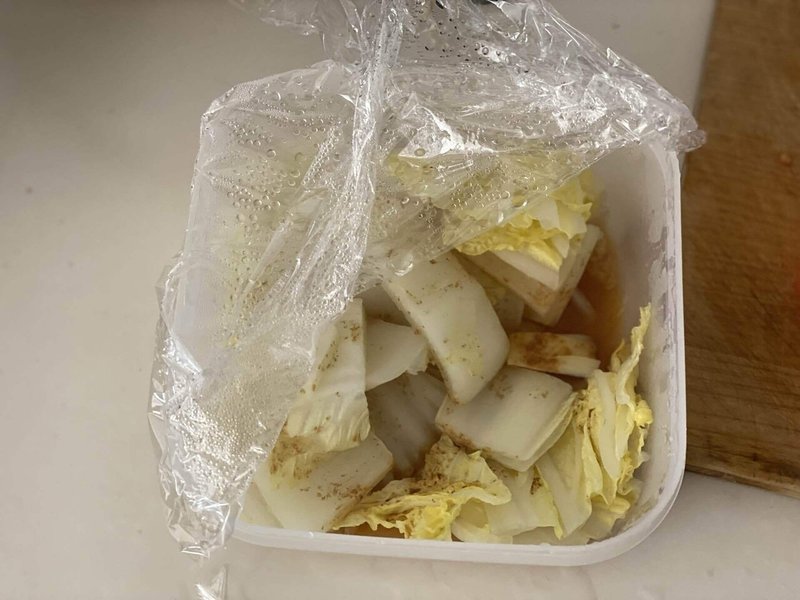







3月2日
今日は定期検診その1。病院に行きました。
今まで少し遠出だったので、近くの病院に転院することにしました。
小さなころから本当にお世話になったし、感謝しかありません。
先生からはすごく落ち着いているから大丈夫だよと笑顔で言われました。
ついつい眠りすぎてしまう体質のわたし、なんだか胸がいっぱいで……。
先生とのお別れをさみしい一日にしたくなかったので、帰りに奮発してハンバーグ屋さんでハンバーグをランチでいただきました。
心も体も潤いました。
明日は読書日和にします。新作1編。


3月3日
ひな祭りですね! なんだかにぎにぎしい気持ちになります。
わたしも今は在宅フリーランスで主婦で母親ではありませんが、どんな女の子でも、どんな女性でも「かつては娘だった」ということを思い起こさせる日だなあと思っています。
たくさんの選択肢と、やらなければならないことに満ち溢れているけれど。
わたしもそして母親やわたしと同じようなアラサーを生きる女の子たちも、みんなかつては娘だった。
そして、そこに帰っていくんですね。
今日は、そんなことを思いつつ、瀬戸内寂聴先生と伊藤比呂美先生の著書を読んで来ようと思います。
女にはできることがたっくさんあるとわたしに教えてくれたお二人です。
今日はバスに乗って図書館に遠征してきます。

・外山美樹『勉強する気はなぜ起こらないのか』筑摩書房
わたしは割とやる気をコントロールできているのかもしれません。
一緒に暮らしている相方さんから、時間を区切って生活することとポモドーロを教えてもらい、この本で言えば内的動機として、目標を常に持つこと。
そして、毎日のタスクをリマインダーで整理すること、時間と環境を変えることを学びました。
それがわたしが周囲に与える「やる気」の波及効果なのかもしれません。
この本は先週の宮スケ今週本で宮崎智之さんが紹介しておられて、在宅フリーランスの作家としてとてもわかる気持ちになったので読んでみました。
・ボッカッチョ 平川祐弘訳『デカメロン上中下』河出文庫
さまざまな老若男女が、10日間100の物語を語り合う。
それは、ペストでのパンデミックの中、行われたものでした。
パンデミック小説として名高いデカメロン。
アメリカのニューヨークでは2020年に一番売れた本らしいです。
わたしとしては初読になってしまいましたが、この流行病の中で読んでみる、また今の情勢の中読んでみることは大事かなと思って読んでみました。
物語を語る時、ある種人は自分の内側を癒していくものだとひしひしと感じます。
それが毎日続く日々は、疲れ切って消耗したパンデミックの中で、人々をどう転換させたのか。
これから生きる道標として読みたい本です。
・瀬戸内寂聴『愛することば あなたへ』光文社
女性の作家が恋について書く時、そして女性たちに書く時、それは女性男性と分ける分け方ではないかも知れませんが、時として愛について語る時。
わたしは彼女たちが何物かに恋しているのを知っています。
なぜなら、わたしが書く時にことばに恋したり、問題に恋していることを知っているから。
果たして恋とは、愛とはなにものなのでしょう。
その先に見据えた創作というものはなにものなのでしょう。
覚悟を決めて書くことがわたしの一つの答えかなと思います。
・瀬戸内寂聴『いのち』講談社
長く女性の作家として生きていると、
恋すること、結婚すること、仕事をすること、そして子供を産むこと、親の介護、そういったさまざまなライフイベントに自ずから立ち向かうことになります。
それはどれも平坦な道ではないのですが、なぜかわたしたちはその苦楽を求めてしまう。
もがき苦しむことを求めてしまう。
それがきっと生きるということなのでしょう。
寂聴先生はそれをよく理解して、作家として書き続けておられたのだと思います。
どうか、成仏してまたあの世で会える日まで、またわたしも書き続けていきます。
・伊藤比呂美『切腹考』文藝春秋
自ら命を絶つこと、その壮絶さを体験しながら、生きるということを懸命に感じ取る。
英語圏という中で、伊藤比呂美先生が感じ取ってきた生きるということ。
それは、女性として生きること、
詩人として生きること、
日本語話者として生きること、
その全てのように感じます。
命果てるまで、きっとわたしたちはもがき苦しむでしょう。そして、そこから穏やかになっていく瞬間が、もしかしたら作家としての生命の新たな始まりなのかもしれません。
わたしは伊藤比呂美先生よりだいぶ年下ですが、
比呂美先生も寂聴先生も、
血を流しながら書いてきた感じがすごく感じ取れて、その中で穏やかになっていく29歳という問題を抱えています。
その中で、相方さんとどうこの読書と創作の毎日を送っていくのか。
ぼうっと、生きること、暮らすことと書くことが一体になっている今日この頃を考えます。
・伊藤比呂美『木霊草霊』岩波書店
どんな命にも、かたちがあります。
それが、動物の姿をとっているか、植物の姿をとっているかの違いだけで。
比呂美先生がこれを書かれたのは『犬心』と同時期だったようで、
さまざまないのちというものを見つめて書かれていらっしゃるのではと思いました。
自分が生きてきた場所に、宿るもの。
それが植物です。
植物のいのちです。
場所に宿るって結構大事で、そこに根を張るか、
たくさんの場所を彷徨うかで人は生き方として根本的に違うのかもしれません。
わたしは多肉植物とあじさいたちと暮らしています。
彼女たちが辿ってきた花の命。
またこの夏もあじさいは咲くかもしれません。
長い命なので。
・伊藤比呂美『女の絶望』光文社
女が生きていくこと。
睦み合うこと、そして恋すること、なにかしら絶望すること、
そういうことを繰り返しながら女は悩んでいくものなのでしょうか。
でも、人が生きていく道は苦悩ばかり。
詩人は語ります。
何事もOKだと。
それでも、理不尽な殺し合いだけは避けなさいと。
詩人は語るために生まれてきたもののようなものです。そして食えません。
それでも、生きていくことを大切にしていきたいです。
・伊藤比呂美『犬心』文藝春秋
伊藤比呂美先生と過ごした、生きてきた犬達。
そして、家族ということ。
お母さん。
子どもを産む、産まないにかかわりなく、わたしたちは何かで家族とつながっているような気がするし、これから何事かで家族になる人が現れる可能性もあります。
それは、人を追い求める気持ちと同じで、
人間も犬も猫も変わらないかもしれません。
そして、制度上は家族でないにしろ、やがて家族になっていくというものもあります。
犬と心が通ったら、わたしはお母さんになる。
実家にいた時は犬のお姉さんでした。
なんとなく、目の前の植物たちを眺めています。
・伊藤比呂美『日本ノ霊異ナ話』朝日新聞社
人間の業。
人が人を求めたり、獣と睦み合ったり、
人間というものにはよくわからない業があります。
それでも世は末ですが、
死ぬまで生きる。
それこそがこの世の中で生きていくために必要なただ一つのことなんじゃないでしょうか。
わたしがいずれ死んでしまうとしても、
わたしたちのことばはいずれ残ります。
それを誰かに託しながら、日々死ぬまでの期間を生きているのだ。
終わりを見ながら、それでも生きていくのだ。
と、思います。
・朝井リョウ『もういちど生まれる』幻冬舎
朝井さんとはかなり歳が近いように感じるのですが、彼の描く大学生、そしてそれから大人になっていくもがきというものは多くの人のリアルでもあります。
あまりにそれがリアルで、そしてリアルタイムで進行しているものでもあり。
それでも、リアルタイムであった頃を懐かしく思い出したい。
そんな思いを持った時に読みたい作家さんです。
この本は2011年に出版されました。
わたし自身が大学受験を終えて、これからの生活についてときめいていた頃に起きた震災、それからのパニックの日々。
なんとか入学できて、駆け抜けてきた日々。
そして、それを分かち合った同期たち。
色々な意味で、この一冊に書かれた子たちのように、駆け抜けて、生き抜いてきた感じがあります。
あの震災のこと、そして今目の前に起こっている現状を見続けるのはすごく難しくて苦しいものがありますが、その中で守り抜くものが何になるか。それは、わたしには自分の中での生活における生きたことばだと思っています。
だからこそ、わたしは日々、生きるように書いていきます。
3月4日
服を買いました! なんでだろう、空がとてもきれいだったことを記録しておきたい。
昨日は夕寝してしまったのでラジオを聞けず、今朝追っかけで聴きました。
体調の変化があったのか、ぼうっとAirPodsを図書館に持っていくのを忘れてしょんぼり。AirPodsとポモドーロがないとわたしは読書に集中できないんです。あとは深夜と早朝の作業かな。


・川上未映子『魔法飛行』中公文庫
時として、何かに絶望したくなる時。
本当はそんなこと起こっちゃいけないのだけど。
わたしは言います。深く傷ついていました。
それでも春の服を着て今日も読むぞと思っていたらAirPodsを図書館に持っていくバックの中に入れるのを忘れて、ポモドーロどころじゃなくてまたしょんぼりしました。
そしてそれ以上の出来事で泣いている人々を思いまたしょんぼりしました。
わたしにはまだ仕事があるのに。
この一冊には、そんな「仕事があるのになんだか悲しい」気持ちと共に体調不良が続いていた川上未映子さんのエッセイです。
ちょっと救われたというか。震災という出来事と向き合いながら、消耗していく自分自身をまっすぐに見つめ、それは時にうちなる小さな叫びであるように思いました。
・川上未映子『人生が用意するもの』新潮社
震災のとき、そして今の情勢からして、
わたしもうまくやる気をコントロールして仕事をしないといけないわけでして、
それは書くということ、そして書き続けるということでして、
そしてそれがまた誰かに届くのを待つように、自分の中で感情をあたためさせるものでもあるのですね。
わたしはそれをギフトだと思っていて、
川上未映子さんが震災後何を原稿に書いてきたのか、そして妊婦という不思議にどう立ち向かっていって仕事をしていたのか。
それは同じ女性詩人としてすごく興味があったことでした。
仕事に集中するあまり外には出られないのだけど、わたしは歩かないと書けないので、ある種通勤のように歩いているのが現実です。
それでも憂うつになってしまって仕事も何もできなくなるよね、と思う3月。
そうだよね、と思う一冊でした。
・朝吹真理子『きことわ』新潮社
心を整えたいときにこの本を開く気がします。
とても大切にしたい本。朝吹真理子さん。
とても静謐で、それでいて写生的でもあり、
その中に上品で知的なことばが織り混ざっている。
わたしはとても感謝しなくてはいけない方の近しい方でもあるので、
やっぱり読んでみたいと思いました。
女だということを一種他の作家とは目線が違うところで書いていて、そこになんというか、静謐だけど逞しい、でも儚い音楽が流れているような気がする。
・太宰治『惜別』新潮文庫
明るさは、滅びの姿であろうか。
まだ見れていないんですよね、大河ドラマ。
今週見よう、見ようとしているのに夕寝してしまって、普段つけることのないテレビを見るという習慣をなくしてしまって。
ただ、この物語を読むとなんだか春の悲しみと気だるさにとらわれてしまって泣きたくなります。
春は色々な気持ちが混じる季節。
それを自分がいる現在地として肯定していくのか、太宰治のように真っ向から否定していくのか。
わたしたちにはその選択が待ち受けています。
それでも、死ぬまで生きていくしかないし、生きていくことはわたしにとって書くことであり仕事でもあるので、死ぬまで仕事は続くわけです。それでも、そのことを肯定し続けていきたい。
わたしが死んだ後もわたしのことばが残るとしたら、今のこの情勢を何か記録として残した詩人になると思うんです。だからこそ、詩人たちは流行病の時期に日記を書いていた。
わたしも続けようと思います。
どこにも発表していない、誰にも見せていないクラウドメモの日記があります。
わたしがいなくなったら、ささやかな29歳も30代もそれ以降も生きたであろう詩人の記録を読んでください。
・尾崎翠『第七官界彷徨 他四篇 琉璃玉の耳輪』岩波文庫
尾崎翠についてはすごく好きです。
わたし自身この心と体が変に分離してしまう感覚をきちんと書けた作家って少ないと思いますし、彼女にはもっと書いてほしかった。
なぜこれ以降書かなかったのかはすごく謎なんですが、
彼女にもっと理解のあるパートナーがいたらなあとしんみり思うんです。
彼女と感覚を共有したい、
それがどんなに分かり難いものであったとしても。そういう人が現れないと、こういうものを生涯書き続けていけないと思うんですね。
内的世界と外部の世界、そして、精神世界の美しさに到達するまでの道を、書いていくのが作家であり詩人です。
わたしはそれを、書いていく。
・ほしおさなえ『ヘビイチゴ・サナトリウム』
東京創元社
ほしお先生の作品の中では読んだのが久々か、多分すっごく昔に読んで忘れていたのかもしれません。
ほしお先生のミステリーは色々と考えさせられるものがあって、
人が生きていく理由を当時の作者としてももがきつつ探していたような気もするんです。
でも、それから年代を経て、先生の『活版印刷三日月堂』を読んだ時にわかりました。ご一緒させていただいた時間全てが宝物のように輝いていて、それはまだ輝き続けていくと。
先生がこの小説を書き始めた時、多分わたしたちフェリスの学生を教えるとか、震災のこととか、そしてほしのたねや流行病のなかでの星々の誕生など、思いもしなかった生きる理由が、生まれていったように思うんです。
わたしはそれを、希望と呼びたい。
こんなふうにミステリーの中で自死を遂げてしまう若い子たちも、
歳を重ねるのは悪いことじゃないよ
とわたしは微笑んであげたい。
死ぬまで生きて。
3月5日
生きていくために書こう。
わたしたちがいなくなったら、クラウドメモに残した日記を、読んでもらおう。
そんな思いで、毎日、毎時間変わっていく感情や出来事を連ねていきました。
今日、きっかけがあって朗読の先輩と少しラインしました。ありがたかったです。
そして、近々詩集のことでよいニュースをすることもできるかもしれません。
うれしい知らせが舞い込みました。来週も忙しくなりそうです。
どうぞ、来週からもよろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
