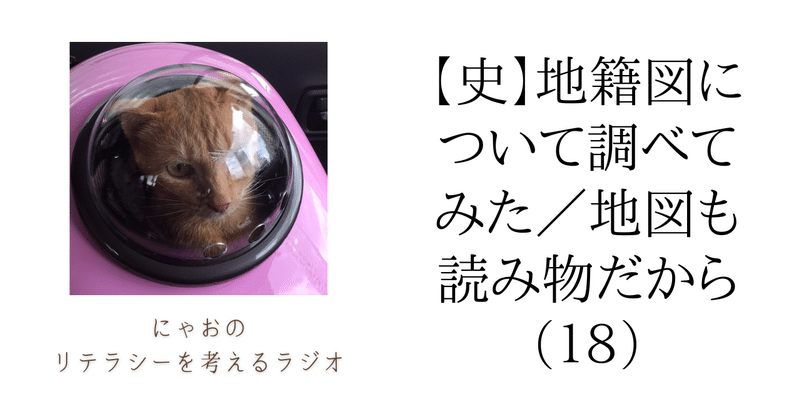
【史】地籍図について調べてみた/地図も読み物だから(18)
聴いてみよう
この記事は、Podcast「にゃおのリテラシーを考えるラジオ」の2023年2月25日配信の書き起こしです。
読んでみよう
にゃおのリテラシーを考えるラジオ
読書と編集の千葉直樹です。
このチャンネルでは、読書と IT 時代の読み書き、そろばんを中心に様々な話をしています。
今回のタイトルは、
【史】地籍図について調べてみた/地図も読み物だから(18)
です。
土曜日は地図を読む話をしています。
地図と言ったら?
あなたが地図と言われてイメージするものはどんなものでしょう?
最近はスマホで表示するGoogleMapsみたいなものを思い浮かべる人も多いかもしれませんね。
比較的のんびりした地域に住んでいる方だと、町内会が作ったその地域の建物や住んでいる人の名前まで入っている地図が街角に掲示されているのを見たことがあるかもしれません。
日常的にはそれほど考えないことですが、土地には所有者がいるわけですよね。今日はそんな地図の話です。
一般図と主題図
地図には一般図と主題図という分け方があります。
一般図というのは簡単に言うと何でも書いてある地図です。道路がどうつながっていて、そこにこんな建物があるとか、地名とかその境界とか、土地の起伏とか、 さまざまなことが記入されています。なんでも書いてあるので見る人が必要に応じて情報を拾っていく汎用タイプの地図が一般図です。
逆に主題図は使う目的に応じて情報を絞ってある地図です。これは目的によって様々な種類があるわけですけど、 例えばさっき言った町内会が作った住民の家が分かる地図なんかは、主題図の一つと言えるでしょう。
この手の地図は形とか距離はあまり正確ではないことが多いですが、道路のつながりはきちんと描かれていて、ざっと目的の家に行く道順を知ることができますよね。
道順といえば、お店のパンフレットなんかに最寄りの駅からのざっくりした地図が書かれていることがありますが、あれも主題図のひとつと言えるでしょう。
そんなふうに主題図のことを調べていて、ちょっと興味を持ったのが地籍図でした。地図の地に戸籍の籍と書く地籍の図ですね。
地籍図とは
文字からイメージできると思いますが、 ある土地に関するさまざまな情報を記録したものが地籍です。土地の場所、所有者、面積などが主な情報ですが、実際にどんな形をしているとか、隣接する土地との正確な境界線などは地籍図という形で図にするわけです。
以前ここで話をしていた札幌歴史地図明治編には土地割図というものが出てきます。メインストリートに沿って土地の持ち主を並べただけの簡単なものですが、まあ、これも地籍図の先祖と言えるでしょう。
写真をいつものとおり書き起こしのnoteに載せておきますので、興味がある方はそちらを見てくださいね。

どんなときに使う?
さて、地籍図がどんな時に必要になるか、です。
一番考えやすいのは、一戸建ての家を買うというケースだと思います。
家を買うって言いますけど、買うのは建物だけではないですよね。大抵は、その家を建てる土地も一緒に買うことになります。そのとき、自分の土地が実際にどこからどこまでなのかをちゃんと考えますよね。そして、それが自分のものであることを何らかの形で証明できるようにする必要もあるわけです。
いつもはそれほど真面目に考えないけれど、売り買いをするとなると慎重に調べることでしょう。こういうことのベースとなるのが地籍図なのですね。
ということは、どこかに正確な地籍図があるはずです。そうです、これが法務局にあるわけですね。
法務局にある「正確な地籍図」とその歴史
さて、ここからが問題です。先ほど正確な地籍図と言いましたが、法務局にあるのが必ず正確な地籍図かというと、実はそうではないのだそうです。
「それじゃ、自分が家を建てるために買った土地が正確にはわからないってこと?」って思うかもしれませんが、まあ、そこは大丈夫です。
比較的頻繁に取引が行われる場所は、大体正確な地籍図があるはずです。問題は昔からある土地です。
直接現代につながる地籍の考え方の基礎は明治時代から整備を進めてきたものです。
でも、地籍の考え方自体はそれ以前からあるわけですよね。
そもそもは、土地をベースに課税するためにつくられたのが地籍ですから、古くは大化の改新にまでさかのぼれるわけです。
で、時代に応じて必要な地籍図的なものは作られていたんですが、想像できると思いますけど正確な図ではなかったわけですね。実用上問題ないレベルで運用されてきたんですから。
明治政府はそれらを引き継いで、近代国家として法整備をして、土地を正確に記録する必要がありました。もちろん、主目的は課税のためです。
まあでも、明治政府ができたからいきなり近代的な正確な地籍図が作れるかというと、そんなわけはありません。その時代に使用可能な技術を使い、必要なところから近代的な地籍図を作っていたのです。
それから150年ほども経ちますから、今は日本全国である程度正確な地籍図が整備されていますが、それでもまだ半分程度なのだそうです。
土地の売り買いみたいな必要に迫られたところから、正確な地籍図を作っているからで、まあ、そういう取引が発生するのは、土地全体のほんの一部ということですよね。
古くから受け継いでいる土地を手放す場合などには、大抵正確に測量し直すということが必要になります。そのタイミングで、正確な地籍図ができるという感じですね。
地籍調査の経験談
実際、僕も10代のころに実家の土地に関して、そんなケースを経験したことがあります。
たまたま、隣接する土地の持ち主が土地を手放すことになって、その正確な境界を定め直すことになったのです。
境界の杭があるところもありましたが、住民が以前から使っている通路などで漠然と区切られていると考えていたところもありました。
大体は隣の家とここら辺という合意がありましたが、正確に図面に残すに越したことはないわけですね。
測量した結果は我が家にも連絡が来て、その時の話が結構面白かったのです。
うちの境界は思っていたとおりだったので何ら問題なかったのですが、やはりみんなが通っていた通路のところは曖昧で、通路の両側の所有者が損にならないように境界を決め直したのだそうです。損にならないというのが面白いですよね(笑)
まあ、所有者は境界は曖昧でも大体自分の土地の面積は知っているんですね。それをベースに固定資産税を払っていますから。
そもそもがあまいな形になっている境界線を引くときに、各所有者の土地が減らないように決めていくのです。
まあ、減ったら文句言いますよね(笑)
実家の土地も、元々の面積よりもちょっとだけ広くなる形で確定しました。
それで、税金がどうなったかまでは聞かなかったので知りませんが。
まあ、そんな形で地籍図を整備するのが地籍調査というそうで、正確な地籍図は都市計画とか災害対策にも必要となるため、国土交通省が所管で市町村が主体となって今も地道に進められているのだそうです。
どうでしょう?
遡ると大化の改新、歴史の積み重ねのような地籍図の世界。面白そうじゃありませんか?
マガジンはこちら
コメントはこちらで
noteのコメントだけでなく、Stand.fmのコメントや Twitter の DM などでコメントをいただけると嬉しいです。
今後配信の中で参考にしていきたいと思います。
おわりに
読書と編集では IT を特別なものではなく、常識的なリテラシーとして広める活動をしています。
ITリテラシーの基礎を学べるオンライン講座をやっています。
詳しい内容については、概要欄のリンクから、または「読書と編集」と検索して、猫がトップページに出てくるホームページをご覧ください。
概要欄にリンクがありますので、フォローいただけると嬉しいです。
この配信の書き起こしをnoteで連載しています。
今日もワクワクする日でありますように。
千葉直樹でした。
ではまた。
Youtubeもやっています
登録していただけると嬉しいです。
Podcastの聴き方
Podcastの聴き方は以下のnoteをお読みください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
