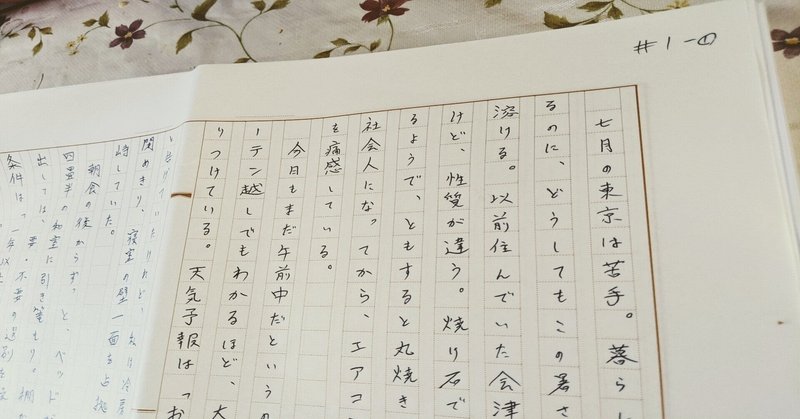
岩本先生と「シド・ヴィシャスのすべて」
わたしは文章を書くのが仕事でもあり、趣味でもある。仕事で書いている文章と趣味で書いている文章は全くの別物だけれど、いつでも同じ「文章」を取り扱っている。
普段自分を物書きという風に呼んだことはないけれど、大きくジャンル分けすると「物書き」という人種になるのだろう。物書きの人たちは、自分が文章を書くことに目覚めたきっかけを、それぞれ持っているようだ。
わたしが自分の文章を意識するようになったきっかけは、たぶんあのときのあの先生だったんじゃないかな、と感じさせる言葉が思い浮かぶ。
◇
わたしは小学生のときから作文が得意だった。でも、別に好きではなかった。嫌いでもないが、好きでもない。ただ、頑張らなくても評価された。
棒付きキャンディーをペロペロっとなめるくらいの感覚で書いたものが、なぜかいつも評価された。廊下に張り出されたり、全校生徒の前で読まされたりした。自慢みたいに受け取られたら嫌だなと思うが、これは言い逃れできない事実だ。
子どもの頃のわたしにとって文章を書くことは、それほど自分にメリットのあるものではなかった。他に頑張らなければいけないことが、いっぱいあったのかもしれない。
とくに自分の文章について意識しないまま、中学3年生になった。
当時、国語を担当していた岩本先生のことが、わたしはとても苦手だった。小柄で白髪交じり。あまり笑顔のない顔に眼鏡をかけた先生。なんだか冷たい印象があって、とっつきにくかった。堅物という言葉がよく似合う。散々な言様だが、そう感じていた。
そもそもわたしは国語の授業も、あまり好きではなかった。テストの成績は悪くなかったが、それが逆に「もっとも勉強する意味のわからない教科」に感じられた。授業中は眠ったりしていたし、先生もわたしのことをよく思っていないだろうと感じていた。
そんな中学3年生の夏休み明け、わたしは読書感想文を提出した。感想文の題材に選んだ本は「シド・ヴィシャスのすべて」
◇
シド・ヴィシャスとは、パンクロックの代名詞のような人物だ。当時わたしは15歳の思春期真っ盛り。1970年代半ばを中心としたイギリスの初期パンクが好きだった。ラモーンズ・ピストルズ・クラッシュ・ダムドあたりが有名だ。なぜ初期パンクが好きなのかといわれると、よくわからない。単純にかっこいいからだ。
15歳の夏休み直前、「シド・ヴィシャスのすべて」というバイオグラフィ本が発売されたので、わたしはそれを個人的に読んで楽しんだ。宿題の読書感想文用に、他の本を読むのは面倒だ。宿題として提出する感想文の題材も、これでいいだろうという安直な考えでこの本を選んだのだった。
筆は確かに進んだ。好きなものについて書くのだから当たり前だろう。棒付きキャンディを舐める……よりも少し力がこもったかもしれない。でも、やっぱり「いいものを書こう」とか「賞をとろう」とか一切思うことなどなく、ただただ思いの丈を書いて提出した。
その作文は、読書感想文コンクールで入賞した。課題図書のような本を読んだクラスメイトが特選を受賞していた。
学校のホールで表彰が行われたが、正直恥ずかしさだけが突き刺さった。校長先生が表彰状を読み上げるのだが、作文の題名を何度も嚙む。
「シド?ビ?シドビ…シドビ、シヤスのすべて……以下同文です」みたいにして。
題名を読み上げられるのも恥ずかしかったけれど、つっかえて何度も繰り返されたのも恥ずかしかった。背後に感じる全校生徒の視線が苦しかった。誰もそんなに、わたしのことなど見てはいなかっただろう。早く終わらないかなって、思っていた人が大半だろう。でも、そのときは心底恥ずかしかった。
クラスに帰ると、友達に若干からかわれた。「ねぇねぇシドビシャスって何?」「知ってる、セックス・ピストルズだろ?」「セックスセックス!」などと言って、悪ふざけのいい材料になった。
そのあと、例の国語の岩本先生から「作文の原稿を返すから職員室に来なさい」と伝言があった。岩本先生に会うのはちょっと憂鬱だったが、わたしは言われたとおりに、職員室に入っていく。
◇
職員室には岩本先生しかいなくて、シンとしていた。先生は、わたしに作文の原稿を手渡しながらひとことだけ、こう言った。
「あなたさぁ……
本が違ったら、特選だったのに。もったいない」
わたしは、苦笑いしながら会釈をするのが精いっぱい。何も話せなかった。その時は、言われた言葉の意味をあまり深く考えなかった。先生は、少し笑っていたような気がする。
「もっとマシな本を読んで、ちゃんと書け」と言われるのなんて当たり前だ。怒られるって、わかってた。カトリックスクールだもんね。でも、アンチクライストの意味なんて書いてない。先生、その辺のことわかって言ってるのかな?なんてグルグル考えながら階段を下りたのを覚えている。
ただそのあと、言われたことの意味をずっと考えてしまった。
本が違ったら、全く別の感想文ができあがるはずなんだ。この作文とは全然違う内容で、まったく別ものの文章になるはずなんだ。今回評価されたのは「この作品だった」はずである。なぜ、本が違えば評価が上がるのだろう。
わたしより優れた評価の「特選」を受賞した子だっているではないか。その子の作品はどうなの?先生は、わたしの「まだ書いていない文章」の話をしているの?先生は、わたしの「作品」の話をしているの?意味が分からないよ、先生。
先生は、何の話をしていたの?
15歳の未熟すぎる頭では、それをうまく理解できなかった。その年の秋が深まった頃、わたしは学校に行かなくなり、卒業式にも出ないまま、誰にも会わないまま中学生を終えた。
◇
今わたしは、文章を書いて仕事をするようになった。あの頃みたいに、好きなことを好きなように書いても、評価されなくなった。棒付きキャンディーみたいなどうでもいい存在だった文章を、好きになったり嫌いになったり、うんざりしたり愛おしくなったりと、忙しくもなった。
「文章を書くようになったきっかけ」がはっきりわからなくて、声を大にして言えなかったけど、やっぱりあの先生の言葉は今でも忘れないしときどき思い出す。冷たくて堅物で大の苦手だった岩本先生の言葉は、17年も経った今「あたたかいもの」としてわたしの中に残っている。
「本が違ったら特選だったのに」は「他の本のことを書いたとしても、誰よりもいい文章が書ける」という意味だと、思っていいのかな。
まだ考え続けているけど、いつからかそう捉えるようになった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
