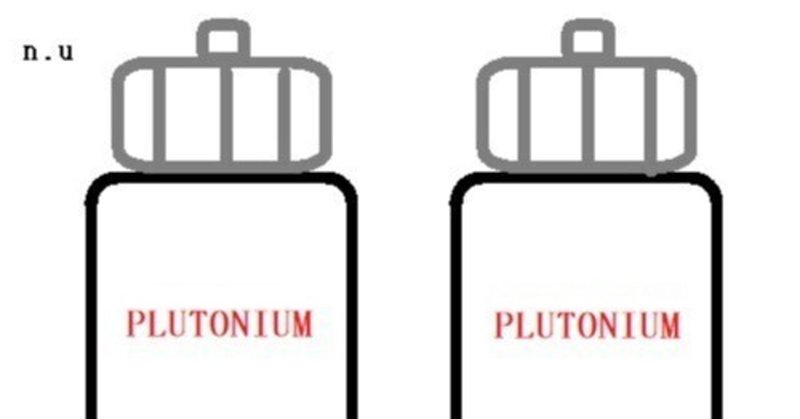
【SF掌編】プルトニウム・レース
「あれがゲートか」
背中から、しゃがれ声が飛んだ。こいつは俺の右手の文庫には関心を持っていない。
「そうみたいだな。思ったより近いじゃないか」
俺たちの向かう先、狐色の砂漠にぽつんと建つ、あの竜宮城みたいな塊しか目に入っていないようだった。
ひび割れた土を踏み続けて数分ほど経過している。乾いた地に二人の足音が響いた。
汗を含んだ文庫は、こぼれ落ちる心配がない。道すがら拾った輪ゴムでしっかり束ねてある。指先に力が入ったのか、本の題名が滲んでいる。
俺は振り向かずに言った。
「いつまでくっ付いている気だ? お前、母親じゃないだろ」
数分程度で、右手の文庫は別物に換わった。
「これが有害物質か」
リュックの中、銀色の表面に自分の顔が映っている。2本、ちょうどペットボトルと同じくらいの大きさだ。今からこれを背負って、競技会場に向かわなければいけない。
ゲート付近には大勢の輩でごった返していた。どいつも皆、腕にド派手なタトゥーを入れている。
信じがたいルールだけ一人歩きしているようだ。俺たちも一応、そのルールに乗っ取った馬鹿に違いない。
男は言った。
「背中にプルトニウムなんて誰が考えたんだ? 頭やられちまってるよな」
〈レース参加の申し込み、誠にありがとうございます〉
中古のノートPCに残る文面を見る限り、運営は参加者の素性を知らないはずだった。
必要な物は文庫本2冊のみ。特にどの年代の本か、それすら指定がないと来ている。
初参加の人物が何を差し出すか、データ徴収くらいは行うだろう。漱石とブラム・ストーカー。この二人なら怪しまれることもない。
なぜ文庫を入場券に換えようとしたのか、もう少し話す必要がある。
どんな競技も参加条件として、〈心身ともに健康であること〉を掲げる。 だがこのレースは特殊だった。健康であることはもちろん、本好きであることも最低条件だった。
大型書店で文庫を購入した客にのみ、レシートにてパスワードを提示。指定したサイトにて入力すると、例の文面〈誠にありがとうございます〉が並ぶ。彼らは後に汗だくとなって自転車を漕ぐ者を選別する。
サイトの背景に目を凝らすと、微かにプルトニウムらしき物体の絵が見えた。それは銀色のスプーンより眩しく、池に沈んだ一円玉よりも鮮明だった。
おっさんたちの懐を肥やす点では、現実世界と寸秒も変わらない。利権に目を付けた会場付近は、もはや村でも町でもなくなっている。あれは灰色の雲が占める、ただの地域だ。
俺は本棚から『草枕』と『ドラキュラ』を取り、部屋を出た。
ふとアスファルトに目が留まった。
きっと工作好きのJKか、他の誰かが落としたものだろう。ツキを得た気がした。右手を覗く。文庫が2冊。すぐにその輪ゴムで束ね、近くの地下通路へと急いだ。
暗闇から温い風が迫り込んでくる。一歩足を踏み入れた途端、頭がくらくらした。湿気のせいだった。
天井はガラス張りで真昼の太陽がくっきり見える。通路の先は果てしないほど遠い。
この先に陸上競技場があるなど誰が知るだろう。壁は照明の灯りで白くなっていた。おかげで、どこかのガキが描いた醜いスプレー作品が台無しだった。
通路は二手に分かれていた。
正面は上り坂、右の方向には階段が地上に伸びている。
レース会場に向かう条件。それは通路外へと身を押し出す、圧倒的な脚力があること。
出口は上り坂の先にある。助走を始めた。漱石とストーカーが離れないほど、強く握った。
「お前も通路から来たのか」
ずっと背中にへばり付いてきた野郎にしては、まともな問いだった。
俺たちは会場裏の待合室にいた。壁はもちろん、床一面も濃いオレンジで気色悪かった。おまけに紺色の文字でwelcomeと殴り書いてある。控えめに言ってもセンスの欠片すら感じない。
ここには少なくとも数十人が待機している。
「通路から出て、すぐに出くわしたよな。同じ目的地だってわかったよ。お前の手にも本があったからさ」
何の本か、確認できなかった。こいつも書店にてレシートを貰い、謎のサイトにアクセスしたのは事実だ。
俺は続けて言った。
「いいか。あの通路に突入できるほど世間のやつは馬鹿じゃない。原子炉につながる場所だって知ってるからな。ましてお気に入りの文庫握って消えるなんてことはしたくないはず。俺たちは現実から漏れたんだよ。オムツなしの体でさ」
きっと海の向こうで大会が決まった瞬間から、見えない所で札束が積まれていたはずだ。
国を挙げて新設したはいいが、作業員の過労死も付いてきた。「安全には最善を尽くしてきた」が連中の言い訳だった。若く、体力のある若者が次々と現場近くで倒れたのだ。
結果、自国開催に沸き立つ、広告屋の目尻の皺を増やしただけに終わっている。豊かな資源と豊かな資金、豊かなスポーツ教育を急いだ、あまりに貧しい結果だった。
シン・国立競技場を古代ローマのコロッセオに変える者など、この国にはいない。
少なくとも、俺たちがさっきまでいた世界には。
「正式名、知ってるか?」
「……何とかチキン・レースだっけ?」
「そう言いたいところだが」
背中の物質を見て、とぼけるわけにいかなかった。
「プルトニウム・レース、で合ってるか?」
「正解だ。至って単純な名前だろ」
推し量ったように、待合室のモニターに電源が入った。
会場はすでに埋まっている。子供から大人まで、どの人間も似た顔をしていた。
「あいつら、なんて言ってる?」
男はモニターを見て言った。
「さあな。人よりパターン持ってるかもしれないぜ。どうせ決まったことしか言えないんだろ? RPGの村の住人と変わらないさ」
「……パターンか。例えばどんな感じだ?」
「……がんばれ。がんばれ。ありがとう。俺たちと変わらないんじゃないかな」
通常のレースとの一番の違いは、言うまでもなく背中の燃料だ。転倒して中身がこぼれても助けてはいけない。ゴールまで対戦相手に体当たりして、進路を妨害することは許されている。
若い女のアナウンスが聞こえた。野郎どもの耳が一斉に集中している。
「エントリーナンバー119と344の方、まもなくレースの出番です」
自動で扉が開いた。その時、初めて床の文字welcomeがまともに見えた。
119と344は待機室から出た。二人とも余裕なのか、笑みを見せていた。国籍はわからない。きっと自転車競技の強い国からエントリーしたのだろう。ジムに通う筋肉マニアの金髪野郎と言った印象だ。
自分がいつコールされるかわからない。だが負ける気はしなかった。
119のゼッケンが画面に映っている。観客席のカメラは、たった今、赤いリボンを付けた少女を捉えた。
俺は自転車に跨り、目を閉じて、突き刺さるような客の目を殺した。
衝撃音が走った。リュックから、2本のプルトニウムがこぼれ落ちていた。耳をつんざくほどの歓声が消え、辺りは静寂が包んでいた。
波を打った静けさだった。
倒れた自転車。そこから離れた位置に、男がいる。
人影に気付いたのか、口を開いた。辛うじて言葉を発している。
「……ハロー」
腕の部品が露わとなって、鈍く陽の光を反射していた。
男の声は、はっきりと届いた。
「俺が、現場から逃げてきたことくらい、あんたらには予想できたはずさ。レースに参加する馬鹿から、質のいいプルトニウムを分捕る。それが、目的だったはず」
ゴール付近で転倒した直後、右手は吹き飛んだようだ。悲鳴はハヤブサほどの速さで会場を駆けた。リュックの中身より、千切れた右腕に視線が集まっていた。
「運営に言っておいてやる。これ以上、読書好きを巻き込むなと」
頬の筋肉が緩んでいる。俺の言葉に反応していた。
顔を見る限り、ヒトと何ら変わりない。
「このレースは、テロに適した者を、かき集めるためにある。俺は、潜入捜査に、来ただけだ」
プルトニウムについて、今更禁止だなんて言う輩はいない。おかげで俺の稼業も成立している。
「一つだけ、教えよう。俺たちにも、タイプがある。中には、輪ゴムを飛ばした程度で、くたばるやつもいる……役に立てば、幸いだ。このスペースでは、誰もが、的になるから」
アンドロイドの目は開いたままだった。瞳孔が変わらず俺を捉えている。右腕から、虫の音ほどの小さな音がジッと漏れた。何かが停止した音らしい。それはヒトがよくやる舌打ちのように聞こえた。
「どうして、この商売を選んだ? お前たち、人間の動機が、知りたい」
男は口から言葉を絞り、ついに動かなくなった。
リュックには4本、土産物が詰めてある。
いずれも239型で、会場近くの原子炉から流れた物だ。世界のどこかに散った有害物質を横取りする。それが俺の仕事だ。
アンドロイドの言う通り、運営はテロの素質を試している。背に触れたプルトニウムに怖気づいたところで、破壊工作など務まらない。あいにく俺は不採用らしい。
ふとポケットに手を突っ込んだ。
帰りの地下通路入口が迫ってきた。歩きながら、ポケットからの輪ゴムを右手の小指に掛け、甲に巻き付けてみる。これを自家製のピストルと呼ぶには、きっと早い。
遙か先の暗闇から、足音が飛び込んでくる。何かが猛烈な勢いで駆けてくる。足音は次第に大きくなって、数秒後には何かが姿を見せる。
右腕を伸ばした。それから人差し指を通路に向け、小指の力を抜いた。
(了)
