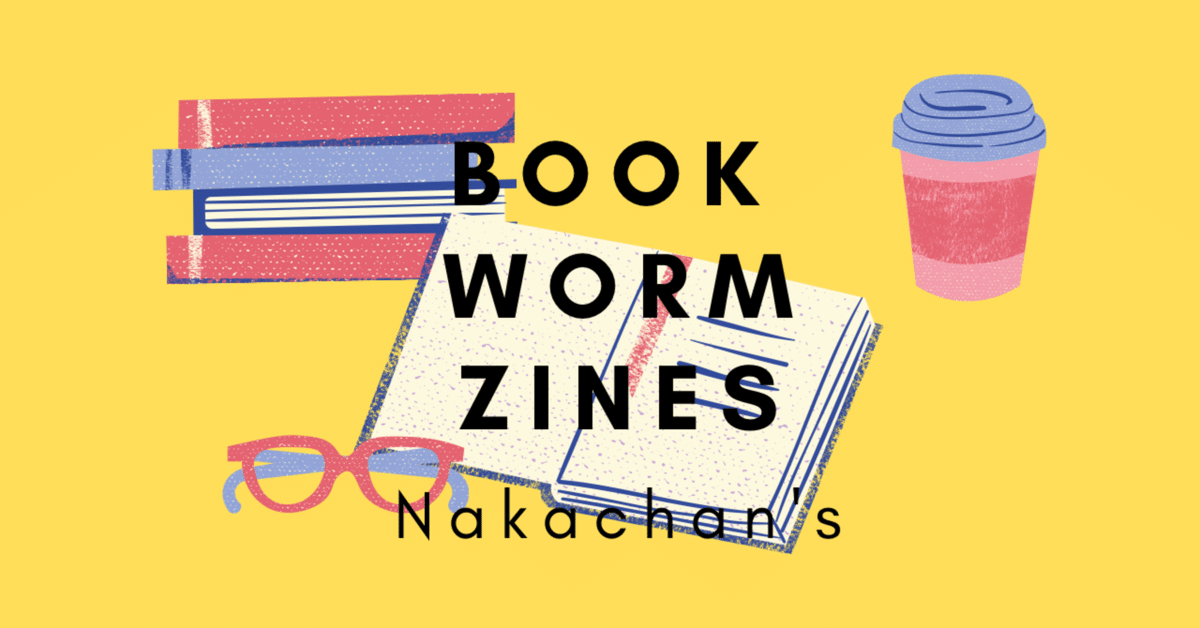
【読書】星月夜(ほしつきよる)
こんにちは
ナカちゃんです。
ラジオでは、3つのパターンで放送しています。
① 5分で聴ける ミニ版 → 一冊だけ、短い配信で紹介。
② 通常版 →15〜20分くらいで 一冊または2冊の本を紹介しています。
③ ライブ配信 → 長くても50分ほどで、その時の気分に合わせた本を数冊紹介。皆さんとのおしゃべりの流れで、本にまつわる色々を話しています。ちなみに、昨日紹介した本は 『怠けてるのではなく、充電中です。』『絵本の春』『吠える その他の詩』『らしく生きよと 猫は言う」の4冊でした。
で、どの回の配信でも、既読の本で紹介できていなかったのが、今回の『星月夜』。
著者は、李琴峰(り・ことみ)さん 台湾出身の作家・翻訳者だ。
2013年に来日、その後2017年、『独舞』で第60回群像新人文学賞優秀作を受賞している。芥川賞の候補になったことで、作品を読まれたこともある方もいらっしゃるのではないか。
この作品が自分にとっては、初めての李琴峰作品だったので、最初は読みにくさも感じた。主人公は2人。台湾から日本に留学し、大学で外国人留学生に日本語を教えている柳凝月。もう一人は、新疆ウイグル自治区から日本に留学している玉麗吐孔(ユーリートウーズー)。彼女は、中国人ではあるが、漢人ではない。言葉こそ同じかもしれないが、宗教も、顔つきも、故郷の厳しい状況も(政治的にも、経済的にも、思想的にも)、日本人の知っている中国人とは相容れないアイデンティティーを持っている。そして、恋愛対象は、いつも女性だ。
柳についても、台湾で躾に厳しい両親の下で育った。躾と称し暴力によって、子どもを支配する毒親。「日本語を学びたい」と願うことすら、「烏魯木齋」(オーローポッゼ)と蔑まれてきた。そして、彼女もまた、好きになるのは女性ばかり。台湾から、家族から、逃げるようにして、日本に渡り、大学での教職についたものの、故郷の呪縛から逃れることができないでいる。
物語は、2人の視点が交互に入れ替わるようにして紡がれていく。所々に中国語が点在し、日本にいながら異邦人である2人の姿が、文章から浮かび上がって来る。点在する中国語が理解できない読み手は、まさに、登場人物の「絵美」の気持ちをなぞっている。ユルトゥズに恋愛感情を抱く絵美だが、柳とユルトゥズが中国語で意思疎通する場面を目の当たりにし、自分はユルトゥズのことを何も分かってはいないと愕然とし、彼女の前から姿を消してしまうのだ。
日本には今、多くの留学生や技能実習生、就労している外国人がいる。だが、身近にそのような人の存在を感じでいないからなのか、「日本にいながら、日本人になれない」もどかしさや不自由さ、理不尽さを私たちは理解できていないのではないか。柳も、ユルトゥズも、故郷に帰国する選択は無い。周りの留学生や、同僚が、それぞれの国に帰国したり、結婚したり、「落ち着くべき所へ、落ち着いて」いくのだが、彼らは、そうしようとはしない。だからといって、ユルトゥズは、大学院の試験に失敗し、これからの日本での暮らしを見通せる保障は何も無い。そして、柳もまた、老いた両親を台湾に置いたままで、結婚もせず、異国の地で一人で生きていくことを選択した。
ラスト付近で、「在留カード」を持ち歩くことを忘れたユルトゥズが、警察に連行される場面が描かれる。日本人には、想像もつかない扱いだ。指紋採取、唾液採取など、「本人確認」のためとはいえ、こんな扱いを受けるなんて。
私たちはまだ、知らないことが多すぎる。日本に生活の拠点を移そうとやって来る外国の人たちに対して、私たちはどれだけのことを知っていて、否、知ろうとしているのか。「外国からの観光客」には、手厚い「おもてなし」はするけれども、「隣人」としての外国人に対して、エンパシーを持って接することが出来ているのだろうか。
以前、紹介した本の中で、「アイデンティティーとは何か」を考えさせられた本を紹介したが、この「星月夜」もまた、「漂流するアイデンティティー」について考えさせられる一冊である。台湾と、中国と、新疆ウイグル。ジェンダー、結婚観、家族との関係。異文化として見過ごされてしまいがちな、かつ、センシティヴな問題を、繊細な文章で、淡々と綴る。決して声高に叫ぶわけでもなく、センセーショナルな事件に仕立てるわけでもないが、李琴峰の言葉は、日常の中に潜む、「大きな課題意識」を静かにあぶり出していく、そんな鋭さを感じることが出来る。
コロナ禍の今、多くの人の意識が「内向き」になり、苦しい状況が続いている人が多い。「閉塞感」に押しつぶされそうになりそうなとき、顔を上げて、周りを見渡してみたい。「同じ船に乗り合わせた隣人」として、できることはないだろうか。隣人を「カテゴライズ」し、壁を作る前に、その人自身と向き合い、出来ることを一緒に探すこと。それが、コロナ後を生き残るため、「本当のダイバーシティー」社会の実現の第一歩になると考えている。
サポートありがとうございます。頂いたサポートは、地元の小さな本屋さんや、そこを応援する地元のお店をサポートするために、活用させていただきます!
