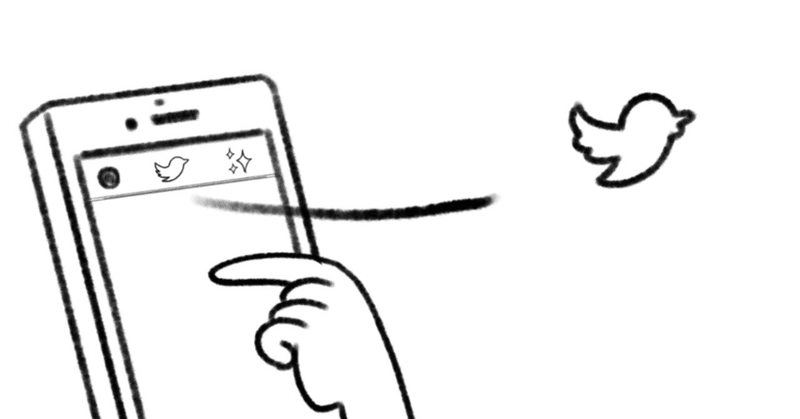
多くの人に情報を届けるためTwitterについて考えた
医療介護現場で繰り返されるミスを減らしたい
医療介護現場での課題解決を行う一つの方法としてプログラミングの知識が役に立つのではないかと考え、2021年10月に「ものづくり医療センター」に入学し、同時にプロトアウトスタジオでの学びを開始しました。
在宅医療の現場で感じた課題をもとに、室温が上がったらお知らせする仕組みを作ったり、孫の声で励まされて足上げ運動を頑張る仕組みを作ったり、ヘルステック領域の記事分析を行なったり、全然仕事と関係ないラグビー部とサッカー部を顔で判断する仕組みを実装するなかで、医療介護現場で行われているヒヤリ・ハット報告を紙ベースからデジタル化することで報告と共有を行いやすくして、同じミスの繰り返しを減らし重大事故も減らすことにつながるのではないかと考えるに至りました。
また、この医療介護現場におけるヒヤリ・ハット報告の活性化は、たとえば受診する病院や入居する高齢者施設を選ぶ際にも一つの重要な指標にもなると考えています。
仕組みの検討と並行して情報発信の方法についても考える
ヒヤリ・ハット報告のデジタル化については、どういった仕組みにするか、それをプログラミングでどう実装するかは検討中です。
一方で、今回の仕組みについては多くの医療機関や介護施設で使ってもらえばもらうほど、ヒヤリ・ハットの報告・共有が増え、それによってミスの繰り返しや重大事故を減らすことにつながるため、仕組みの実装を検討することと並行して、今回の取り組みを多くの人に知ってもらうための方策についても並行して検討を行なっていくことが重要だと考えました。
このため、それまで行っていたfacebookに加えて上記のようにnoteやQiitaでも記事を書くようになり、さらにtwitterもはじめました。
今回は、この中でtwitterに注目して、いかに効果的に情報発信を行うかについて考えてみようと思います。
Twitterアナリティクスの活用
今回Twitterの分析をしようと思って初めて、Twitterアナリティクスという画面が公式にあり、ツイートの詳細な分析が行えるようになっていることを知りました。

この画面をみれば、どのツイートが多くみられ(インプレッション)、どのツイートが多くクリックされたか(エンゲージメント)、などを簡単に知ることができます。
ツイート分析
ここ10日(11月7日から16日)の記事を分析したところ、もっとも画面に表示されクリックされたのがこちらの記事。
認知症当事者が介護専門学校で講師をする。
— naoki uchida (@naokiuchid) November 10, 2021
とても素敵な取り組みだと思います。#認知症 https://t.co/fR9sZFg747
ツイートの表示数が4286で他と比べても圧倒的数です。
認知症当事者が働くことについてのニュース記事の紹介で、数日間はニュース動画もみれるというものでした。
ハッシュタグ認知症をつけていることが一つの因子と考えますが、これは他の記事にもつけています。
表示された数が多い記事の多くに共通しているのが、樋口直美さんによるリツイートでした。
フォロワー数が多い方からリツイートされることで多くの方の目に触れるというのは自然なことだと思います。
この点を考えると、自身のフォロワー数を増やすことは多くの人に情報を届けるために重要だという当たり前の結論に落ち着きました。
いかにフォロワー数を増やすか
単にフォロワー数を増やすだけなら、「相互フォローします」と書いている方をフォローしまくるのが手っ取り早いのでしょうが、最終目標はフォロワー数を増やすことではなく自分の情報を多くの人に届け興味を持ってもらうことなので、この方法は不採用。
知り合いや、同じプログラミングスクールの関係者であれば共通の興味を持つ人からフォローをし返してもらえると考えて、ツイートをたまたまみかけた知人やプロトアウトスタジオの関係者をフォローすることにしました。これによって、11月7日に25人だったフォロワー数は、11日に50人まで増えました。
しかし、プロトアウトスタジオの関係者はだいたいフォローし終わる一方、知り合いの中で誰がTwitterをしているかもわからないのでこの方法の限界が訪れました。そこで、いつも情報発信を行なっているFacebookでTwitterを開始したためフォローしてほしいと呼びかけを行うことに。
11月11日の夕方にFacebookへ記事を投稿したのですが、その効果は抜群で同日中にフォロワーは80人に増え、翌日には150人まで増えました。
ユーザープロフィールクリック数に注目
フォロワーを増やすという視点に関して、Twitterアナリティクスで示される数値のうちユーザープロフィールクリック数に注目しました。
なぜなら、フォローを行うにはユーザープロフィールの画面に行く必要があるからです。
最もユーザープロフィールクリック数が多かったのは、前述の認知症当事者が働く記事についてのツイートで21回クリックされていました。
二番目にユーザープロフィールクリック数が多かったのはツイート表示数が1846件と二番目に多かったこちらのツイートで6回のクリック。
11月20、21日に「みんなの認知症情報学会第4回年次大会」がオンラインで開催されます。
— naoki uchida (@naokiuchid) November 11, 2021
オンデマンド視聴も可能とのこと。#認知症https://t.co/Prpiv2iwWp
ついで、クリック数4回のツイートが3つあるのですが、興味深いことがありました。
こちらの記事は樋口さんの記事を紹介するツイートで表示数が808件。
レビー小体病当事者の樋口さんより、「認知症って何なのよ」https://t.co/Rwd7lCInwL#認知症
— naoki uchida (@naokiuchid) November 8, 2021
二つ目は、こちらで記事の表示数は254件。
ヒヤリ・ハット報告をオンライン化することで報告共有が行いやすくなることを考えたが、@ma_anago さんがおっしゃった職場の心理的安全性に配慮することも報告数を増やすことにつながるだろうし、そもそも報告者にメリットがあまりないことについても考えなければいけない。#クラウドファンディング
— naoki uchida (@naokiuchid) November 14, 2021
三つ目はこちらで記事の表示数は154件。
#緩和ケア #がん診療 https://t.co/pR3I79INBJ
— naoki uchida (@naokiuchid) November 15, 2021
二つ目と三つ目の記事よりも表示数が多い記事は複数あるものの、この二つの記事が特にユーザープロフィールクリックに繋がっていることに注目しました。
二つの目記事は他ユーザーのアカウントを記事内に入れ込んでいて、三つ目の記事は他ユーザーのリツイートです。
つまり、普段私と関係が薄い人にツイートが届くとユーザープロフィールをクリックしてもらいやすいと考えました。
しかし、ユーザープロフィールのクリックが最も多かった記事が投稿された11月10日から11日にかけて増えたフォロワー数は7人で、そのうち私がフォローしてなかった方は1人のみで、この記事の効果でフォローされたのは1人だけでした。ユーザープロフィールのクリックをされたからと言って、それが即フォローに繋がるわけではないということも注目点です。
個人的に、プロフィール欄を見た時にフォロワー数が多い人、特にフォロー数よりもフォロワー数が多い人の方がフォローしようという気になります。
この11日時点では、私のプロフィールはフォローワー数が少ない上にフォロワー数よりフォロー数が多かったこともあり、ユーザープロフィールのクリックがフォローにつながらなかったかもしれないと考えました。
プロフィール欄を変更
また、そもそものプロフィール欄に載せている情報をあまり吟味していなかったため、説明文を160字の上限ギリギリまで書き、アカウントの名前と写真も変えました。
旧プロフィール

新プロフィール
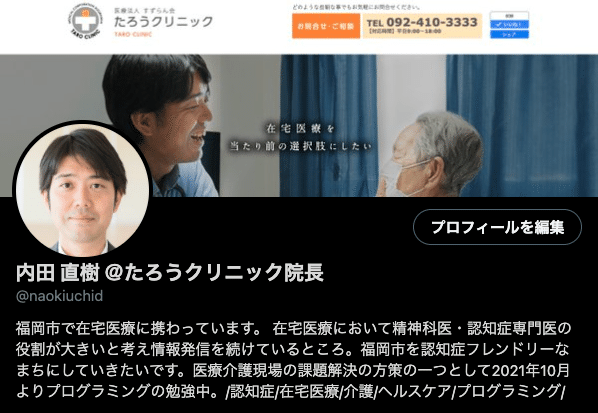
この変更によって、ユーザープロフィールのクリックがフォローにつながりやすくなるのか、これから注目です。
やはりツイートの内容が重要
もう一つ興味深かったのがこちらのアカウントについて。
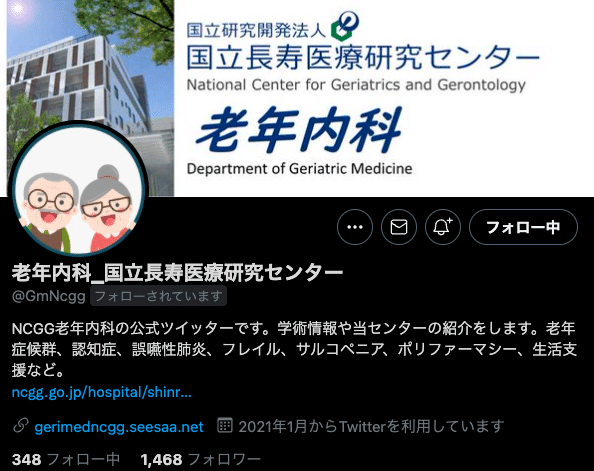
毎日興味深いツイートをされていたので11月7日にフォローしました。
こちらのアカウント、見ての通りフォロワー数がフォロー数の4倍以上あり、フォローしたからと言ってフォローバックをされるわけではありませんし、中の人に面識もありません。
ところが、11月14日にこのアカウントの記事を引用リツートしたところ、
食欲低下か不眠があれば、うつ病のスクリーニングが必要であり2質問法が有用です。
— 内田 直樹 @たろうクリニック院長 (@naokiuchid) November 14, 2021
1.この 1 ヶ月間,気分が沈んだり,憂うつな気持ちになったりすることがよくありまし たか
2.この 1 ヶ月間,どうも物事に対して興味がわかない,あるいは心から楽しめない感じ がよくありましたか#ヘルスケア https://t.co/MhFDQjDCJV
引用リツイートした同日に、このアカウントからフォローをされました。
おそらく、引用リツイートで書いた内容が評価されたのではないかと考えます。
やはりツイートする内容が重要だという当たり前の知見が得られました。
ツイートの内容によって反応が異なるかみてみたいこともあり認知症など医療関連とプログラミング関係のツイートを見比べましたが、明らかに認知症や医療関連のツイートの方が反応が良好でした。
これは、私が医師で認知症を専門としていることからツイートの質が高かったのだと考えます。
今後の運用について
分析から、フォロワー数が多い人や普段繋がりが薄い人とのリツイートや引用リツイートが多くの人の目に触れることがわかりました。
また、ツイートの内容としては、自分の専門である認知症や医療関連のツイートが注目を集めやすいようです。
プログラミングを学びはじめたばかりということもありプログラミング関連のツイートが多くなるのですが、情報発信の場を広げるという視点で考えると認知症や医療関連のツイート(特にリツイートや引用リツイート)を意識して行なっていこうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
