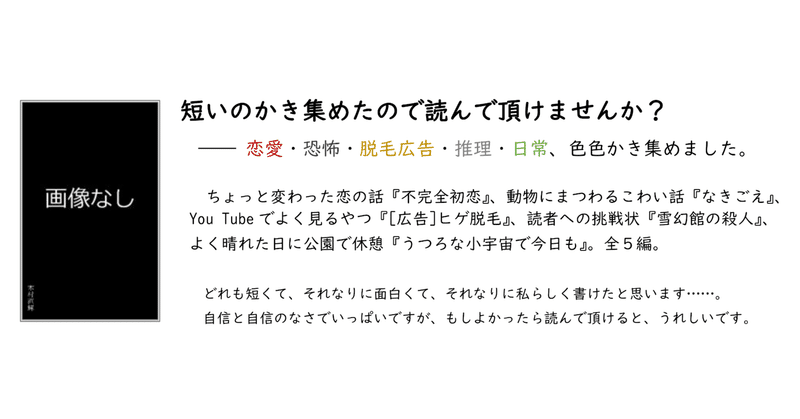
うつろな小宇宙で今日も
公園のベンチに座って視線を放る。
ボールが弧を描く、空中のその先は、青い空が広がって、やさしげな白い雲がふんわりと浮かんでる。
あたたかな日差しが、遊ぶ子供たちを、見守る大人たちを、木々を道を花びらを、地上の全てを穏やかに照らしている。
ああ、これが小説の一節なら、それは間違いなく心地よい心の内をほのめかす直喩だろう。
でも、本当につらい時。世界が色あせて見える時、好きなものさえ気に障ってしかたがない時。
ううん。少なくとも私には、こんな明るい情景さえ苦痛の比喩に使えてしまう題材だ。
土砂降りの雨や、真っ暗な道こそが苦痛の象徴だなんて幸せな奴ら。と心の中で捨てゼリフを吐いて立ち上がる。虚しい毒が、蝕んだのは誰だろう。
――私の最後のよりどころだった女性が、一昨日この世を去ることになった。
死ぬわけではない。でも、もういなくなるのだ。すべて消えるのだ。死と同義だ……。
それでも夜は二度明けた。どんなにつらくたって、気持ちの整理がつかなくたって、時間も日々も待ってくれない。今日も私は働かなくちゃ、来月の私が生活していけない。
「死にたい」という言葉が出てくる時もあるけれど、そんな時ばかりだけれど。死ぬ意外にこの苦しみから逃れるすべがないだけで、死にたいわけでないと私は自覚してしまっている。
「疲れちゃうよね……」
スマホの脇を親指で押して、画面に向かってそうこぼす。
残る休憩時間の少なさを知らせる数字から目を逸らし、画面いっぱいに映る大好きなVTuberを見つめた。いつもそこで、彼女の残像が、私を待ち受けてくれている。
彼女は一昨日、バーチャルユーチューバーとしての活動を辞めると発表した。彼女は何も悪くない。彼女は、色々と疲れてしまったのだと言った。
私は彼女が好きだった。ううん、今も好きだ。
ママが紡いだビジュアル、魂が振舞うキャラクター、運営が添えたセッティング……。そういった要素の集積、好きなところとそうでないところ、彼女を構成する全てによって構成された彼女そのものが私は好きだったのだ。
バーチャルだから、特別?
違う。そうじゃない。だってみんなそうでしょ?
例えば私はこれから職場へ戻る。そこで知り合った人たち。彼らを私は知っている。でも、私が知っている彼らは、私の中に映った虚像でしかない。
例えばその姿は、彼らに当たった光の反射が私の目を通して、その奥で結ばれて、網膜に映った虚像を神経で運び、脳で感じているに過ぎない。
そういった虚像の集積で、私たちは他人を、物や事を、自分さえも自分の中に形づくる。主観で世界を構築している。
そんな虚ろなこの世界で、バーチャルもリアルも、本質的に違いがあるだろうか。
ただ、その切り抜き方が違うだけ。それを重く見るかはひとそれぞれ。私は重く見ない。
いや、違う。それよりも大事だと感じるものを、いつしか感じるようになってしまっただけ。
私は彼女が好きだ。VTuberの、彼女が……。
彼女はきらきら輝いていて、まるで星のようだ。そう、私と彼女の距離はまるで星。
今、地上に届いている星の光は、何万年も前の、ずっと昔の光だという。この、あたたかな日差しもそうだ。何光年もの距離を経て、いくつものフィルタを通して、私たちは太陽を感じている。
まるで、私と彼女の距離みたいだ。
この地上で行われている生配信でさえ、ラグがある。アーカイブや音声作品などともなれば、そのラグはもっと大きくなる。
過去の光を、過去の音を、過去の彼女を、画面を通して私たちは感じている。過去と今を重ね、通じ合っている。それはまるで、ちょっとした宇宙旅行だ。タイムスリップ。星と星の交信だ。
――そんなことを考えながら、職場に戻る。
ここでもたくさんの星が、ぶつからないように忙しなく惑っている。画面を通す時も、そうでない時も。
私はまた、スマホの脇を親指で押す。休憩は、そろそろ終わりだ。
私は、いつも変わらず待ち受けてくれている彼女だけでは足りなくて、Twitterをひらく。
彼女が選んだ言葉の残像を求めて……。
「……」
あった!
それを見て、思わず笑みがこぼれる。彼女らしい。
みんながきっと、桜に目を向けるこの季節。彼女はオオイヌノフグリが綺麗だったとなにげないつぶやきをしていた。地べたに咲く、小さな花を拾い上げて……。
彼女のそういうところが、例えば私は好きなのだ。
その名前の由来は下ネタだけど、とても可愛らしい青い花が群生して咲く姿は、まるで星々のようだ。『星の瞳』という別名もあった気がする……。
私は気を取り直して、午後の仕事を始める。
何の気持ちの整理もついていないけれど、それでも。星々と引き合うその力で、私は今日も生きていく。
