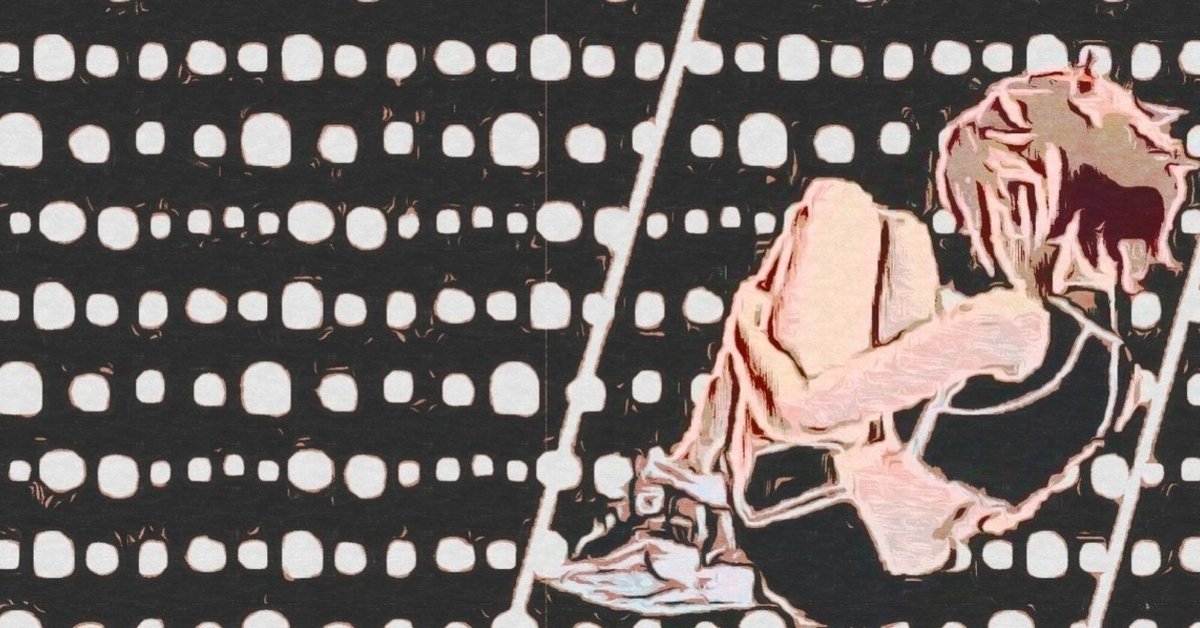
監督の愛人3
一旦一区切り。
後でまとめ・推敲版をあげます。
畜生、こん畜生。
口に出して言ってしまったら、心の中の何かが一気に決壊しそうだった。
唇を引き結び、悪態は胸のうちでがなりたてながら、寮までの帰途を急いだ。
3回犯されて解放されたのは午前0時すぎ。
そのまま即座に寮に戻ることもできず、結局あの男の部屋で朝まで明かした。
部員たちの朝は早い。
出来るなら誰とも顔を合わせず、自分の部屋に逃げ込みたくて、まだ薄暗いうちに出た。
どうしたってそのまま部屋にこもっている訳にもいかないのだけど。
どれだけの娘があの配信を視聴したのだろう。
あの男のことだから、本当に部員全員必ず観るようにと根回ししていたかもしれない。
もしかしたら、一般生徒の間にさえ漏れ伝わっていたのではないか。
カメラの前で演じたさまざまな痴態がよみがえってくる。
「えー、それではぁ、これからいよいよ監督にお尻の穴を犯されまぁす! 前のおま✕✕はもうバッチリ開発済みな訳ですがぁ、ケツ、アナル、アヌスはこれが初、マジモンのバックバージンどえーす! きゃー!」
何故か、かつて受けたインタビューのことが一緒になって思い出される。
これでも1年の時から抜擢を受け、場数も踏み、注目もされていたものだ。
今となってはお笑いの「美少女アスリート」のレッテルも貼られ、ちょっと怖いようなファンレターをもらったこともある。
「そうですね、今は本当、監督や緒先輩につれてきてもらった、ていう意識で、自分で何かをなしとげた実感はないです。この全国の舞台から何かを持って帰れるように、頑張るだけです」
憧れのユニフォームに袖を通して脚光を浴びる誇らしさと緊張に、足下も覚束ない状態だった。
優等生めいたお決まりの受け答えしかできず、当時やはり正規メンバーになっていた瑞穂にずいぶん助けられたものだ。
「とにかく持てるものを出しきって」
「フギャア! お尻ぃ、お尻の穴ぁ!」
「名門の名を汚すことだけはないように」
「入ってる、入って来てますぅ! う✕こひりだすところに監督のステキおち✕ぽがあぁ!」
「一生懸命やって、その上でこの空気を楽しめたら」
あまりに正反対な自分の姿がグルグルまわり、まざりあう。
笑い出したいくらいみじめで、泣きわめきたいほどに滑稽だった。
こんな将来など思ってもみなかった過去の自分に舌打ちしてしまう。
「ああん! お尻、お尻の穴広がっちゃうのぉ!」
ドアを開けた途端に自分の声が耳に入り、ぎょっとした。
はっとした顔で瑞穂がふりかえる。
机の上のタブレットには、紛れもない昨夜の私の姿。
「ち、違うの、アリサ、これは」
「い、いいから消してよ!」
あわててドアを閉める。
いきなりだったので盛大な音量のように聞こえたが、朝のこんな時間のことで、瑞穂ももちろん音量はしぼっていたはずだ。
誰かに聞かれたということはないだろう。
そう思って、そもそももうみんなに観られてしまっているんじゃないかとすぐに気付く。
「き、昨日のこれ、録画してたんだ?」
「うん。ていうか、部員の娘たちはほぼ全員だと思う。あの……」
監督の指図なのは聞くまでもない。
「人に見せたりしない、よね?」
「そんなことする訳ないじゃない!」
「うん」
もちろん瑞穂はしないだろう。
部員たちだって、そうだと信じたい。
でも、本当に?
そもそも去年、最後まで私と戦ってはくれなかった娘たちではなかったか。
20人以上になる1年生部員については、顔と名前の一致しない娘もいる。
ひとりひとりの人柄まで知り尽くしているとは到底言えない。
そして昨夜のあの煽りの数々。
「あ、あーあ!」
沸き上がってくる疑念を圧し殺したくて、さばけた声をあげた。
「こんなことになるんだったら、もっとこう、身だしなみだって気を使っていったのになぁ。大体セックスはいつもトレーニング着でってのがないよねー、どこまでフェチなんだか」
「アリサ」
「ね、実際のとこどうだった? 私の配信映え?」
「そ、それはその、綺麗だったわ」
「本当? でもさー、これからはメイクも少しは覚えた方がいいよね。今度ちょっと教えてよ」
「う、うん、それはいいけど」
「前に雑誌で写真出た時もさぁ、瑞穂にずいぶん助けてもらったよねー。出来てきた雑誌、ほとんど別人で笑った笑った」
「アリサ!」
優しすぎで人を押し退けるということの出来ない瑞穂だが、それでもやはり体育会系育ちだ。
その気になれば腹に力のこもったいい声を出す。
ちょっと驚くくらいの強い声音だった。
「瑞穂?」
「ここでくらい、私に対してくらい、そんなに強がらないでよ。私、私……」
勝っても負けても、誰より先に涙を流すのが瑞穂だった。
私もつられ泣きさせられたことは数知れない。
だけど今はそんな風に泣かないで欲しかった。
こらえきれなくなってしまうのが分かっていたから。
「う、く、うぅ……」
限界だった。
床に崩れ落ち、身も世もなく号泣した。
どんなに悔しかった試合でもそんなには泣いたことはないというくらい。
「ああああぁ! うわぁあああん!」
もう滅茶苦茶だった。
痛かった、苦しかった、悔しかった、恥ずかしかった、つらかった、お尻が今でもヒリヒリする、もうこんなの嫌だ、嫌だ嫌だ嫌だ。
何をわめき散らしたのか、自分でもよく分からない。
そんな私に瑞穂はずっと寄り添ってくれていた。
「あひゃあ! お尻がお尻が! ああん! お尻いいのぉ!」
気がつけば結局動画を停止しないままになっていたタブレットでも、同じように訳の分からないことを私が口走っていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
