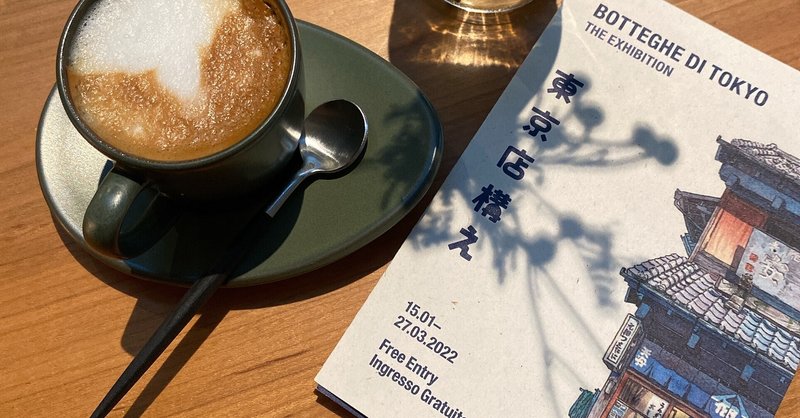
「東京店構え」(BOTTEGHE DI TOKYO):ミラノで開催中の特別展、マテウシュ・ウルバノヴィチが描いたリトル・トーキョー
今回のnoteでは、2022年1月15日よりミラノのTENOHA(テノハ)にて開催中の特別展「東京店構え」(BOTTEGHE DI TOKYO)について書いていく。
1. ミラノにて日本を発信する文化複合施設TENOHA(テノハ)
TENOHA(テノハ)は、2018年4月にイタリア・ミラノにオープンした文化複合施設である。
もともと東京・代官山にて、2014年11月から5年間限定でオープンしていたTENOHA。
パワーアップする形でミラノにやってきた時、ミラノ在住の人々の中で話題になったものだ。

2500平米という巨大なスペースと持つTENOHAは、主にメイドインジャパンの製品を扱う「SHOP」、レストランの「TASTE」、ワーキングスペースの「WORK」、イベント会場の「DISCOVER」、展示場の「KNOW」に分かれている。

過去にミラノのノマドカフェをまとめる時に、こちらのTENOHAを利用したが落ち着いた空間で居心地が良かった。


また2019年にはフオーリ・サローネの会場ともなっており、nendoとDAIKINのインスタレーションが展示されていた。
それでは次の章から実際に展示の紹介に入っていくこととしよう。
2. ポーランド人アーティスト マテウシュ・ウルバノヴィチ(Mateusz Urbanowicz)氏
ここでマテウシュ・ウルバノヴィチ(Mateusz Urbanowicz)氏について簡単に説明をしよう。
ポーランド人の画家・アーティストのマテウシュ氏は、現在、東京のアトリエにて、漫画家である妻カナ氏と活動している。
ポーランドのシレジア地方で生まれ育ったマテウシュ氏は、ワルシャワに位置するポーランド日本情報工科大学でコンピュータグラフィックスを学び、アニメーションを学ぶために来日。

神戸芸術工科大学を卒業後、スタジオにて背景デザイナー・アニメーターとして働き始めたマテウシュ氏は、映画『君の名は』(監督 新海誠・2016年)の背景を手がけるなど、活動の場を広げている。
そのほか、本展の元となった画集『東京店構え』を出版するなど、精力的に活動を続けているマテウシュ氏であるが、最終的には自身でストーリーや架空の街を生み出すことを目標にしているとのことである。
3. 「東京店構え」(BOTTEGHE DI TOKYO)
3-1. 飛行機に乗って日本・東京へ
マテウシュ氏の画集 『東京店構え』(BOTTEGHE DI TOKYO)をもとに構成される本展。
入り口から入るとそこは飛行機の中。

ミラノから東京に向かうという設定の機内である。


到着ゲートはこちら。

左手のコインロッカーに荷物を預けることができる。
空港でよく見るスチールの椅子も設置されている。


なかなか飛行機に乗って旅に出ることができないご時世において、フライトを擬似体験することができる演出が粋である。

3-2. ミラノのリトル・トーキョーへようこそ

中へ入っていくと、ほぼ実物大だと思われる大きなパネルが立ち並んでいる。
入り口付近には、パネルのモデルとなった店の位置が描かれる大型の地図が設置されている。

品川、赤羽、日本橋、秋葉原、北千住、浅草...と東京の様々なスポットに建つ様々なお店たち。
チェーン店が増え、どんどん変わりゆく街並みの中で、このような個人経営のお店を発見するとちょっとホッとするのではないであろうか。
次の節からお店のパネルたちを見ていくこととしよう。
3-3. 懐かしのあのお店たち
「座ぶとんのこいずみ」
上の方まで映っていなくて申し訳ないのだが、こちらの3階建てのお店は、一階はお店、二階は工房、三階は居住スペースとなっている。

特に座敷がある家には、座布団は必需品。
お客さんが来た時にはさっと並べ、お客さんがいない時には隅に積み上げておく座布団。
しかも職人さんのお手製ならば、丈夫で長持ちする。
大型家具店で安いクッションを買える、そもそも畳の部屋がない今、個人の座布団屋さんは苦労しているのではないかなどと思いを馳せた。
「菊谷橋カメラコーナー」と「天安」
手前にある「菊谷橋カメラコーナー」は、かっぱ橋道具街の一角に店を構えるカメラ屋さんである。
お店のショーウィンドウには、地域の人の成人式、七五三、結婚式の時の写真が並ぶ。
今ではコンビニや駅の前に証明写真機が至る所に見られるが、証明写真といえばこのようなお店に行って撮りにいっていた。
またビデオダビングの小さな看板も気になるところ。
1990年代に子供時代を過ごした筆者は、ビデオにお世話になったなと思い出した。
また「菊谷橋カメラコーナー」の背後にあるのは、佃煮屋さんの「天安」である。
小魚や海藻、貝を濃い味で煮付けて保存食とした佃煮。
ご飯のお供に最適であり、海外生活が長いとこういったものが一番重宝する。
天安のパネルの前には、海藻の見本が出されていた。
イタリアのスーパーの寿司コーナーでもごま油で和えたワカメサラダも置いてあるので、イタリアでも海藻が知られていないわけではない。
それでもなお、おにぎりの海苔、ふりかけのひじき、出汁の昆布と様々に海藻を使い分ける日本の食文化を海外の人に説明するのは難しそうだと思ったのであった。

「プリクラ機」
懐かしのプリクラ機を発見。
このプリクラ機をイタリアまで運んだことを思うと、ただただ驚くばかりである。
こちらのプリクラ機はもちろん使うことができるとのこと。

またブースには、説明をしてくださるイタリア人キャストの方が待機していた。

日本が好きという外国の方に出会うと、とても嬉しくなるし、本当にありがたい限りである。
「菊屋モータース」
さらに「天安」の奥に位置するのが、「菊屋モータース」である。

もともと1950年代より、バイクや車を販売していたお店であったが今では自転車を販売しているとのこと。
高校の通学路にはこのような自転車屋さんがあって、パンクした時や空気がなくなった時に立ち寄るスポットでもあったことを思い出した。
「菊見せんべい総本店」
こちらの立派な瓦葺のお店は、煎餅屋さんである。

お店の前には、旧式のレジ。

またお煎餅を焼く動画がプロジェクターで映されており、その音や雰囲気にまるでそこに香ばしい煎餅があるかのような錯覚を受ける。

なおこちらの煎餅たちは、TENOHAのショップで購入することが可能とのことである。

どさくさに紛れて(?)ハッピーターンがある。
憎い品揃えである。
あの魔法の粉の煎餅が食べたくなってしまった。

ブースにいたイタリア人女性が「これは何?」と私に質問してくださったので、「お米でできた甘くないビスコッティで、グルテンフリーだよ」と答えておいた。
こういったお煎餅が瓶詰めになって店頭に並んでるのもまた良い。
さらにその奥のブースにはたばこ屋さんがあり...

週刊誌や公衆電話が設置されていた。
あのオロナミンCのホーロー看板、筆者の子供時代の1990年代にもわずかに街に残っており、古ぼけた大村崑の顔がちょっと怖いとも思っていたのであった。

「鶴屋洋服店」
こちらの洋服店は、1928年創業のテーラーであったが、今ではヴィンテージ品を扱うお店となっている。
オーダーメイドでスーツを仕立てるということが珍しくなっている現代であるが、たとえ他店で購入した既製服だとしても、このような洋品店では修理をしてくれるのでとてもありがたい。

「マテウシュ氏のアトリエ」
さらにブースの奥に進むと、マテウシュ氏のアトリエが再現されたブースにたどり着く。

畳のある日本家屋の中にいくつもの机が並べられ、隅には資料の入った本棚、イタリアの人が見るとなんとコンパクトなアトリエだと思うかもしれない。
もしかしてマテウシュ氏がヨーロッパのどこか他の国にアトリエを構えていたらまた違った空間となっていたと思うのだが、決して大きくはない日本の家屋の空間はなんだかとても居心地が良さそうである。

マテウシュ氏の原画もここに。


またマテウシュ氏の道具も展示されている。

なお、マテウシュ氏個人のホームページには、彼が製作に使う道具が詳しくリストアップされている →★


職人さんの手仕事というか、作品だけではなく、その制作の工程や道具も見ることができるとても楽しいブースである。

「さいとう」
「さいとう」は阿佐ヶ谷の近くの商店街にあるパン屋さんである。
カラフルでポップな看板のパン屋さん、学校の近くに一つはこのようなパン屋さんがあったのではないかと思い出した。


左端には何故かどら焼きがディスプレイされているほか、配達用のバイクも似たようなものが設置されるという凝った演出であった。
「コバヤシ理容室」
こちらの理容室は、色のコントラストといい、ファサードの造りといい一段と独特なデザインである。
機能性よりも凝ったデザインの店構えを見ることがとんと少なくなった気がする。

また実際に理容室で使われていた椅子も設置されている。
ちなみに筆者は、美容室にて、このような椅子でシャンプーやヘッドスパをしてもらうとき、いつも気持ちよくて寝てしまう...

「フェローズ」
フェローズは、表参道に2011年にオープンしたハンバーガーショップである。
もともと1980年代に建てられた建物を利用して営業しているとのこと。

お店の周りには観葉植物が並べられ、ちょとした森のような雰囲気を醸し出している。
古い建物をリノベーションして営業しているお店、耐震性など問題はあると思うが、なるべく長くそこで続いてほしいと思うのである。
「中島屋酒店」
「中島屋酒店」は、目白台にて1936年から営業している老舗である。
サザエさんの三河屋さんのように、大型スーパーマーケットができるまでは、このようなお店が地域の家庭に配達に回っていたのであろう。
また酒屋さんの前に必ずといっていいほどある自販機。
普通の自販機だけではなく、他にはないお酒の自販機もあるからよくよく観察してみると面白い。
「誠心堂書店」
古本街の神保町にて1950年代から店を構える「誠心堂書店」。

古本だけではなく、和本なども扱っているため、学生さんや興味がある人にとってはたまらない空間であろう。

ここTENOHAのブースでは、実際に本棚に古本が並べられており、手に取って読むことができる。

岩波文庫のゲーテの『イタリア紀行』が欲しくなってしまった。
イタリアを愛した詩人ゲーテによる『イタリア紀行』には、イタリア各地の都市が出てくるので別の版元の電子版は持っていたのだが、やはり岩波文庫は紙で読みたいなと思ったりしたのであった。

「中央物流店」
こちらの物流店の前には、なんと本物のフォークリフトが設置されていた。

先ほどから、店前に描かれた乗り物の実物がパネルの前に置かれているなと思っていたのだが、まさか日本のフォークリフトもここにあるとは思わなかった。

さらにブースの一角ではポストカードが販売されており、

日本のポストに入れれば、届けてくれるとのことであった。
イタリアのポストも赤いことは赤いのであるが、この日本のポストの形が懐かしいと感じた。

「栄屋食堂」
こちらの食堂の前身は、ミルクホールだったとのこと。
ミルクホールとは、政府が日本人の体格を向上させるために牛乳を飲むことを推奨した明治・大正期にかけて、牛乳や軽食を提供していた飲食店のことである。

今では鄙びた食堂であり、ツヤツヤの食品サンプルがとても魅力的である。

日本のように食品サンプルやメニューに料理の写真が当たり前のようにあるのは、実はヨーロッパではとても珍しいことである。
イタリアのレストランでは、メニュー名と原材料しか書いていないので、名前からメニューを想像するということはしばしばである。

チャーハンの上にチキンライス?とよく分からない感じだが、とても美味しそう。

食品サンプル制作教室など、日本にはあると聞いているが、イタリアでそのようなワークショップをやったら流行りそうだとも考えた。

-------------------------------
以上、ミラノのリトル・トーキョーを歩いてみた。
どこのお店にも大体自転車やバイクがあったのを見て、平成の初め頃までは、自転車やバイクで移動できる距離で、地域に根ざして商売をするお店がまだ生きていたのではないかということに気づいた。

日本でも人口が減り、高齢化が進む中、小さな個人商店が存続するのはとても難しいことなのであろう。
古き良きものもを懐かしみ、残すことは、残念ながら私たち自身の暮らしの形に合わなくなっているのかもしれない。
それゆえにマテウシュ氏のイラストは、古き良き東京の街並みの標本のように感じる。
近い将来、このような古き良き店構えを存続させることが難しくなっていくとしても、ひょっとしたら100年後、200年後にリノベーションさせることができるかもしれない。
そのためにデザインの標本というものは、貴重な資料として後世に生きることであろう。
BOTTEGHE DI TOKYO
住所:
会期:2022年1月15日から
開館時間:11:00-20:00
入場無料
公式ホームページ:bottegheditokyo.tenoha.it
マテウシュ・ウルバノヴィチ(Mateusz Urbanowicz)氏の公式サイト:mateuszurbanowicz.com
参考:
「ミラノで大盛況。日本の発信拠点「TENOHA」はなぜウケているのか|前編」『Forbes Japan』(2020年2月22日付記事)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
