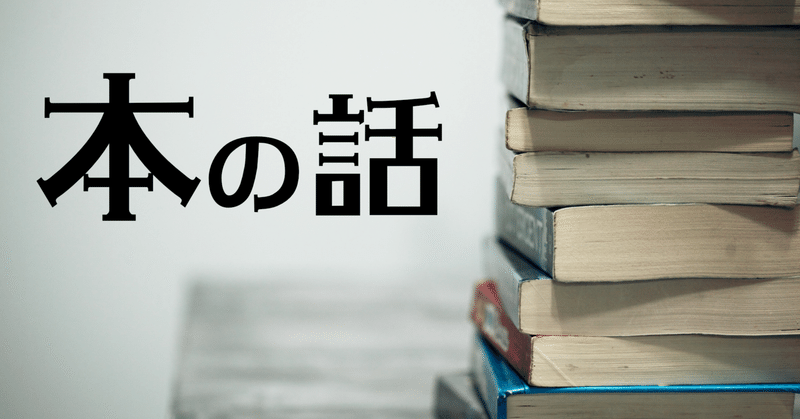
2022年上半期に読んで印象深かった小説をご紹介
上半期は上下巻などの分冊も別カウントしたら21冊の文芸書を読んでいました。その中から特に印象深かった7作を紹介します。5月以降は一度読んだことのある京極先生の「百鬼夜行シリーズ」を読み続けています。こうやって振返ってみて、色々読んだからこそ新しい出会いがあることが改めて認識できたので、今読んでいる『鉄鼠の檻』が終わったらまったく毛色の違う小説を読んでみようか思っています。
森見 登美彦著『熱帯』
読書中のワクワク感、世界観の快適さは上半期ベストだった小説。スティーブンソンの『宝島』や、『ロビンソン・クルーソー』のような冒険小説と、話しがマトリョーシカのように何重にも入れ子構造になっている『千夜一夜物語』の奇怪さを同時に楽しめる小説。
伊坂 幸太郎著『逆ソクラテス』
それぞれの話が面白いが、どの小説もゆるく繋がっていてそこもまた良い。表題作もいいけど、「アンスポーツマンライク」もよい、「非オプティマス」もいいし、「スロウではない」もよかった、「逆ワシントン」も捨てがたいし、結局すべて良い。
何をどう考えるのか、どう捉えるのかと言うのは、根源的な権利だし、どういった状況でも我々が自由にできる唯一のものだと思う。 でも、現代社会ではその自由を無視する人やメディアがあまりにも多い。だから、あばれる君は「自分はそうは思いません」と言うんじゃないかと思った。
伊坂幸太郎著『ペッパーズ・ゴースト』
久々に小説を一気読みしました。
普通に書けば重くなるテーマ(ニーチェ、集団自殺、テロ)で、これだけ心地よい読了間を出せるのは流石。
ニーチェの永劫回帰と言うこの世は同じことが何度も繰り返すという考え方は、まさに読者が読むたびに同じ体験を何度も繰り返すことになる、小説の登場人物に当てはまるんやなぁと思ったりしました。小説はネタバレになって他人の楽しみを奪いそうでなんやかんや書けないですね。
米澤 穂信著『黒牢城』
本能寺の変より四年前、天正六年の冬。織田信長に叛旗を翻して有岡城に立て籠った荒木村重は、城内で起きる難事件に翻弄される。動揺する人心を落ち着かせるため、村重は、土牢の囚人にして織田方の軍師・黒田官兵衛に謎を解くよう求めた。
あんまり時代小説や時代劇は好きじゃないんですが、この小説では作者が武士というわけの分からん生き物の精神構造を、現代人である読者に非常にうまく説明してくれている点が良かったです。おかげで時代物へのアレルギーがちょっとマシになるやもしれません。
砂川文次著『ブラックボックス』
今年の芥川賞受賞作品。これは私の話だ。定職に就かずに同じような毎日を繰り返していたり、CAAD10に乗っててディレイラーハンガー折ったり、苛立ちや不安から自暴自棄になったりしていた私からすると、一つの可能性としてありえた自分の姿だと思った。そんなこんなで私には非常に刺さった。グサグサと。
平野啓一郎著『本心』
社会が残酷だからこそ、個人の正義や、愛情がより素晴らしく見える作品。
決して理解することが出来ないと分かりながらも、その人の本心を推し量り続けることが、愛情なのかもしれん。
この小説の舞台となっている近未来は、現代よりも格差が酷く、取り残された人たちはバーチャルな世界に救いを求めている、そうした世界はきっと到来するので、その心づもりにも良いのではないでしょうか。
あんまり愛情について考えるのとかは好きでないんですが、そんな私が上記のような感想を書かざるを得ないような本でした。ストーリーが有るものなのであんまり色々書けないのが歯がゆいですが良かったです。
京極 夏彦著『魍魎の匣』
百鬼夜行シリーズで一番好きな『魍魎の匣』を読み直しました。思うところがあったので感想をまとめてみました。
読み終わったときに出てきた羨望を潰す感想。
こちらは「テセウスの船」について考えてみた感想。
2021年に出合った良い本
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
