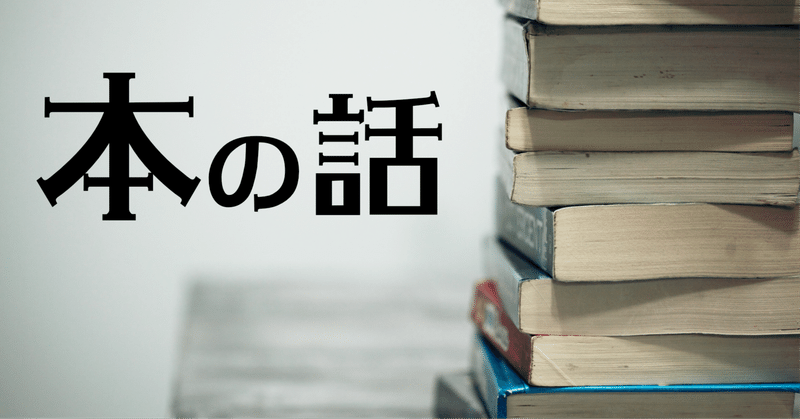
小川哲著『ユートロニカのこちら側』を読んで
ニートという生き方にも、向き不向きがあると私は感じています。私は比較的ニートに向いているので、社会に出てから特に理由もなく合計3年半ほど働かず、学ばず、何かを修めることもなく過ごしていたことがあります。
私は他人とコミュニケーションすることで疲れやすいタイプです。例えば、ある言葉に対して持っている概念が違うからそこからすり合わせするのは面倒くさいなぁと感じたり、この人の見ている世界ではそうなのであろうなと思って何も言えなくなったり、私の言い方が悪く伝わってないなぁとか、さっきのは以前の発言と矛盾するなぁなど思ったり、とにかく面倒くさいことをグダグダ考えてしまいます。そのため、私からすると人とのコミュニケーションはストレスになることが多いわけです。
私のような人間にとって、一般的な会社で人と関わりながら働くのはそれだけで強いストレスになります。逆に言うとニートをしていればその強いストレスが無いわけなんですが、今になって思い返してみると、ニートをしていた当時はそれまで気にも留めなかった小さなことにストレスを感じるようになったり、自らストレスを感じに行っていた節があります。「ニートは好きなことしかしなくてストレスが少ないだろう」と思う人もいるかと思いますが、ニートをしていた時に感じていたストレス量は、仕事をしていた時とあまり変わらなかったです。
以前読んだ本によるとストレスと言うのは刺激と言う意味なので、適度には必要で、過度にあるのは良くないのだそうです。ニートをしていてもストレス量が減らなかったのは、ストレスが人にとって必要だったからなんじゃないかと思い至りました。
『ユートロニカのこちら側』では選択や思考をAIに外注して無意識に生きている人が出てきます。意識の定義についてはややこしいので、ここではAIに言われるがままの生活に満足を覚えている人と定義します。
確かに、情報を精査せずにデマゴーグに踊らされる人や、自身の快感のために炎上に油を注ぐ人が現実にいることを思うと人間のする選択なんてものは碌なものではないですし、また、一々立ち止まって考えなくてもこれまでの経験で我々は半自動的に生活できるというのも事実です。さらに、昨今の生成AIの進化を勘案すると、人が選択をAIに外注して無意識に生きる未来と言うのは現実的なのではないかと思ったりします。
ただ、ストレスと同じように思考を0にすることはできないのではないでしょうか。例えどれだけイケてるAIに選択してもらっても、起こっている出来事をどう解釈するのかまでは外注できないですし、AIの選択肢に対するフィードバックはその人だけの物であるはずです。
このことから個人的には、出来事をどう解釈するかやどう感じるかが、人間よりも優れた選択をするAIが生まれた世界で、人に残る最後の自由なんじゃないかと考えています。
ただ、逆に思考を手放せないからこそ、解釈に自由が許されているからこそ起こる問題もあるんじゃないかと考えています。
生きていれば年々知識や体得している概念は増えると私は考えていて、私自身の世界の見方や、出来事に対する解釈の仕方は年々多様になってきていると感じています。その代わりに反応が鈍くなっていますが、個人的にはどんどん生きることが楽に、そして楽しくなってきていると感じています。
グラデーションなので2つに分けられる話ではないと思いますし、他人の頭の中は覗けないので実際のところそんな人はいないかもしれませんが、逆に経験の蓄積によって年々多様な解釈を手放している人もいるのではないでしょうか、そういった人は年々蓄積された経験のみで動けるようになるのでそれはそれで楽だし、素早い判断が可能なのかもしれません。
ただ、そういった人が全く思考しないわけではなくって、出来事に対する解釈は自身で行うのではないでしょうか?その解釈は個人の経験値から導き出された歪んだ概念や、これまでの人生経験から得られた知識から無理やり、事象に対する因果を導き出すことになるので、トンデモな陰謀論や、現代の科学を超越した理論に結び付くんじゃないかと思ったりします。つまるところ一人で体験できることなんて限られてますからね。
まぁ、ここまで書いた文章には何か証拠がある話ではなく、この因果関係も所詮私の持ってる限られた概念や知識から、事象に対する因果を勝手に導き出しただけなんですけどね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
