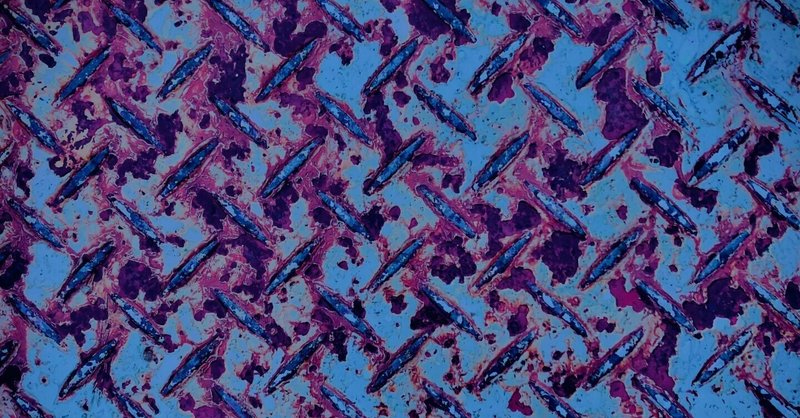
アウトサイド ヒーローズ:エピソード9-9(エピローグ)
センセイ、ダンジョン、ハック アンド スラッシュナカツガワ・コロニー唯一の酒場、“白峰酒造”。最後の客を見送ったドアベルが乾いた音をたてた。
「ありがとうございました」
青い肌の女給が戸口で脚を見送ると、大きな両手でのれんを下ろした。カウンターの下から二本角の男が顔を出す。
「お疲れさん。アオ、のれんをしまったら、もうあがっていいぞ」
「はあい」
アオは返事をしながら、するするとのれんを丸めた。戸口の横に立てかけると、いつも通りに淡々とカウンターを片付けている店主の背中を、ちらりと見た。
「“父さん”」
「おーう……何だ?」
アオの義父でもある酒場のマスター、今代の“タチバナ”は手をとめて振り返る。
「その……レンジさんたち、大丈夫かなあ」
「まあ、便りがないのは無事な証拠だろう。先代……クニテルさんは子ども好きだし、マダラがいれば、悪いようにはならないだろうし」
気にする素振りもないタチバナの顔を見て、アオはホールの椅子に腰かけた。
「クニテルさんって、どんな人なの?」
「お前はまだ、赤ん坊だったからなあ」
タチバナは懐かしそうに目を細める。
「うん……この店の元のオーナーで、兄さんにメカニックを教えた人だったことは、知ってるけど」
「俺も教わったんだぞ」
「えっ、父さんも?」
「ちっとも身に着かなかったけどな、ハハハ!」
意外そうな顔の義娘を見て、タチバナは大きく口を開けて笑った。
「それでクニテルさんはあきらめて、俺にはこの店のことや、格闘技を教えてくれたんだ」
「何でもできる人なんだね」
「ああ、すげえ人だったよ。全身が頑丈な結晶でできてて、一度も勝てなかったどころか傷ひとつつかなかったからな……」
思い出しながら天井の辺りに視線をさまよわせる。
「父さんは、よかったの? その、ええと……クニテルさんに、会いに行かなくても?」
「いいも悪いも、先代からの指示はマダラと、雷電とマジカルハートの三人だろう」
「そうだけど……」
カウンターから出てきたタチバナは、湯気ののぼるマグカップをアオの前に置いた。ハチミツをひとさじ溶かしこんだホットミルクだった。
「ほれ、それ飲んで、寝な」
カップを持ち上げると、甘い香りが漂う。アオはふう、ふうと息を吹き、ちびりちびりとすすり飲みはじめた。
「まあ、先代が会いたくないんだったら仕方がない。元々、“タチバナ”の名前とこの店を俺に譲ったときに『もう、会うつもりはない』って言ってたからな。それでも、コンタクトを取ってきたんだ。それなら、先代のやりたいようにやってもらえばいい。……それに、マダラにも頼んであるからな」
「えっ、何を?」
アオが顔を上げると、タチバナはわざとらしく口を開けてあくびした。
「ふわああ……んじゃ、俺はそろそろ寝るから。カップは自分で洗っといてくれ」
「えっ、ちょっと……」
タチバナはひらひらと手を振って、さっさと店の奥に引っ込んでいく。
「もう……兄さんが戻ったらどういうことなのか、聞かせてもらうんだから!」
「へくしょん!」
「大丈夫、エアコン上げる?」
ハンドルを握りながら大きなくしゃみをしたマダラに、助手席のアマネが声をかける。
「ありがとう、でも大丈夫だよ。ちょっと、鼻がムズムズしただけだから……」
「なら、いいけど……もう少しでナカツガワに着くから、頑張って!」
タイヤが瓦礫を乗り越え、時折車体が大きく揺れる。
湾岸の長い街道を走り、ナゴヤ・セントラルとカガミハラ・フォートを通り過ぎた2台は暗闇の中オールド・チュウオー・ラインを東に突っ走り、ナカツガワに向かっていた。
「うん、大丈夫。後は休憩なしで、いけるよ。……レンジはどう、このままいける?」
車載端末機に話しかけると、スピーカーがザリザリと音を立てる。
「『ああ、俺もいけるよ。ただ……着く前にちょっといいか、マダラ』」
「うん? どうかした?」
「『“お前は”よかったのか、あの爺さんのこと?』」
レンジの質問に目を丸くしたのはアマネだった。
「ちょっとレンジ君、何で今さら……!」
「『今さらも何も、あの時には爺さんの希望通りに動くのが第一だったんだ。訊けるわけないだろ、こんなこと』」
「それは……でも……だって、直接会えなかったんだよ!」
「いや、いいんだ」
黙ってやりとりを聞いていたマダラは、落ち着いた声で口をはさんだ。
「“ドット”を使ってモニターしてた時からわかってたんだ。あのプラントはどこもかしこも、運転が停まりかけてた。どれだけ持つかはわからなかったけど、爺ちゃんごと動かなくなるのは、時間の問題だったんだ」
「それなら、なおさら……」
「オレが直接会ったら、あの場で全部言わなきゃいけなくなるだろ。……だから、これでいいんだ」
アマネが黙り込むと、マダラは自分に話しかけるように小さく言った。
「それに、モニター越しだけど爺ちゃんの顔を見たし、おやっさんから頼まれたものも渡せたから。だから……うん、これでよかったんだよ」
「そっか」
もう少し力強く言うマダラの顔を見て、アマネも微笑んだ。
「『おい、二人とも、見てみろよ、空』」
レンジの呼びかけに、二人は慌てて視線を上げる。
「えっ」
「何かあった?」
「『いや、何もないけどさ、ほら……朝焼けがきれいだ』」
見上げると金色に輝く陽光が山の向こうから射し、薄紫色の雲が鮮やかに照らされて白んだ空に浮かんでいた。
そして両側に黒々とした森が茂る旧街道の先には、塁壁に囲まれた町の灯が見えていた。
照明の落ちた地下に、乾いた靴音と鼻歌が響く。
「フンフンフフン、フフフフ~ン……」
ひょろ長い影法師は調子の外れた陽気なメロディを口ずさみながら、“中央指令室”の扉を開いた。
「タチバナさん今晩は! どうしたんです、今日はえらく暗いですなあ! エレベーターも止まってたんで、こっちでハッキングして勝手に動かしちゃいましたよハハハ! いやまあすいませんなあ!」
白髪がわずかに混ざり始めた初老の男が開いた扉から顔を出すなり、息継ぎもせずにまくしたてる。ぼんやりとした照明灯が点いて、中央のコンピューター群が闇の中に浮かび上がった。
「何だ……相変わらずうるせえな、無玄。俺はもう”タチバナ”じゃねえって、いつも……だがまあ……間に合ってよかった……」
顔を上げた老人が弱弱しい声で返すと、“無玄”と呼ばれた男は暗闇の中をスキップするように歩いて、クニテルのそばにやって来た。身に着けていた暗視ゴーグルを外すと、いたずらっぽい少年のような大きな両目が老人の顔をのぞきこんだ。
「間に合った、って、どういう事です? だいたい、何で今日はこんなに暗いんです?」
「おい、おい……わかんねえ、とは言わせんぞ」
クニテルは口の端を引き上げて笑う。一方の無玄は軽薄な笑顔を引っ込めていた。
「プラント全体が、とまりかけてる……」
「その通りだ。けど……そら」
大型の作業アームが天井から降りてくる。コントロールを失った金属塊は勢いのまま、硬い表情でうつむく無玄の真横に落ちた。
「やっぱり、力が入らねえな……ほれ、それはお前の分だ。好きに使いな」
床にめり込んだアームには、白く輝くインゴットが握られていた。
「けど、タチバナさん、これは……」
ぽかんとした顔で振り返る無玄を見て、クニテルはからからと笑う。
「ここまで付き合ってくれた礼だよ。……それにしても、てめえがそんな間抜け面をさらすとはな!」
「だって、タチバナさん……これを作るのはリスクが高すぎるから、やめにしようって……!」
「いいんだよ」
無玄が必死になってすがるのを気にしない様子で、クニテルは目を閉じる。
「……俺は充分生きた、色々なものを見てきた。この遺跡の制御回路を生命維持装置代わりにして、ここまで生きてきたが……わかっちまったんだ。このままじゃ、死ぬこともできない、ってな」
「でも、まだ早いよ……!」
「確かに、今はお前も、ちょくちょく顔を出してくれてるがな」
クニテルは目を開けると、透き通った瞳で無玄を見上げた。
「このままだったらずっと……きっとお前が顔を見せなくなって、くたばった後も、ずうっと俺は、ここで生き続けるのさ。エナジープラントの生体部品としてな……」
小さな作業アームが震えながら動き、紙片を無玄に手渡した。
「お前はまだ、俺の事を“タチバナ”だと呼ぶがな……もう名前は譲ったんだ。次の代も、その子どもたちも頑張ってる。もちろん、お前もだ、無玄。だから俺の命は、ここが使いどころだろうと、そう思ったんだ……」
「そんな、タチバナさん……!」
「だから、俺はもう、“タチバナ”じゃねえ、って……」
クニテルが目を閉じる。結晶体の頭部につながった機械の体も、作業アームも凍りついたように動かなくなった。
「タチバナさん……!」
先代“タチバナ”の最後の弟子は薄明りの中、師匠が渡した紙片に目を凝らした。
「写真? ……これは……!」
弟子の両目が世をすねたな老人のような暗い光を放つ。無玄は動かないクニテルに再び視線を向けた後、持っていた写真に両手をかけた。写真の中のアカオニ……今代の“タチバナ”の顔を真っ二つに引き裂こうと力をこめて、
「ぐっ……」
しかし、歯をきつく噛みしめながらも写真を破くことをあきらめた。
「俺にとっては、あなたがずっと、“タチバナ”です……」
無玄は写真をクニテルの作業アームに握らせると暗視ゴーグルのバイザーを下ろし、振り返らずに“中央指令室”を去っていった。
少しずつ光量が落ちていく照明の中、透き通ったクニテルの顔が光を集め、作業アームにかざされた写真を照らす。
それは、“白峰酒造”の前で撮られた記念写真だった。
赤い二本角の男を中央に、オレンジ色と青色の兄妹が左右を囲む。鱗肌の少女と犬耳の少年が手前に並び、真人間の若い男女がそれぞれ、列の端に立っていた。抜けるような青空の下、一同は輝くような笑顔を浮かべて画面に収まっていた。
(エピソード9;センセイ、ダンジョン、ハック アンド スラッシュ 了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
