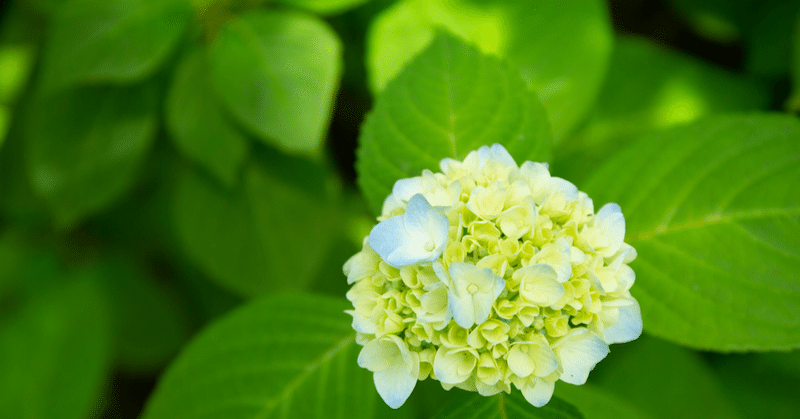
舞鶴旅行記2
遊覧船を降りて向かったのは、舞鶴引揚記念館。引き揚げやシベリア抑留を後世に継承し、平和の尊さを広く発信する施設として昭和63年4月に開館したものだ。
引き揚げとは、1945年(昭和20年)8月15日に日本が第二次世界大戦で連合国に降伏したことを受け、日本の外地・占領地または内地のソ連軍被占領地で生活していた日本人が日本の本土へ戻されたことを言う。敗戦時点で海外に在住する日本人は軍人・民間人の総計で660万人以上に上り、引揚げした日本人は1946年末までに500万人にのぼった。
だが、残留日本人の詳細な数や実態については現在も不明である。舞鶴への引き揚げ者の数は、66万2,982人。舞鶴港が1945年9月に引揚港に指定されてから、1958年9月の最後の引揚最終船の入港までの13年間に、延べ346隻の引揚船を受け入れた。舞鶴は日本海に面している関係で、ソ連からの引き揚げが全体の7割近くを占めていた。
対露重要拠点として発展してきたら舞鶴。ロシアよりアメリカの脅威が増していく時代になると、その地位は徐々に低下していったが、シベリア抑留を生き延び帰国した引き揚げ者を迎えたことで、舞鶴は再び脚光を浴びることとなった。舞鶴にソ連からの引き揚げ者を迎え入れるまで、日本とソ連の関係はどのような経緯を辿ったのか。日清戦争から引揚完了までを整理しておく。
日清戦争(1894〜5年にかけて行われた日本と清国の戦争)で台湾と遼東半島を手にいれた日本。しかし三国干渉(フランス・ドイツ・ロシアによる領土返還圧力)によって遼東半島を清国に返還。だがその後1898年(明治31年)には、そのロシアが遼東半島の南端に位置する旅順・大連を租借し、旅順に太平洋艦隊の基地を作るなど、満州への進出を進めていく。ロシアは、海軍強化のための不凍港を求めて大陸に進出し、南下政策を採っていたのだ。南下の方向として、バルカン半島方面への南下は困難と判断し、極東方面へと絞っていた。そんな折中国で義和団の乱(1900年に中国で起こった排外主義の民衆蜂起)が起こり、その鎮圧を口実に満洲を軍事支配してしまう。その様子に日本とイギリスが危機を覚え、イギリスが”光栄ある孤立”を捨て日英同盟を結ぶことになる。共通の危機を持つもの同士の同盟だ。イギリスがついたのだから大丈夫という声もあったが、政府内ではギリギリまで戦争回避の道を探っていた。そして1903年8月からの日露交渉において、朝鮮半島を日本、満洲をロシアの支配下に置いて戦争を回避するといういわゆる満韓交換論を提案したが、ロシア側がこれを拒否。このままでは日本独立の危機であり、戦争やむなしとして日露戦争(1904〜1905年)に。
日本勝利の後、ポーツマス条約締結。日本は満州におけるロシアの権益を賠償として取得し、ロシアの極東進出は後退を余儀なくされた。アメリカは、ポーツマス条約の仲介により漁夫の利を得て満洲に自らも進出し極東への影響力強化を企んでいたが、このアメリカの影響力を排除することで日本とロシアは利害が一致し、数度にわたる日露協約を結んで満蒙(南北満州と蒙古)における両国の権益・勢力範囲を分割した。第一次世界大戦ではともに連合国側に参戦するなど歩み寄った2国だったが、ロシア革命によりロシア帝国が倒され、日露協約は破棄。日本は極東への共産主義の波及を怖れ、同じくソビエトを敵視する英仏伊と歩調をあわせシベリア出兵。7万人以上の兵士を送り込んだ。撤退後、主に経済界からソ連との関係改善を望む声が多くあり、1925年1月20日に北京で日ソ基本条約を締結。その一方で、日本の共産化を目的とする日本共産党の活動には、厳しい目を光らせていた。
1939年9月にヨーロッパで第二次世界大戦が始まり、南進を可能にするため背後のソ連を敵にしたくない日本と、ドイツとの交戦に備え背後を固めておきたいソ連との利害が一致し、1941年に日ソ中立条約を締結。しかし、1945年8月9日、ソ連がアメリカのルーズベルト大統領と行ったヤルタ会談(同年2月)で対日参戦の密約を交わしたことにより、条約を一方的に破棄し満洲や南樺太へ侵攻。ソ連との戦闘は終戦となった8月15日以降も続けられ、8月23日にようやく停戦となる。そして、ソ連による旧敵国側の軍人と民間人の抑留が始まった。ソ連軍に降伏した多くの日本兵や一部の民間人は、「トウキョウダモイ」(東京へ返してやる)と言われながら、実際はシベリアをはじめとするソ連領地内へ強制連行された。こうした抑留は、戦争からの復興のための労働力確保のために行われたそうだ。他の国(中国・朝鮮・東南アジア)からの引き揚げが比較的順調に進んだのに対して、主権回復後も1956年まで国交を回復できなかったこともあり、ソ連からの引き揚げは容易には進まなかった。1946年12月から始まったソ連からの引き揚げは、1950年以降は舞鶴港が国内唯一の引揚港となり、1958年に終了した。
舞鶴の人たちは引き揚げ者に対して、旗を迎えお茶を振る舞ったり、暖かいもてなしを施したそうだ。過酷な環境にあった引き揚げ者たちはその気遣いに、どれだけ救われたことだろう。一方で、引き揚げ船に家族が乗っていると信じて舞鶴にやってきたが、再会の願いは叶わず、涙する人も多くいた。息子の帰りを信じ船を待つ母は、いつしか岸壁の母と呼ばれるようになったという。
では、過酷を極めたというソ連領地内での抑留生活はどんなものだったのか。氷点下を下回る環境の中、森林の伐採や炭鉱の採掘、鉄道の建設といった重労働の毎日。充分な食料を与えられず、日に日に痩せ細り栄養失調となり、一年目の冬を越せずに亡くなる人も多くいたそう。衛生状況も劣悪で、身体中にノミやシラミが湧き、赤痢やコレラといった伝染病が発症し、5万5000人を超える多くの犠牲者が出た。ただし、重労働ではない役務を課した収容所もあり、ソ連国民との交流が芽生えた例もあったという。館内には実際に抑留された極寒の地での住居を再現したものがあり実際中に入ってみたが、1つの暖炉に対して体を伸ばすのがやっとの簡易ベット(二階建て)がいくつもあるだけの簡素な部屋で、本当に寒かった。
記念館の展示の中で印象に残ったものの中に、抑留生活の日記や日本にいる家族との手紙のやりとりがある。家族への手紙はロシア兵に検閲されるため、なかなか本音は書けなかったというが、些細な日常の出来事や家族のことなど、それだけ知れただけでもどれだけ心の支えになったであろう。さらに、筆舌に尽くし難い抑留生活中で日本にいる家族のことを思いながら仲間と和歌を詠み合うことで、生きる希望を絶やさないようにしていた人もいたそうだ。冬はマイナス30度を下回るという過酷な環境の中、苦しい肉体労働に耐え人間としての尊厳を保つために、こうした文化活動がとても大きな役割を果たしたのだと思う。苦しい状況ですら和歌という知的表現へと昇華させていった当時の抑留者の人々へは、尊敬というよりもただただ畏敬の念しかない。現代は自分の心情を残す方法として和歌を詠む人は、ほとんどいないだろう。和歌は限られた字数や季語などの制約の中で、言葉に様々な意味を含めながら心情を詠むもので、日本独自の高尚な遊びとでもいえる。戦後まもなくの日本人に和歌を嗜む豊かな心を持つ人がたくさんいたということは、同じ日本人としてとても誇らしいことだと思った。
日記・手紙もさることながら、1番印象に残った展示は「坂井仁一郎さんによる抑留者安否確認活動」である。当時25歳の坂井氏は終戦から3年経ったある日、大阪門真市の自宅でラジオを聞いていると、偶然旧ソ連の国営ラジオ放送「モスクワ日本語放送」を受信。それがシベリア抑留者の安否情報だとわかると「聞き捨てならない」として、抑留者の名前と住所などを必死にメモに取ったという。そうしてその情報を、抑留者家族へと手紙で知らせた。実際に坂井氏が投函した葉書は、700通余りで、その内約半数は宛先不明で返送されてきたといわれる。以下、葉書の内容。
前略 突然のお葉書を差し上げる失礼をお許し下さい。さて昨7月1日午後12時のモスクワからの放送は抑留者通信としてナカガワ ハロウ様からの貴殿への『元気で近い帰国を待っています。こちらも御無事でお過ごし下さい。皆様によろしく』とのお便りを放送していましたからお伝え致します。もしお心当たりがあれば幸甚、なければそれも結構です。お破り捨て下さい。お名前は音訳ですから、それに稍(やや)聞き取り難いので誤りあるやも短(し)れません。右念のためご通知まで。 草々
偶然聞いた内容を自分が伝えなければならないと考えたその使命感によって、実際に手紙を送って知らせるという行動を起こした。今のようにネットに投稿すればすぐに誰かが拡散してくれるような時代ではないなかで、自分の耳で聞き手で書き、どうにかして残された家族にその情報を伝えようと努力なされた。坂井さんのその行動によって救われた家族は数知れない。後世まで名を残すに相応しい、本当に稀有な人だと思った。坂井さんからの手紙を受け取った家族からの御礼の返信も、以下かいつまんで紹介。
「淋しい淋しい、どん底生活の中に、貴女様からの暖かいお便り、どんなに喜んだことか、御想像下さい。目の覚めた思いです。・・かしこ」
「拝啓、本日は以外なる御書を辱(かたじけな)く深く御礼申し上げます。・・貴殿の御厚情な便り頂き一同安心致しましたと同時に衷心感謝して居ります。甚僭越乍ら右紙上を以て謹んで御礼申し上げます。敬白」
「拝啓、残暑の候、朝夕は涼気を覚ゆる時候と成って参りました。・・本當に此の生活苦と闘ひつつ首を長くして待って居るのです。・・右御禮迄 草々」
「拝啓、・・本當に御忙しい所わざわざ御便り下さいまして厚く御礼申し上げます。無事私は御蔭様にて七月一日に歸国致しました。・・先は御礼方々御通知迄。草々」
「・・私は九月二六日、シベリヤより無事故郷へ歸りましたから他事ながら御安心下さい。・・私も今日から吾々働く者の明るい豊かな住み良い日本を創る為に頑張る覚悟でおります。・・日共の下に結集されて御奮闘されん事をお願い致します。」
どの手紙も、家族の無事を知らせてくれたことへの感謝で溢れている。その溢れんばかりの感謝をどう表現しようか、そこにそれぞれの人柄・個性が出ているようだった。しかし、どの手紙もとにかく文章がガチガチに堅い(何となく言いたいニュアンスは伝わるだろうか・・)。昭和40年代はただの一般人でも、こんなにかっちりとした文章を書いていたのかと、少し驚いた。
文章がガチガチだと感じた理由の一つは、旧字体が多く使われているから。「旧字体」とは、画数の多い難しい漢字のこと。昭和24(1949)年に旧字体をやめて画数の少ない簡略化された漢字である「新字体」を使うようにと,内閣が国民に「当用漢字字体表」を告示するまで、一般的に使われていた漢字だ。「新字体」というと1949年に”新しく作られた字体”だと思ってしまうが、それは違う。漢字には昔から”正字”、”略字”、”俗字”など、一つの漢字に対して複数の異体字が存在することが普通であり、正字以外の字体も一般的に使われてきた。昔からある様々な異字体の中から、最も簡単に書ける簡略化された漢字を選んで「新字体」とされたのだ。ではなぜ、昔から簡単な文字があるのにも関わらず、抑留者家族の手紙にはあえて難しい漢字である旧字体を多く使っていたのか。それは明治期になってから隆盛した活版印刷において、旧字体が多く含まれる”正字”の使用が好まれていたからだ。戦前の書籍や新聞に、「國」や「學」などの旧字体が多く含まれるのはその影響だそう。この手紙が書かれたのは1948〜9年ころだろうと思われるので、まだ新字体の普及が進んでいなかったということだ。
もう一つの理由は、拝啓からの時候の挨拶を入れ敬白や早々・かしこで締めるという頭語・結語をきちんと押さえている文章だから。手紙なんだから当たり前だと言われてしまえばそれまでだが、恥ずかしながら私は今まで、頭語で始まり結語で終わる文章を書いたことがない。「草々」の具体的な使い方もよくわかっていないし、「かしこ」なんて言葉、実際に使った手紙を見たのは初めてだ。平成生まれの私はつくづく現代っこなんだと身に染みて思うが、それは仕方のないこと。物心ついた頃にはパソコン・ケータイがあり、何でもメールでやりとりするのが当たり前になりつつあったし、ビジネスメールの書き出しは頭語・結語は使用せず「お世話になっております」が基本。さらに現代は手紙という文化そのものがどんどん失われつつあるのだから、これからは手紙で頭語・結語を押さえた文章を書いたことがない世代ばかりになるだろう。時代と共に、文字や文章の型もどんどん変化していくもの。それは当然だし仕方のないことだけれど、やっぱりきちんと文章の基礎をおさえている文章は、単純にかっこいい。そして手紙がなくなってしまうのは、とても寂しい。ガチガチの文章を難しい漢字を使って書くという今はもうほとんど書ける人がいない文章を、物珍しさを含んだ憧憬の対象として、私は吸い付くように眺めていた。
正直に言うと私は、この記念館を訪れるまで「引き揚げ」ということについてほとんどと言っていい程何も知らなかった。戦争というものに対しても、客観的な事実(歴史)としてしか捉えられないとでもいうような、まだ少し距離感を持っていたような気持ちでいた。しかし、偶然だが隣で展示を見ていたご婦人が、館内の語り部さんと話しているのが聞こえてきた。その方は、ご自身がまだ母親のお腹にいる頃、他の兄弟たちとどこか外地から引き揚げて来られたそう。当時の話を2人でされているのを遠耳で聞きつつ、戦争終結によって起こった抑留・引揚の苦難というものが、私にとってまだ客観的な事実に過ぎないかもしれないが、ここに現に存在している人間に起きた紛れもない現実であるということを、バチっと思い知らされた。歴史を学ぶ上で、そういった現実を体験された方から教わることは、本当に貴重なこと。私は祖父母が戦争体験者であり、当時の話を本人から聴けることもできた世代だ。軍服を着た祖父の写真をみたり、父がまとめた祖父の自伝を読んだりして、少なからず戦争という歴史に対して自分との接点を持つことができたが、それでもなお距離は遠いと感じていた。やはりどこかで戦争というものに触れてはいけないという意識があり、それを経験した祖父母に対して、積極的に自分から当時の様子を聞かせてと言うことは出来なかった。たまたま話の流れでポロッと話してくれたものに対して、質問をする位しかできなかった。既に3人の祖父母を亡くした今になって、もっと自分から話を聞いておきたかったなと思う時もある。歴史が風化していくのは本当に早い。私の世代でも、接点が全くない、もしくは接点を持つことに興味がない人もたくさんいるだろう。ましてや私の子どもの世代ともなれば、この事実を現実として実感を伴う形で接点を持つことはほぼなくなる。そうなった時、何も実感が持てない世代にどうやって歴史を伝えていくのか。歴史を語り継いでいく大切さとその難しさを、まざまざと思い知らされた気がした。
記念館からの帰りの車の中、窓から漫然と外を見つめながら、記念館で見た一枚の写真を思い出していた。引揚船の中で母を亡くし、子ども達だけ身一つで舞鶴港に降りてきた時の写真。呆然とすることもできず、カメラを睨みつけているような表情の子供たち。この子たちは必死の思いで日本に帰ることはできたが、親はいない。戦争孤児はこの時代至る所にいたとは思うが、この子たちは一体どのようにして戦後の混乱の中を生きていったのだろう。途中、人生を逃げ出したくなることもあっただろう。それでも、辛くて辛くて認めたくないような現実の中を、生きていくしかないと心に決めて、この子たちは生き抜くことができたのだろうか。先のことがわからない真っ白な人生の中にも、少しでも希望の色を見つけて生きていて欲しい。ふつふつと感情が揺さぶられた一方で、こんなことを思うようになった自分自身に驚いた。母になる以前の私は、知らない子供に対して感情移入して揺さぶられるなんて絶対になかった。私もいつの間にか母になり、窓から見る景色が知らぬ間に変わっていくのと同じで、あっという間に年をとった。でも年をとった分、より多くのことに共感できる人間になれたということは、案外とっても嬉しい。
降りかかった不幸は比べられるものではないが、衣食住に不自由なく暮らしている私でさえも、人生楽しいことばかりではない。それでも、どうにもならない現実の中で、その人生をどう捉えてどう生きていくかは自分次第。楽しいことばかりではない人生の中にあっても、自分なりのささやかな楽しさを見つけて、家族と共に生きていきたい。改めてそう思った、舞鶴旅行でしたとさ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
