
都市で生きるとは?一一『ひとり空間の都市論』
建築家・伊東豊雄が、1989年に雑誌「新建築」に寄稿した論考「消費の海に浸らずして新しい建築はない」。この時私は生まれてすらいないが、どうやら当時の建築家社会+その界隈に、強烈なインパクトを与えた論考らしい。
たしかに、毎月コンスタントに発刊される雑誌の冒頭たった数ページの論考が、今もなおあらゆる局面で引用されるというのは、情報が横溢するこの時代には少し驚きを覚える。
伊東は「凄まじい勢いで建築が建てられ」と語り始め、高度経済成長期のピークを経て社会が成熟し始めた当時の建築界の状況を読解し、「消費の海を前にしてわれわれはその中に浸り、その中を泳いで対岸に何かを発見するしか方法はないのだ」と、その行く先を提示した。
また吉本ばななの小説に描かれるような、ノマド的に巧みに都市生活を享受する少女たちを「遊牧民」と例え、彼女たちに相応する建築を提案している(「東京遊牧少女の包(パオ)」)。
さて、伊東が建築の行く先を案じ警鐘を鳴らした89年、それから30年近くが経ち、今年こんな本が出された。
南後由和『ひとり空間の都市論』(2018、筑摩書房)
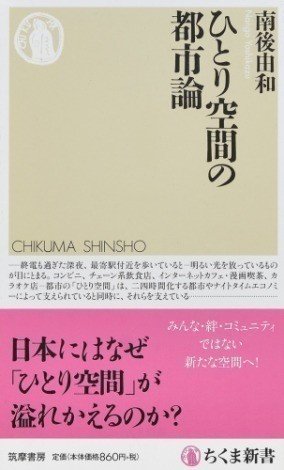
著者・南後は、ひとり空間=「個室であるか否かにかかわらず、何らかの仕切りによって、〈ひとり〉である状態が確保された空間」と定義する。そして〈ひとり〉には、人間の数え方や単位としての〈一人〉と、他人から独立し他者に束縛されない存在としての〈独り〉という2つの意味合いがある。
〈ひとり空間〉を生み出す何らかの仕切りには、壁や扉のような仕切りも、ウォークマン、携帯電話やスマートフォンなどのモバイルメディアの使用によって立ち上げられる「見えない仕切り」も含まれる。つまり、都市の「ひとり空間」は、物理空間のみならず、メディアを介して形づくられ、経験される。
本書では、「住まい」「飲食店」「宿泊施設」「モバイルメディア」に関する〈ひとり空間〉に焦点をあて、それらの事例(木賃アパート/牛丼屋/カプセルホテル/ウォークマンなど)を交えながら都市論を展開している。たしかに現代の都市社会には、多くの〈ひとり空間〉が存在する。交通機関や宿泊施設、娯楽施設など、それらは一人を単位として空間が商品化され、まさに建築は消費されていると言えよう。
冒頭の伊東の論考と、南後のこの都市論はパラレルに存在する。
つまり80年代から現代まで共通して、都市における〈ひとり空間〉が都市生活者たちの住機能を担ってきた。それは特に単身者に顕著なライフスタイルで、大衆食堂に始まり、銭湯、コインランドリー、喫茶店・・・などなど、就寝以外の住機能が都市空間に散りばめられている。
ならば、〈ひとり空間〉と住空間の外部化について、二人の論の違いはどこにあるのだろうか。
二人の違いは、それぞれの時代性に直結する。
80年代と現代を比較すると、〈ひとり空間〉という存在は、移動手段の更新と、都市社会における「まなざし」の存在によって意味合いが変わってきた。
移動手段の更新とは、杉浦康平『時間のヒダ、空間のシワ 時間地図の試み』(2014、鹿島出版会)に描かれたような、インフラの整備によって移動のハードルが下がり、移動の容易さに応じて空間的な歪みをもたらした状況を指す。
そして見田宗介が『まなざしの地獄 尽きなく生きることの社会学』(2008、河出新書房)で述べたように、都市社会には他者による「まなざし」が存在する。しかし見田が論じた60年代の「まなざし」は、「他者のまなざしがない=見られない」ことが苦痛であったのに対し、現代の都市社会は他者のまなざしが不在である。今の都市の姿を担保しているのは、それぞれの匿名性である。そして、この匿名性は炎上的キッカケで、瞬時に裏返されることもある。
今月の「建築雑誌」の特集で、建築家・内藤廣が「渋谷はビルに入ったら何も見えない場所である」と言っていた。たしかに渋谷のような、人々の匿名性が高い場所では、〈ひとり空間〉や〈身内空間〉が集積し都市が成立しているようにも見える。
移動とまなざしの変化により、住宅の選択も、それに付随する〈ひとり空間〉の性格も変わってきた。かつて木賃アパートという狭隘な住環境は、住み手にとって積極的な選択ではなく、あくまでも辛抱の場所だったが、けれども今では、都内でわずか3畳の部屋を好んで選ぶ者がいる。
彼ら彼女らは、移動性により住機能が担保され、自分の部屋とまではいかないものの、ほとんど他人を推し量ることが必要とされない都市環境に身を置き、まなざしをシャットダウンしている。
このように都市生活者は、「ひとり」を謳歌する。
しかし一方で、身内的な「コミュニティ」や「みんな」を使いこなし、それぞれ個人の内部に二極化した分人を抱えているのだろう。そして、おそらくその二極化は加速しつつあり、見て見ぬふりをするのが得意な、都市の居心地の悪さを体現しているのかもしれない。
しかし南後があとがきで綴ったように、〈ひとり〉は本来人の初源的状態であり、なにも特異なことではない。ならば、〈ひとり〉という状況に意識的であることが肝ではないか。
かつて、自ら進んで消費の海へダイブしていった伊東。伊東が今再び筆をとれば、〈ひとり空間〉が溢れる都市を嘆くことに意味はない、と言うのかもしれない。
