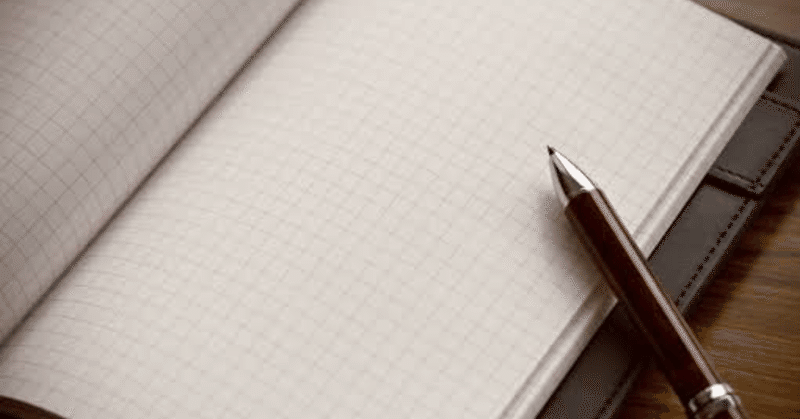
小説作法
読書が好きな方なら、小説家になりたいと思ったことが一度はあるのではないでしょうか。私はあります。読書を始めたての高校生の頃、中島敦のように精緻な文章を、谷崎潤一郎のように滔々と流れるような文章をいつかは書いて見たいと思い、鉛筆を手にとりました。
ところがいざ取り掛かってみると、全く書けないんですね。書けば書くほどこんがらがっていって、出来るのは当初の構想とは程遠いものばかり。脳内の考えをアウトプットすることの難しさを知りました。これはマズいと思った当時の私は文章読本の類を読みあさります。しかし…
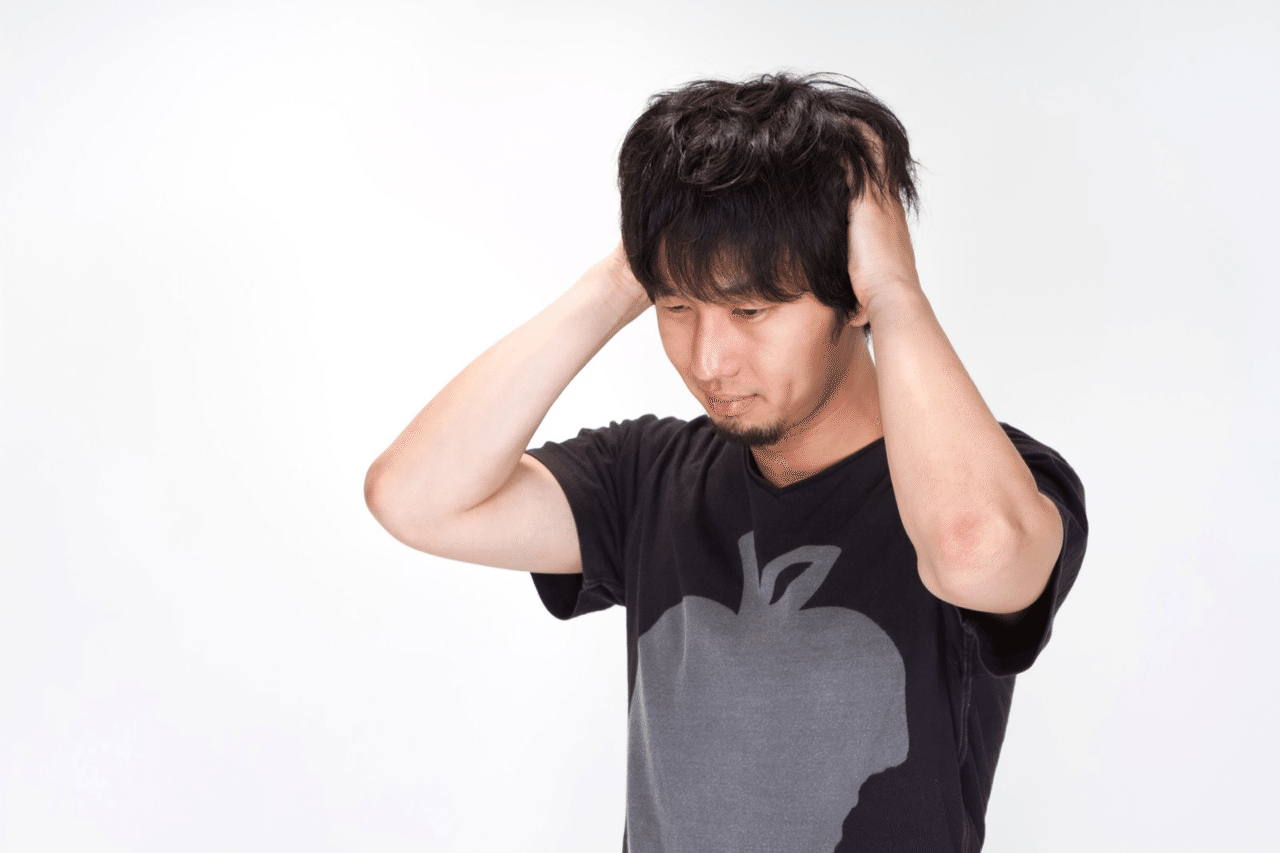
無駄な文章はなるべく削れ、教養のある文章を書け、名文を繰り返し読め、読書を娯楽に堕すことのない真の読者であれ…各々主張している内容が違いすぎる!!結局はオリジナリティの追求に落ち着くんだな〜と思ったものの、それが無くて困っている自分はどうしたらいいのかと途方に暮れました。
そんな時に出会ったのが岩波文庫『永井荷風随筆集(上)』の内の一段、『小説作法』でした。
荷風の主張

荷風の主張はこの上なく現実的です。
「文芸の道は天賦の才がなくては叶わず、下手の横好きで突き進むのは自信ではなくて迷いだ」
「文芸雑誌の投書欄に作品が載ったくらいで大喜びする人に大成の見込みは無い」
等なかなか歯に絹着せぬ物言いをします。
そんな中でも私が心を打たれた一節を原文のまま引用します。擬古文調なので少し読みづらいかも。
『読書思索観察の三事は小説かくものの寸毫も怠りてはならぬものなり。読書と思索とは剣術使の毎日道場にて竹刀を持つが如く、観察は武者修行に出でて他流試合をなすが如し。読書思索のみに耽りて世の中人間実地の観察を怠るものはやがて古典に捉はれ感情の鋭敏をかくに至るべく、己が才をたのみて実地の観察一点張にて行くものはその人非凡の天才ならぬ限り大抵は行き詰まってしまふものなり。前の二事は草木における肥料に等しく後の一事は五風十雨の効あるもの。肥料多きに過ぎて風に当たらざれば植木は虫がつきて腐ってしまふべし。さればこの三つ兼ね合ひの使ひ分けむづかしむづかし。』
読書思索観察。この3つは小説を書くのに限らず、様々な事をするにあたって欠かせない要素ではないでしょうか。
読書と思索だけでは机上の空論に陥り、観察のみでは大局的な視点に欠ける。理論と実践を両立させるためには全要素をまんべんなく押さえておく必要があるのです。
これを読んだ時に、私は今まで何かを書こうと意気込むだけで、何を書きたいのかが定まっていなかったことに気がつきました。読書も思索も観察も足りない。アウトプットをする前に、思考を醸成する基になるだけのインプットが圧倒的に不足していたのでした。

それがわかってからは、無闇に何かを書こうと急ぐことはなくなりました。まずはインプットの時間だと読書や部活に勤しんで、戯れに短い文章を書いては楽しむという落ち着いた生活をしています。
自分のいる状態をはっきり悟り、正しい方向に導く道標として『小説作法』は良い体験でした。
むすび
ここまで自分の体験に照らして、永井荷風の『小説作法』の話をしてきましたが、ここに挙げたものはそのごく一部です。和漢洋の広い学殖を素地として、荷風自身の小説家としての心得や意見を忌憚なく述べた『小説作法』、ひいてはその他の随筆まで一度読んでみてはいかかでしょうか。
ここまで読んでくださった方へのお礼をもって結びとさせていただきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
