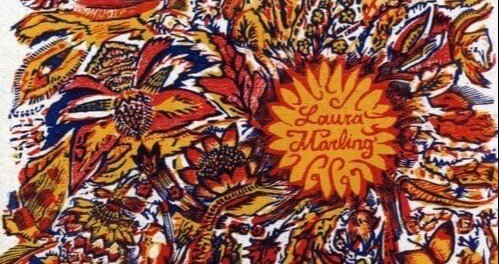
- 運営しているクリエイター
#アンビエント
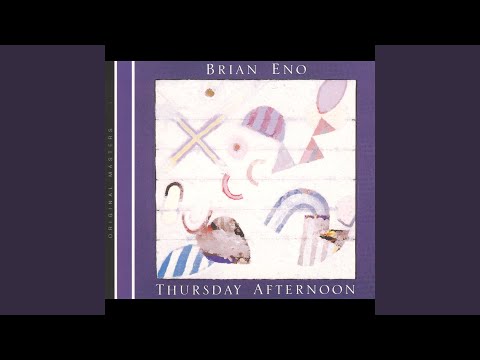
「Thursday Afternoon」Brian Eno(1985)
https://www.youtube.com/watch?v=pZ6V8pH4HPY http://kisonoabaraya.qcweb.jp/thursday.htm (転載はじめ) かすかに持続する低音のノイズ(ドローン)の上に、 シンセサイザーの澄んだ音が、まばらな星のように、 はじけて消えるシャボン玉のように、きらめき、たゆたう60分。 真剣に聴きいるための音楽ではなく、壁紙のような、 部屋に漂う香りのような、バックグラウンドとして制作された音楽。 目を閉じると、ほの暗い海の底で静かにまどろむ深海魚になった気分。 あわただしい日常から解放され、 ゆっくりほどけていく音の絵巻に身体をまかせる心地良さ。 自分という存在がだんだん小さくなってゆき、 あと少しで悟りが開けるんじゃないかと思いながら 30年ほど聴き続けています。 いまだ悟りは開けず、世俗の塵にまみれるばかりですが、 心の安らぎが欲しい時には、ふとこのCDをかけたくなります。 (転載おわり) 音楽は、聴く対象であり、「聴かれる音楽」と「音楽を聴く自分」には 境界線があり、そのラインは明瞭。 しかし、音楽を弱めにし、音楽を聴きとろうとしなければ、 弱めの音楽も、強い意識を持たない自分も、 その場に存在する「なにか」でしかない。 naka ♬ --------------------------------------------------------------------------------- 養老さん言われる 「脳」が物で、「心」が機能とすれば、「音楽」とは機能となるか。 存在ではなく。。。

聴く「Screen」Visible Cloaks(2017 米国)・「Jupitor」Miyako Koda(1998 日本)
アルバム名「Reassemblage」は、ベトナムの映画監督:Trinh T. Min-haの1982年同名作に由来。 という解説で目にとまる。 トリン.T.ミンハさんの著書 「女性・ネイティブ・他者 ーポストコロニアリズムとフェミニズム」、 一読したが、結局、頭の中でまとまらなかったので、今年の心残り。 その方の、映像作品をアルバム名にしている Visible Cloaks(米国ユニット)は、何者かと思いましてね。 ミニマルミュージック、エクスペリメンタル・ロックなどと







