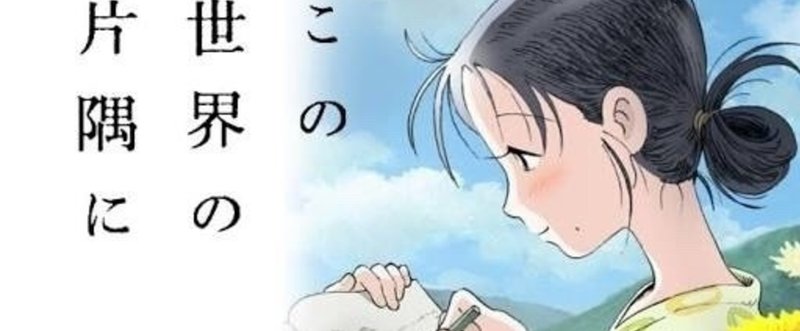
映画「この世界の片隅に」
見てきました。
原作読んだのがたぶん3年ほど前。その原作が好きすぎて、アニメ化の話題を見ても、最初はこわくて行く気になれなかった。たまにメディア露出される記事も、『長らく干されていた、あの!のんこと能年玲奈の復帰主演作!果たしてこの先の芸能活動は…!?』みたいなゲスい扱いが多くて、余計に食指が動かなかった。
でも、近頃映画を観に行く機会が多くて、ちらりと流れた予告編がよかった。これなら大丈夫かも。そう思って劇場まで観に行くことにしました。
行ってびっくり、各回満席で立ち見席が出てる!早めに予約しといてよかった…

記念撮影できるパネルもあるよ。
テアトル新宿で見たのですが、ここでは作品コラボメニューとしてタンポポ茶を出してます。このドリンクを注文すると、おまけとしてキャラメルを一個くれるの。このつつましいサービスが、作品世界とリンクしてる感じがしてグッときた。作品とその世界を、スタッフの人たちまでみんなが大切にしてる感じが伝わってきて、見る前から期待が高まる。
見終えた作品は、ひとことでいうと『ものすごく、よかった』。文句なしの五つ星でした。この先10年、20年と見続けられる映画だと思ったし、それを満席の劇場でみられたのも幸せだった。上映後に自然に拍手が沸き起こるような映画なんて、そうそう何度も見られるものじゃない。
でも、この良さをひとことで説明するのは難しい。テーマがテーマだけに、原作があまりの名作であるだけに、いろんな予断をもって見にくる人(とか、私みたいにアニメを避けてしまう人)も多いんじゃないかと思う。でも、とにかく見に来て!と言いたいです。
戦争モノだから「泣ける」というわけじゃないし、暗い日々の中を明るく健気に生きる主人公の姿に「元気をもらいました!」的な映画でもない。
描かれるのは市井の人々のありふれた日常で、起きる出来事のひとつひとつも、カレンダーをめくるように淡々と描かれる。主人公すずさんの失われた右手ですら、いつか当たり前のように画面に馴染んでいく。よくある「あの日」を頂点とするドラマじゃなくて、すべては地つづきの日常なのだ。そこがこの作品のすごいとこだ。
「暮らすこと」の中にあるさまざまな感情は、スクリーンに見入っている現代の私たちと何にも変わらない。毎日、楽しいこともあれば、もやっとした気持ちもある。戦争という時代を日常として生きるすずさんの暮らしの中にも、心からの笑い、ざわっとした悲しみ、恋心、いろんな生き生きとした感情がある。私たちはスクリーンを通して、そういうリアルなすずさんと、過去と繋がる。
そんな日常という絵に、ぼたん、ぼたんと黒い墨が落とされるように戦争が落としていく傷。それをゴシゴシと手洗いしながら「暮らすこと」「生き続けること」は、あの時代を家庭の中で生きた多くの女性たちの無言の闘いだったのだなぁと。

どんなことがあってもご飯を炊いて食事を用意し、繕いものをし、洗濯ものを干して「生活」を続けること。空襲にあっても人が死んでも、また食卓に並ぶ料理に、ぼんやりして見えるすずさんが死に物狂いで闘っていることを、私たちは知る。おっとりしたすずさんが、時に見せる激しい感情の生々しさ。抑制された表現だからこそ「日常」が踏みにじられていくことの怖さや怒りがひたひたと身にしみる。
前線の兵士たちを描く多くの戦争映画が伝え損なうことを、この作品は伝えている。「『この時、この場所』と、私たちの生きている『いま、ここ』は、地続きなんだよ」ということ。
この「地続き感」の凄さは、予告編でも使われている決め台詞のシーンが、しごくサクッと流されていくことにも表れている。ここ、こんなにあっさりなの…!?って拍子抜けする人もいるかもしれない。こうやって【拒まれた】ドラマチックなクライマックスの直後から畳み掛けられるシークエンスの激しさ、新しい家族を迎えてさらに続いていく北條家の営みの力が、この映画の「らしさ」を決定づけている気がする。
こういう作品の凄みを、果たしてわかって演じているのか感性で嗅ぎとっているのかよくわからないけど、アホの子の空気をただよわせつつ時折抉るようにひやっとしたものを突きつけてくる能年玲奈は、やはりただ者ではない気がする。
ついつい原作よりの話をしてしまうけど、アニメとしてもとてもよくできた作品だと思います。着色され、動き出したすずさんの世界は、漫画の世界と違和感なく、すっと入っていけた。細部に至るまで、どれだけ丁寧に作られたのかが画面から伝わってくる。
原作も実に緻密な取材の跡がみてとれる作品だけど、アニメのスタッフのフィールドワークも負けていない。作品は1日1日の日付と共に、すずさんの生きる毎日のエピソードが綴られるスタイルなんだけど、その日、その日の出来事だけでなく天候まで調べて描いているそうだ。
あとで読んで驚いたのだが、街並みのシーンでは史料提供してくれた方々の当時の家族の姿なども書き込まれているんだとか。
疎開世代のうちの母ももう80代。戦争の語り部が高齢化していなくなっていく時代に、本当に貴重な映画だと思います。時代を知る人も知らない人も見て欲しいし、原作も是非手にとって欲しい。
エンドロールにはクラウドファンディングで協力した人たちの名前が連なる。ここで流れる映像も作品の一部なので是非最後までしっかり見てください。
なんて野暮なことをわざわざ書くまでもなく、立ち上がる人なんていなかったけど。ネタバレになるので書きませんが、原作で好きだったエピソードなので、こういう形ででも残してもらえて嬉しかった。
ここからは個人的な話になるけど、原作を読んでから映画を観るまでの間に、たまたま仕事で日本の戦艦のことを調べる機会があって、呉の大空襲の話などを知っていたのは作品をみる上でよい知識だったなと思う。
あと、おざわゆき「あとかたの街」、岡野雄一「ペコロスの母に会いに行く」「ペコロスの母の玉手箱」などの漫画、梯久美子のノンフィクション「昭和二十年夏、女たちの戦争」あたりも、戦時中の市井の人々の生活を知るきっかけになる作品だと思うのでオススメです。
にしても、こんな良作の上演館が少ないことが本当に残念です。デジタル配信も始まってますが、上映する劇場を是非増やして欲しい。そして是非是非、世界中の人に見て欲しいと思います。こんなご時世だからこそ、余計にね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
