
会社設立以降毎年『論語』を読み返す竹谷がゆるくその解説をしてみます。
先日、こういうツイートをしました。
今日は年に一度のルーティンとして『論語』を読んでました!会社を設立してから毎年読んでいるのですが、忘れていた言葉や新たに気づく思いがあって、自身の心の変化を感じますね…!もっと心を鍛えないとあかんなあと改めて思う日や!
— 竹谷 彰人(ミリアッシュ代表)@パダワン (@akitotakeya) January 7, 2020
さて出かけるぜ!! pic.twitter.com/y2LwWLnFei
ツイートの通り、『論語』を読んだのもこれで4回目となります。もともとは渋沢栄一を敬愛しており、その渋沢栄一がビジネスと人生において重用していたのが『論語』だったため、竹谷も『論語』に拠ろうと思った次第です。なぜ毎年の初めに読んでいるかというと、年に一度は精神を調律する必要があるとなんとなく感じており、比較的時間に猶予のある年始が好機なためです。
『論語』を少し説明しますと、今から2,500年くらい前に生きていた孔子の教えをまとめた書物です。孔子は四聖のひとりとされ、ほかの聖人は仏陀、ソクラテス、キリストです。あれ、ムハンマドも入っていたような気がします。どうでしたっけ。まあ、つまり、ゲーム『DARK SOULS』で言うところの「四人の公王」が5人いるようなものですね、たぶん。世界の大きな宗教や哲学における、レジェンドたちの一員だと思っていただければ大丈夫でしょう。
孔子が開祖の儒教は、日本ではその学問体系のひとつである「朱子学」として、江戸時代に武士の教えとして重宝されていました。武士の学問ですから、明治に入り、武士の消滅に伴いじわじわと人気がなくなっていったのではないでしょうか。渋沢栄一も、幼いころ、つまり江戸時代から『論語』に触れていたようです。今から150年前までは、割と『論語』の教えは日本で認知度があったみたいですね。
さて、ふわふわで怪しげな概要はこのあたりにして、『論語』の内容へ話を進めます。今回記事に残そうと思い到ったのは、34歳の竹谷が『論語』を読み、どの言葉が印象に残ったかを記しておこうと欲が湧いたからです。来年に5度目の『論語』を読み終えるだろう、35歳の竹谷へ向けた備忘録となります。ただ、それだけでは面白くないので、『論語』の内容を竹谷なりに雑に解釈したものも添えることにしました。
「『論語』ってなんか難しそう」
そういった方に、わずかでも興味を持ってもらえる契機となれば嬉しい限りです。また、これから竹谷が引用するのはすべて岩波書店発行、金谷治訳注の『論語』であることを、あらかじめお伝えしておきます。
子の曰(のたまわ)く、君子は徳を懐(おも)い、小人は土を懐う。君子は刑を懐い、小人は恵を懐う。
先生がいわれた。「君子は道徳を思うが、小人は土地を思う。君子は法規を思うが、小人は恩恵を思う。」(p72)
先生は孔子を指します。君子は「超すごい人間」、小人は「普通の人間」、といったところでしょうか。それを踏まえて竹谷なりに解釈するとこうなります。
お金や「俺がこれをやったんだからなんか寄こせ」ばかり考えてないで、優しく正しくありたい。
さすがに雑すぎな気もしますが、いつもこの文を読む度にごもっともだなあと思います。竹谷は特に見返りを求めがちなので、そうなってはいけないなと常に気を引き締めています。
子の曰く、位なきことを患えず、立つ所以を患う。己れを知ること莫(な)きを患えず、知らるべきことを為すを求む。
先生がいわれた。「地位のないことを気にかけないで、地位を得るための(正しい)方法を気にかけることだ。自分を認めてくれる人がいないことを気にかけないで、認められるだけのことをしようとつとめることだ。」(p77)
承認欲求が猛威を揮っている昨今だからこそ、気をつけなれければいけないことではないでしょうか。竹谷の中ではこう解釈されます。
人気じゃなくて目的と手段が大事。認められないと嘆くより努力しよう。
「なぜ人気がほしいのか」「どう努力しようか」といった、目的と手段をたがえずに考えられる人間であろうと常々思います。
子の曰く、譬(たと)えば山を為(つく)るが如し。今だ一簣(き)を成さざるも、止(や)むは吾が止むなり。譬えば地を平らかにするが如し。一簣を覆(ふく)すと雖(いえど)も、進むは吾が往くなり。
先生がいわれた。「たとえば山を作るようなもの、もう一もっこというところを完成しないのも、そのやめたのは自分がやめたのである。たとえば土地をならすようなもの、一もっこあけただけでも、その進んだのは自分が歩いたのである。」(p177,178)
会社を作る時も、なにかを新しく始める時も、脳裡で反芻してきた大好きな言葉です。
やめるのも続けるのも、自分の決断。だれのせいでもない。
外的要因でなく、内的要因を考えたほうが良いといつも思います。それにしても、「止むは吾が止むなり」って名言にもほどがありますね。やめる時はいつだって、自分がやめようと思ってやめるわけですから。
子の曰く、衆これを悪(にく)むも必ず察し、衆これを好むも必ず察す。
先生がいわれた。「大勢が憎むときも必ず調べてみるし、大勢が好むときも必ず調べてみる。(盲従はしない。)」(p317)
これはもう解釈いらないですね。今から2,500年前に、SNSなどでいわゆる「炎上」に遭遇した際の、臨むべきひとの姿勢について言及しているわけです。ましてや現在は色々と調べやすい時代なので、情報量の少ない古代と比較し、じっと考えずに付和雷同してしまう悲しさは、より大きいのではないでしょうか。
以上が4回目の『論語』通読で、改めて感じ入った言葉です。3回目の時と割と近いようでいて、もう気にならなくなった言葉もあるように思います。それにしても、読むと必ず「ああ、これ俺まだまだちゃんとやれてないなあ!」と恥ずかしくなります。「不惑の四十」が人格完成の年齢とするなら、あと5年でなんとかまっとうな人間にならなければいけません。
頑張れ竹谷頑張れ!!俺は今までよくやってきた!!俺はできる奴だ!!
マンガ『鬼滅の刃』の竈門炭治郎から勇気をもらいつつ、心技体の心を鍛える意識をしっかりと持ち、勉強して参ります。
しばしのお別れだ、『論語』よ。また来年。
――――――――――
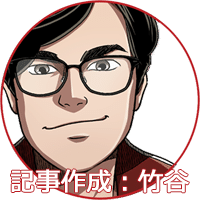
■ミリアッシュはイラスト・ゲームイラストの制作会社です!
■ぜひほかの記事もお読みください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
