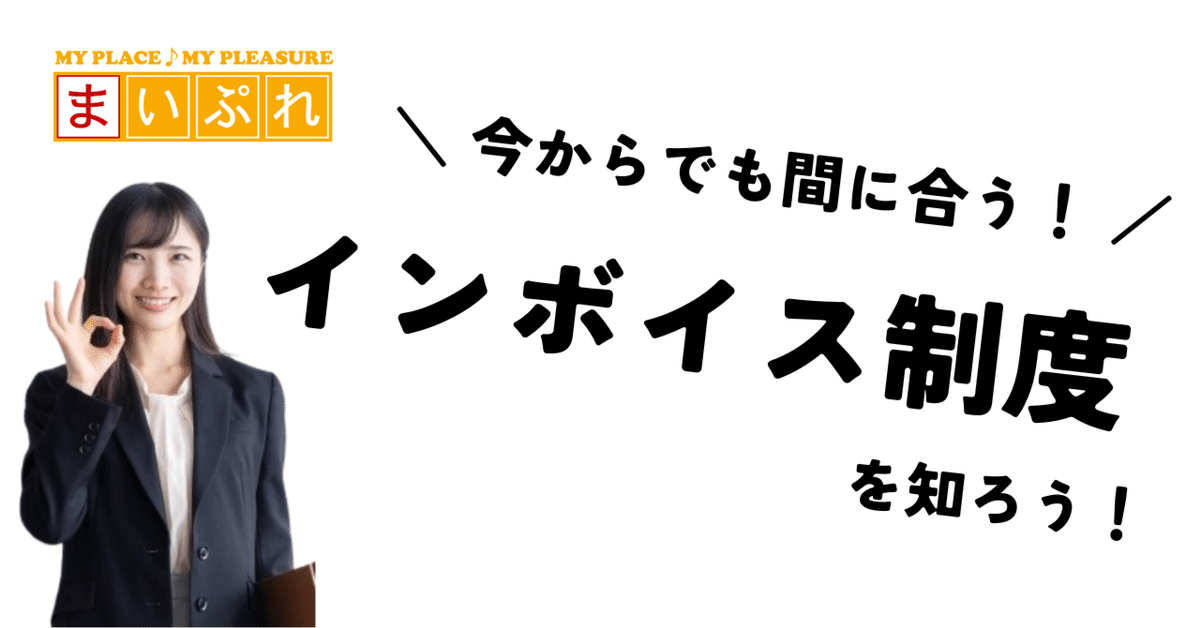
今からでも間に合う!インボイス制度【2023年10月~】
「いよいよインボイス制度が始まる!」「何から考えたらいいかわからない……」
どんな場合に対応が求められるのか、今回は「インボイス制度」についてできる限り簡単に解説を行っていければと思います!

まいぷれ本部の田口です。
ここ数年「インボイス」という単語を何度も耳にされた方もいるかと思います。
創業支援の立場でいろいろとご相談をいただく中で、たまに「インボイス制度に関してはどうしたら良い?」という質問をいただきます。
今回は「そもそもどんな制度かあまり調べられていないんだよね……」という方向けに説明していきますので、詳細というより必ず押さえてほしい基礎の内容を集中して紹介しようと思います。
そもそも「インボイス」ってなに?
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
この適格請求書(インボイス)の保存形式について取り決められたのが「インボイス制度」なんです(言葉通りの表現になってしまいすみません……)。
かなりざっくり言うと、「売手側と買手側との間で、消費税額などをいくらでやりとりしました!」という情報を正確に管理するための取り決めですね。
令和5年(2023年)、つまり今年の10月から正式に導入されます。

なぜ消費税額などを正確に管理する必要があるの?
「仕入れ税額控除」という仕組みが関係しています。
どういう話かと言うと、まず法人では事業年度終了日の翌月から2か月以内に法人税・消費税を納付しているんですね(法人前提で書いてしまいますが、個人事業でも税納付は同じです)。
この際、自社が顧客に対して請求した金額に上乗せされる「消費税」は、自社内に残るのではなく、決算後に税金として納付するものです。
しかし販売にあたって例えば卸売業者から仕入れを行っている場合、卸売業者から自社への請求においても消費税は課されていますよね。
すると、同じ商品を卸して販売する流れの中で、「卸売業者→自社」「自社→顧客」と二重に消費税が発生しているわけです。
そのため、「自社が顧客から受け取った売上に関連する消費税のうち、卸売業者に払った消費税の分は納付しなくて良いですよ」という扱いになっています。
これが「仕入れ税額控除」です。

具体的には、例えばA社が
1,000円(+消費税100円)でB社から仕入れ、
1,500円(+消費税150円)でC社へ販売した場合
A社が税務署へ納付する消費税は、仕入れ時の消費税分が控除され、
差額の150円-100円=50円
となるということです。
免税事業者の存在
しかし、事情が変わってくるのが免税事業者です。
前提として、基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合、消費税納税義務が免除される制度があります。売上が大きくないうちは、免税のメリットを受けながら活動している方が多いのもこれまでの現状でした。
一方でインボイス制度が導入されると、「免税事業者になるか」「インボイス発行事業者になるか」をどちらか選択しなければならなくなります。
※インボイス発行事業者は免税適用になりません
するとどうなるか?……解説していきますね。
自社の仕入れ元が免税事業者(=インボイス発行事業者ではない)であった場合を考えてみましょう。
この場合、仕入れ元からインボイスを発行してもらうことができず、仕入れ時に自社が仕入れ元へ払っている消費税額を明らかにすることができません。
すると、自社の顧客から受け取った消費税額を全額自社で納付することになります(先ほどの仕入れ税額控除が適用にならなくなるということです)。
仕入れ元の業者がインボイス発行事業者であるかどうかによって、自社の消費税納付額が変わってくるのです。

そうなると消費税額の負担を考え、取引相手として基本的にインボイス発行事業者を選びたいと考える事業者が多くなるのではないかと考えられます。
実際に今年10月の制度導入に向け、インボイス発行事業者となっているかどうかを取引先に確認される事例も生まれているようですね。
もちろん場合によりますが、取引先との契約を円滑に継続するため、自社でもインボイス発行事業者として申請しておこうと考える事業者が一定数いるのではないでしょうか。
※内容によってはインボイスがなくても良い取引もあります。詳しくは国税庁のWEBページにて
インボイス発行事業者になるために
所轄税務署への申請を行う必要があります。e-Taxでの申請もスムーズでおすすめですね。
ただし、この申請を行う場合、自身が課税事業者であることが必須となります。前述のように免税事業者として活動している方々は、そのまま免税メリットを優先するか、外部との円滑な取引を想定してインボイス発行事業者となるか一考の余地があるところです。
まいぷれ事業では
まいぷれ事業における取引では、弊社がまいぷれ基本サービスの開発を行い、そのサービスを各地で活動する「運営パートナー」の方々が地域店舗・事業者に販売しています。
この際、弊社はインボイス発行事業者として登録済みですので、取引時にはきちんとインボイスを発行いたします。(パートナーとしての運営をご検討の方々、ご安心ください!)
また、パートナーの方々の中には、別事業もあわせて営まれている方々もいらっしゃり、その際には卸売の立場になることもあるため、自社でインボイス発行事業者になるケースも多そうですね。(もちろんまいぷれ事業の中でも顧客である地域のお店・企業からインボイス発行を求められることも想定されます)
以上、おおまかなインボイス制度の解説でした!
※わかりやすさ重視で省いてしまった注釈なども細かくあるため、ご自身の経営において正確な情報を得られる際は国税庁の案内などをよくご確認ください
まいぷれ運営パートナーにご興味のある方へ
お問合せはこちらからお願いいたします
Youtubeでも情報発信をしています
