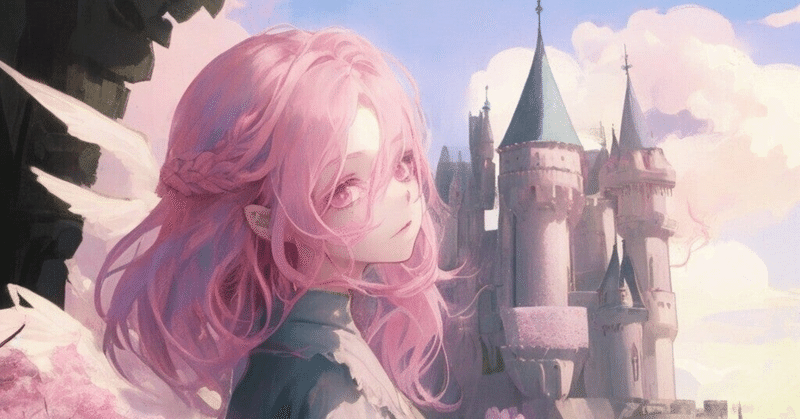
⑩攫われの姫君と、聖騎士の忘れ形見
生まれ持っての力。生まれ持っての身分。
私は、エルム王家始まって以来、初めての魔導石を持って生まれた王族となった。
他国の例を見ると、魔導石を持つ王は独裁的で圧政を敷くらしく、私の扱いについては国王である父とその他の王族、貴族院達と散々協議された。
結果、王位継承権を剥奪するのは道理がないので、最下位に位置づけられ、実質、それはないようなものにされた。
そしてその力故、どこかへ嫁がせることもなく、軟禁のような生活を送ることを強いられた。一部では、いっそのこと殺してしまえばという話もあったらしいが、流石にそこまでするのはという僅かな人の心が私を生かした。
私は文字通り、鳥籠の中の鳥のような人生を歩むことになった。
幼い頃に、仲の良い友人ができた。同い年の男の子、誰かの子どもなんだろうが、その正体を知るまでもなく、出逢って数週間でぱったりと現れなくなった。理由はわからないが、その喪失感から、私は友人を作るのを諦めた。変な期待は時として、自分を傷つけてしまう。
普段の生活は朝目覚めると、朝食前に王宮の庭園を散歩し、その後朝食を摂る。
午前中は勉学に励み、昼食後はアフタヌーンティーを、その後は特にすることは無く物思いに耽る。
退屈な生き方。幼い自分でも、それがそうだと認識できた。
同い年の平民の生活。教育機関で仲の良い友人と、共有する話題や時間。
それは、私にとってとても羨ましいことだった。時には妬みたくなる程に。
王宮から出ることを許されていない私は、退屈しのぎに王宮の人目につかない場所へと向かった。
そこは薄暗い、木々の生い茂った裏側。庭師も流石にここは手入れをしていない。それを責めるつもりはないが、逆にそれが心地良かった。何故ならば、管理されていない様を味わえるからだ。
私のような頭の先から足先まで徹底的に管理されている存在と、相反するその木々の様子。好き勝手に伸びる蔓、枝葉、飛び交う揚羽蝶と幹を這う甲虫。
私は、そこが好きになり、足繁く通う。
それがいけなかった。
ある日、目の前が真っ暗になった。
私は麻袋に詰め込まれ、文字通り攫われてしまった。
父には好都合だったろう。扱いに困る娘が、誘拐された。もういっそのこと殺されてしまえば、気を揉むこともない。都合の良い口実だ。
あからさまに距離を置かれていることに気付いていた私にとって、そう考えることが自然だった。何なら父の仕業ではないだろうかと思う程に、父への精神的距離を感じていた。
こんな力をもって生まれたのだから恨まれてこそ、愛されているわけがない。
気を失って目が覚めると、猿轡と目隠しで何処にいるのかわからなかった。
図太い男の声と、甲高い女の声。
男はどうやら怒っている。話の内容から察するに、父が要求を全く以て無視しているらしい。
本当に、いよいよ自分に対する父の評価が明らかになり、気持ちは萎えた。期待していたわけではないが、ほんの僅かな期待の欠片が砕け散った気がした。
諦めた瞬間、楽になった気がした。
気を張ることなく、王族として振る舞う必要もないのではないか。何の権力もない王族に何の意味がある。こうして攫われて、いっそのこと何処か関係のないところへ連れて行ってはくれないか、そう考えていた。
結局、各地を転々としながら交渉をしたが、最早私という存在を無かったことにする王家に対して業を煮やし、人売りへと売り渡された私は、気づけばその商品を詰め込んだ荷馬車の中だった。
布の切れ端のようなワンピースを着さされ、膝を抱えるようにして狭い荷馬車の中で揺られていた。
そして、そのままスウィントンへと運ばれた。
縄で前後の商品と繋がれ逃げられないように行列を作り、順番に競売に掛けられる。
この国の隅っこではこのようなことを行われているのかと、少し幻滅したが、最早私にとって、それは必要のない杞憂だった。
ふとした瞬間、一人の少年の熱視線に気付く。つい癖で微笑みを返してしまう。仕方がない、そういう教育をされてきたのだから。
まるで疾風のように駆け抜ける彼が少し気になった。
しかし逆に羨ましく、妬ましく見えた。自由に駆け回る少年が、そう見えた。
鳥籠での生活、手足を縛られている現状。
結局、私には今まで自由と呼べるものはなく、唯一あるとすれば、思想は自由だったろうか。
ついに諦めの沼の底まで辿り着いて、凡そ感情と呼べるものが薄れてくる。
喜びも怒りも哀しみも楽しみも感じない。自暴自棄と言ってもいい。
次に気がついたのは衛兵が騒いでる時だった。私の手足を縛る縄が短剣で切られ、腕を掴まれた。
素足のまま走り、路地裏にあった靴を拝借して逃げる。
走り疲れては励まされ、それの繰り返し。
私の経験上、この短い人生で最も走った瞬間だった。
坂を駆け下り、入り組んだ路地裏を抜けて街の外壁から抜け出せる穴を潜り、小さな舟で大河を渡る準備をする。
不安、それだけが感情を埋めており、なぜこんな事をするのか解らず、だが無我夢中に駆けていた時の興奮は忘れられない。
初めての自由だった。腕を引かれてとはいえ、思うがまま走ることができた。
そして何より、この気持ちが初恋だとわかったのが暫くしてからだった。それが何から来るものなのか、そんなのはどうでもいい。
彼――ルカから伝わる温もりと鼓動、息遣い。伝わるものが全て心地良かった。
知らない人から特別な人になった瞬間、とでも言うのだろうか。
胸の高鳴りを隠して、私はルカと歩む。
途中、大きな月が見えたり、溢れるほどの星空が見えたり、夜の虫の声や動物。色んな知らないものを見て、触れて。ここまでの経緯を忘れてしまいそうになる。
知らないものに触れる喜び。鳥籠の外は自由で、どこまでも飛んでいける気がしていた。
ボスウェルに来てからもそうで、存在は知っていても、実際見たことがない大道芸人の芸を見ることができて感激したし、行商人達の露店の活気の良さには驚かされた。
何もかもが、今まで触れてこられなかったもの。
夢中になっていると、ルカがいないことに気がついた。
よろしければサポートいただければやる気出ます。 もちろん戴いたサポートは活動などに使わせていただきます。 プレモル飲んだり……(嘘です)
