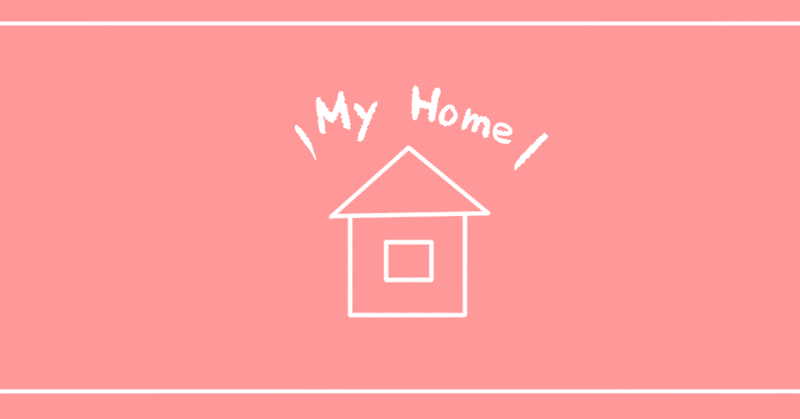
自分のコト | 住まいの変遷
生まれた時から現在に至るまでの住まいの変遷をまとめてみます。一人暮らしの経験はほぼありません。
子供の頃…親都合の転居
生まれてから幼稚園までは千葉に住んでいました。父の会社の社宅(団地)でしたが、同じ歳の友達も多く、幼稚園も年長・年中とも5クラスあるマンモス幼稚園でした。親は団塊世代、私は団塊ジュニア世代なので、子供の数が多かったのだと思います。
小学校に上がる前に、茨城に分譲戸建を買って引越しました。いわゆる「ニュータウン」というもので、同じような大量の戸建てに同じような家族構成(サラリーマン+専業主婦+子供2人)の家族がたくさん住んでいました。小学校は7クラス、途中で新しい学校ができて半数がそちらに移りました。田んぼの中に家も学校もあって、平和だったなーと思います。
小学校2年生くらいで、母が自宅で学習塾を始めました。少しして父が家を出て行きました。詳しいことは知らされていませんでしたが、中学受験をして、中学に上がるタイミングで東京に引っ越しました。
この時点で、母は私と妹を育てるために、東京で働かないと、と思ったのだと思います。都内の賃貸マンションに引っ越して、母は会社員として働き始めました。妹も中受をして同じ学校に通うようになり、私が高2になるタイミングで公社住宅の抽選にあたり引っ越しました。それまでの民間の賃貸マンションは、2年ごとに更新料や家賃の値上げがあったので、公社のマンションに移れてかなり助かったと思います。(エリアも最高でした!)
高3で、父と母が離婚しました。高1の時に私が父の住所を訪ね、別の家庭があることは認識していたのですが、その後どんな話し合いがあったのかはわかりません。母方の祖母が、孫(私と妹)が結婚するまでは離婚しないで欲しいと言ったとか、父の新しい家庭で赤ちゃんが生まれたとか、いろいろあったのだと思いますが、大学受験前に離婚したと聞かされ、勘弁してよ(=勉強に集中できない💢)と思った記憶があります。
その後、母によると、どこかのタイミングで父からの仕送り(養育費)が途絶えたようです。大学の入学金は出してもらえたようなので、私が就職した頃だったかもしれません。
結婚・独立まで…初めての家探し
就職して、自宅マンションの家賃を1/3負担することにしました。大学生になってからはアルバイトとサークルと、あとは友人や恋人の家に泊まることが多く、家で過ごす時間は少なかったのですが、就職してからは家で過ごす時間が増えていたと思います。
入社2年目に、大学生の妹がデキ婚することになり、なんだかもうこの頃はカオスでした。里帰り出産と言うことで妹と旦那さんがなぜかずっと我が家にいるという笑 でも生まれた甥っ子は超可愛くて、妹夫婦が自宅に帰ってからも毎週子守に通っていました。(妹はまだ学生だったので、授業がある日に子守に行っていました。)
数年後、妹の旦那が三重に転勤になり、妹の3人目が生まれるタイミングで、母は仕事を辞めて三重に行きました。この頃私は1人暮らし状態だったのですがあまり記憶がない笑 むしろ私も三重に行って子守りをしていた記憶の方が鮮明です。
妹家族が東京に戻って来てからまもなく、私も結婚することになりました。公社新築マンション住まいが快適すぎたので、この頃次々にできていた公団新築マンションへいくつか応募していました。落選ハガキが何枚かたまると当選しやすくなる、という仕組みがあったのですが、幸いその前に実家(公社マンション)の近くの部屋が当たったので、結婚の約半年前に家を出て、夫との同居生活が始まりました。姉妹とも家を出ることになったので、母は公社住宅を引き払って、祖母が住む実家(既に祖父は他界)に引っ越しました。
育児期…住む場所の選び方
新婚時代を公団住宅で過ごしたのち、結婚3年半で子どもが生まれることになりました。妹が母と私のフルサポートを受けて育児をしていたのと、それが子供達にとっても良かったと感じていたので、私も母と妹のサポートを受けて子育てすべく、引越しを検討することになりました。
母が住むエリアと妹が住むエリア(妹は義親との二世帯住宅に居住)のどちらが良いか悩んだのですが、この時点で妹の第3子が4歳、妹も仕事を始めようとしていたので母にサポートして欲しい、ということで、妹の家の近くに住んで、母が両家を行き来できるようにしよう、ということになりました。賃貸マンションを探しましたが適当な物件がなく、妹の家から徒歩3分ほどの中古マンションを購入しました。
長女が生まれ、生後4ヶ月で復職した後は、平日は母が育児(家事も)をほぼ全て担ってくれました。2年後に息子が生まれ、同じく生後4か月で復職しましたが、この時は保育園に入れたものの、相変わらず洗濯や夕飯の支度は母に頼り切りでした。
その後、母と祖母の折り合いが悪くなり、祖母の家の近くに母がマンションを買って祖母の家を出たのですが、母は平日は我が家(時々妹の家)、週末は祖母の家を行き来する生活を数年続けていました。それでも夜に1人で静かに眠れるから快適だと言っていました。
祖母が亡くなった翌年に我が家の末娘が生まれました。この時点で、その時住んでいたマンションに限界を感じて、広い家を探し始めました。マンションではさらに広い家は望めなかったので、中古と新築の戸建を探しましたが、駅近を諦めることで納得できる分譲戸建に巡り合い、引越しを決めました。長女は小学校に通っていたので、学区が変わらないことが条件でもありました。子供がいると家を選ぶ際に学区が重要であることを痛感しました。
それから4年、コロナ禍で母に手伝いに来てもらえなくなってまもなく、母の癌が見つかります。即入院になりましたが、孫達との面会も叶わなかったので、最後の数週間は妹の家で過ごし、在宅で看取ることになりました。在宅看護は家族の負担が大きいですが、妹と力を合わせてやれるだけのことができたと思っています。夏休み中の子供達も毎日会いに行くことができ、妹の家の近くに住んでいて良かったと思いました。
将来は?…家族近居したいけど
今の家は駅からは少し遠いのですが、リビングの窓から公園の木々が見え、環境は申し分ないです。母もとても気に入っていました。数年前に隣の土地が売りに出たので購入して賃貸戸建を建てました。(毎月家賃収入あり)
子供が独立したら今の家は広過ぎるので、子供達の誰かが家庭を持ったら住んで欲しいなあとか、隣の家に親やきょうだいが住んだら助け合って暮らせるんじゃないかな、とか妄想を広げたりしています。子供達が大きくなっても、家族(親戚)仲良く暮らせたらいいなと思っています。
一方で、私は長女を33歳で産んだのですが、長女が同じ歳で子供を産んだとして私はその頃66歳…孫と過ごせる時間はそんなに長くないのと、年寄り過ぎると近くにいてもかえって迷惑かな、なんてことも考えてしまいます。私は母にたくさん助けて貰いましたが、母が若かったから可能だったのだと今更ながら思います。そして晩婚・晩産が進んでいるので、子供達の世代は親の援助を受けにくくなるんだろうな、とも。我が家はともかく、一般的にはきょうだいも少ないから助け合うのも限界があるだろうし、子育てが困難になって少子化がさらに進んでしまうかもしれないですね…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
