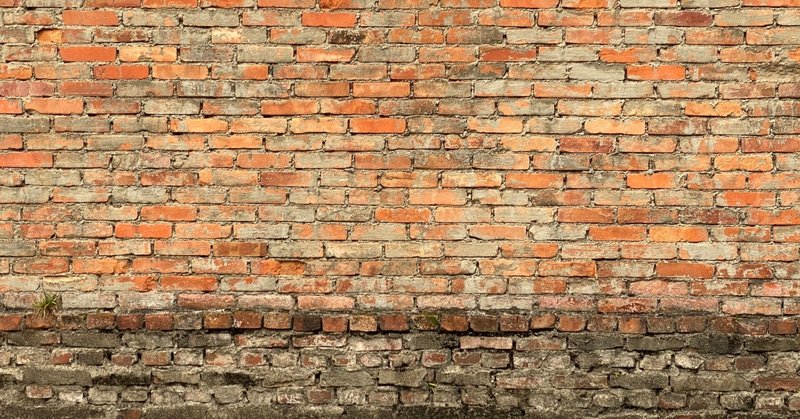
小説と短歌連作と映画と
今日は昼頃に目を覚ました。枕元に置いてあった恩田陸の『月の裏側』をなんとなく手に取って読み始めた。
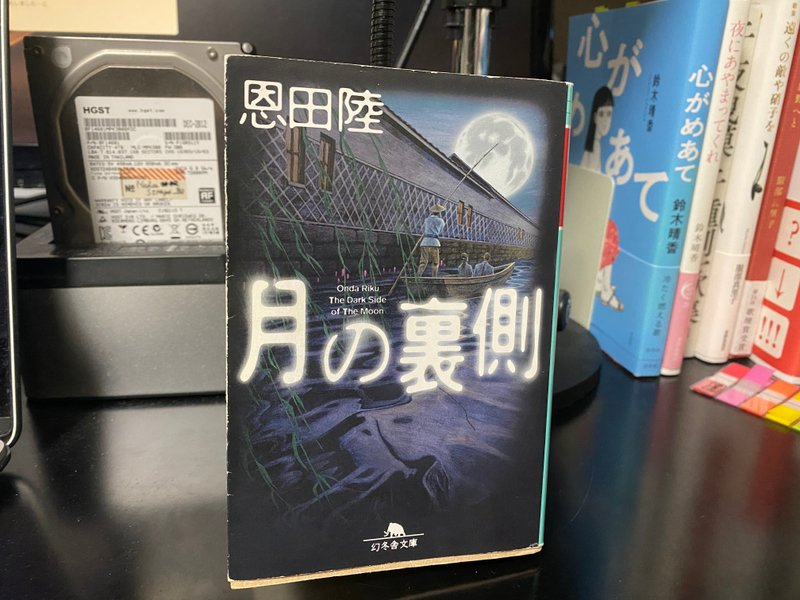
北原白秋や福永武彦のゆかりの地である福岡県柳川市をモデルとした、箭納倉(やなくら)という街が舞台の(あるいは街が主人公の)小説。ジャンル分けは……とても難しい。
恩田陸の小説はどれも好きだが、恩田陸の小説の中でもなぜかこの『月の裏側』を、一番繰り返し読み返している気がする。定期的にふと手にとって読みたくなるのだ。
文庫本にして450ページほどのこの長編を最後まで読んでもいいし、今日みたいに最初の100ページほど読んでもいい。ラスト近くでの主人公の塚崎多聞とある老女との会話のシーンが好きなのでそこだけ読むときもある。とにかくこの小説の言葉に定期的に触れたくなるのだ。
さて。そんな小説を今日読んでいて、ふと気づいたことがある。それは、「本筋に関係のないような登場人物たちの会話」や「ストーリーにはあまり絡んでこない風景描写」が、この作品を魅力を高めているのではないか、ということだ。一歩間違えば冗長さを生みかねないこれらが差し挟まることで、作品世界にリアリティが増すように思う。
もちろん、「本筋に関係のないような登場人物たちの会話」とは言っても、その会話の中には、登場人物たち各々のものの考え方や視点のありようが潜んでいる。それは、他の重要な場面での彼らの考え方や行動の仕方とうっすらと響きあっているように思う。
「ストーリーにはあまり絡んでこない風景描写」にしても、その風景によって、この作品世界のリアリティのある空気感が作られていることを感じさせる。
ここまで考えてきてふと思う。これって、魅力的な短歌連作と構造は同じなんじゃないかしら、と。
わたしは、魅力的な短歌連作を作ることができた手応えをまだ感じたことはない。それでも、名のある歌人の連作を読んでいて、心が強く惹かれたものの多くは、こういう構造が潜んでいるように思う。最近読んだ中では、例えば、松村正直「おとうと」(『紫のひと』収録)や、吉川宏志「鬼やんま」(『夜光』収録)だ。
わたしが連作をつくると、どうしても「言いたいことと強く関係するもの」ばかり詠んでしまいがちになる。あるいは「本当に関係のないもの」か。そして、〈作中主体〉が誰であれ、そのリアリティは弱い。
それから、心惹かれる短歌連作は、それが何首連作でもそこに流れる「時間」はあまり変わらないともよく感じる。恩田陸の小説もそういうところがある(名作とイマイチのものとあるが……)。短編でも長編でも、良くできた小説の時には、恩田陸特有の時間が流れ始める。
ここでまた別のジャンルの創作物を思い出す。ベルナルド・ベルトルッチの映画だ。ベルトルッチは有名な『ラスト・エンペラー』をはじめ多くの映画を生み出してきたが、そのキャリアの中で、極端に長い映画と短い映画を撮っている。
『1900年』(Novecento)という5時間以上の映画と、『水の寓話』という10分の映画だ。
どちらもとても良い映画なのだが、面白いのは10分の映画を観終わった時に感じる「時間というものの質量」と、5時間強の映画を観終わった時のそれが、ほぼ同じなのだ。
どういうマジックでこれが出来ているのか、本当にわからない。わからないけれどもどちらも魅力的なのだ。
ここから先は、分析を続けてみないとわからないし、短歌連作も5首と30首と50首では、また別物とも聞く(実際にそうだろう)。
それでも、恩田陸の『月の裏側』のような、あるいはベルトルッチの『水の寓話』のような、短歌連作をまず志してみてもいいのではないか、と今思っている。
どの長さであろうとも、「余白」と「背景」が存在し、読後感に「リアリティ」や「時間の重さ」を感じさせる、そんな連作を作れるようになりたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
