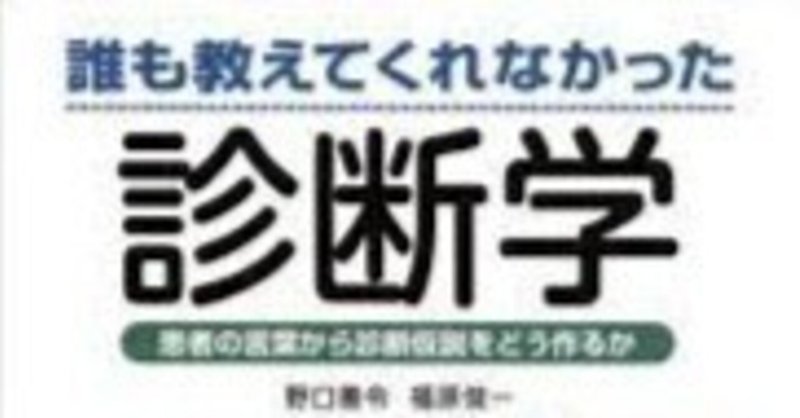
検査はすればするほどいいわけではない
臨床には不確実性がつきものです.100%確実に診断できる患者は例外であり,多くの場合,その疾患をもつ可能性が高いか,低いかというレベルでしかわからないのがふつうです.また治療の効果も100%確実に予測できません.こういった臨床医学の不確実性を認めて,医療とはあくまでも確率を高めることしかできないと認識するところから,エビデンスに基づいた医学(EBM)がはじまったと考えられます.
個々の患者がある疾患をもつ確率が30%とすると,おなじような患者を集めてみると,そのうち30%が病気をもつという意味です.ひとりの患者についてみれば,その病気であるかないかのどちらかであり,30%だけ病気ということはありえません.これは遺伝における同胞の再発危険率とまったくおなじで,ARであれば25%です.4人の子をもてばそのうちひとりが病気になるだろうという意味であり,ひとりの子だけでみれば遺伝疾患はあるかないかのどちらかです.
いま野口善令「誰もおしえてくれなかった診断学」という本を手元においていて,ときどき読み返しながら書いています.この本は診断推論を非常にわかりやすく解説した名著で,レジデントや後期研修医ならばすくなくとも本の名前くらいは知っているでしょう.
「藪医者」の診療行為の特徴として5点あげられていて,非常におもしろいです.そのうち後半の3つが,「③患者のクリニカルプロブレムの訴えに応じたアプローチができず画一的に検査を行う」「④鑑別診断に際して可能性の高い疾患と可能性の低い疾患を同じウェイトで検査してしまう」「⑤疾患を確定,除外するのに不適切な検査を施行する」となります.
⑤の「不適切な検査」については,筆者は高校生の胸痛にたいして「念のため」にとあいまいなままトロポニンTをオーダーした」例で説明しています.ここではわかりやすいように産科領域の例に移しかえてみましょう.
たとえば妊娠28週下痢で受診した妊婦の鑑別診断にあたって,下腹部痛を訴えているので,「念のため」に頚管粘液中の顆粒球エラスターゼ検査をだしたとします.このとき検査前確率が極端に低いため,陰性とでてくるのがあたりまえであり,仮に陽性とでれば意味もなく悩むことになります.「念のため」とあいまいなまま検査をオーダーしたための失敗であり,この妊婦に頚管エラスターゼをおこなうのは害だけあって益のない行為でした.
こういった考えかたがEBMにもとづいた診断推論です.検査前確率と検査の特性を考えて,疾患の可能性を高める(確定診断)か低める(除外診断)検査法を選択します.最初に述べたように,「100%確実に診断できる患者は例外であり,多くの場合,その疾患をもつ可能性が高いか,低いかというレベルでしかわからない」わけです.これは確率論的世界観とでもいうべきものでしょう.
すなわちEBMにもとづいた臨床医学の診断とは,おおげさですがある種の世界観にもとづいたものといえます.すぐれた臨床医は,世の東西を問わず,このような診断にいたる考えかたを経験的に身につけたのでしょう.90年代の臨床疫学はこういった臨床推論を数学化,理論化したものだとわたしは考えます.
北米にくらべて日本の臨床医学では,こういった蓋然性を中心にすえた確率論的な認識が伝統的に欠けていたのではないでしょうか.あまり主語をおおきくしすぎると,いろいろな誤解が生じてきますが,いずれにしろ日本人の伝統的な心性はこういった世界観と縁遠いものと思われます.
検査はすればするほどいいわけではない.確定診断ないしは除外診断に適切な検査を選ぶべきであるし,場合によってはやってはいけない検査があります(上のトロポニンTとか頚管エラスターゼなど).繰りかえしますが,検査はすればするほどいいわけではなく,それは医療資源とか医師の裁量といったこととはまったく関係のない話です.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
