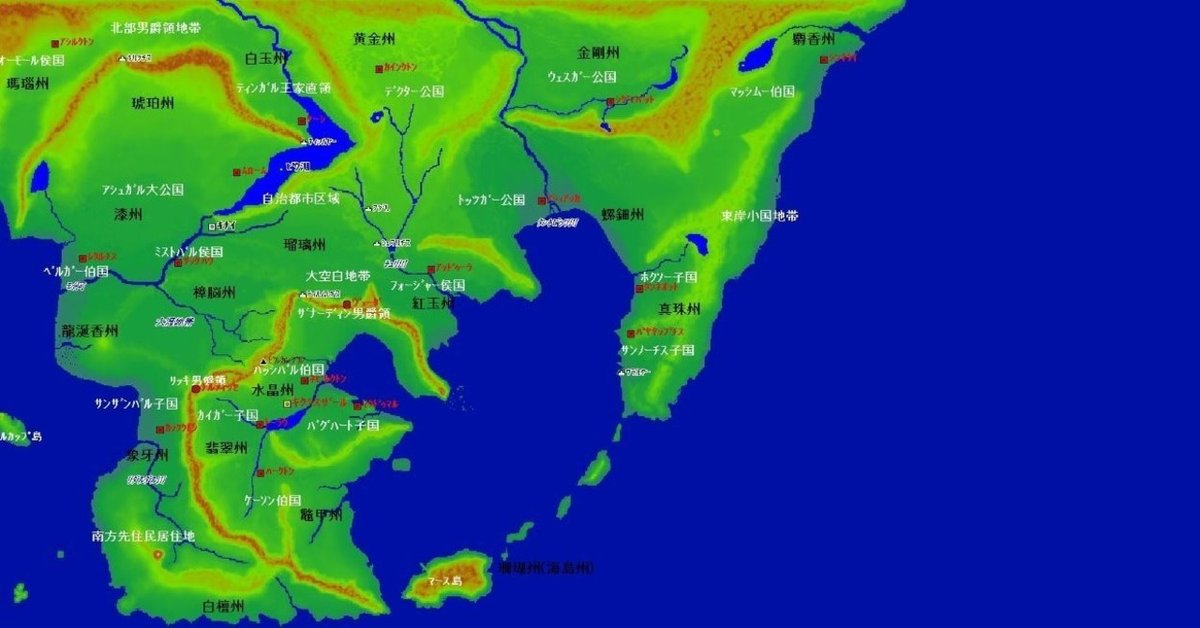
ティルドラス公は本日も多忙③ 冬終わる日に人来たる(10)
第三章 二都の角逐(その1)
夜半に近いマクドゥマルの城を冷たい風が吹き抜ける。夜回りの兵士が数人、かじかむ手で角灯をかざしながら庭を横切っていくが、その灯りもやがて角を曲がって消えた。
と同時に、闇の中から三つの黒装束の人影が現れ、滑るように物陰を伝って、手近な建物の裏手の暗がりに身を寄せる。
「これより、おのおの城内の適当な場所に潜伏して様子を探れ。」三人の頭目らしい男が声を潜めて言う。「三日後に城を抜け出し、申し合わせ通り、街外れの廃屋で待つバルトルディのもとに集合して、報告と次の探索のための打ち合わせを行うこととする。不測の事態が生じた場合は銀色の砂をどこかに残して合図とせよ。」
「はっ!」うなずく他の二人。
「よし、散れ!」声とともに、思い思いの方角に走り出そうとする三人。しかし次の瞬間、その足が止まる。いつの間にか、やはり黒装束に身を包んだ二つの人影が、闇の中、彼らの行く手に立ち塞がっていたのである。
「………!」三人のうち一人が無言のまま短刀を抜いて斬りかかるが、相手はそれを軽く受け流し、後ろに跳びすさって身構える。
「何やつ!」
「それはこちらが訊きたいことだがな。」頭目の言葉に応じたのは『蝉』だった。続いて傍らの『蜘蛛』が何かを薙ぎ払うように右手を大きく振ったかと思うと、三人の忍びの上に銀色の糸のようなものが覆い被さり、彼らの体に絡みついてぎりぎりと締め上げる。
「うおおっ?」悲鳴を上げながら身をよじる三人。だが、もがけばもがくほど糸はいよいよ堅く締まり、たちまち全身を絡め取られて三人はその場に倒れ込む。
「殺そうと思えば簡単に殺せるのだ。だが、ティルドラス伯爵はむやみに人を傷つけたり殺したりすることを好まれぬ。だから手加減しておるだけよ。余計な手間をかけさせるな。」『蜘蛛』は言う。「取りあえず逃がさぬようにはした。後は他の者に任せるか。」
『蝉』が頷いて片手で何かの印を切り、甲高い呼子笛のような音が周囲に響き渡った。たちまちあちこちで声が上がり、警備の衛兵たちがばたばたと集まってくる。「曲者だ。忍びの者らしい。」、身動きできずに地面に転がる三人を見やりながら『蜘蛛』が言った。
「どこの国の間者だ!」衛兵たちの指揮官が、忍びたちに向かって居丈高に怒鳴る。「ケーソン家か! カイガー家か! あるいはミストバル家か!」
「……ハッシバル家の者だ。」憮然とした様子で頭目が答える。「懐にハッシバル家の符節(ふせつ。任務を証明する木片)がある。確かめてみろ。」
周囲から上がる驚きの声。「チノーさまをお呼びしろ!」指揮官の命令に、数人の兵士が慌てて駆け出していく。
間もなく、チノーとサクトルバス、さらに騒ぎで目を覚ましたティルドラスまでが眠い目をこすりながらやって来る。「ネビルクトンから参ったと聞くが、まことか。」周囲のぴりぴりした空気とは少々場違いな穏やかな口調で、忍びたちに尋ねるティルドラス。
「摂政さまからの命を受け、この地に遣わされました。」少し口ごもりながら、頭目は答えた。「マクドゥマルにおられる伯爵を、陰ながらお守りするようにと……。」
「そうだったか。それは大儀である。」鷹揚に頷くティルドラス。
「お前たちの他にも送り込まれてきた者がいるのか。」チノーの口調はティルドラスのように穏やかではなかった。「何人ほどだ。今どこにいる。」
「十人ほど……。残りは城の外で待機しております。」
「では、他の者たちとともにネビルクトンに戻って叔母上に伝えてほしい。」とティルドラス。「お気持ちは感謝するが、見ての通り、私の警護は十分に足りている。私も他の者も知らぬまま身の回りに潜まれては、他国の間者と見分けがつかずに同士討ちをしてしまう危険もあるので、お気遣いは無用である、と。――放してやるが良い。」
彼の言葉に応じて『蜘蛛』が右手を振り、忍びたちの縛めが解ける。一礼してあたふたと逃げ去っていく彼らを見送りながら、ティルドラスはわずかに眉根を寄せた。
とぼけてはみせたものの、サフィアがティルドラスに何も知らせぬまま忍びの者を派遣して彼の身辺警護を行わせるなど、どう考えても不自然である。おそらくティルドラスがネビルクトンの支配から離れてこの地で独自の勢力を築くことを警戒し、様子を探るため忍びの者を送り込んできたのだろう。伯爵家の当主である彼が国都から離れた地に独自の勢力を築くというのも妙な話だが、今の彼自身、それを目指して行動しているのも事実だった。
ネビルクトンを初めとするハッシバル家本領の支配権はサフィア一派に完全に握られており、彼自身は飾り物の地位に置かれているに過ぎない。しかしキコックが言った通り、新たに得たこの旧バグハート領であれば、戦後処理を口実に、サフィアの意向に左右されず彼自身の方針で政治を行い人材を登用することができる。いずれネビルクトンに戻らねばならぬにせよ、その前にやれるだけのことはやっておきたい――。そう考えて、ここしばらく彼は、この地で自分なりの政策を行うことに精力的に取り組んでいる。
バグハート家時代の密告制度は廃止された。ハッシバル家本領との連絡を円滑にするための街道の整備と、その街道の安全を脅かす山賊の掃討も行われている。住民が逃散(ちょうさん)して荒れ地になった農地に流民や生業のない貧民、帰順した盗賊を定住させ、農具や種を貸し与えて収穫が軌道に乗るまで手助けをする試みも小規模ながら始まった。
社会が落ち着き力で押さえ込む必要も薄れたということで、デューシンは配下の兵とともにネビルクトンへと帰還していく。むろん、帰途の略奪は厳禁である。代わってデューシン麾下の第二軍に所属する雑号将軍であるトゥンガ=フーが、国境を接するようになったケーソン伯国への抑えとしてこの地に派遣されてくる。
トゥンガはティルドラスの祖父・キッツ伯爵の代からハッシバル家に仕える宿将だった。上将軍の称号こそないものの、宮廷内での序列は雑号将軍の第一位であり、個人的武勇・兵の指揮力ともに優れ、他の将兵からの信望も厚いハッシバル軍の重鎮である。一方で、摂政のサフィアに近い立場を取るデューシンとは異なり、彼自身はティルドラスへの忠誠心を公言しており、このためデューシンやサフィアからは快く思われていないと噂されていた。今回の旧バグハート領への赴任も、何かと目障りな彼をネビルクトンの宮廷から遠ざけておくためというもっぱらの噂である。
辛くも生きて牢獄から出ることができたツェンツェンガは、傷が癒えるのを待って一族の者たちとともにティルドラスの麾下に加わった。バグハート家時代のように将軍の地位を与えることはできなかったものの、校尉としてリーボック=リーの副官的な地位に収まり、ティルドラスの近くで相談に乗ることが多いリーボックに替わって白甲兵の指揮に当たっている。
ジュゼッペ=ナックガウルは、以前と同様、出処進退の自由を持つ客将としてハッシバル軍に復帰することに同意する。彼と同時に、と言うより彼より少し早くティルドラスに仕えたのが、彼の一人娘の婿でバグハート家の官吏であったオルフェ=オールディンという人物である。後世、子孫に破天荒な芸術家を輩出するものの、豪放で傍若無人な岳父とは対照的に、彼自身は謹厳実直で小心翼々とした小役人だった。もっとも官吏としては有能で、チノーを手助けする形で国事に伴う膨大な雑務を手際よく処理してくれている。彼とチノー、そして主に外部との交渉や各機関の間の調整・連絡を受け持つイック=レックの三人が、現在、ティルドラスのもとにあって旧バグハート領の行政を担う主な顔ぶれである。
こうしてみると、ティルドラスの周囲を固める者たちも、それなりの陣容は整ってきている。だが、それが一方でネビルクトンのサフィアとの間に隠微な対立を生んでいるのも事実だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
