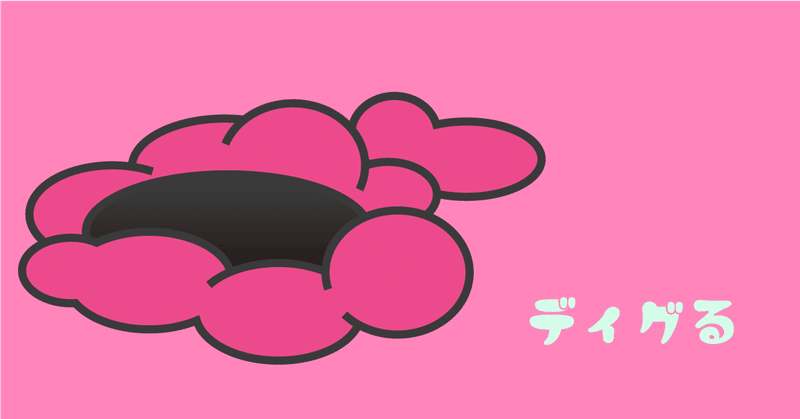
息子世代が楽しむコンテンツは、自分が体験したものとは違うものになりそう
月並みですが、こどもから学ぶことって多いなと思っている者です。
息子のコンテンツへの触れ方を見ていて、自分の世代との違いを感じることが多くあります。まず、息子の世代は生まれた時点で当たり前のようにスマホが存在していて、当たり前のようにフリック操作を覚えて、当たり前のようにYoutubeで情報や楽しめるコンテンツを探します。
この記事では、息子(2023年2月時点で8歳)を観察して気になったことを文章にしてみたいと思います。
息子を観察して気になったこと
「かなり古いもの」と「ちょっと古いもの」の差がない
Nintendo Switch Online など、最近は最新のゲームを楽しめる環境で数十年前のゲームを楽しめることが珍しくありません。音楽の世界でも、Spotifyに代表されるサブスクサービスで、時代性を無視してどんな曲でも聴くことができます。
少し前、息子がNHKの影響ではっぴいえんどの「風をあつめて」を口づさんでいました。今は、アニメの影響で「めざせポケッモンマスター」をよく歌っています。息子と一緒に映画館へ足を運んだ作品に「THE FIRST SLAM DUNK」と「シン・ウルトラマン」があります。
新しい古いに関わらずコンテンツが溢れ、古い作品も頻繁に再評価・リメイクされる昨今の状況は、新しい価値観を生み出しそうだと感じます。
面白がっているポイントが近いツイートを見かけました。まさにこの図の通りの感じ方を、ゲームに限らず、うちの息子もしていると思います。
CGの感じ取り方についての、メモ pic.twitter.com/XdKSP2HRRP
— てらちあ (@terachia_a) January 23, 2023
「Youtube解説動画」の位置付け
最近、ポケモンSVを買いました(サンタクロースが届けたていで)。
ショックだったのが、息子がサンタからのプレゼントを見て、包みを開けてプレイを始め、最初のひとくだりを終えたところでゲームを中断し、解説動画を見始めたことでした。
細かいニュアンスがなかなか文章にはしづらいのですが、息子は「自分で試行錯誤することが苦手で、効率のいい答えを求めた」訳でも「自分で開拓していくことにワクワクしない」訳でも「自分で進めるのが煩わしく、ネタバレに頼った」訳でもない印象でした。
僕が思うに「授業を受けるために、教科書とノートを用意した」ような感じに受け取れました。教科書が解説動画で、ノートがゲーム。セットで揃えることでより適切にゲームを楽しめるみたいな感じ。彼のなかでごく自然な行動のようでした。
自分の感覚に置き換えると、それによって「ゲームのなかで、新ポケモンに出会う感動」は薄まるように感じます。しかし、彼にとっては「新ポケモンにゲームの中で出会うも、解説動画の中で出会うも、同じように感動はする」ようで、不思議でした。
「最新」の価値がひくい
大人の目線からはコンテンツの賞味期限はとても短くなってきたように映ります。先にも触れたポケモンSVは、発売日の夜にはゲーム実況が乱立し、次の日にはクリア報告動画がアップされまくり、息子がプレイを始めた発売から2ヶ月後くらいには一通り情報が出揃ったような状況になっていました。なので、「息子にポケモンというコンテンツをムーブメントも含めて楽しんでもらうためには、発売日に購入すのが良いのかな」と考えてしまいます。
ところが、息子は「発売日あったら嬉しい」くらいの反応でした。これは、ポケモン以外にいくらでもコンテンツは選べること、ネタバレ動画からもプレイしたと同レベルの感動ができること、に起因しているような気がします。「誰よりも早く自分で感動したい」とは思っていなさそう。むしろ、さまざまな媒体のいづれかから「誰かと感動を共有できさえすればいい」という感じなのかなと思いました。
息子の行動全般から「誰よりも早いこと」を高い価値としていないように感じます。
「映画 フィルムレッド」が大ヒットしたワンピースも、ぼくたち世代と息子の世代で受け取り方は違いそうです。そもそもぼくたち世代には「物心をつく頃には90巻を超えるボリュームがあり、映画が大ヒットするほどメジャーな作品」なんてありませんでした。
息子の「フィルムレッド」を見た最初の感想は「ロビンって仲間になるんだね」でした。
ポケモンに興味を持ったら1000を超えるモンスターがすでにいる、プリキュアに今日にをもったら50を超えるキャラがすでにいる。目の前のコンテンツは「基本追いきれない、見切れない、集めきれない」というマインドセットがあるように感じます。
「既出の情報も基本的には追いきれない」なら「誰よりも早いこと」は確かに価値が薄そうです。

さいごに
発見を文章にするのって、めちゃくちゃ難しいですね。
もう少し、整理をして、検証をして、結論をまとめてとしたかったのですが、現象の記録までになってしまいました。自分の今の能力と持ってる時間だとこれが限界。うーん、悔しい。今年は「発見をしっかり仮説にする」ちからを養いたいと思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
