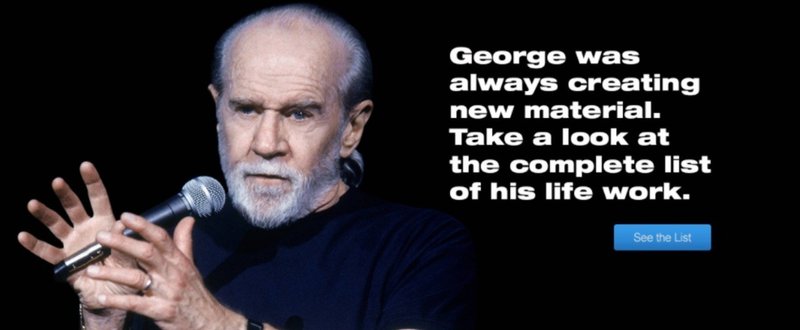
政治に、社会に、中指を立てたコメディアン ジョージ・カーリンについて
昨年末にウーマンラッシュアワーが、政治風刺を交えたネタをTHE MANZAIで披露し、注目を浴びていた。日本のテレビではあまりお目にかかることの政治ネタに対し、茂木健一郎さんや想田和弘さんなど、多数の著名人も賞賛を寄せていた。
ツイッター上に寄せられたコメントなかで目に留まったのが「ジョージ・カーリンを思い出した」という褒め言葉だ。
(日本のコメディーに詳しくはないが、村本大輔のスキットは政治的で、ジョージカーリンを思い起こさせるエッジが効いている。もっと彼のコメディーを見たい)
ジョージ・カーリンをリスペクトしている村本さんにとって最上級の褒め言葉だったはずだ。とはいえ多くの日本人にはあまり馴染みのない名前だと思う。
ジョージ・カーリンは1970年代から00年代まで活躍したアメリカのスタンダップコメディアンだ。タブーを恐れぬ過激なネタで、亡くなってからも絶大な支持を集めている。鬼気迫る表情で怒り哲学する彼の語りは、英語がわからない人にも強烈な印象を残すだろう。
お笑いネタは説明すると面白くなくなるのが常だが、いくつか彼の代表的な“過激なネタ”を挙げてみたい。
7 Words You Can't Say On TV(テレビで言えない7つの言葉)
カーリンが「過激なことを言う芸人」として、若者から大人気になるきっかけとなったネタ。米国のテレビでは禁じられていた7つの言葉“Shit, Piss, Fuck, Cunt, Cocksucker, Motherfucker, Tits.”を何度も口に出し、特定の言葉がタブーとなる状況をバカにしていく。
'There are no bad words. Bad thoughts. Bad intentions, and wooooords.(この世に悪い言葉はない、悪い考えと悪い意図、そして言葉だ)'
ちなみにこのネタを子どもと一緒に聞いた父親が、放送したラジオ局に苦情を送り、FCC(放送通信事業の規制監督を行う機関)がラジオ局を訴える事件も起きた。その際に最高裁は「子どもが聞く可能性のある時間帯に不快な言葉が含まれていた」というFCCの主張を支持する判決を下している。
・Euphemisms(婉曲法)
初期は「言ってはいけない言葉を言う」危険な笑いが特徴だったが、後期のネタでは言葉を通して見える社会そのものをネタにしている。
このネタでは婉曲表現がいかに政治家によって巧みに利用され、私たちの社会の見方を規定しているかを具体例とともに挙げていく。
例えば第一次大戦で生まれたShell Shock(戦争での精神的緊張によって起こる兵士の精神的な不調)という言葉。第二次大戦の頃にはBattle Fatigueとなり、朝鮮戦争ではOperational Exaustionに、ベトナム戦争時にはPost-traumatic stress disorderと呼ばれるようになった経緯をなぞり、「音節がどんどん増えて、強い意味を持つ単語がマイルドなものに置き換わっている」と徹底的にからかっている。
・America is one big lie and you are a fool for believing in it.
アメリカのバカバカしさを指摘するネタも鉄板だった。その鋭い刃は、“All men are created equal(全ての人間は平等である)“と唱えたアメリカの建国者たちにも向けられる。独立宣言も憲法も国旗も、“奴隷と黒人と女性以外は”全員平等と考える白人の奴隷所有者によってつくられたfull of shitじゃないかと言い切る。
カーリンは「神」や「宗教」に対しても疑いの目を向ける。「神なんぞいない」と断言するネタは、映画評論家の町山智浩さんがラジオでジョージ・カーリンを紹介していた際にも言及されていた。「神がいるならなんで戦争や病気、死、貧困が溢れているんだ」と嘆くネタだ。
If this is the best God can do, I am not impressed. Results like these do not belong on the résumé of a Supreme Being.(これが神がベストを尽くした成果なら関心できない。この程度の成果なら神のレジュメに載せられないだろう)
正統派コメディアンとしてのスタート
全方位に喧嘩を売っているようにみえるカーリンだが、元から過激な芸風だったわけではない。1937年に生まれた彼は、空軍を経てラジオパーソナリティーとして活躍、1959年のボストンで後の相棒Jack Burnsと出会った。当時“どちらかと言うと保守”だった彼は、Burnsとの会話と通して“政治やリベラリズムについて”学んだそう。
彼らがロスに移る数年前、1950年代半ばごろから、アメリカではレニー・ブルースなどのコメディアンが、忖度なしのネタで人気を博し始めていた。「The Comedians: Drunks, Thieves, Scoundrels, and the History of American Comedy」のなかで、カーリンはいかにレニー・ブルースから影響を受けたかを語っている。
反抗的な態度のある題材、優れた物真似芸、知性、そして彼らが持っている自由。それらを可能な限り真似しようとした。当時の私たちは時事ネタを扱い、自分の立場を明確にしていた。レイシズムやクー・クラックス・クラン、ジョン・バーチ・ソサエティ、宗教について扱った。子どもにヘロインを与えることについてもだ。(筆者訳)
1960年代以降の風刺コメディーへの転換
その後カーリンはコンビを解消して一人で活動を始める。カトリックを批判して逮捕されようが動じないレニー・ブルースを目の当たりにしてきたカーリンは徐々に過激な芸に方向転換していく。
そして冒頭のような政治風刺を交えた過激なネタを続々と世に送り出していった。1972年には先述のネタ「7 Words You Can't Say On TV」を野外フェスティバルで披露し、その内容が理由で逮捕されてしまう事件も起きた。
その危うい芸風により彼は複数のコメディークラブを出禁になってしまう。しかし、長髪に髭を生やし、LSDでハイになったまま舞台にあがる彼は、ヒッピーたちから圧倒的な支持を受けていた。
1972年に発売したレコードで最優秀コメディー・アルバムを受賞、1975年にはのちに国民的コメディー番組となるSaturday Night Liveの第一回目にゲストホストとして登場。危険なネタを披露しながらも堂々とメインストリームで活躍していた。
カーリンはメジャーの場で活躍する機会を得てもなお、“何でも自由に発言できる”ライブという場を愛していた。彼の死後に出版された「Last Words」には、彼がテレビ出演を“自身の宣伝にすぎないと考えていた”とある。
(SNLに出演した際のカーリン。フットボールとベースボールにまつわる言葉の違いを取り上げたネタだ)
Carlinが活躍した60年代後半〜00年代は、タブーを気にせず社会を鋭く刺す笑いが、米国のメインストリームに踊り出た時期とも重なる。それはアメリカのテレビ業界、そしてアメリカ社会全体が混沌さを増していく(あるいは明るみに出ていく)時期とも重なっていた。彼はその転換期を体現するような存在でもあったのだと思う。
カーリンのネタが現実になる時代
ちなみにトランプが政権に就いて以来、カーリンが生きていた頃の発言が現実になっていると指摘する記事もよく目にする。
例えば少し前には、男根のメタファーを交えて北朝鮮を批判したトランプ大統領が、まさにカーリンの指摘した“bigger dick foreign policy(俺のナニは大きいぞと威張り他国に侵略するような外交政策を批判するネタ)”だと取り上げられていた。
こうしたカーリンの記事や動画のコメント欄は、「彼が生きていたら何と言っただろう...」と嘆く人たちで溢れている。彼のネタを無邪気に笑い飛ばせる日は遠そうだ。
最後まで読んでいただきありがとうござました!
