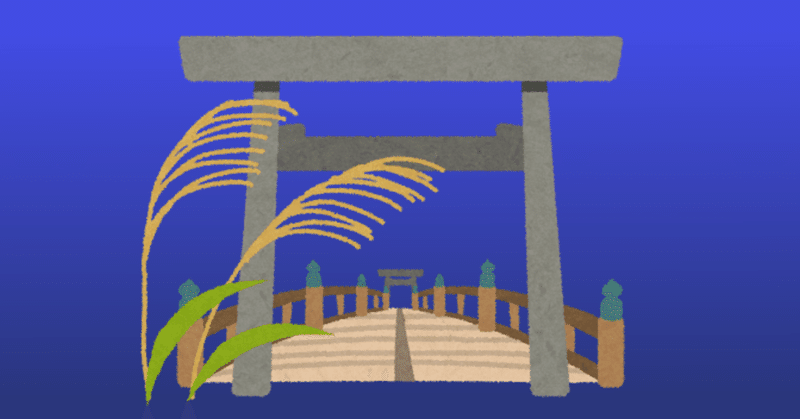
橋を渡りかける
月夜の晩、あぜ道を1人でとぼとぼと歩いていた。周囲の畑に植えられているのは真っ白なヒガンバナ。月の光を浴びて、青く妖しく染まっていた。
「もうすぐかな。きっと、もうすぐだよね」わたしの口からは、そんな言葉がしきりに繰り返される。
何がもうすぐなのだろう。自分でつぶやいていながら、さっぱりわからない。歩き続けなくてはならない、それだけが頭の中にあった。
ヒガンバナの畑を過ぎると、広い広いススキ野原へ出る。風を受けて穂が一斉に波立つ様は、銀色の大海原のようだった。
「だいぶ近づいてきた。そろそろだ」また、わたしは独り言を言う。新しい何かを期待しているような、古い何かを捨てる覚悟を決めたような、これまでに味わったことのない奇妙な感情が湧く。
自分の背丈ほどもあるススキをかき分けながら、先へ先へと進み続ける。軟らかい土の感触が、スニーカーを通して足の裏から伝わってきた。
ススキの最後の一房をくぐり抜けると、小石のゴロゴロ転がる河原が現れた。川は、向こう岸が霞むほど幅があり、たいそう流れが速い。
「泳いで渡るには遠すぎる。船ではたちまち流されてしまう」ひとりでに口を突いて出る。もっとも、わたしの主観も同様だった。
さて困ったぞ、と辺りを見渡すと、ずっと下流の方に橋らしい影が見える。このまま立ち止まっていても仕方がないので、下流へ向かって歩く。
月明かりに照らされ、大きな橋が現れた。
「あの橋を渡ればいい。あとはただ、1本道を行くだけだ」わたしは言う。
橋は木のアーチ橋だった。緩やかな弧を描いて高く高く登り、大河を一またぎしている。
橋のたもとに、1羽の白いウサギが座っていた。両耳を背中にペタンと寝かし、わたしをじっと見ている。
わたしはウサギの前にしゃがんで、チョッ、チョッ、と舌を鳴らしてみせた。ウサギは耳をピクン、と動かしてそれに反応する。
「こんなところで何をしてるの? 夜禽に襲われても知らないよ。巣穴にお帰り」
わたしが声をかけると、もそもそと立ち上がり、橋へ向かって這い始めた。
少し行っては立ち止まり、こちらをうかがう。まるで、わたしについてこいと言っているようだ。
どの道、この橋を渡るつもりでいたので、わたしはウサギの後をのんびりと歩き始める。寂しい道中、連れができたことに、わたしはちょっと心和んだ。
ウサギは、先を行ったかと思えば、ふと後戻りをしてわたしの横に並ぶ。寄ってくると、決まってわたしの手の甲をぺろりと舐めた。熱くてざらっとした舌の感触が、くすぐったくて、心地よい。
何度か行き来するうち、白かったウサギの体が、だんだんと赤みがかってきていることに気付いた。
妙だな、と思い、自分の手の甲を見てみると、べったりと血がついている。血は腕についた無数の切り傷から流れ落ちているのだった。
「ああ、さっきススキの中を歩いたから、カミソリのような葉で切ってしまったのか」
振り返ると、橋の上に点々と染みがついている。ウサギは地べたに落ちた血の滴までも、ピチャピチャと舐めていた。
ウサギの毛色は、今やすっかり血の色だ。
橋の真ん中まで登ってみると、着物姿のおばあさんが立っているのが見えた。
「むぅにぃかい?」おばあさんは細い声で聞く。
「もしかし、おばあちゃん?」わたしは驚いた。祖母は数年前に亡くなっているはずだった。
「この橋を渡っちゃいけない。お前はまだ、あっちですることがあるんだからねぇ」
「でも、ウサギが……」真っ赤なウサギが、わたしの足元で丸くなっている。このウサギが先へ進もうとすれば、もはやわたしの意志など、なんの意味もなさないのだった。
祖母が、パンッと両手を打つ。すると、それに驚いたウサギは飛び上がり、勢い余って、欄干の隙間から川へと転げ落ちてしまった。
「ほら、これでいなくなった。さ、引き返すんだよ」
祖母に促され、わたしはもと来た道を辿る。帰りは下り坂なので、足取りが楽だった。
振り返ると、まだこちらを見送っている。
「そうだ、老舗の栗蒸しヨウカン。おばあちゃんは、あれが大好きだったっけ。忘れずに買っていこう」
わたしは親指を折って、握り隠した。大事なことを、いつまでも覚えておくためのおまじないだった。
「帰ろう、帰らなくっちゃ……」わたしは口に出して言う。
誰に言わされているのでもない、わたし自身の言葉だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
