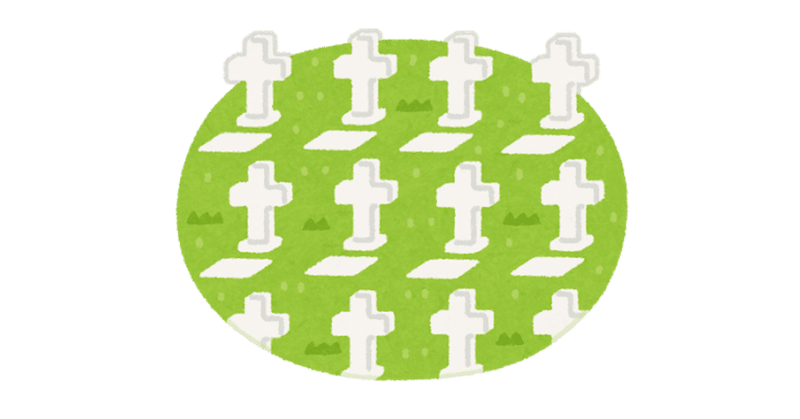
押し入れから外をのぞく
目が醒めた。あんまり暗いので、まだ夜なのかなと思ったが、そうではない。
ここは押し入れの中だった。
ふすまに指で穿ったような穴が開いていて、外からの光が漏れてくる。反対側の壁には、ピンホール・カメラの原理で、ぼんやりとした逆像が映し出されていた。
最初に、右の目で穴をのぞいてみる。自分の部屋を想像していたけれど、そこに広がるのは荒涼とした平地だ。
戦争が行われていた。
どこの国かはわからない。戦争の背景については、なんとなくだが理解している。
そこは半島で、元は1つの国だったのが、とある事情により分断し、同じ民族同士で争っていた。
国境は深く険しい溝で分かたれており、鳥ですら行き来することがままならない。飛び交うものといえば、赤く熱せられた砲弾ばかり。
胸に無数の針を突き立てられるような、とても悲しい光景だった。
わたしの右目は涙で溢れ、もはや何も見ることができなくなったので、今度は左の目でのぞいてみる。
緑の溢れる谷間だった。あちこちに集落が見える。牧歌的で平和な様子だ。
石畳の街路は人で賑わい、どの表情も明るい。肩を叩き合って笑う者、屋台の果物屋の前で、買ったばかりのリンゴを囓る者、熱心に議論をたたかわせながら散策する者。
この国には「不幸」という言葉が存在しない、そう直感が告げている。地上の楽園と呼ぶにふさわしい場所だった。降り注ぐ日の光までもが、黄金色の輝きを帯びて見える。
わたしの左目は喜びのあまり涙ぐんでしまい、また物が見えなくなってきた。
ポケットからハンカチを取りだすと、両の目をぬぐう。
どちらが本当の光景なのだろうか?
いくらかためらいもあったけれど、勇気を出してふすまに手をかける。
まぶしい光が押し入れの中の闇を追い払った。
緩やかな丘が地平線の彼方まで続く。柔らかな日差しの下には、何百何千もの白い十字架が整然と並んでいた。
わたしは芝の上に足をおろし、名も無き墓標を見つめる。
ただ静かだった。
全てが終わり、もはや変わるものが何1つないのだ。
もう、涙が流れることはなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
