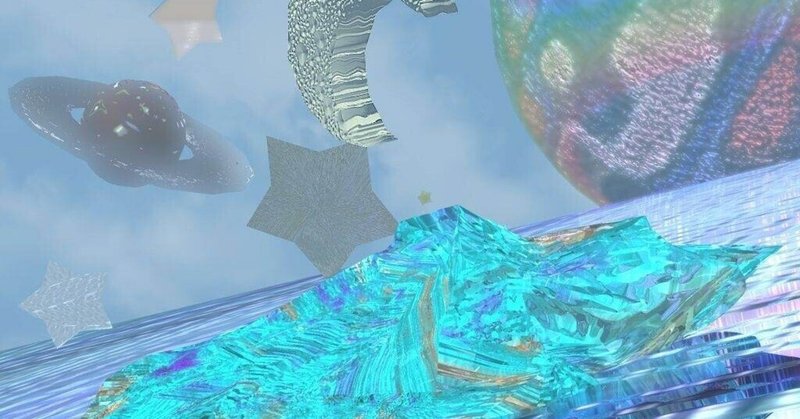
ガラスの海を越えて
大海原のど真ん中、友人の桑田孝夫と小舟で揺られている。
「陸はまだかなぁ」わたしは大あくびをした。正確な時間はわからないが、少なくとも半日は漂流している。
「おい、むぅにぃ。なんだか変だと思わねえか?」ふいに桑田が言い出した。「ほら、聞いて見ろよ。シャリン、シャリンって、音がするじゃねえか。回りはどこも海だ。船にはおれとお前しかいねえ」
「波の音じゃないの?」わたしは気にもしなかった。
「ばかっ、これのどこが波なんだ。もっと、よく聞いてみろっ」
改めて耳を傾けてみると、なるほど、さっきまでのザブン、ザブン、という音ではない。何かが砕けるような、涼やかな響きだった。
わたしは波間に手を伸ばしてみた。
「痛っ」指先が硬いものに当たって、撥ね返されてしまう。
「どした?」と桑田。
「水に手を入れようとしたんだけど、なんだか固いんだよね」
「そんなばかなことがあるか」そう言うと、自分でも手を突っ込んでみた。「おっ?! なんだこりゃ」
「ねっ? 変でしょ」
「うん……。まるで、ガラスだな。どうなってるんだ」
波でガラスが砕け、飛沫となって弾ける。その度に、シャリン、シャリン、と音を立てた。
細かく散ったガラスの欠けらは、雪片が溶けるように、再び海へと還っていく。
「ガラスって、こんなふうにしてできるんだね」わたしは感心した。
「ああ、不思議なもんだな。なあ、むぅにぃ。このガラス、そっと手を置いとくと、すーっと沈んでいくぞ。抜くときも、そっとやらなきゃだめだがなっ」
桑田が海に手を沈めたり、抜いたりして遊んでいる。
「ちょっと、やめなよ桑田。そのまま手を持ってかれちゃうよ」わたしは心配になった。
もしも、ガラスの海に投げだされたりでもしたら大変だ。初めのうちこそ波の上に浮かんでいられるだろうけれど、そのうちにずぶずぶと沈み始めるに違いない。
そうなったら泳ぐこともできず、ゆっくりと海の底へ落ちていくのだ。
「ああ、そうだな。やめるとするよ」桑田は船縁から体を引いた。「実はいま、ちょっと引き込まれそうになった。ははっ、危ねえ、危ねえ」
わたしのほうがゾーッとした。
遠くに島影が見えてくる。
「やっと陸か。無人島じゃなけりゃいいがな」手をかざして仰ぐ桑田。
「やけにキラキラ光ってるよね。あれ全部、宝石とかだったらどうする? 一生、遊んで暮らせるかも」わたしは皮算用を始めた。
「うーん、たぶんだが、そんなたいそうなもんじゃないと思うぞ」桑田は悲観的だった。
「でも、あの輝き方は水晶かもしれないよ」なおも、わたしは言う。
「島に着いてみればわかるさ。おれには、だいたいの見当はついてるんだ」
船は、導かれるようにして島へ向かって流れ続けた。
浜辺に打ち寄せられ、わたし達はようやく地に足がつく。
「ああ、そういうことか……」島にたどり着いて、わたしはやっと悟った。
「なっ?」と桑田。
どこもかしこも、ガラスの山がそびえていた。日の光を受け、四方八方と乱反射し、ダイアモンドのように美しく輝いているのだった。
「ここはガラスが流れ着いてできた島らしいな」桑田が推測をする。
あちこちに切り出したような跡が見られることから、どうやら石切場ならぬ、ガラス切り場として利用されているらしい。
「ここからガラスが切り出されて、世界中に運ばれていくのかな」わたしは思いめぐらす。
「うん、きっとそうだ。おれ、将来ガラス屋にでもなろうかな。なんせ、原材料がタダなんだもんな」
河原や砂浜で小石を探していると、たまに角の取れた丸っこいガラスを拾うことがある。
ああいったものは、ガラスの島から波に乗って、たまたま運ばれてきたものなのかもしれないなぁ、とわたしは思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
