
多世代のいえは何のためにある?(2024年9月加筆)
止まっていた建設に、ようやく再開の目処が立ちました!
2020年に構想を始めた時から、つくっては壊し、つくっては壊してきたアイデア。全く新しい複合的高齢者施設、みたか多世代のいえ。
今回は、「多世代のいえ」が現時点でやりたいこと、何のためにあるか?その背景にあるストーリーと共にお送りします。
チャレンジすること・したいこと
・「最期まで私らしく暮らす」
それを絵に描いた餅にしないための、きちんとした苦痛緩和
・一つ屋根の下で共生する高齢者と幼児によるシナジー
彼らをつなぐ“家守医師”の存在
・何歳になっても、どんな病気や状態でも、
社会とのつながりを実感できる居場所スペース「とまり木」
・個々の「持ち味」を見える化するさまざまな取り組み。
「自分の本棚」が数十個集まった「まちの図書館」
・地域通貨。自然な支え合いを生むための起爆剤
・生活そのものがリハビリになる「生活リハビリ」の場。出来ることが増えれば幸福度も増す。そのために風呂もトイレも洗面台も専用設計
一旦これくらいに ^^;
(他にもまだまだありますが・・・)
これらやりたい事に共通する、理念というか
「目的」をはっきりしておきます。

意外と地味ですかね ^^;
もっとキラキラした目標、例えば
「最高の笑顔で、誰もが自分らしく過ごせる場所を作る」
のようなもののほうがポジティブかもしれません。
たしかに、いずれそれも目指したい。
でも、まず目指すべきはそこじゃないです。
というのは、高齢者福祉の現状において、
もっと直視すべき問題があると思うからです。
それは、高齢者のうつ病です。
高齢者のうつ病の頻度
ここで、一つ質問です。
自宅で生活する平均80歳で介護を要する高齢者のうち、何パーセントがうつ状態で悩んでいると思いますか?
答えはこちら。
〈自宅で過ごす高齢者のうつに関する2006年の報告〉
介護保険認定を受けた1400人強(平均80.1歳)を対象にした調査で、
・うつまたは高度なうつ、の出現頻度はそれぞれ57.2%, 23.1%
(合計80.5%。評価にはGDS-15を使用)
・うつの出現は要介護度の上昇に伴い増加した。
・それらうつ病のほとんどが未治療であった。
答えは80%以上です。皆さんの予想はどうでしたか?
そして驚くべきは、うつ病がほとんど問題視されていないという事実(未治療のまま)。
一つ現実にあった話、
私が主治医を担当していた患者さんを紹介します。
どこにでもいる老夫婦
つい数年前、ある所に二人暮らしの80代の夫婦がいました。
お子さんに先立たれ、それぞれ兄弟姉妹も近くにいなかったため、夫婦二人で長いことマンションの自室で生活されていました。
奥さんは何年も前から認知症でしたが、旦那さんが家事全般を担い、生活を維持していました。
奥さんは元々は刺繍が大変得意で、趣味を活かしたサークル活動に認知症が始まってからも積極的に参加していました。
部屋の壁にはひな祭りなどテーマにした鮮やかな作品が所狭しと飾られていました。
コロナウイルス流行をきっかけに
ある時期から私が訪問診療で担当することになり、毎月1〜2回家にお邪魔するようになりました。
毎度、壁の作品を指差して「これ素敵ですね、写真撮ってもいいですか?」とこちらが言うと、大変喜んでくれました。
しかし程なくして、コロナウイルスの流行をきっかけにほとんど全てのサークル活動がストップしてしまいました。
それからというもの、奥さんは一日じゅう家の中で寝たり起きたりの生活となりました。
介護保険の拒否
唯一外部の人間として関わっていた私は、それでは体に良くないと説明。デイやリハビリなどのサービス利用のための介護保険申請をお勧めし、各種サービスの相談役であるケアマネージャーを速やかに選定してもらおうとしました。
しかし、旦那さんは「妻はまだ歩こうと思えば歩けますし大丈夫です」とそれを受け入れませんでした。
仕方ない、の境地
介護生活の状況が変化すると共に、旦那さんの気持ちもいずれ変化するだろうと思い、その時は必要以上に強くは推しませんでした。
が、その後奥さんの足腰が急速に弱まっていく中でも、なかなか旦那さんは介護保険サービス導入について首を縦に振りませんでした。
一度その理由を直接聞いてみましたが、はっきり要領を得ませんでした。
しかし、ボソッとつぶやいた印象的な言葉がありました。
「歳を取れば仕方ないでしょう、こういうことも」
つまり「諦めているから余計なことはしないでいい」そういう考えなのかもしれない、と察しました。
それでも動揺はする
さらに数ヶ月経つと、奥さんは立ち上がることなく自宅でほぼ寝ている生活となりました。また、記憶障害が進み、さっきと同じ話・つじつまの合わない話を、繰り返すようになりました。食欲も低下し、食べたり食べなかったり。
旦那さんは「歳を取れば仕方ない」と言っていたので、寝たきりになる事について、受け入れていると思ったのですが、様々介護ストレスもあるのか?さすがに焦っている様子でした。
「夫婦の距離をおいて、まずお互い休めるようにショートステイというのもありますよ?」と提案してみたものの、今まで同様保留されました。
意外な要望
「それはさておき、ワクチンはどうしても受けられませんか?」と頼まれたことに、私は少し驚きました。
当時患者さん宅でコロナワクチンを打つことは態勢確保が非常に困難だったので一度断っていたのですが、他のクリニックと連携しどうにか用意しました。
とはいえ、介護保険を頑なに拒否されてきたように、「余計なこと」はしてほしくなかったはずでは?と、ギャップを感じたのも事実です。
取り下げられたSOS
そして迎えたワクチン予定日の前日、旦那さんからお電話がありました。
「数日前から妻の具合が悪くて食事が取れない。どうすればいいのか」
よくよく話を聞くと、食事が減っているのは以前からだし、全く食べられないわけではなく、苦しそうにしているわけでもない様子。
すると旦那さんは、
「分かった、もう何日か様子をみる。また連絡する」
「こういう体調なのでワクチンは残念だが辞退する」
とおっしゃいました。
この時もし、私にもっと余裕があれば「いやいや、様子見に行きますよ」と言えたのですが、その日は臨時往診が重なってあまりにスケジュールが詰まっていて、どうしてもそうもいきませんでした。
「分かりました。お困りの際は、いつでも電話くださいね。」
とその場は電話を終えました。
衝撃
その2日後、朝6時ごろ私の携帯電話が鳴り響きました。クリニックからでした。
そんな時間に電話がかかってくることは通常あり得ないのでいぶかしげに応答します。「もしもし?」
「◯◯さんご夫婦が、昨夜火事で2人とも亡くなりました!警察から事情を聞くため電話がかかってくると思うので対応お願いします」
「え!?どういうこと?」
と、呆然としたのも束の間、私は瞬時に思い返しました。
「……もしかしたら、不注意や事故ではないかも知れない」と。
即座にネットニュースで調べると、見覚えのあるマンションの一室から黒煙が出ている画像が目に止まりました。2LDKが焼け、火は1時間で消し止められたがその場で高齢男性の死亡を確認、搬送先の病院で高齢女性の死亡が確認されたと。
現実を突きつけられた私は、得も言われぬ感情に襲われました。
「自分に責任はなかったか…」
「何か出来ることはなかったのか…」
そうです。私は旦那さんが無理心中を図ったのではないかと直感したのです。そしてその原因は、部外者として唯一介入していたにも関わらず事態を防げなかった私にもあったのではないかと感じたのです。
「SOS」があったあのワクチン前日、
どんなに忙しくても、夜遅くになっても、家まで様子を見に行けばよかったのではないか?
自分がいけないなら誰かに無理して頼んででもその日に行ってもらっていたら?
勤務日かどうか関係なく「その後大丈夫?」と電話でフォローできていたら?
それ以前に、介護で煮詰まった二人を引き離すために半ば強制的にでもショートステイに行かせるべきだったんじゃないか?
兎に角、もっと他にもすべきことがあったんじゃないか?
その問いが頭の中をぐるぐると回り続けました。
しばらくして現場検証した警察の方から電話がかかってきました。
「最近のご夫婦について、先生が知っていることを聞かせてください」
私は、こう答えました。
「もちろん不注意の事故の可能性もあるのでしょうが…もし私が旦那さんの立場だったら、日に日に弱っていく妻を前にして、無力感、閉塞感、絶望感に囚われていたと思います。
どうしたからいいのか。
この先どうなるのか。
どうにかなるのか。
頼れる人、いや、頼りたい人は誰も居ない。
そんな未来を悲観して、
ふとした拍子に自分で火をつけてしまった。
それくらい追い込まれていたとしてもなんら不思議ではありません…」
迷った末での決断
他に選択肢は無かったのでしょうか。
本人たちは揺るぎない意志のもと最後の決断に至ったのでしょうか?
いや、きっとそうではなかっただろうと想像します。
生きたい、一方でもう終わりにしたいという気持ちの狭間で、彼らは揺れていたと思うのです。
自殺既遂者の多くは最後の最後まで引き止めてくれる人からの連絡を待って携帯を握りしめているといいます。
その証拠にご夫婦も「ワクチン」という未来への希望を、ギリギリまで捨てていなかったのです。介護保険を拒否してきたのは、何もかも諦めていたからではなかったのです。
だから、何か別のかたちで、未来への「希望」を感じてもらうことが出来たらば、まるで違った未来が待っていたのではないかと思うのです。
私たちに出来ること
このご夫婦は決して特別ではありません。
大小違いはあれど、今この瞬間にも日本全国で似たようなことが起き続けているのです。
だからこそ、一体私たちに何が出来るのか?考えたい。
・引きこもりでもちょっと出かけたくなるバリアフリーな居場所がある
・そこはあたかも自分の家のようである
・そこには話をただ聞いてくれる人がいる
・そこでは人と自然につながれる
・そこには泊まることもできる(短期・長期)
・そこでは小さな子どもも遊んでいる
・そこでは自分の持ち味を発揮できる
・そこでは支え合いが日常的にある
・そこにはたまたまお医者さんも住んでいる
それが、みたか多世代のいえ。
これらがどれくらい本当に役に立つか?
時間をかけて練りに練って来ましたし、大切な仲間もできました。自信もありますが、実際のところはやってみないと分かりません。
他にこういう場所は私の知る限り無いからです。
だからこそ、挑戦したくなりました。
時を戻して、またご夫婦と出会うことができたとしたら、
今度こそ、未来への希望を感じてもらえるでしょうか?
うん、きっとできるに違いない。
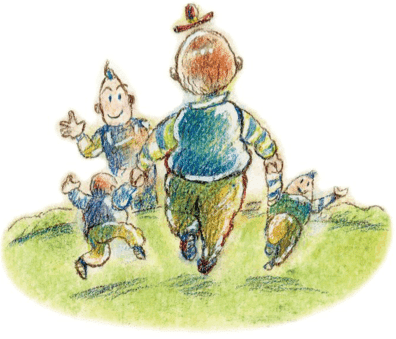
私たちと共に、挑戦してみませんか?
「人生、捨てたもんじゃないな」
目の前にいるシニアが心からそう思える居場所 を作るために。
2025年春オープン以降、
ケアを担ってくれる看護師さん、介護スタッフさんを
若干名、募集中です◡̈
(常勤1名・非常勤数名)
興味がある方は、下記までご連絡お待ちしています♪
info@tasedai.or.jp
※お名前、電話番号、メールの題名にスタッフ応募の件とお書き添えください。思いある方々と、対話し共にチャレンジできるのを楽しみにしています。
みたか多世代のいえ発起人
家守(やもり)医師/在宅医療専門医、緩和医療認定医
村野賢一郎
シニアにとって安心とは何でしょうか。手厚い見守り?緊急時にすぐ病院に入れること?たしかにそれも大切です。しかしそれで充分でしょうか?自分を家族のように気にかけてくれる隣人がいる。いつまでも人生に価値があると思える。信頼できる医療者が最期はきちんと苦痛を取り除いてくれる。 その瞬間手を握ってくれる人がいる。この世を去った自分を思い出してくれる仲間がいる。それこそ「多世代のいえ」が提供する安心です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
