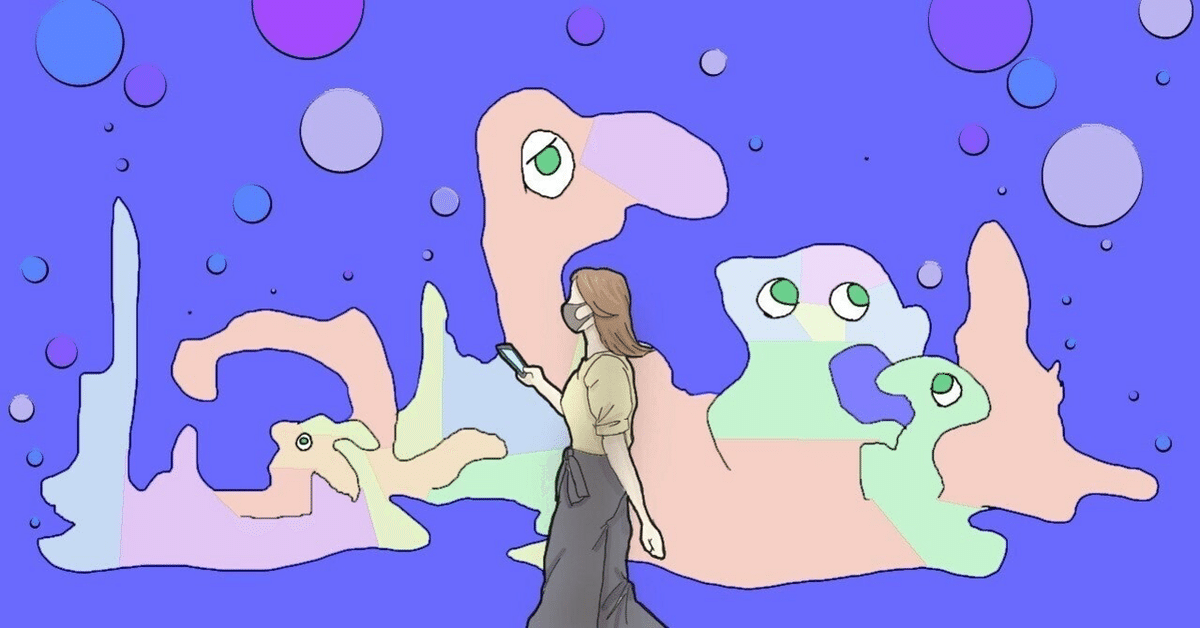
詩の温度
□
詩は殺すつもりで書かなきゃならない。対象ははっきりしないが、影のようなものを切るような感覚。
そして冷たくあるべきだ。わざとらしい温度を感じる詩はいらない。青い炎が燃えたぎるように、冷ややかな見た目から仄かな温度を生み出す。それが理想の詩だと思う。
□
短歌には韻律がある。韻律はことばたちを冷ややかに目立たせる役割を担っている。「五七五七七」と韻律によって言葉が分けられるとき、意味をもった言葉たちが即座に数字として、リズムとして存在するようになる。その瞬間に抒情が生まれるのではないかとわたしは思う。韻律のなかではありとあらゆるものが詩になるのだ。
ただ、一概に最初から温度のないものを書いていくことがいい詩作かといわれれば、そうではない。温度のあったものを冷ましていく過程にもっとも詩情は生まれる。あたたかかった、鮮やかだったものがふっと冷たくなる瞬間。わたしたちはその瞬間に異常なまでの心の揺らぎを感じる。それはきっと人が死ぬ瞬間に似ているからではないだろうか。
電解質で満たされた世界のことを (音のない世界のことを) 言う
□
温度差による抒情の最たる例が恋愛だと思う。恋愛におけるもっとも詩的価値があるところは「離別」だ。恋人同士が離れてゆくとき、いままでの思い出や色づいていたものが全て無に帰されたとき、抒情は最高到達点に達する。
わたしはそこの抒情を掬いたい。その冷めた抒情を味わいたい。なぜなら、その瞬間が紛れも無く痛い瞬間だからだ。
指切りの離れるときにあの日々のすべてのプレイリストを乗せて
□
わたしにとって詩のことばは痛みがなければならない。それは自分にとっての痛みでなくても、だれかの痛みであっても背負わなければならない。
そもそも、痛みのないことばで誰かを刺そうとしても、それは空を切る。冒頭で言った通り詩は殺すつもりで書かなければならない。痛みに対して、痛みで応える。それが詩である。
□
ネットのなかで生きるわたしたちは詩を書けばしばしば「痛い」と言われる。それは詩壇というプロの領域にいないからかもしれない。しかし、権威をもたないことは仕方がない。なにも持たないものがなにかを訴えるには痛みを持つしかないのだ。
メタの視点で書く物語はとうに終わりを告げ、いまは主観を書きたい。痛くありたい。そう思うようになった。
もがき苦しんだあとの言葉に意味があると思う。いまはもがくしかない。血や傷を感じるほどのことばを書きたい。これがわたしが18年間生きてきて考えた理想の詩だ。
ビデオ通話でフィルターがはずれてからの被傷性の会話 ゆがんだ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
