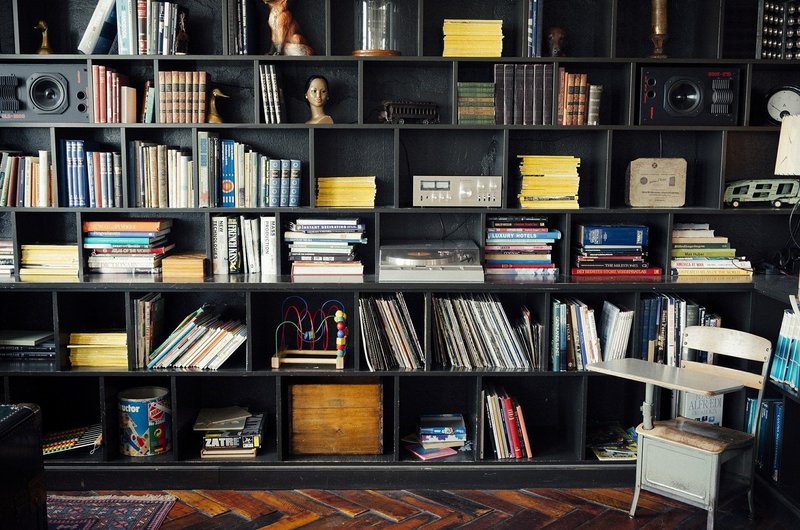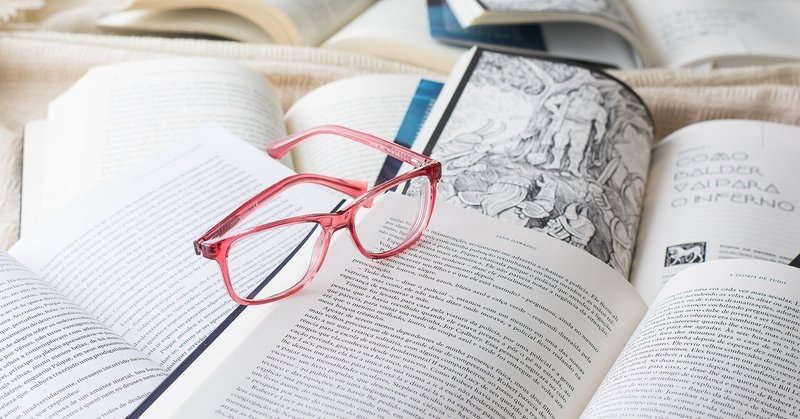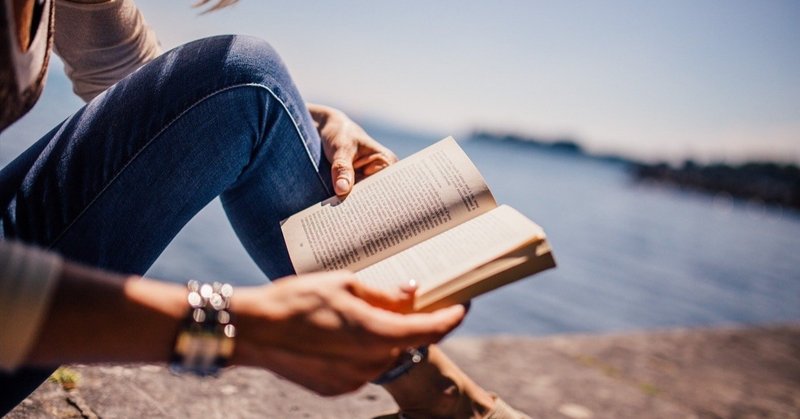記事一覧
差別を子供に教えるべきか?
社会で生きていく上で、「差別」と無関係ではいられません。差別について長年腑に落ちずにいたことが、思わぬところで目にした文章でスッキリとしたので、記録。
差別を植え付けられたと感じた子供時代私が小学生の頃、あるお友達が「私のお母さんは、中国人なの」と話していて、「そうなんだ!日本人じゃないんだー!中国人かぁ!」と反応した日のこと。
その場にいた母に、夜家に帰ってから、「日本人じゃないんだ!とか中
大人になっても信頼関係を築ける人に育てるために必要なこと
「皇室外交」を読んで気づいたこと「皇室外交」という本を以前、読んだことを思い出しました。この本を読んだ時、あることに考えを巡らせて、育児にも関わる気づきを得たことを記録しておきたいと思います。
なんせ、結構前ですから、引用はできないし、不正確であやふやな記憶もあるのですが、あえて読み直しせず、記憶に残っているママで書こうと思います。
結論から言うと、
「若いころ苦労しないと、大人になってから人
子供が外でうろちょろすることにイライラしていませんか?
子育てにうまくいかないことはつきもの。
でも、知ると気が楽になることってあります。そう言うことだったの、と腑に落ちるだけで、不思議なほどストレスが軽減されるんです。
今回は、私のそんな経験を記録しておきたいと思います。
外では自由に闊歩する娘、家ではベタベタの謎子供が1歳時代のこと。
よちよちと自分で歩き回れるようになり、最初の頃は愛らしいのですが、だんだんと行動範囲が広がり、外では自由に歩
反省よりも先に、子供の負の感情に向き合う
前回に引き続き、『反省させると、犯罪者になります』を読んで考えたこと。
この本は、人は、生きづらさ、しんどさ、不平不満、寂しさ、悲しさ、そういった負の感情をオープンにせず、抑制したままにすると、いずれ爆発(非行や問題行動)しますよ、という主旨です。「反省すること」に重きを起きがちだけど、反省しなければならないようなことをしてしまう背景には必ず、負の感情があり、そこまで掘り下げて自覚させることなく
「反省しなさい」封印の決意
『反省させると犯罪者になります』と言う本を読んでいます。
まだ途中なのは、読みながら中断して考え出してしまうため、なかなか進まないのです。でもしっかり言語化しておきたくてツイートしたのですが、連投しすぎてむしろまとまらなかったので、noteに記録しながら読むことにします。
まだ読書の途中であり、しっかりを読み込んで本の著者が伝えたいことを捉えられたと言う段階ではありません。あくまで、ここに記録