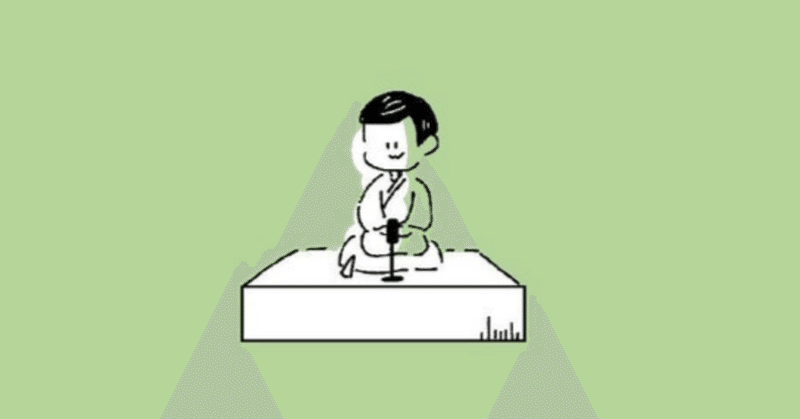
書き残すは夏の思い出。取り戻すは仮初めか~晩夏の前座編~
お口が前がマナティよ
お口が下がジュゴンだよ
尻尾がしゃもじがマナティよ
尻尾が三日月ジュゴンだよ
マナティとジュゴンについてそれほど知りたかった人生ではなかった。
1人実家に向かう車の中で、それがオリジナルソングなのか、そうではないのか。どちらかわからないまま、どこか呪文のように吹き込まれた歌を歌う、息子のメロディーを自然と口ずさんでいることに気付いた。
マナティとジュゴン。どっちが人魚のモデルだったのだろうか。リビングで歌う息子を思い出しながら口ずさみ、いつもそういう些細なことが気になってしまうのだが、たとえその正解を知っていても、私はそれを自ら口に出すような大人にはなりたくもないなと思っていた。
真実は、口に出さない時があってもいいと思う。
車を実家に置き今日は泊まるからと親に伝え、
歩いて2、3分の場所にある友人の家を訪ねた。友人とは四半世紀の付き合いになる。少し前に建てたその家は、まだ木の香りが少し感じられて、新しい家族が共に馴染んでいく経過だと感じた。
リビングに通され、大きなテレビの前のソファーで友人の子供が昼寝をしていた。人の気配に気付いた子供は、私を確認すると寝起きの不機嫌さも出さずに、今年一番可愛いだろうという笑顔を見せてくれた。
私は、ソファーの後ろにあるダイニングテーブルのベンチ型の椅子に座り、子供番組を友人の子供と一緒に見ながら、台所にいる友人の方を見た。
「呑みに行く前にビール呑むかい」
友人は、ビールを注いでくれてカウンター越しに渡してくれた。流しのあるカウンターは目の前に壁ではなく、いつでも子供を見回せる空間がある作りになっていた。友人は自分の分のレモンサワーを手に取り、カウンター越しに私に渡し、ダイニングテーブルのベンチ型の椅子の私の隣に座った。
「それはあえてのお隣席かい?」
横並ぶ中年に私は、私なりのツッコミを入れて友人を向かい側へ座らせ一度目の乾杯した。
友人は、レモンサワーを一気に呑みながら、とにかく早く私に言わなければならないと喉ごしを味わう間もなく、考えていたことをそのままの勢いで伝え始めた。
「なぁ。女性の記憶がどこまで正しいとお前は思っている?」
一瞬で私の心を掴む術を知っている友人に感謝しながらも、真面目な表情は壊さずに答えた。
「どこまでもだ。正しいのはいつだって女性だろう。仮に、私が全く覚えていない記憶を話されたとしても、それが全くの嘘だったとしても、その嘘を自分のためだけに考えてくれて、創作してくれた時間を考えるならばそれは嘘ではなく私のことを考えてくれている真実だ。それだけで私はハッピーだ」
ハッピー論を饒舌に私に喋らせながら友人は、私の答えなど最初から全く興味がないように自分の言いたかったことを続けた。
「相変わらず何を言ってるかわからないが、俺の話をするよ。この間、同窓会という名のもとに高校の同級生の男女数人が集まったんだ。その中に俺の元彼女がいた」
私は、このあと友人に話すことを友人の子供には聞かれたくないと思い、ソファーに座る友人の子供がテレビに夢中になっているのを確認してから努めて冷静に答えた。
「まず一ついいかな。高校の同級生の男女が数人と言ったね。私の記憶も今振り返ったのだが、仮に私の記憶が正しいのならば、私も君と同じ高校の同級生だったと思う。だが卒業してから20年程度になるけど、同窓会が開催されていたことは今まで一度も確認出来ていないんだ」
私は、小学校生活が始まったばかりの麗しい友人の子供に、同窓会に呼ばれたことがないオジさんとしての立ち位置で記憶には残りたくはなかった。
幸い友人の子供はテレビに夢中だった。
「ほら、俺ら10クラスもあっただろう。400人位いてさ。それでも全然地元に残ってないだろう。大半は連絡先すら知らない。その中で地元に残っている奴らと会うと自然に仲良くなるんだよ。今度誘うよ」
地元意識の繋がりは、年齢を重ねるにつれ、より繋がりが強固になっていくことを知っている。私は地元に帰って来ながら転校生の気分を味わっていたのだが、そこを怒ることよりもその飲み会に参加さえ出来れば、私にもワンチャンあるかも知れないと思い直し、にこやかに話の続きを聞くことに成功した。
「それで、その日の帰り際に急に数ヶ月だけ付き合ってた子に言われたんだ。『マラソン大会で50位以内に入ったら結婚しよう』って約束していたらしい。それを覚えていたんだ」
私の高校は、一年、二年と合同で冬に河川敷で10キロのマラソン大会が行われる。各部活の体育会系のプライドを賭けた闘いの場でもある。そういう空気が苦手な私は、人の気配のしない良い場所で靴紐を結ぶフリをして方向転換をして、人より短い距離でゴールしていた記憶がうっすら残っている。
『今年もズルをした人がいました』
と、先生が怒りながら閉会式で言っていたのを記憶している。半分の場所で手のひらにマジックでチェックされるのだが、マジックを常に数色持参している私にしたらチェックポイントはチェックポイントに非ずだった。
どうやら友人は、高校一年の冬に付き合っていた当時の彼女と結婚の約束をしていたらしい。本人にはその記憶は皆無だったのだが、久しぶりの同窓会の別れ際に言われたその一言は、彼の青春を巻き戻すには充分過ぎる程だった。
「で、君はマラソン大会の50位以内に入ったのかい?」
私は、聞きたくもない結果を聞く役に徹することにした。
「その記憶が曖昧なんだ。お前はどう思う?俺はその時はまだ部活辞める前でかなりマラソンの練習をしていた記憶があるんだ。そして俺が仮にその約束を言い出したのなら俺は自分で絶対クリアしてると思うんだ」
私は友人が言ったことは責任持ってやる男だと長年の付き合いから知っている。だがこの話は、私と知り合う前の話だ。その当時の真面目に部活をしている友人の記憶はない。
「君がそう言ったのならきっと50位以内だろうね。それは信じたい。しかし、それなのに現在結婚していない事実は大きな問題だな」
「高校の時とかって彼女とすぐ結婚の約束するだろうよ。どうして別れたのかも記憶にないさ。お前にもそういうのあっただろ」
友人は軽くプロポーズする気持ちの同意を求めて来たので、私も同意しようと過去を振り返ってみたのだが、私の高校時代にそもそも彼女がいた記憶がなかった。そんなワケないだろうと考え直したが、やっぱりいなかった。
「私の記憶も探してみるが、少し答えに時間がかかりそうだな。ま、私にしたら君のそのプロポーズ大作戦の結末を知らないで今日を終われない気分だ」
友人は、私のその言葉を待っていたかのように、子供に負けず劣らずの今年一番の笑顔を向けてきた。
「あ、ママ帰って来たよ」
友人の子供が玄関に盛大に仕事帰りのママを迎えに行った。友人は、レモンサワーとビールのグラスを片付けながら呟いた。
「さぁ、送ってもらって謎解き編の時間だ」
私は、友人の子供のママに挨拶をして駅まで送ってもらった。友人の子供のママは、友人の子供のママになる前は、ライバルがいっぱいの有名な可愛い女の子だった。私は、友人の子供のママとも同級生だった。友人の子供のママだとしょうがなく納得させることで必死に心を落ち着かせている。間違っても友人の嫁とは認めないようにしている。
後部座席から仲良し夫婦である2人を見ながら男と女。夫婦という形の真実は、曖昧だけど強固な絆を感じるという、どこか形の定まらない矛盾の中にいるものだと思わずにいられなかった。
40歳を越えても物語の中心の友人が何だか羨ましかった。主役になれないのならそれを記録しようと書き続けているが、どこかでいつか来るだろうと自分のターンを信じ続けて随分経過している。
自分に何が書けるか、何を求めているか、探している途中ですが、サポートいただいたお気持ちは、忘れずに活かしたいと思っています。
