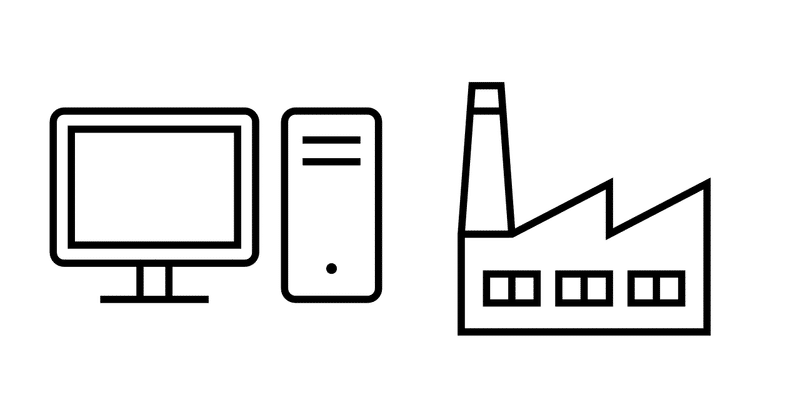
ソフトウェア企業と製造業の企業のマネジメントの違いに関する考察
私は製造業の大企業を2社経験していますが、マネジメントの有り様について思うところがあり、まとめてみたいと思います。
一つ間違えるとただ動かないプログラム、一つ間違えると人が死ぬ現場
私は業務で社内用のごく簡単なwindowsアプリケーションをVisual StudioでC#で作成したことがあります。また、pythonで画像処理や機械学習のプログラムを作り、社内の別の部署に提供したこともあります。
一方、製鉄所で働いていたときは、毎日の工場の朝会の始まりは「安全」でした。工場で前日にもし「災害」(業務上の事故のことを歴史的にこう呼びます)があれば、その報告がなされ、他の製鉄所、または鉄鋼他社で重大な災害があれば、その報告書が読み合わされ、自分の現場に即して何をなすべきか考えるようなやり方になっており、様々な災害事例に目を通してきました。
GAFAに代表されるソフトウェア企業(アマゾンはちょっと違いますが)は安全をさほど考える必要がありません。顧客の安全は考えるでしょうが、ベルトコンベアに腕を巻き込まれ切断する事例や、大きな移動機械と壁に挟まれ圧死する事例について見聞きすることはほぼないでしょう。
ピュアなソフトウェア企業であれば、少しの失敗があっても、「そこから学べばいい。次頑張ろう!」で済ませられると思いますし、括弧やコロンを忘れればただ動かないだけで済みます。しかし、製造業では、点検している制御盤を隣の制御盤と間違えて電源を入れてしまうことで、点検中の作業者が死ぬことがあります。ボタンを一つ間違えるだけで人が死んでしまうことがあるのです。
人を尊重し互いにリスペクトする職場、特に経験の浅い人の自由を抑制し軽視する職場
以上で書いたようなソフトウェア企業と製造業の「凡ミス」の影響度の違いが、(製造業側では)長い歴史の中で「文化」となって残存し、マネジメントの有り様にも影響を与えているように思われます。
ソフトウェア企業では、GoogleのWork Rules!の受け売りではありますが、互いに尊重しリスペクトし合う文化があるように思われます。一方、製造業では、若い人や経験の浅い人を軽視する傾向があるように思われます。私個人としては卓越した上司に恵まれ、どちらかというと尊重の文化「寄り」だと思っていますが、今思い返すと自分の中に他者を「軽視」する驕りが生まれていたように思われ、それは知らずしらずのうちに、文化の影響を受けていたのかもしれません。「凡ミス」が文字通り致命的なら、「凡ミス」しやすい若い人や経験の浅い人に自由を与えず、ルール通りに動くように指導することが企業活動として有益だったのでしょう。その反動で、ベテランや役職者には自由を与えるため、その自由に勘違い「させられ」、自由のない若い人や経験の浅い人を軽視することになるのかもしれません。
若い人と経験の浅い人の軽視≡年功序列の文化 と製造業の卓越の関係性
日本は世界の中で製造業が卓越している国だと思っています。このことと、未だに太平洋戦争から何も変わらずに年功序列で「末端有能、指揮官無能」の構図が続いてきたことに関係があるように思います。年功序列では、半ば必然的に若い人と経験の浅い人に自由が与えられません。そして、若い人側もそれを当然のものとして受け入れるところがあり、このことが「凡ミス」命取りの製造業におけるマネジメントにおいて丁度都合が良かったのかもしれません。
これからどうすべきか
トヨタもモビリティカンパニーになるといっており、「モノからサービスへ」の大きな流れがあることは事実だと思っています。一方、ものづくりでも極めると圧倒的な利益を生みうるということをTSMCは証明しているように思われます。企業の存続を考えるなら、大事なことは、自分の企業が提供する価値を実現する上で最適な「文化」が何かを理解し、現状の文化との差異を正しく把握して、軌道修正するような経営だと思います。そして、「あるべき文化」を「目指したい未来」と合わせてビジョンとして示し、従業員にわかりやすく伝えることができる経営者がいる企業が今後生き残るのでしょう。
私のいる企業はそんな感じではないので、沈みゆくと思っていますが、可能な限り抗いたいと思います。自分だけ生き残るのは比較的簡単と思いますが、私は一般的にはいわゆる「エリート」であり、そのような「エリート」は器を持たなければなりません。つまり、企業存続に力を尽くし可能な限り多くの人を助けるべきと思います。自分が起業したほうが多くの人が助けられるなら、それも選択肢と思います。人が持たない素晴らしいもの(頭脳と運)があるならば、それに応じたお金や生活を求めるよりも、持たざる人の力になるべきと思っています。そのようなエリートへの信頼が(今までもなかったかもしれませんが)失われたことが、ポピュリズムの広がりにつながっており、世界を覆う悲壮感や閉塞感になっているように感じられるからです。
もし上記のような考えに共感いただけるなら、ともに頑張って行きましょう。道のりは果てしないと感じられますが、「諦めたらそこで試合終了」ですからね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
