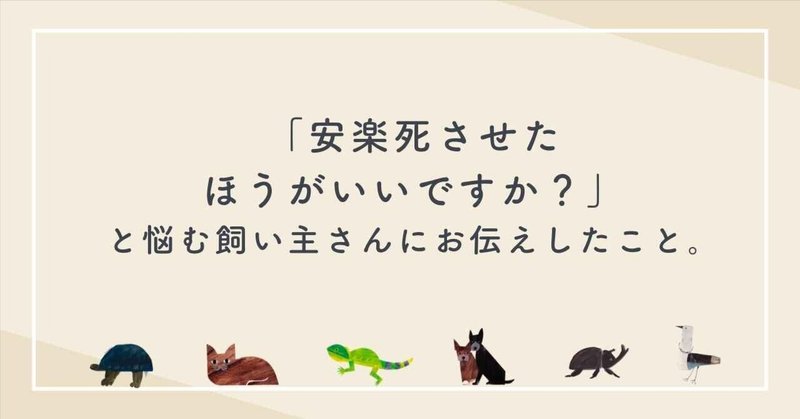
「安楽死させたほうがいいですか?」と悩む飼い主さんにお伝えしたこと。
こんにちは。獣医師の田代修です。
沖縄県西原町にある動物病院「杜ノ庭どうぶつ病院」の院長をしています。
「動物病院」と聞くと「動物と楽しく過ごす、楽しい場所」というイメージが浮かぶかもしれませんが、実態はだいぶ違います。
時には、動物に引っ掻かれて傷だらけになることもあるし、シビアな現実を飼い主さんにお伝えしなければならないこともあります。こうした現実に直面して「こんなはずではなかった」と感じる方もいるようですが、そうした状況でこそ深いやりがいを得ることもあります。
今日の記事では、そんな動物病院のシビアな現実、そしてそこにあるやりがいについてご紹介したいと思います。
「この子を、安楽死させたほうがいいでしょうか?」
とある飼い主さんから、飼っている愛犬について、こう訊ねられたことがありました。
「この子を安楽死させたほうがいいでしょうか?」
この方の愛犬は、認知症の症状が悪化し、かつての姿とはまるで別の存在になってしまっていました。
夜のあいだずっと鳴き続けて、近所迷惑になるし、自分たちも眠れないし、家族みんな疲弊している状態で来院し、上記のように訊ねられたのです。
これは、とても重い問いかけです。
あなたならば、どのように受けとめ、どのような言葉を返すでしょうか。
「飼い主さんが、動物と向きあえる状態をつくること」が先決だ
僕が、この話を聞いた時、真っ先に思い浮かんだのは
「安楽死をさせたほうがいい」と感じずにはいられないほどに追い詰められてしまった飼い主さんの状態を、何とかしなければいけない!
ということでした。
この飼い主さんは、決して愛情のないひどい飼い主さんではありません。
ずっと可愛がってきたけれど、状況が変化して、愛犬のことをしっかり考えられないほどに疲弊してしまっているのです。そして、追い詰められた結果として「安楽死」という発想が頭をよぎっているのでしょう。
そもそも「安楽死」は、苦しみから解放するための処置です。
「もう手を尽くせないから、これ以上は無理をさせないほうがいいんじゃないか」ということで選択することはありますが、今、愛犬は、苦しんでいるわけではありません。だとしたら、もし、今、苦しまない方法で命を絶つとしたら、それは「安楽死」ではなく「殺処分」になってしまいます。
しかし、この方が、それを本当に求めているわけではないのは、明かでした。
だから、僕は「安楽死するか否か」には、直接は取り合いませんでした。
「愛犬が苦しいから、解放してあげたい」のではありません。
飼い主さん自身が苦しいから、まずは「自分自身(飼い主さん自身)が解放されたい」というのが、本音なのです。
飼い主さんの「不安」や「辛さ」を受けとめる
実は、似たような話はしばしばあります。本当は自分が辛いのに「この子が辛いから」と動物のせいにしてしまうのです。
この状態では、いくら「動物のことを考えたい」と思っても、難しいのではないでしょうか。だから、まずは、飼い主さん自身が不安や苦しみから解放されて、動物と向き合えるようになる状態をつくることが大切だと思うのです。
そのためにできることは、まず、飼い主さん自身と向き合い、その不安や苦しみを受け止めることではないでしょうか。
この飼い主さんの場合も「安楽死するか否か」に直接は取り合わなかったものの、お話を伺いながら、上でご紹介したようなことを情報提供し、次のように付け加えました。
「これだけ長い間、一緒に過ごしてきたのに、最期の最期でそんな気持ちになって向き合うのは、何だか悲しいことですよね。
これまでとは関わり方は変わってしまいますが、最期まで邪魔者みたいな扱いにならずに、しっかり向き合って過ごしてほしいと思います」
途中で、ふっと何かに気づく瞬間があったようです。そして、飼い主さんの目から、急にボロボロと涙が溢れ出ていきました。
「最初は、この子が可哀想だし、安楽死を選択してあげたほうがいいんじゃないかと思っていたけれど、結局は、自分たちの都合で、自分たちが辛いから”安楽死を選びたい”と思ってしまっていたのですね……そのことに気づきました」
飼い主さんは、このように話していました。
とはいえ、気づきはしたものの、飼い主さんが疲弊している状態は変わりません。
そこで「まずは飼い主さん自身がコンディションを整えたほうがいい」と考え、こう提案しました。
「まずはこの子(愛犬)をお預かりましょうか?
ゆっくり休んでください。
そして、今後どうしていくかをもう一度ご家族で相談してみてください」
すると飼い主さんは「お願いします。今、自分たちは限界だから預かってほしいです」と。まずは1週間くらい預かることにし「たまに様子を見に来てあげてくださいね」と、飼い主さんを送り出しました。
「私たち、どうにかしていました!」
とても反省したご様子で来院されたのは、それから3日後のことです。
「家族みんなで話し合って、自分たちが何ができるかを考えなければいけなかったのに、自分たちのためにこの子をどうするかと論点がすり替わっていました。それに気づけて本当によかった。危うく一生後悔するところでした」
そして「みんなの気持ちが固まったから、連れて帰ります!」と言って、愛犬を連れて帰られました。
この時の飼い主さんの表情は、今でも印象に残っています。
何かを覚悟し、まっすぐに受けとめていこうと決意し、覚悟を決めたような、どこか清々しさのある様子でした。
このような飼い主さんの変化に立ち会えることは、仕事の喜びの一つかもしれません。
この飼い主さんは、その後、時折、必要なサポートを受けながら、最期まで自宅で看取られたといいます。詳しくは飼い主さんご本人しかわからないことですが、寂しさや悲しみはあるものの、おそらくご家族なりに「納得のいくお別れ」を迎えることができたのではないでしょうか。
動物も、飼い主さんも含めた「家族」の生活を支える獣医師でありたい
僕は、獣医師です。
だけど、ここでご紹介したケースの中で、僕は「獣医療的なこと」は、ほぼ何もしていません。僕がやったのは、飼い主さんのお話を伺ったうえで、情報と自分の気持ちを伝えたこと、そして、飼い主さんが冷静に考えて判断できるように、一時的に飼い主さんに「時間」をつくりだしたこと。
僕が提供したのは「ゆとり」と「きっかけ」だけです。
極端な話かもしれませんが、これだけならば、専門的な技術は要らないし、誰でもできることかもしれません。
むしろ、こういった状況で「色々な治療法があって〜」とか、そういう話をしても、意味をなさなかったでしょう。だって、それら(治療法や技術)は、ツールでしかないのですから。
もちろん、治療法や技術は大切です。
だけど、それ以上に大切なのは、動物も、飼い主さんも含めた家族が、共に、より豊かで充実した時間を過ごすためのサポートをすることではないでしょうか。
これからの時代、AI等の発展に伴い、診断や治療方針の検討は、どんどん自動化されるようになるのでしょう。
そんななかで、人である獣医師や獣医療関係者がやるべき仕事は、動物はもちろんのこと、動物を取り巻く人や家族と向き合って、より納得感のある選択をしていくためのサポートをすることなのではないでしょうか。
僕は、そういう獣医師でありたいと思っていますし、そういうサポートができるスタッフが育つ環境をつくっていきたいと思っています。
* * *
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
このnoteでは「動物と人間の暮らし」についての気づき、想いを綴っていきます。ぜひまたお読みいただければ幸いです。
スタッフ採用実施中
私たちの病院で、一緒に働きませんか?
沖縄県内の方はもちろん、移住者も大歓迎(県内在住者上限20万円・県外在住者上限40万円移住補助もあり)。
詳しくは杜ノ庭どうぶつ病院の採用サイトをご覧ください。
現在募集中の職種
獣医師 *移住者歓迎!
愛玩動物看護師 *移住者歓迎!
獣医療助手(未経験可)
受付(未経験可)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
