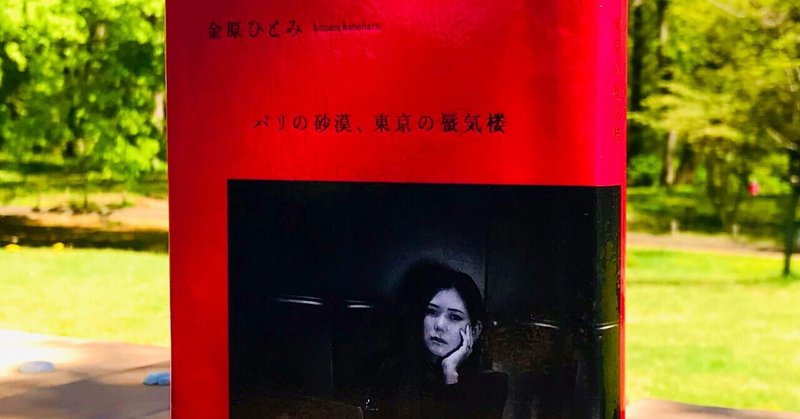
『パリの砂漠、東京の蜃気楼』生きることは痛みを伴うことだから
本日はさんの『パリの砂漠、東京の蜃気楼』をご紹介します。
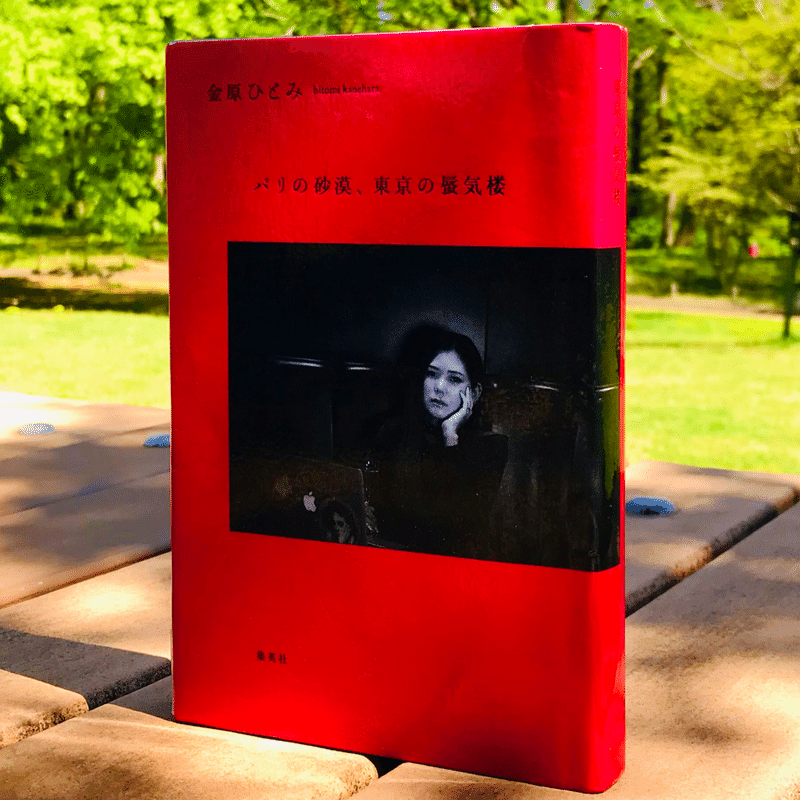
金原さんが小説で描く歪んだ昏い愛の形が、私は割と好きで。
ほぼ読んでいます。
今回は、金原さん初めてのエッセイ本だと言うことで手に取ってみました。
短いエッセイの中に、短編小説のような濃厚で奥行きのある世界が広がっていました。
パリでの、テロや自死、老人の孤独死など。
常に死の気配と隣り合わせの日常。
唇のサーキュラーバーベルを試みて流血する様子は、痛みすらここにいることの確認作業のようでもありました。
生きている実感というか、手触り感のようなもの。
退廃的な気持ち。ひたすら感じる恐怖。
作家として、作品に対する逡巡の気持ち。
子育ての中で感じる娘の成長、そして夫との関係性で変化する気持ち。
なぜパリに来たのか。
なのになぜ、また日本に帰りたくなったのか。
金原さん自身が、鬱や生きづらさを抱えているのは初めて知りました。
"きっと私も、無自覚にあらゆる人を傷つけてきた。
差別や悪意以前に、存在するだけで、誰かを愛したり、誰かを生理的に嫌悪したり、誰かに対して個人的な感情を抱くだけで、常に何かに傷つき、何かを傷つけて生きている。
生きているだけで、何かに何かの感情を持っただけで、何かに傷つき、何かを傷つけてしまうその世界自体が、もはや私には許容し難い。(p71)"
日本に帰ってきてから、「そこに住む理由」が腑に落ち、日常で幸せと感じる瞬間もありながら、そこには書く自分との乖離もあるとおっしゃいます。
その乖離によって、生き永らえているようでもあり、首を絞められているようでもあると。
"あの時あんなに幸せだったのにと思い起こされる幸せは全て幻想だと知っている。
ずっと泣きそうだった。
辛かった。
寂しかった。
幸せだった。
この乖離の中にしか自分は存在できなかった(p209)"
このエッセイを読むことで、なんとなく理解できたような気がしました。
彼女自身の「乖離」の中から醸造されている、世界の片鱗を。
金原さんが生み出す小説が放つ、愛の生々しさ。
キリキリさせられるような魂の叫び、痛み。
そうして、またピアスを刺していくんだろうか。
読みすすめていくうちにジワリと効いてきました。
よろしければサポートのご支援をお願い申し上げます。本の購入代とさせて頂きます。インスタとnoteに毎日投稿して世の中に還元いたします。ありがとうございます。
