
石井隆さんのこと(①夜中の長電話)
石井隆さんのネットのニュースを見てから3週間ばかり経つけれど、まだぼんやりとしている。他界されたのは5月22日の夜だったというからひと月を過ぎたのか、、。
石井隆さんは、わたしが上京し、いまの仕事をはじめてたから出会った「師匠」でもある。92年に「週刊宝石」という雑誌の特集企画で電話をしたことからだった。
「それは、消えた漫画家ってことですか?」
すこし笑いを含みながら聞き返された。ひやっとした。一言でいえばたしかにそうで、失礼だという気持ちもあったからタドタドしい喋り方をしていただろう。憤慨されるかと身を固くした。
意外にも、「三流エロ劇画」のとカリスマのようにもてはやされたころほどではないが、いまも細々とヤングコミックという漫画誌では描いていて、筆を置いたわけでく「消えた」の企画の趣旨に合わないかも。
「でも、若いひとたちはヤンコミ知らないか」
まあ、それでもいいんだったら取材を受けてもいいですよ、と。とても穏やかな口調だった。
当時、お世話になっていた編集プロダクションが請け負っていた仕事のひとつで、スタッフ何人かで手分けし、一世を風靡した有名漫画家の現況を聞くという企画。どういう経緯か割り振られた中に「石井隆」の名があった。
大阪にいたころに知り合いの書店の店主が石井隆のファンだというのが頭の中にあったくらいで、名美の漫画も読んだことがなかった。正直にそう話したとおもう。
石井さんは、知り合いの店主の話を面白がって聞いたうえで「もうすぐ映画を撮るんだけど」と話しはじめた。
それが、永瀬正敏と大竹しのぶの映画『死んでもいい』。興味があるなら取材に来たらいいよとまで言ってもらえ、「ああ、さっきの話。ボクはいいんだけど、念のためヤンコミの編集長にも聞いてみるね」と。
その後、石井さんから「あれ、ダメだって。ヤンコミの編集長にえらく怒られちゃったよ。石井サンはいまもうちの看板なんだから、そんな失礼な取材はぜったい断ってくださいと言われちゃって」
すまなそうに告げられ、ああ残念という思いとともに、ホッともした。あと、担当編集者が予想外に憤慨してくれたというのを石井さんのこころを癒したとおもう。
「でも、映画の現場に興味があるなら来ませんか。出来たらどこかで宣伝してよ」
このときの石井さんはもう映画のほうに気持ちが傾いていたから「消えた漫画家」といわれてもそれほど気に病んだりもしなかったのかもしれない。
資料箱を漁ると「シティロード」誌に連載していた「『死んでもいい』とも日記」に、石井さんがその一件を綴っている。そうだ。「名前は伏せるけど、あのこと書いてもいい?」と聞かれ、事実ですからと応えたのを思い出した。映画のメイキングとともに石井家のことも綴られていて、独特の文体にも惹かれ、連載が終わるまで、半年ばかりその欄を読むためだけにシティロードを買っていたんだ。
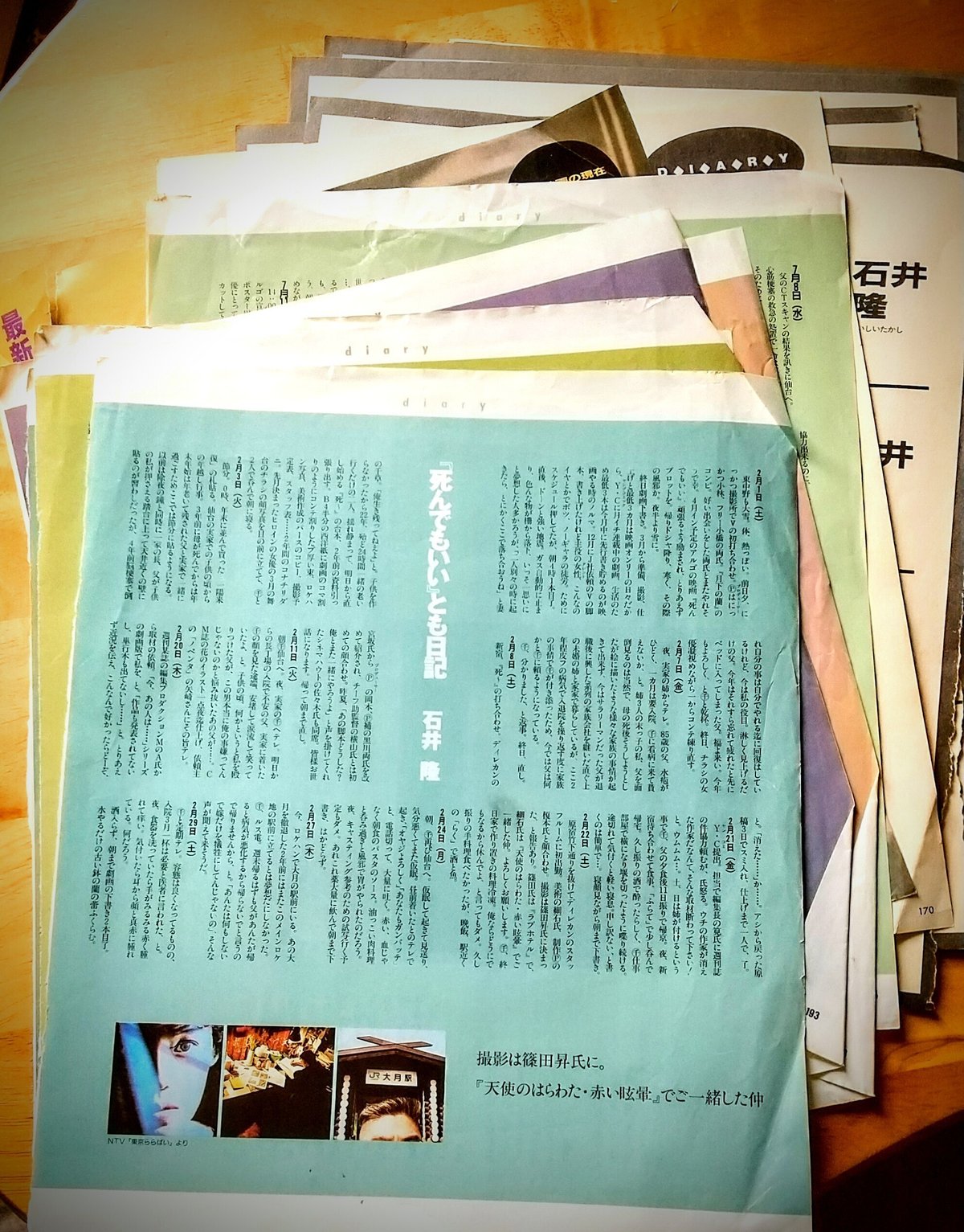
新宿の地下に降りる居酒屋だった。「『死んでもいい』のオールスタッフの打ち入りがあるから、アサヤマくんもよかったらおいでよ」
ふだん知り合いの場に出かけるなんて考えられないのに、あの日は石井さんの声を頼りに出かけていったのだ。
総勢で70人くらいだったか。助監督から撮影、照明、録音さんたちが一堂に会した「石井組」のイベントで、人数の多さに圧倒されていると、撮影監督の佐々木原さんに石井さんが「バラさん。このひとだよ。ボクを消えた漫画家にしたのは」と笑いながら。その場の注目を浴び、周りから「ええーっ」とツッコミを入れられ、そんな華やかな場はじめてだったし、どうしていいのか居方のわからずにいた。だから、からかいは救い水になった。インタビューの仕事をしながら、ほとんど人と話せないでいた時期だったから。いまおもうに石井さんは、そういう引きこもり的なところを見抜いていたのだろう。
あのころ何度か深夜に電話のやりとりをしていた記憶があり、いつも電話をかけると伴侶の千草さんが「はい、イシイです」と。石井はいま出かけていてというときに千草さんと話すのが愉しく、石井さんが電話を取ったときは、あ、残念と思ったりしたものだった。
「いいとも日記」を読み返すと、当時、石井さんのお父さんの介護で千草さんは仙台の実家と行き来していた。映画のことがあり、行けない石井さんの代わりに。のちに『ヌードの夜』で竹中直人が「なんでも代行屋」の男という役柄で出演しているが、墓まいりの「代行」のシーンなどのきまじめなその仕事ぶりは、あのころの石井家の生活背景が加味されたものではなかったか。


『死んでもいい』の取材で山梨県の大月に行ったのは、92年4月。駅前の不動産屋のシーンの撮影で、狭い屋内、スタッフ外のわたしたちが中を覗けるわけもなく、ずっと屋外待機。もらっていた台本とスタッフの動きから中の様子を想像するしかなく、石井監督はというと夜中の電話とはちがい、まったく話しかける間合いもなく、カメラマンの奥野安彦さんと、どうしましょうね。カメラを察知すると、プイと顔を背ける。撮影に難渋したのを覚えている。
それでも、このときの取材記事が載った「QA」(平凡社が出していたサブカル的な総合誌)には、いい写真が載っている。とくに後ろ姿の写真は奥野さんならでは。台本を手に不動産屋の前に立つ後ろ姿が石井さんらしい。
当時わたしは映画取材など初めての出来事だったし、いまになって気づくことだが、大月の撮影現場にいた取材者は奥野さんと二人きり。現場でいったい誰に声をかけたらいいのかわからず、そのあたりの判断は取材キャリアのある奥野さん頼りで、現場にいながら何がいま行われいるのかサッパリ。おれ、いったい何をしているんだろう。そもそも宣伝スタッフを介さずに現場に入るということが異例で、その後の原稿確認にしても監督と直接やりとりした。
「QA」(92年8月号)「この人に聞け」記事は4頁構成で、まだフリーランスのライターに転職して間もないし、それまで1000字程度のインタビュー原稿しか書いたことがなく、原稿用紙10枚超えは未知の領域、エベレストのように思えていた。
通常、その連載欄はインタビューの一問一答構成でまとめるものだったが、確認用のゲラを石井さんに送ったところ、戻ってきたものは真っ赤で、呆然うなだれた。直しの多さもだが、インタビュー形式をルポ仕様に変えるように指示があり、えっ!?「あのう、これインタビューの頁なんです」電話すると、石井さんの答えはこうだった。
「だけどね、編集者に相談してみて。通常はそうなのかもしれないけど、東宝のスタジオにも来てくれたし、アサヤマくんは何回も現場に足を運んだんだから、一回会ってハイ話を聞きましたと読めてしまうのはもったいない。手間と時間がかかった記事なんだというのは残していかないと。これはボクがどうではなくてね。アサヤマさんがこの仕事を続けていこうと思っているなら、そういうことにも多少は上手くならないとね」
学生結婚した石井さんは生活のため実話雑誌の記者をしていたことがあり、キャリアのないわたしに、次につながる仕事の仕方を伝授しようとしたわけで。おそらくだが、そういうお節介はわたしに限らず石井さんはしてきたのだとおもう。クンと言われたり、サンと呼ばれたり。でも、クンの響きがやさしいひとで「センパイのアドバイスとして聞いといてよ」と言われたのだった。
編集者と相談し、今回はと聞き手の一問一答を地の文章に直し、それに石井さんが応えるというふうに書きかえた。具体的には、
〈4月初旬。大月のロケ現場で見る石井隆は、ボソボソ声とは裏腹に元気だった。しぶとそうにも見えた。〉
〈撮影を終え、仕上げ段階の6月。石井隆の顔には疲労の色がたまっていた。〉というふうに。
たしかに、取材者の地の文に、月日や場所などを加えることで、要した日数、手間が伝わるとともに記事に厚みも増した。のちのちインタビューの際にわたしはこのスタイルを流用することになるのだが、ことの意味を掴めておらず、そもそもライターとして仕事の仕方を教わることなく取材に関する本を読んだり、見よう見まねだったわたしは暫く放心状態だった。
だから石井さんは、実地に記事の書き方を教わった唯一のひとでもある。
そうそう。あのとき石井さんから「ボクのこと知らないでしょう。古本で買ったりすると高いから」これ貸したげると渡されたのが「別冊新評」の石井隆特集だった。いまならネット検索すればすぐだが、そんな雑誌があることすら知らなかった。大宅図書館で調べはじめるようになったのもその頃からだったかも。
つづく。
あなたの石井隆に関する話をきかせてもらえたらうれしいです!
最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。
