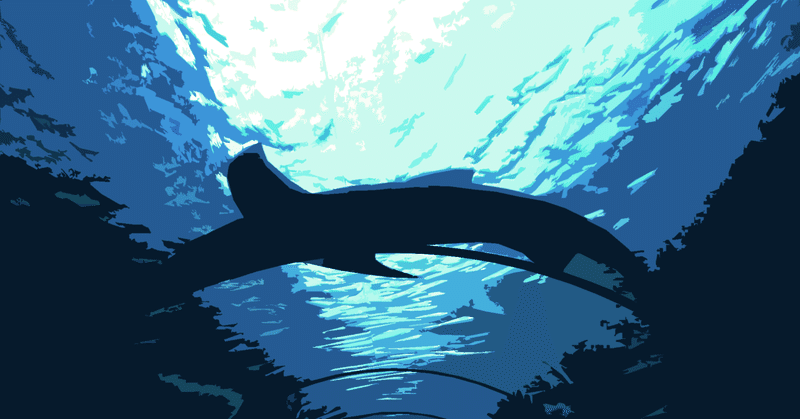
えんぴつ男と憂うつ女(9971字)
1/7
見るからにうすら寒いロビーだった。
私の洋服がひらひらとし過ぎていたのかもしれないけれど、それにしてもあの日の気温は低く、よく覚えていないけれど、外では雨も降っていたと思う。
だから私は外になんか出たくなくて、階段の格子にお猿さんのようにしがみ付き、階下のフロントに立つ女の人と、その女の人の目の前にある、壮大に青と白のモザイクタイルが埋め込まれた固そうな床を吐きそうになりながら眺めていた。
実際その日、私は既に一度吐いていた。
今日は一日お外を見て回るのだから少しでも朝ごはんを食べてくれなきゃ、お母さん心配だよと言うものだから、クロワッサンに味のしないバターを塗りつけて口にいれたら――違う、口に入れたから味がしないと分かったのだ――その、味がしない、パサパサで温いクロワッサンの、濡れたティッシュみたいな感触が私の敏感な口の中を這っていく。酸っぱいオレンジジュースで流し込んで、もう十分食べた、もう食べられないというのにまた母が、トマトも少しというものだから私は怒って口を結んだ。母が私に食べさせようとしているのはミニトマトで、明らかに一口大で、少しも何もないじゃないかと思った。一口で食べるしかないじゃない、中途半端に齧ったら中からトマトの種と汁がこぼれてしまう。そうなったら怒るくせに、トマトも少し、なんて厚かましいことをよく言えたものだ。
私はまだ幼すぎて言葉にできないそんな鬱憤を、泣いて、泣くことで吐き出した。どうして泣くのと母は言うけれど、悔しいからだった。「くゃ、あしい…」と私はえずきながら言うけれど、母は下唇を少し前に出すだけで、それ以上詳しく聞くつもりはないようだった。
泣けば喉が詰まる。喉が詰まれば反動で気道が開いたようになって、ああ今吐くのに丁度いいみたいなことを考えると同時くらいに私は吐く。かえって面倒くさいことになると知っているので口に手を添えるような無駄なことはせず、拭きやすそうなところにどろろときれいに吐く。ほとんどがオレンジジュースで、そこによく噛んで食べていたクロワッサンの茶色。
母は怒らず、驚いたような顔をする。吐しゃ物を、厚手のナプキン23枚を使って、集め、吸いとる、手先で語る。
2/7
本来であれば涼し気な印象を与えるはずの、ロビーを彩るタイルは薄汚れて全体的にくすみ、もっと言えば今すぐ固く絞ったモップでごしごし擦りたいほど薄汚れていて、白は灰色で、まったくキレイじゃない。
元々汚いものが汚くてもなんとも思わないけれど、本当はキレイなはずのものが汚いと気分が悪い。
父さんがいつかの病院の帰り道に言ってたことは多分そういうことなんだろうと私は思った。
そんなことを考えているとエレベーターがスーっと私の後ろを降りて行く気配がして、だけど私は振り向かず、気配を感じたことが本当だったことを確かめるためにじっとロビーを眺めていると、果たして親子らしき二人が私の足元のアーチをくぐって現れた。
男性に手を引かれた男の子の方に私の目はいっぺんに奪われる。歳はおそらく私と同じくらい。同じくらいの歳だから、ということがまったくなかったとは言い難いけど、私が彼に目を奪われたのはそんな理由からではなかった。
男の子の歩いた後が真っ黒だったから、私はその子から目が離せなかった。男の子はえんぴつの足を削りながら歩いているみたいに、炭のような色の、頼りない線が、うすら寒いロビーに引かれている。
感情が足元から流れて固い床に浸み込んでいるのだと私は知った。私と同じように、あの子は外に出たくないのだ。足が重くて仕方ないのだ。
今度は私の番だった。
父に後ろから声をかけられ、手すりから強引に私の手をはいで、自分の手に収めようとする。
私たちは階段を下り、先ほど上から眺めていた女の人の前に行く。フロントの前に立つと私の身長はデスクの高さを越えないので、女の人の顔は見えない。私に何か言ってくれたようだけど、全然聞いていなくて、気付けば何故か父が私の顔を上から覗き込んでいる。
なに?
何じゃないだろう。今日はどこに行くんだ?
いや知らない知らない。
私は多分あのとき、すごく嫌な顔でにやりとしてしまったのだと思う。
父のその質問は、フロントの若くてキレイなお姉さんが私に発したものだったらしいとそのとき気付いた。若くてキレイなお姉さんだと知ったのは、父が眉を上げて人が良さそうな顔を作っていることに気付いたから。父は良い恰好をしようとしている! と私は知った。キレイなお姉さんが気さくに子どもと接したのだから、子どもである私は無邪気に答えなければならなかった。父は私に何かを答えさせようとした。でも私はその日どこに連れていかれるのかを知らなかった。なのに、どこに行くんだ? なんて父に聞かれれば、お父さんが知らないんだったら、じゃあ誰が今日の行先知ってるのさという気持ちになって、意気地なしの笑いがこみあげてきた。父の顔を見ながら、さあ、と言った顔をしたつもりだった。するとフロントのお姉さんが少し身を乗り出して、パパとママとお出かけ? と言ってくる。私は多分、さあ、という顔をしたとき、小さな子特有の、頬を肩に寄せながら、視線だけは上方向へ向ける不満そうな仕草をしていたのだろう、誰か助けて欲しい、代わりに何か言ってほしいと思っているときの顔。フロントのお姉さんは私のその顔を見て、助け舟を出したのだ。ああパパとママとお出かけするのって言えば十分だったのか。今なら分かる、お出かけするのって言えば、父が、今日はちょっとどこどこまで足を伸ばそうと思っておりまして、とか言って、フロントのお姉さんはフロントのお姉さんからフロントの女性社員に変わり、でしたらどこそこのお店のスフレが人気なのでぜひとか、今日は生憎の天気ですが、普段はどこどこの景色が、とかインフォメーションするんだろう。
そして実際にそんな会話が繰り広げられていて、私は退屈を感じる。自分の足元から黒い色が出ていないかと確かめるためにかかとのあたりを見ると、フロントのお姉さんが可愛いワンピースだねと言う。面倒。それより私の頭に引っかかっていたのは、フロントのお姉さんが私と父しかその場にいないのに、パパとママとおでかけ? と聞いてきたことだった。お母さんはいないけど…とまだ新しい母に慣れていなかった私は最初に思って、次に、私のお母さんを知ってるの? と思った。
私はそのとき、フロントのお姉さんが、漠然とした母親ではなく、相田知美のことを知っていると思い込んだ。そして、相田知美の娘が自分であることを結び付けて考えていることを不思議に思った。だけど勘違いだった。相田知美を知っているはずがない、今の母は木下ゆかりさんであって相田知美じゃない。
私は現在の母である木下ゆかりさんが私の吐いたものを拭いていたから、木下ゆかりさんを相田知美と勘違いしたのだと思った。なぜなら、子どもの吐いたものを顔色一つ変えず拭けるのは母親に違いないからで、母親に違いないのは相田知美だったからだ。あのとききっと見られていたんだ。このお姉さんは私がクロワッサンとオレンジジュースを吐いたことを知っていて、それでもなお、私に優しいフリをしていたのだ。
あのときの私の思考はこんな感じだった。
私は恥ずかしさでのた打ち回りそうになった。恥ずかしさが怒りに近いものに変わる。デレデレしている父親が気に食わない。支度の遅い木下ゆかりが気に食わない。寒そうな外が気に食わない。ペラペラのワンピースが気に入らない。開け放たれたエントランスのドアから人が入ってくる。その人はフロントを介さずまっすぐエレベーターに向かう。エレベーターの中はあの男の子の足跡で真っ黒になっていたが、その人が乗ったことでリセットされたと私は思った。
3/7
雨が降っていたという視覚的なはっきりした記憶はないけれど、雨粒が、むき出しの肩やサンダル履きの素足に当たる感触を覚えている。雨が冷たかったというわけではなく、むしろぬるく柔らかく、当たれば何となく皮膚が痒かった。
それでもまだ雨が降っていたという確信が持てないのはどうしてだろう。それはきっとあの日私が運河沿いを歩いていたからで、皮膚に当たっていたあれは雨ではなく飛沫だったのではないかと思えてならないから。
男の子が残した跡とは、エントランスを出てしばらくしたらお別れだった。その日、唯一鮮やかに見えた彼が残した跡と行先が違うことを私は残念に思った。ホテルから出るまでは一緒の、炭色の、憂うつの道を歩いていたのに、男の子の跡は駐車場の方へ伸びていた。私たちは徒歩でホテルの敷地を出て、坂を下った。
街中でも相変わらず父親に手を引かれ、幼い私は延々と運河沿いを歩いた、というより歩かされた。あのどこかうすら寒い日、うすら寒いロビーを出て、少し開放的になったと思ったが、均一なねずみいろの空、小さななみが立てるタプタプした不快な音、密度の濃いくうきは臭く感じる。午前中の私にとって、それらは全部吐き気を催すザラザラしたものが喉を這う感覚を思わせるものだった。
私の前で無口な父が右、左手には綺麗でもなんでもない運河。父と私のちょっと前には新しい母がいる。私たちに当てつけるように早足で歩く。歩調が、今日を早く終わらせたがってるのが分かった。わたしだって楽しくないけど、あの人のようにはしない。私が父の隣を歩いていたのは、手を掴まれているからというのもあったけど、父が私の手をいつもよりも離そうとしないせいでもあった。そんな不安に思わなくてもあの人と同じようにはしないよと、さすがに優しい言葉をかけたくなった。
父は母がどこに行きたいか、何をしたいか分からず、ふらふら先を歩く母の後ろ姿を眺めていた。何度も、唾をのみ込むように握り返される手の、汗の隙間を流れる空気の冷たさが気持ち悪い。
いずれにせよ、私は閉塞感と罪悪感のお化けみたいな父に手を握られながら歩いた。
今思えば私はあの頃から気象病を持っていた。低気圧が訪れる日は憂うつで、言いようのない不安を抱えている。その不安は言葉にしようとすれば、「なんか変」の一言に尽きる。
大人になった私はどんなときも体調や気分が優れないときは「なんか変」と言って寝ている気がする。子どもの頃の方が、よっぽどいろいろなことを考えていたんじゃないだろうか。
4/7
最初、幼い頃の思い出を水崎俊哉に話したのは、彼があの日見たあの男の子かもしれないという疑問を、いい加減、解消したいと思ったからだった。
だけどあのとき私が行ったホテルの名前は覚えておらず、検索してもこれだというものは出てこない。あれからおよそ10数年、もうつぶれてしまったか、幻だったか。
彼も私とだいたい同じ歳に見えたほど幼かったわけだから、仮にそのホテルの名前が分かっても覚えているかどうかは分からなかったけれど、あのロビーのモザイクタイルとか、馴れ馴れしいフロントの女の人とか、薄いガラス張りの頼りないフロントドアとか、そういうキーワードを一つずつ、的当てをするように輪投げをするように、そうやって手数を費やすことが決め手の一つになるような遊びのように、ぶつけ続けた。
水崎さんは何度その頃の話をしても思いだせないようだったけど、私のその話が好きで繰り返し話さなければならなかった。
そうしているうちに、あの日どんよりしていたのは何より私だったのだと知る。車の免許を持っていなかったお父さんも、どこからともなく漂ってくるように感じた悪臭も、げんこつみたいに大きなたこ焼きも、寒そうな格好をしている人力車のお兄さんも、ガラス細工の数々、仮面舞踏会に付けて行く仮面、そういう、一度はやけに陰気に見えたものが全部、恥ずかしく思えたものが全部、思い出してみると、弾けださないばかりに活き活きと浮かび上がってきては沈んで、上手に加工された写真のように、今更鮮やかに感じる。
そんなイメージが、いつか彼と見た、青い水槽に入ったクラゲがふわふわ、ふわふわ、浮いたり沈んだりする様子を思い出させた。浮かび上がっては、漂いながらいつの間にか沈む、あの捉えどころのない、かつこんなにもはっきりした……。
よく私の話を聞く彼は、「で結局、それでご両親とは今も仲が悪いわけ?」とからかうように言う。
だから、仲全然悪くないって。かれはそうやって口を挟むことで、続きを促しているのだ。私はまた余計なことを話すことになる。
けっこう大きくなってから分かったんだけど、あの時期、お父さんとお母さんしょっちゅう喧嘩してたみたいで、その原因の一つが私だったことと、あとお母さん、初めての私たち家族の旅行が小樽ってのが気に入らなかったみたいなの。そもそも喧嘩しがちだったあの状況で旅行を提案してきた辺りもちょっと気に入らなかったみたいで、でもご機嫌取られてやろうかって思ってたんだって。
それで、お父さんが青の洞窟に行くっていうからイタリアだと思ったらしいのね。頭からイタリアだって信じてた訳じゃないとは言うけど、第一印象、青の洞窟と聞いたらイタリア、と思ったらしいのね。
そしたら小樽だって言うし、お父さんパスポートどころか免許も持ってなかったし、ナポリの、カプリ島の、青の洞窟のことなんか知りもせず、これはゆかりさん喜ぶぞと思って、真心込めてお父さんなりに色々調べて。でも車で一時間ちょっとのところが目的地だなんて、この人のこれが、いろいろな意味で限界なんだと思うと不憫に感じて、あと恥ずかしかったらしい。車無いからJRだし。私がいるから遠出は難しいし、分かるんだけど、でも、あのときはそんなことであまりにも憂鬱になってしまったと後に母は笑って言ったのだった。今となっては頼まれたって飛行機になんて乗りたくないと母は言う。
「そりゃ不機嫌にもなるよね」と私は過去の母をフォローする。
挙句、あの日の私たちは小樽の青の洞窟も天候不良で見られない。私はブスッとしてるし、朝一で吐くし、げんこつたこ焼き見てなぜか二回目の嘔吐だし、最悪だよね。お父さんがずっと私の手を握って、というかもうはっきりあれは私に縋りついていたのだと思うけど、お母さんの機嫌を伺って、大きな声も出せない。景色でも食事でも買い物でも、どれか一つでも正解があればと思いながらお父さんはあの街を歩いてたんだ。どれか少しでも、お母さんがちょっとほころぶような出来事があればなんて思いながら、きょろきょろと辺りを眺める。それで何か見つけたら、ゆかりさんに何か言うまえにほら愛子、あそこに何々があるぞとか甘いもの食べたくないか? とか聞くの。私は私でリアクションに乏しいし、肝心のゆかりさんに届いてないし、私に質問しといて私に意識が向いてないのは分かるから容赦なく不愉快な顔の私。お父さんはお父さんで地獄だったと思う。
当時11歳。当時の私はすごく神経質で、旅行とかはそもそも苦手だったんだけど、前のお母さんのことをまだ唯一のお母さんだと思ってたし、今のお母さんに対する嫌悪感みたいのもちょっとあって、とにかく陰気で、毎日憂うつだった。あの日は特に。
家の中がどんより暗かった記憶がある。電気をつけていても暗い。空気が淀んでいたのか、自分の目に陰気フィルターがかかっていたのかは分からないけれど、そこには活気や温度を遮る力ない煙みたいなものがいつも立ち込めていた。
5/7
始めて水崎俊哉を見かけたのは水族館の中だった。
この話も水崎さんのお気に入りだ。
大学の後輩の男の子にデートに誘われて舞い上がり、水族館にでもと言われてがっかりして、休み一日しかないから小樽までドライブでと言われてまた舞い上がる。
ドライブデートに舞い上がるのは父が免許を取ってからというもの毎週のように私を連れ出してくれた思い出に起因している。
デートに誘ってくれた後輩の男の子は背が高くスタイルも良いけれどよく見れば顔はあまりよくない。唇が薄くて色が悪く、耳が正面の方に開きすぎていて目立つ。歯は白く頑丈そう。肌の色にはムラがなく、トラブルも無さそうだけれどゴムを思わせるような融通の利かない質感がある。笑うと張りつめたゴムのような質感が増すようで、白い歯も作り物めいて見える。私の生理的に苦手なタイプの顔をしているが、当の本人も顔のパーツや質感にはコンプレックスを抱いているらしく、だからデートは薄暗い水族館なのだと思えば健気で可愛らしくもあった。しかし薄暗いところであればもっと近くで映画館でも良かっただろうに、そうしなかったのはきっと、彼は私と話をしたいと思っているし、運転のテクニックを見せたいと思っているのだと思った。よって私はトータルで舞い上がった。どちらかというと舞い上がった。
ちなみに当時、水族館は私の大の苦手分野だった。あの薄暗さと青さの中を歩けばお腹の底から冷えてしまう気がするし、「水族」ってなにっていう気持ちが幼い頃からずっとあった。
海に生息する生き物を水族と呼び、それらを集めて生態を観察できるように仕掛けた施設を水族館と呼ぶことによそよそしさ、もしくは恐怖に裏打ちされた防壁の存在を感じた。何かに対して「族」という言葉を使ってしまうと、一生相容れないことを前提にしているような、不可侵な領域を予め設定しているような気持ちになる。
暴走族、裸族、貴族。
族とつけて何かをまとめて呼ぶことで、あいつらと自分たちとは生来違うものなのだと暗に日向に訴えて、そうやって寄せ付けないようにしているような気がする。
「へえ、家族は?」と水崎俊哉は言う。すると私はあっけなくドキッとする。
家族はどうなの?
一生相容れないの?
だから、私たちは今別に普通だって。普通に仲良いし、普通に喧嘩もする。
その普通ってのが俺には分からないから。
「そんな融通の利かないこと言わないでよ」と少し機嫌を損ねた素振りを見せると、水崎俊哉はへへ、冗談だってとか言って、その話、つづきはどんなだった? という顔で私の目を見る。
「その水族館で、なかなか楽しくデートできたんだけどね」私は続きを話す。結末は彼がよく知っているから、オチは必要のない気楽な話である。
緩やかな、だけど長い階段を降りた先の暗い小部屋には、ブルーライトの光に反応して光る何種類かの熱帯魚などが飼育されていた。
小さなその魚たちを見るために水槽に顔を近づける。きれいですねと言って後輩は、こっちを見て笑った。私はブルーライトに照らされて均一に光った彼の立派な歯を見て、すっかり彼を受け入れられなくなってしまった。歯に特別な手入れをしているからこんなに光るのか、私の歯も光るのか分からなかった。大学生の身で歯にお金をかけられて、その結果彼の歯だけ異様に光っているなら何となく引いてしまうし、これから彼が笑うところを見るといつも今日のことを思い出してしまうだろうと思った。もし普通の歯も光るのなら、私は笑えないと思った。どちらのパターンを考えても、私はその場で一切笑えなくなった。
彼は今も私とのデートがうまくいかなかった理由を見つけられていないだろうけど、私にはこんなことがダメだった。
水崎俊哉はこの話が大好きだった。私がこの話をしたのは、彼と会ってからもう3回目になっていた。
6/7
ちなみに続きはこうだ。
後輩の、暗闇で白く輝く歯の残像を必死に記憶から振り落としながら明るいところに出ると、少し遠くのアザラシだったかカワウソだったかペンギンだったか巨大な蛇だったかでっかいカエルがいるスペースだったかの掃除をしている水崎俊哉がいた。
私は残像を見た。後輩の白く光る立派な歯とはまったく正反対の、足元から真っ黒な灰をまき散らして動き回る足跡の残像。
不意に懐かしくなる。
かつて私の父と、死んでしまった母の代わりに現れた新しい母の3人ででかけた小樽。2泊したホテルのロビー。私の後ろをスゥっと降りていったエレベーターに乗っていたのは、父親に手を引かれ、真っ黒な足跡を残す少年だった。
私は私の憂鬱が目に見えたような気がして、一人ぼっちじゃないような感じがしてその男の子から目が離せなくなった。私と同じように、今日を最低に思っている人がいるというだけで、私は何とかあの日、父と母との奇抜で憂鬱な一日を乗り越えることができた。
私はあの日、掃除をする水崎俊哉に一瞬で目を奪われた。
デッキブラシでゴシゴシゴシゴシ、念入りにフロアを磨くけれど、彼の足元は動いた先から黒くなる。まったく掃除をしている意味がないところを見ると可笑しくなるけれど、隣の後輩には黒さが見えていないようだし、私にだけ見るものだと思ってまた運命を感じた。ところが彼はとても楽しそうに仕事をしていて、光る汗をマンガのキャラクターみたいに腕で拭う。その場でつい彼に話しかけてしまった。考えて見たらあの日ホテルのロビーでだって話してないのだから完全に初対面なのに、初めて会ったような気がしなくてつい久しぶりみたいな感じで話しかけて、デートに誘ってくれた後輩の前で会う約束までしてしまった。
小学校の頃の同級生で、懐かしくてと言ったけど後輩はまったく信じていなかった。ほんとごめん、逃したらダメだと思って。今日しかチャンスはないと思って、私至上最大の失礼を働いてしまった。
7/7
ところで。ねえお母さん。
新しいお母さんとはすっかり仲が良くて、あなたの記憶も正直薄れかけているけれど、あなたがいなくなってからの私の毎日はとにかく憂鬱で、いつもどこか視界がスッキリしなくて、落ち込んだり吐いたりばっかりしていました。
お父さんはあれから免許も取ったし、車も買ったし、小奇麗な家にお母さんと住んでます。私を大学に入れてくれて、毎月多めの仕送りをくれます。
多分お父さんはお母さんにできなかった色々なことを私にしてくれます。ドライブに連れていってくれたのは一回や二回じゃないし、小まめに色々と調べて旅行のプランを考えてくれます。これは新しいお母さんの功績も大きいけれど、多分お父さんは私のためにそういうことをしてくれて、本当はあなたのことを考えていることが私には分かります。
まるで罪滅ぼしをするかのように、お父さんはあなたのことばかり考えているようです。
罪滅ぼしなんて物騒なことを言うようですが、私は、幼いときに聞いたお父さんの言ったことがまだ頭のどこかに引っかかっているのです。
元々汚いものが汚くてもなんとも思わないけれど、本当はキレイなはずのものが汚いと気分が悪い、って、そんなことを言っていたって、よく覚えています。お父さんは病気と闘っているお母さんのことを言っていたのだと思います。つい言ってしまったのだと思います。未だ好意的に受け取れないお父さんの発言です。お父さんは私がそれを聞いていて、今も覚えているなんて思っていないでしょう。お父さんが私にどれだけ愛情を注いでくれても、その度に、私にそんなことをしたってしょうがないでしょという冷めた気持ちになります。お父さんが私の顔色を伺えば伺うほど、惨めな気持ちになってしまいます。心のどこかで、お父さんはもう一生幸福を感じないでほしいと私は思っていて、思い返せばあの小樽でのお母さん――ゆかりさん――の容赦ないお父さんへの態度に、今更喝采を送っている私がいます。同じようにあの日のJRの雰囲気、うすら寒いロビー、陰鬱な顔をして二度も吐く私、薄暗い曇り空を映す小樽運河の全部が、お父さんを追い詰めた大事な仲間として私の中に備わっている気がします。そしてそうやって憂鬱を味方につけたことに少し罪悪感もあって、私は、はっきり言って、お父さんと会う度に淀んだ気持ちになります。
水族館のフロアを真っ黒に汚しながら楽しそうにお仕事をする水崎さんは、私を安らかにしてくれます。私のあるべき姿を映し出してくれているような気がするのです。
彼は私が見たえんぴつ男の話を聞くといつもニヤニヤしながら言います。
「それで、僕がその子じゃなかったらどうすんの? 全然別人でも僕のこと好きでいてくれるの? その黒い跡って単に好みの男に自分でつけてるマークってだけなんじゃないの?」
そんな意地悪を言う男をどう思いますか?
「もし本物のえんぴつ男が現れたらどうする? 僕もその大学生の男の子みたいにその場で振られてしまうの?」
お母さんがどう思うか分からないけれど、私の好きな人はこんな人です。
お父さんと違って、なんでもぐいぐい遠慮なく言ってくる人です。
家族は?
一生相入れないの?
水崎さんはそんなことを言う人です。明らかにデリカシーが足りません。
その代わり、後ろめたいところはなさそうです。
えんぴつ男と憂うつ女(完)
いただいたサポートは本を買う資金にします。ありがとうございます。
