
岡山新報デジタル【創価学会の正体】
●創価学会の正体③
海外での活動
1970年代(昭和45年)以後より創価学会は、日本国内での布教活動(会員数)が頭打ち傾向になってきたために、1975年(昭和50年)1月26日にアメリカ合衆国グアム島に51か国の代表が集って創価学会インタナショナル(SGI)を結成して海外への布教活動を積極的に行うようになった。
1975年(昭和50年)のSGI設立時には海外全体で150万人のメンバーだったが、2022年(令和4年)現在は、宗教の布教活動が厳しく規制されている中国、北朝鮮や中東諸国のイスラム教圏を除いた、日本を含む世界192カ国・地域に広がり、海外全体で約280万人のSGIメンバーを擁している。
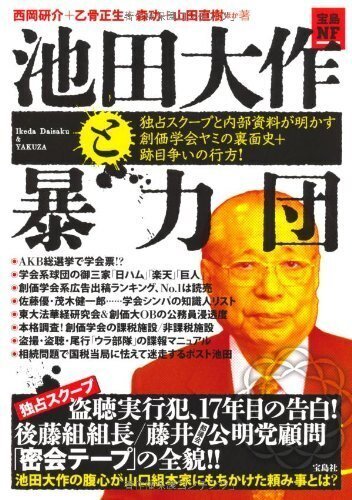
組織の活動
座談会は、三代の会長が最も大切にしてきた伝統行事であり、活動である、とされている。寺田喜朗は、1950年代~1960年代(昭和30年代~昭和40年代)の高度経済成長期、農村から都市へと多くの労働者が移住し、生活と将来への不安を抱えた人々が、座談会に参加する中で、悩みを分かち合い、「コミュニティー」を築いたと指摘する。そして、学会が、この座談会などの活動を通して会員を教育し、社会のさまざまな分野に人材を輩出する「総体革命」を目指していた、としている。また、央忠邦によると、座談会は班や地区の単位で行われ、1968年時点で、座談会の拠点は日本に二十万か所以上あった、とされる。
アメリカ・モアハウス大学のローレンス・カーター教授は、創価学会・SGIのユニークな特徴として、「座談会」を挙げており、そうした集まりが、寺院や教会ではなく、会員宅で開催されているのは、「SGIが在家運動であることが関係している」と指摘する。加えて、寺院などの場で行えば、聖職者の権威に特別な力が宿る一方で、庶民の自宅で集えば、「自然と皆が普段着で来られるような大衆的、民主的な場になる」ため、その点が「SGIの基底部に埋め込まれた平等主義の表れ」であるとしている。
差は存在するが、東京の場合では友人葬の基本料金は概ね35万円位から50万円位である。 友人葬を取り扱う葬儀社によっては、一式で基本料金に含まれているケースとオプション料金として別料金になる場合がある。
詳細は葬儀社への確認が必要である。
納骨は、地区部長を通じて申し込むと、全国にある創価学会墓地公園が利用出来る。
儀典長を中心に、生前の名前で葬儀を行うため、戒名料・読経料はかからない。

布教活動
無宗教あるいは他の宗教を信仰する者を改宗させる事を「折伏」(しゃくぶく、しゃくふく)という。
1951年(昭和26年)に戸田が「青年訓」を発表し、青年部を中心に折伏大行進と呼ばれる大々的な布教が行われた。布教活動は多くの会員を増やすことになった反面、その強引な手法から社会問題になった。
現在、創価学会では、仏法の人間主義に基づき、自他共の幸福を目指して、自身の信仰体験や仏法の哲理を友人や知人に語っていくことを「折伏・弘教」と定義している。
また、信仰者としての自身の振る舞い、生き方を通して、地域や職場で友情と信頼を深め、学会の理念や活動への理解を広げていくことも「折伏・弘教」にあたるとされている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
