
小説 「僕と先生の話」 43(最終話)
43.邂逅と希望
僕は、いよいよ40歳になってしまった。
先生が忙しくなる時期を前に、僕は連休を取って里帰りをしていた。故郷とはいえ、帰る「実家」が無い僕は、ホテルに滞在するしかない。
僕は、北海道に帰ったら必ず、寿司とラーメンとジンギスカンを食べることにしている。
その日は、一人で墓参りに行った後、高校時代の同級生と数年ぶりに落ち合い、2人でラーメンを食べに行った。
カウンター席に並んで座り、それぞれに麺を すする。
「おまえが内地(本州)に住み着くなんてなぁ」
「住めば都だよ」
「俺は道内でねぇと嫌だな」
「転勤ねぇの?」
「道内しかねぇよ。だから今の会社にしたんさ」
僕らは2人とも、東北地方からの移民の子孫である。この2人で居ると、札幌市民らしからぬ訛りが出る。そんな僕らは、学校内では非常に友達が少なかった。……そして、2人とも未だに独身である。
「今、内地で何の仕事してんの?」
「え。今……大金持ちの家で、ハウスキーパーしてる」
「ハウスキーパー?……家政夫!?」
「家政夫、言うな!」
「なしてさ!
あ、でも……そういうの、似合うな。まめ だもんな、稔」
「そうか?」
「んだ。ノート超きれいでさ。絵うまかった」
「もう忘れたわ……」
「俺、おまえにノート借りてなかったら卒業できんかったわ。たぶん」
僕は、高校時代のことなど、ほとんど憶えていない。
「あ、んだ。俺、おまえから借りっぱなしの漫画があるんだ」
「え?……そんなん、憶えてねぇわ。やるよ」
「なしてさ!?せっかく25年も置いてたのに!」
「要らねぇよ、今更」
「薄情者!」
結局、僕はその友人宅まで漫画を受け取りに行くことになった。
ラーメン屋のある札幌市中心部から、電車で郊外に移動して、住宅街の、雪が積もった道を歩く。
「最近、うちのアパートの、隣の部屋にさ。目の見えないおじさんが引越してきたんだ。で、時々、間違えて俺の部屋の鍵 開けようとガチャガチャしてるんさ……!」
「いや、仕方ねぇだろ。それ……」
「中に居る時やられっと、強盗か思って、びっくらこくぞ!」
「だどもさ……」
「自分の部屋わかるように、ドアに何か、ぶら下げといてほしい」
「それ、本人に言ってやれよ」
アパートに着き、友人が自宅のドアの前で「鍵が見つからない」とモタモタしているうちに、別の部屋の住人らしき足音が聞こえてきた。
「あ、あの人だよ」
「お隣さん?」
「んだ」
がっしりとした体つきの男性が、雪をかぶった廊下を、白杖で探りながら慎重に歩いてくる。
(え……?)
「おばんですー」
「え?あぁ……こんばんは」
僕の友人は、おそらく自分の存在をアピールするために、彼に挨拶した。彼は、その声で自宅のドアの位置に確信が持てたようだった。手探りでドアノブを見つけたら、次は鍵穴を探している。
僕は、その人を知っている。
「あ、あの!……須貝部長、ですよね?お久しぶりです!僕、坂元です」
もう「部長」ではないはずの彼に、思わず そう呼びかけた。
彼は、鍵を挿すのをやめた。
「…………稔か?」
「そうです!」
在職中と同じように「稔」と呼んでもらえたことが嬉しかった。
「おまえ……どうして、こんな所に?」
「ここ、部長の部屋の隣、僕の同級生の家なんですよ。遊びに来たんです」
「何だと!?……凄い偶然だな!」
僕も、そう思う。
「何、おまえ……知り合い?」
「内地の会社で、すごくお世話になった人」
「へぇ……」
友人と、小声でそんなやりとりをする。
「部長、仕事終わりですか?」
「もう『部長』じゃないぞ。……今、稽古が終わったんだ」
「柔道ですか?」
「あぁ、そうだ。こっちに来て、また始めたんだ」
「お元気そうで、良かったです!」
「へへへ……」
こんなに生き生きして、楽しそうに笑っている部長を見るのは、初めてだ。
やっと鍵を見つけた友人が、僕に言った。
「おまえ、そっちの部屋入れよ」
「え?」
「その人と、積もる話があるだろ?漫画渡すなんか、一瞬で終わるわ。……待ってろ、取ってくる」
「いや、でも……」
部長の許可は頂いていない。
「何だ。入るか?うちに」
「いいんですか?」
「外で立ち話なんか、寒いだろ。入れよ」
「お邪魔します」
「見える奴からすれば、汚い所だとは思うぞ」
友人から、古びたリングノートが何冊も入ったトートバッグを受け取ったら、僕は部長の部屋にお邪魔した。(貸していた漫画というのは、高校時代に僕が描いたものだった。完全に忘れていた。今は怖くて開けない。……開く理由も無い。)
今はもう明るさが判らないらしい部長は、室内の照明をつける習慣が無いようで、僕が入っていくまで、部屋は暗かった。僕が照明のスイッチを押すと、部屋が雑然としているのが明るみになった。
部長は、僕に「適当に座れ」と言ってから、ヒーターをつけたり、柔道着の洗濯を始めたり、食卓にコップを並べたり、冷蔵庫からペットボトルのお茶を出したり、黙々と動き回っている。
「お一人で住んでるんですか?」
「そうだ」
「……ご家族は、向こうですか?」
「離婚した」
「えっ……」
「もう、いいんだ。俺は、こっちで新しい人生を始めたんだ」
「お仕事は……?」
「今は、弁当屋で電話番と事務仕事をしてる。今どきは、パソコンソフトが、何でも読み上げてくれるんだ」
(……逞しい人だ)
「飯は食ったのか?」
「友人と食べてきました」
「そうか。俺は、今から食うんだ」
「……お茶、僕が注いでもいいですか?」
「あぁ、好きにしろ」
部長は冷凍のごはんを電子レンジで温めながら、冷蔵庫から出したカット野菜と豚の細切れ肉を炒め、電気ケトルで沸かしたお湯で、インスタント味噌汁を作る。見えていなくても、慣れた手つきで調理をし、食器を用意して配膳する。
僕に「動くなよ」と言ってから、出来たての料理と、冷蔵庫にあった惣菜をパックのまま食卓に並べていく。
僕の分も、箸を出してくれた。
稽古終わりの部長は、かなりの量を食べる。僕も、一部の惣菜を頂く。
「おまえ、こっちが地元だったよな。帰ってきたのか?」
「里帰りです。住まいは、向こうにあります」
「仕事は?」
「……ハウスキーパーしてます」
「何だ、そりゃあ?家事代行みたいなやつか?」
「概ね、そんなところです」
「家事なぁ……。この家にも、たまにヘルパーさんが来るぞ。水まわりをきちんと掃除してもらって、米を炊いてもらうんだ。あと、買い物と洗濯を頼む」
「僕の仕事と似てますね」
「そうか?」
5年以上会っていなかった かつての『師匠』が、今、目の前に居る。当たり前のように、一緒に食事をしている。それが、今も不思議で堪らない。
「あの、部長……松尾さんって、憶えてますか?あの工場に居た……」
「あぁ、憶えてるぞ。あの、口の悪い『社長の犬』みたいな奴だろ?……どうせ、俺の後釜は あいつだろ」
「彼、あの会社辞めて、善治のお姉さんと結婚したんですよ」
「嘘だろ!!?」
「本当ですよ!」
あの2人が正式に婚姻届を出したのは、2年前のことである。彼の姓は、もう「松尾」ではない。
部長は、よほど驚いたのか、食器を置き、頭を撫で回すようにして、短く刈り込んだ自身の髪を触っている。
「にわかには信じられんな。あの松尾が辞めて……あの先生と、結婚!? いやいやいや……」
何度も首をかしげる。
「大体、なんで、おまえが そんなこと知ってるんだ。おまえ、ゼンと仲良かったのか?」
部長だけは、善治のことをゼンと呼ぶ。初めの頃に、名前の読みを「ゼンジ」だと勘違いしていたことに由来するらしい。
「僕、善治のお姉さんに雇われてます」
「そういうことか!……なるほどな。
面白いことになってるじゃないか!俺が居ないうちに」
どんぶり等には移さずに、大きな保存容器から直接ごはんを食べている部長は、いかにも愉快そうに、腹から声を出して笑っている。
「善治とは、連絡取ってないんですか?」
「もう、連絡先が分からん」
「僕、分かりますよ。お伝えしましょうか?」
「いや……」
「スマホだって、メール読み上げてくれるでしょう?」
部長の顔つきが変わった。至って真剣な眼差しである。
「…………あいつは、今もあそこで頑張ってるのか?」
「彼、今は東北で農業用ロボットの開発してます」
「やっぱり、そういう分野に帰ったか……。それが良いわな。せっかく技術があるんだ。部品職人じゃ勿体ない……」
もう何も見えていないはずの部長の眼は、僕には、見えていた頃と何も変わっていないように思えた。濁っているわけでもないし、眼球がふらふら揺れているわけでもない。
「部長の眼が悪くなったこと、善治には言ってたんですか?」
「あいつは、現場で気付いてた。……俺には難しくなった品目を、いくつも引き受けてくれた」
「……彼、部長が辞めてすぐ、社長ぶん殴って辞めました」
「社長を殴った!?馬鹿げた真似を……。パクられなかったか?」
「パクられてはいません……」
「そりゃあ、良かった」
部長は、朗らかによく笑うようになった。新天地での暮らしが、性に合っているらしい。
大量の食事を食べ終わると、部長は満足げにふんぞり返った。
「何にせよ……今のおまえが元気なら、俺は嬉しいよ。身体はもう、良くなったか?」
「はい、おかげさまで」
「良かったなぁ。良い職場が見つかって……」
僕は「はい」しか言えなかった。
その後、特に前置きもなく、僕は話題を変えた。
「部長が、僕のことを憶えていてくださって……すごく嬉しかったです」
「そりゃあ、そうだ。最後の『弟子』だからな。声と、纏ってる【空気】は……よく憶えてる」
僕も、共に働いた現場の匂いや、部長の車の中の匂いは、今でもはっきり思い出せる。
「おまえは、底抜けに優しいが……難しいことを、そうそう簡単には諦めない、根性がある。それが、おまえの強さだ。……教え甲斐のある、良い『弟子』だった」
「恐れ入ります」
僕は、部長と連絡先を交換した。また、善治から許可を得ることが出来たら、彼の連絡先を部長に教えると約束した。
「あの。部長のスマホ……ホームページとかも、読み上げ出来ますか?」
「出来るぞ」
「僕、部長に読んで頂きたいものがあって……」
「何だ?」
「僕が書いた、小説なんですけど……ご興味ありますか?」
「小説!?……何だ、おまえ、家事代行しながら、そんなもん書いてるのか?」
「あ、はい。趣味なんですけど……吉岡先生に感化されまして……」
「吉岡?……あぁ、ゼンの姉さんな。あの人は、凄いな」
部長も、先生のことを少なからず知っているはずである。
「で、おまえの小説が、ネットに載ってるのか?」
「あ、はい。僭越ながら……」
「出してみろ」
部長は、ご自分のスマートフォンを突き出した。
僕がそれを操作して、目的のページを表示して部長に返すと、部長はスマートフォンの背面を何度かタップしてから、読み上げるようにと声で指示した。
すると、電子音声によって、ものすごい速さで閲覧中のページが読み上げられていく。4倍速くらいだろうか……自分で載せた文章のはずなのに、どこが読み上げられているのか、僕には まったく判らない。(速すぎて聴き取れない。)
部長が、スマートフォンを耳に近づけて、にやにや笑いながら聴いている。全てを正確に聴き取れているのなら、本当に凄い。
「後で、これブックマークに入れてくれよ。初めのほうを聴き逃した」
「わかりました」
部長は、電子音声が止まるまで、じっと聴いていた。
「……いい話だな。感動させるようなやつだな」
「ありがとうございます」
僕が書いた あの天文学者の物語を、今はネット上で公開しているのだ。他にも、いろいろと、懲りずに書いては載せている。決して「人気がある」とは言えないけれど……僕としては、どれだけ少数でも、読んでくれる人が居るなら、満足だ。
特に、この天文学者の物語に「スキ」が付くと、僕よりも先生への声援であるような気がして、すごく嬉しくなる。
その2日後。奇跡のような邂逅の余韻に浸りながら、僕は飛行機に乗った。

連休明け。6日ぶりに、先生の家に出勤する。今では、僕も合鍵を持たされている。インターホンで挨拶をしたら、自分で鍵を開ける。
玄関に、小さな靴がたくさん並んでいる。今日は、岩下さんの子ども達を預かる約束の日である。(小学校は冬休みだ。)
「稔くん、おかえりー!!」
「ポックル買ってきたー!?」
小学校4年生の長男・樹くんと、1年生の長女・遙ちゃんが、僕が持参した お土産を目当てに、階段を駆け降りてくる。
「買ってきたよ」
「わーい!!」
「2階で開けるよ。みんなで一緒に食べよう」
「やったー!!」
すぐにまた階段を駆け上がる。上の2人は、とても元気で賑やかである。
「悠くん!悟!お菓子もらえるぞ!!」
2階に上がると、リビングで樹くんが騒いでいる。
生まれてすぐの頃に「とにかく寝ない」として両親を困らせていた次男の悟くんは、4歳になった。彼だけは、とても静かな子だ。誰かと一緒に遊ぶよりも、一人で図鑑を眺めたり、黙々とおもちゃの車を並べたりするのが好きらしい。今も、一人で事務机の下に潜り込んで、薄暗がりの中お気に入りの恐竜図鑑を眺めている。
樹くんが「悠くん」と呼んでいるのは、先生の夫となった旧姓「松尾くん」こと、悠介さんである。彼は、賑やかな2人の良き遊び相手だ。よく、ボール遊びや戦隊ヒーローごっこに付き合わされている。この日も、この部屋で何かが行われたらしく、新聞紙で作った刀のような物が、複数本 床に散乱している。(作ったのは先生であるような気がする。)
「坂元さん、おかえりなさい」
「只今、戻りました。……先生は、上ですか?」
「何か、本を探しに行きましたね。すぐに降りてくると思いますよ」
「わかりました」
「稔くん!お菓子はー!?」
「はいはい……」
僕が紙袋からお菓子の箱を取り出すと、遙ちゃんが奪い取るようにして持ち去り、食卓の上で箱を破り、中の小袋をぶちまけた。それを見た樹くんが駆け寄っていき、アニメの台詞らしきものを叫びながら、3袋も掻っ攫った。
(お父さんの遺伝子は……どこに……?)
3階へと続く階段から「随分と騒がしいね」と声がして、先生が降りてきた。悟くんのために、本格的な恐竜図鑑を持ってきてあげたようだ。
「おはよう。ゆっくり出来たかい?」
「おかげさまで」
「そりゃあ、良かった」
先生が、事務机の側に しゃがんだ。
「悟くん。またそんな所に居るのかい?」
彼は、お兄ちゃんに渡してもらったお菓子を、事務机の下で黙々と食べている。
「君は隠れるのが好きだねぇ」
先生が語りかけても、彼は「我関せず」である。彼は、基本的に「会話」というものをしたがらない。意味のある言葉は、基本的な挨拶と、家族の呼び名と、恐竜の名前くらいしか発しない。そんな彼の意思を、大まかにでも読み取ることが出来るのは、両親と先生だけである。(彼は自閉症と診断されている。)基本的にはすごく静かな子だけれど、激しい癇癪持ちでもある。持ち物や衣類に対するこだわりが強く、お気に入りの物を兄妹に取られでもしたら、火がついたように怒る。また、チャイルドシートが大嫌いで、彼を車に乗せて出かけることを、両親はもう諦めた。
その悟くんだけを、この家で預かる日も度々ある。それでも、僕は未だに、彼と会話が成立したことはない。彼は、僕の顔を見ようともしない。彼は、人よりも書籍に興味がある。
先生が、彼に恐竜図鑑を見せている。彼は、ページをめくるたびに、描かれている恐竜の名前を淡々と述べていく。まだ文字は読めないはずだから、おそらく絵だけを見て判断している。
先生は、彼がページを破ってしまうような子ではないことを知っているから、好きにさせている。
「彼は、将来きっと偉大な研究者になるよ」
「気が早いですねぇ、先生……」
「悠くん!サッカーしに行こう!!」
「えぇー。やだー。寒いー。おじさん疲れたー」
樹くんが外遊びに誘うけれど、悠くんは、やる気が無い。こたつの中でゴロゴロしている。
「行こうよ!!」
「おじさん、こたつから出たくなーいー」
余っている左の袖をぐいぐい引っ張られても、彼は動こうとしない。
樹くんが、眉間に皺を寄せて僕を見る。不満が顔に出ている。
「お昼ごはんを、食べた後に行ったら?」
「そうしよう!」
「俺は嫌だぞー!」
そう言っていたけれど、結局、彼は昼食後に上の子2人を連れて公園に出かける羽目になった。(僕は「夕食の準備」を理由に欠席した。)
子ども達に「おじさんは明日から仕事なんだぞー」と言いながら渋々出かけていった彼は、入社直後には約8ヵ月間に渡って休職したけれど、無事に復職し、今や『新社長の右腕』である。(先生の【恩師】である工場長は、もう引退された。)
先生は、今日は子ども達が来ているから、午睡はしない。こたつの中から、悟くんが再び先生の恐竜図鑑を見ている姿を、温かく見守っている。
「昔から知っている子ども達の成長を見ていると……『あぁ。外では、ちゃんと時が流れているんだなぁ』と実感することが出来て、安心するんだ」
「外……ですか?」
僕も こたつに入る。
「あまりにも長い時間、一人で部屋に篭っていると、分からなくなるからね。何度でも、記憶が『過去』に引き戻されて、自分は20代のまま、時が止まっているみたいに思えてくる……」
凄惨な『過去』のことで頭が一杯の時、先生は、普段から使い慣れているはずの家電の使い方さえ、忘れてしまう。つい先日も「電子レンジの使い方が分からなくなった」と言って、パニックになりかけていた。
僕が居ない時に先生が激しく動揺しても、今なら悠介さんが冷静に対処できる。
「今が何年の何月何日で……自分が何処に居るのか、何のために絵を描いているのか……分からなくなってしまうんだ。私は、いとも簡単に【見当識】を失うんだ」
(今がいつなのか判らなくなるから、『過去』と『現在』を混同してしまうのか……?)
先生は、約2年前に担当編集者が変わってから、ほとんど絵本を出版していない。
先生は、結婚を決意した頃から、フラッシュバックに伴う激昂によって人を攻撃してしまうことは ほぼ無くなったのだけれど、新しい担当編集者は、先生の病態を過剰に警戒し、なかなか この家に訪ねてこようとしない。対面ではなく、インターネットを介したスピーディーかつ効率的な やりとりを要求してくる。しかし、先生は それを頑なに拒んでいる。先生は、絵に関しては筋金入りの『アナログ派』なのである。スキャンや写真撮影によって絵の色味が変わってしまうことを、非常に嫌う。また、デジタル機器の使い方を忘れてしまう頻度も高いため、従来通りの対面と郵送の併用を望んでいる。
そんな先生の大切な【戦友】とも云うべき岩下さんは、部署異動によって絵本の担当ではなくなり、若年層向けのライトノベルの担当に変わった。先生は、それ以来「絵本を書く気になれない」「ライトノベルに転向しようかな」と言い続けている。(今のところ、他社で福祉関係の実用書を書くか、相変わらず ご友人と共に小説を書いている。)
僕は、この先生ならライトノベルでも平然と一人で書き続けられるような気がしている。せっかくのアトリエや高価な画材が趣味専用となってしまうのは、なんだか勿体ない気がするけれど……。
インターホンが鳴る。先生が応対する。
誰が来たのか、小さな恐竜博士に伝える。
「悟くん、父やんが来たよ」
そう言われても、彼は図鑑から目を離さず、恐竜の名前だけを言い続けている。(岩下家の子ども達は、両親を「父やん」「母やん」と呼ぶ。僕はそれを、とても可愛いと思う。)
先生が玄関まで鍵を開けに行く。
父親の哲朗さんが上がってきて、僕と挨拶を交わした後、まっすぐに息子の側へ行く。
「悟。良い子にしてたか?」
「いつだって良い子だよ」
先生が答える。哲朗さんは、静かに笑って応える。そして、恭しく頭を下げる。
図鑑に夢中の息子に語りかける。
「……良いもの読んでるな」
彼は、父親には見向きもしない。相変わらず恐竜の名前ばかり唱えている。
「今は忙しいか」
哲朗さんは、上着を脱いでこたつに入った。僕がお茶を出すと、すぐに飲み干してしまった。(彼は、異動が決まった頃から眼鏡をかけ始めた。)
「編集長、肩でも揉みましょうか?」
「編集長ではありませんよ」
「いつ編集長になるんだい?」
「なりたくありません……」
先生は、半ば独断で彼の肩を揉み始める。彼は、眼鏡を外して食卓に置く。上を向いて、大きくため息をつく。
「やはり……私は、児童向けの書籍でないと、しっくりこないのです……」
「ティーンエイジャー向けのノベルを担当してるんだろ?」
「私自身が、今の若い人の流行に、ついて行けません……。私は、出来ることなら再び以前のように、執筆歴の長い先生方と共に【不変の理】とでも云うべきものについて、もっと幼い子でも解るように書いて……幅広い年代の人々に届けたいのです。ライトノベルは、道徳性よりも娯楽要素が強いものが好まれますし、基本的に『保護者と一緒に読む』ものではありません。……私の性分には合いません」
「相変わらず、志が高いねぇ……。【不変の理】とは、何だい?」
「生き物は、死んでしまったら、二度と生き返ることはありません。……動物は、食べなければ、生きていくことが出来ません。……どんな生き物でも、必ず歳を取ります。いずれ必ず死にます。生命は有限です。……だからこそ、尊いのです」
「君の信条も【不変】だねぇ」
「私は、自分が今『生きて動いている』ことが……嬉しくて、有り難くて、堪らないのです。……そこは、何十年経っても、変わらないのです」
頭と頸の怪我で、長く生死の境を彷徨った彼だからこそ、その境地に至ったのだろう。
「動物とは本来、そういうものだよ」
先生は、悪い箇所を探るように、彼の肩や背中をさする。
「私は、君とでないと……『吉岡 諒』では居られない」
「滅相もない……」
彼は、目を閉じる。
「私には、名前がたくさんあるけれども……君と共に歩んできた『諒』の名が……いちばん好きだなぁ」
夫の悠介さんは、家庭内では先生のことを、ご本名ではなく「諒ちゃん」と呼んでいる。(ご本人が最も気に入っている名で呼ぶことにしたのだという。)
先生は「相変わらず硬いなぁ……」と言いながら、彼の首や背中を、少し力を込めてほぐしていく。
「どうか、無理だけはしないでくれよ。君が、また風呂で溺れたりしたら……私は、今度こそ気がおかしくなってしまうよ」
彼は昨年、一人で銭湯に行き、浴槽内で発作が起きて溺れてしまい、救急搬送された。2日後には意識が戻り、目立った後遺症も無く すぐに退院できたけれど、それ以来、彼が同性の同伴者無しで銭湯や温泉に行くのは【厳禁】となっている。
「私としても……素っ裸で救急車に乗るなんて、二度と御免です」
僕は、悟くんが眺めている恐竜図鑑を、上から一緒に覗く。彼は、それを最後のページまで見終わったら、ぱたんと音を立てて閉じ、父親のもとへ持っていった。
黙って父親の手を掴んで、図鑑に押し当てる。
「どうした。……読んでほしいのか?」
「とーやん」
「……よし」
哲朗さんが改めて図鑑を開き、再び眼鏡をかけてから、解説を読み上げていく。悟くんは、父親がページをめくるたびに、恐竜の名前を正確に言い当てる。時々「たまご」と言う。
「卵だな」
巣や卵も一緒に描かれているページが、いくつか在る。
先生が、哲朗さんから離れる。
公園から3人が帰ってきた。子ども2人が「父やんが居るー!」と騒ぐ。そして、僕からお土産を貰ったことや、公園で遊んできたことを、口々に父親に報告する。
哲朗さんは、それを「そうかそうか」と聴きながら、悠介さんに礼を言う。
騒がしい3人が帰ってきて、悟くんは再び事務机の下に逃げ込む。先生の図鑑は、まだ哲朗さんの手の中にある。
机の下で体を揺らしながらうーうー唸り始めた悟くんに、先生が、彼が家から持ってきたほうの図鑑を渡す。彼は、それを受け取ると静かになった。
親子が帰った後、悠介さんはこたつの中で寝転がりながら「あぁ疲れたー!」と言って、先生に「後で脚を揉んでくれ」と頼んだ。先生は「はっはっは」と笑っているだけである。YESともNOとも言わない。
「俺、もう『おっさん』だよー」
「私より十も若いくせに……!」
使い慣れた台所で2人の会話を聴きながら、僕は夕食の準備をする。今日は、僕が北海道から送った食材を、ふんだんに使う。(カニの足を、片手でも簡単に食べられるように処理するのが、結構な手間である。)
日中がどれだけ騒がしくても、何事も無かったかのように、3人で夕食を摂る。この時間、僕はとても幸せである。
今後、もし僕に戸籍上の「家族」が出来たとしても、僕はこの家で食事を摂ることをやめないと思う。
僕は2人に、地元での奇跡のような邂逅の話をした。2人とも、カニを食べながら「そんな話があるか!?」と、驚いていた。
「いずれにせよ……お元気なら、良かった。安心したよ」
「お二人が結婚したこと、なかなか信じてもらえませんでした」
「そんなことまで話したんすか!?」
「すみません、つい……」
「別にいいじゃないか。隠すようなことでもないし」
「まぁ、そうなんすけど……」
この2人は、式を挙げていない。2人とも、大勢の人の前に出るのが大の苦手なのだ。
食後、悠介さんが「今日は早く寝たい」と言って早めに風呂に入り、僕は久しぶりに先生とリビングで2人きりになった。
「今日の味噌汁は格別に美味しかったなぁ……!」
「北海道の、良い昆布を使いました」
「なるほど」
先生は、初めの頃からずっと「君が作る味噌汁は美味しい」と言い続けてくれている。僕としては、特に何も気を遣わず、いつも通りのものを作っているだけなのだけれど……たったそれだけのことが、何年経っても嬉しい。
「僕、この家でごはんを食べる時間が、いちばん幸せです」
「どうしたんだ。いきなり」
「里帰りをしても、僕には帰る『実家』がありませんから……。こっちに戻ってきて、今日ここに出勤した時、なんだか……『あぁ、帰ってきた』って、感じたんです」
「感覚としては もう、こっちが『ホーム』なのかい?」
「そうかもしれません」
「……君さえ良ければ、いつまでも居てくれよ」
「僕なんかで良いんですか?」
「私達は、君でなければ嫌だよ」
「それは……この上ない誉れです」
「誉れだって!?大袈裟だなぁ!」
先生は、涙が出るほど笑った。
僕は、先生の笑顔が見られるなら、何だって作って差し上げたい。ジビエや食用昆虫も厭わない。いくつになっても一緒に食べられる料理を、研究し続けたい。
帰宅後、僕はあのノートを開いた。旧友から受け取るまでは、すっかり忘れていたけれど、今なら、描いた当時のことを はっきりと思い出せる。これを描いた頃は、まだ父が生きていた。
パラパラとページをめくる。頭の中は、とても静かだ。誰も、僕の漫画を嗤ったりなどしていない。
全てがシャーペン描きで、絵もストーリーも決して巧くはないけれど、当時の自分にとっては「過去最高の出来」だった。
僕は、運良く生き残った この話を、小説の形でリメイクすると決めた。
過去に創られた偽りの僕ではなく、今の、本当の僕が書く【物語】を、読んでもらいたい人が居る。
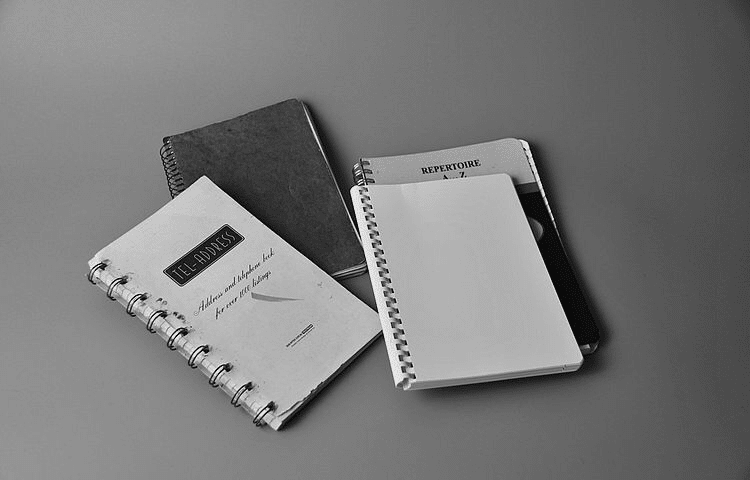
僕の心臓は、まだ動いている。
【完】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
