
今週の日記|すべては他者理解のために
2月18日 はしっこに、馬といる
SNS離れがささやかれてひさしいが、たしかにタイムラインを眺めているとモヤモヤしたり、嫌な気持ちになったりすることも少なくない。
ぼくがツイッターでフォローしている人たちのなかにも、まったく意見の合わないひと、なんでこんなふうに考えることができるのだろうと訝しくさえ思うような人たちが少なからずいる。それでも、そういう人たちをミュートしようとかブロックしようとは考えない。理由は、彼らのことが「わからないから」である。そして、それはたぶん、大学で哲学を学んでいた頃からずっと、自分の関心の中心にはつねに「他者理解」があるせいだろう。
たとえば、いつも「いいね」してくれるような人たちは、わかりやすい。放っておいても自然と友人になれるような人たちだ。それに対して、自分からしたらまったく意見の合わない人たちは自分にとって完全なる「他者」、「エイリアン」といっていい。エイリアンはこわい。だからこそ見えないところに隠れる、あるいは逃げる。その理屈は、ある意味正しい。
だが、自分にはそれができない。わからないならわからないなりに、共感はしなくても理解はしたいと考えてしまう。そのひとがどこでどんなふうに暮らしているのか、どんな環境で育ったのか、それを知ることで相手の思考のツボを探ってみたくなる。だから、よせばいいのに、そのひとのタイムラインまでわざわざ見に行ってしまったりもするのだ。
その根底にはおそらく、たとえどんなにわかりあえそうな人であっても、すべてのひとは基本的に他者、本質的にわかりあえない存在であるという思いがあるからにちがいない。いいねしてくれる人もクソリプしてくる人も、いずれも「他者」であるという点においては変わらない。
理解しようとしなければまるでわからないのは当たり前、理解しようとする努力をやめれば、わかりあえたと思った相手であろうと容赦なく去ってゆく。他者理解への思いは、そうしたほろ苦い現実を知れば知るほどいっそう強くなる。
***
いま、ハラダくんから借りた『はしっこに、馬といる』という本を読んでいる。自分がウマ好きであるということもあるが、とてもいい本である。
東京で編集者として生活してきた著者が、ある日思い立って、ウマとともに暮らすため与那国島に移住する。ほとんどウマについての知識をなにも持ち合わせないままに。
文字通り手探りで、少しずつウマとの距離を縮めてゆくその過程から導き出された著者のことばには、強い説得力と上から目線ではないやさしさが同居している。ウマがウマらしくいられて、かつ自分も力をつかわずにうまくつきあってゆく。そのために必要とかんがえるポイントを、著者は4つ挙げる。
①「このヒトは身内だ」と、ウマに認めてもらうこと
②ウマのこころがどういうふうに動くのか、よく理解すること
③ウマの時間に合わせること
④馬語を話すことができるように、ヒトが、自分の感覚とからだを育てること
ここに挙げられた4つは、相手がウマにかぎらず、他者理解のための糸口でもあるだろう。ウマは、他者とおなじく、基本わかりあえないものだからである。
わかりあえないから否定する、ミュートする、ブロックするというのはかんたんだが、わかりあえないなりに相手との接点をみつけ、対話を始めることからしか他者理解は生まれえない。「馬語を話す」のと同様、他者とのコミュニケーションもまた共通の「ことば」を模索するところから始まる。コミュニケーションの積み重ねをとおしてのみ、ぼくらはただの場所を共通の居場所に変えてゆくことができる。
べつに好きにならなくてもかまわない。みんなが仲良しの世界なんてありえない。ただ、相手は相手のまま、自分も余計なエネルギーは使わずにひとつところで生きられる環境をつくることができればそれでいい。他者理解は、そのために必要な「術(アルス)」である。
この本に書かれたウマと無理なく暮らすための4つのポイントは、そのまま仕事や身の回りの人間関係にも応用できるだろう。
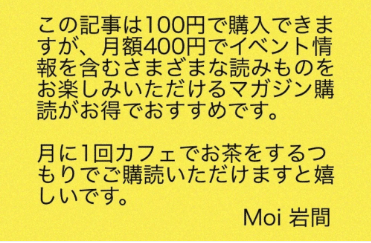
ここから先は
¥ 100
サポートいただいた金額は、すべて高齢者や子育て中のみなさん、お仕事で疲れているみなさんのための新たな居場所づくりの経費として大切に使わせて頂きます。
