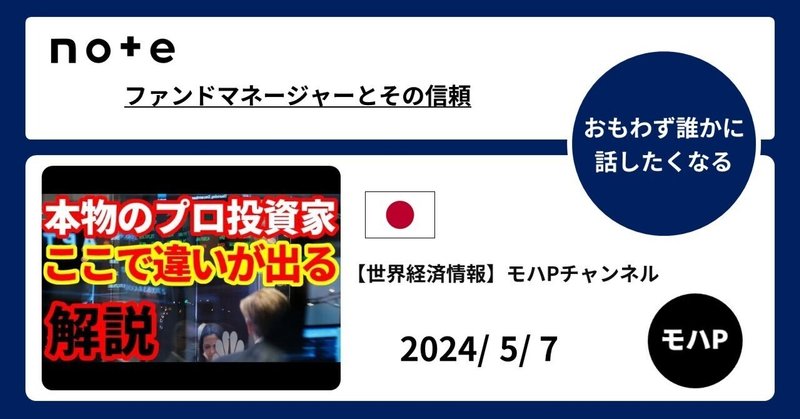
ファンドマネージャーとその信頼
機関投資家とファンドマネージャー
世間では、個人投資家や投資系YouTuberの方が、機関投資家をマーケットを動かす強大な存在として語ることが多いです。しかし、実際には、これらの機関投資家がどのような人々で、どのようなスキルを持って運用しているのかはあまり知られていません。
個人投資家の中には、プロの投資家、つまりファンドマネージャーの考え方を参考にしたいと思っている人もいるでしょう。そして、このプロの投資家、ファンドマネージャーのスキルについては、資産運用を行っている人だけでなく、多くの人が自身のキャリアを考える上でも非常に参考になる部分があると思います。そこで今日は、優秀なファンドマネージャーと言われる人たちはどのような人たちなのか、解説したいと思います。
マネージャーストラクチャー
ファンドマネージャーとは、さまざまな運用会社の中に存在し、その能力はピンからキリまであります。そして、これらのファンドマネージャーを評価する仕事が存在します。例えば、私たちの国民年金を運用しているGPIFでは、株や外国債権については自社で運用せず、外部のファンドマネージャーに委託しています。
例えば、野村アセットマネジメントにいくら、ゴールドマンサックスアセットマネジメントにいくらなど、外部の運用会社にお金を預けて運用してもらっています。
どの会社に委託するかを決めるためには、運用会社とその会社のファンドマネージャーを総合的に評価し、ランキングをつけて依頼する会社を決定します。この委託する運用会社を選定するプロセスを「マネージャーストラクチャー」と呼びます。つまり、運用業界においては、いわゆるプロの投資家を評価する仕事が存在するわけです。
ファンドマネージャーの評価基準
もちろん、会社対会社の話なので、ファンドマネージャー個人の評価だけで決まるわけではありません。しかし、ファンドマネージャーのスキルは当然、検討の材料になります。では、どのようなファンドマネージャーが評価されるのでしょうか。
当然、成績が優秀、つまり運用のパフォーマンスが良いファンドマネージャーは、それだけ評価されることになります。ただし、実はそれだけではありません。
この世界では、運用のパフォーマンスが良いとすごく評価され、パフォーマンスが悪いとすぐに首になるというイメージがあるかもしれません。しかし、実はパフォーマンスだけで評価されているわけではありません。
例えば、ファンドマネージャーになって5年で業界トップクラスの成績を上げているという人がいるとします。これだけでこの人が最高の評価を得られるかと言うと、そう簡単ではありません。なぜなら、この5年間、この人の運用戦略と市場環境がたまたまうまくマッチして良い成績が出ただけかもしれません。むしろ、この人は追い風の相場環境しか知らず、環境が変わったら全然ダメになってしまう可能性があるかもしれません。
マネージャーストラクチャーの重要性
マネージャーストラクチャーを行う場合は、この辺りをしっかりと見極める必要があります。一方で、トップクラスのパフォーマンスは上げていないものの、それなりの評価を受ける場合もあります。その運用会社が得意としている戦略にとって、とても不利な市場環境になっているというような状況で、その中でも損失をなるべく回避し、リターンの最大化に努めていると評価できる場合は、高評価になる場合もあります。
信頼と評価
つまり、将来信頼してお金を託せるかどうかは、過去の運用成績だけではなく、困難な状況を乗り越えていけるか、そうした信頼に値するかどうかということです。
ファンドマネージャーの評価を行う場合は、うまくいっていない時や困難な状況にある時にどう行動したかを細かくチェックします。うまくいっている時は、誰でもうまくできるわけです。うまくいっていない時に何ができるか、そこで力の差が出るわけです。
リスク管理
もう少し具体的に言うと、うまくいっていない戦略をどう分析して損切りをするのか、それとも回復するという確信のもとにポジションを維持するのか、その判断を見ていくわけです。うまくいっていないのに放置する、これが最も良くない対応になります。
プロの世界では、ファンドマネージャーだけで運用しているのではなく、リスク管理部門などがあり、損失が大きくなってきたりすると、リスク管理部門がどういう風に動いたかとか、会社として、うまくいかなくなった時に、その中でもより良い状況に改善するためにちゃんと動けていたのか、そうしたところが重要になるわけです。
成長と評価
これはファンドマネージャーに限った話ではありません。
会社が人を採用する時、ずっと成績優秀でエリート街道を歩んできたAさんと、成績はAさんより劣るものの、人生でいろんな困難を乗り越えてきたBさん、この二人の候補者がいたとします。
同じ土俵に立っている二人の中で、Bさんが乗り越えてきた経験というのがどういうものなのかというので評価が変わることもあると思います。そうした経験が一定の評価を受ける場合が多いというのも事実でしょう。
実際、資産運用の業界もそれ以外の業界もそうですが、世の中は厳しいです。追い風の状況なんてそんなに長くは続かないです。むしろ、向い風の中で前に進んでいかないといけないということの方が多いです。困難な状況の中でそれをどういう風に乗り越えてきたのか、それがどの分野、どの業界においても重要であると思います。
成長と競争
厳しい競争社会の中でたくさんの困難な状況に向き合った方が、人はより成長できるのではないかと私は思っています。そういう意味では、日本の会社は生産性が低いとか成長していないとかよく言われますが、あまりにも失敗を恐れ過ぎているということ、これが成長できない要因の一つだと私は思っています。
資産運用と人生
資産運用の話に戻りますが、個人投資家の中で保有していた一部の銘柄がすごく上がったり、仮想通貨が爆上がりして、急に億り人になったとか、そういう人がいると思います。急にたくさんのお金を手にした人は、多くの場合、たまたま追い風の時にその人の運用戦略がたまたまはまっただけの場合が多いです。
実際、人生でずっと追い風ということはないわけです。無風の時の方が多いです。追い風の中でドカンと儲けたお金と、無風の中でも一生懸命自分を磨いて身につけたスキルや自信、どちらが重要かと言われれば、私は後者の方ではないかと思います。
これから資産運用を始めようという方も、もちろん最大限利益をあげることを考えなければいけませんが、損をしない、失敗をしないようにばかり考えていてはいけません。失敗して、向い風の中にある時に何ができるのか、そこからがスタートだということを覚えておかれるといいでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
